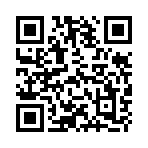keith yoshidaの新・飯がわりに1枚!(Again) › 名盤を探しに行こう!
2009年10月22日
名盤/ Billy Joel & KAN
続・名盤を探しに行こう!/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.81(2001年 01月号掲載)
サイモン&ガーファンクルに続いてビリーですか!
活動再開後、こちらも札幌に来ていたような・・・。
文章駄目ですね!相変わらず。
マディソン・スクエア・ガーデンの前にニューヨークって入れなきゃ!
「ストレンジャー」云々の件は、その曲がニューヨークを思い起こすほど、
一般に浸透している!みたいな事を書かなきゃ!と思う。
あと“。”とかも、ちょっとな~、ってところで使って・・・。
書いていったらキリがない。ホント、お粗末!
ま、人間って簡単には成長しない!って事なんでしょうか?
それとも才能の問題!
「ストレンジャー」は一世を風靡した感がある。
その時に聴き過ぎて、今はもう聴かなくなったのか、
他の作品同様、単なる過去のモノを聴いている余裕など無いくらい、
今、リリースされている最新の音楽状況をチェックするのに
忙しいのかは“?”なんですがね・・・。
そうそう、知り合いのアーティストで文中のビリーの引退コンサート
を観に、わざわざニューヨークまで行ったヤツがいた。
後日談で、強行スケジュールだったがゆえに、ナント、本番中、時差ボケで
殆ど寝ていた!と言う、笑うに笑えない話もあった。
KANさんは、ホント音楽好きらしく、札幌や東京の洋楽アーティスト
のライヴ会場で、良く見かけた。
KANさんに限らず、アーティストの方々はライヴを含めて勉強熱心。
音楽に関わっている皆さんが、ミンナそうだといいのに!
憧れのニューヨークの街の臭いを感じさせたビリーの歌。
柄にもなく、とあるピアニストのコンサートを観に出掛けた。
たまには、この手の静寂さを求められる(勿論オーディエンス側に)のも
いいもんだ。と、じっくりと鑑賞させて頂きました。
でぇ、コンサートの中程で、ちょっとお遊びっぽいコーナーがあって、
そこで一つの曲を国が違えば、きっとこんなアレンジになるのでは?
みたいな事を演っていたの。
確か曲は唱歌の「赤とんぼ」だったかな。それをフランスのパリなら
シャンソン風とかに演っちゃう訳。分かる?
メロディはあくまで「赤とんぼ」だからネ。
それでニューヨークになるとこうなるのでは。と演ったのが、あの印象的
な「ストレンジャー」のフレーズを土台にしたもの。
う~ん、もうすっかり忘れていたネ。その存在を。そうビリー・ジョエル
っていたな~。と。
ここんとこ全然名前も歌声も聴く事がないな~と思ったら、確か2~3年前
に、最後のライヴって事で、マディソン・スクエア・ガーデンで引退(!?)
コンサートを演った事を思い出した。
ニューヨークはブロンクス生まれの彼が注目を集めるようになったのが、
2枚目のソロ・アルバム「ピアノマン」をリリースした1973年の事。
70年代に入ってポップス・シーンに吹き荒れたシンガー・ソングライター
旋風のど真ん中いた訳だが、後々の印象としては、シンガー・ソングライター
と言うより、よりポップス派に近いシンガーのイメージが強い。
それはビリーを一躍世界的に有名人に仕立て上げた、前述のヒット曲
「ストレンジャー」以降の活躍振りが大きいからに違いない。
実際、73年の「ピアノマン」のリリース時は、評論家と熱心な音楽ファン
くらいしか、ビリー・ジョエルに注目しなかったのだから。
それから4年後、アルバム「THE STRANGER」がリリースされ、「ストレン
ジャー」と「素顔のままで」の2曲のビッグヒットが生まれビリーの
存在を決定付ける。

この原稿を書く為に、おそらく10年とか20年振りとかの気の遠くなり
そうな時間をおいたアルバム「ストレンジャー」を引っ張り出し、
本当に久々にターンテーブルにのせた。
そこには、あの当時感じとろうとした、未だ見ぬ大都会“ニューヨーク”
への、仄かな憧れを思い出させる音が一杯詰まっていた。
この前後の数年しか彼の活動振りを知らないが、ニューヨークのポップス・
シーンというと、真っ先にビリーの名前が出てくる。
我が日本で同じピアノ弾きというと、真っ先にKANの名前が浮かんでくる。
あのヒット曲の後に出した自信作「ゆっくり風呂につかりたい」を久々に
聴いてみた。

ホノボノとした作風のポップ・ソングが一杯詰まっていて、まだあの頃の
日本のポップスって良質だったんだ。と再認識。
と言う事で、のんびり湯につかりながら新年!なんていいな~。
BILLY JOEL / THE STRANGER (1977年度作品)
KAN / ゆっくり風呂につかりたい (1991年度作品)
Vol.81(2001年 01月号掲載)
サイモン&ガーファンクルに続いてビリーですか!
活動再開後、こちらも札幌に来ていたような・・・。
文章駄目ですね!相変わらず。
マディソン・スクエア・ガーデンの前にニューヨークって入れなきゃ!
「ストレンジャー」云々の件は、その曲がニューヨークを思い起こすほど、
一般に浸透している!みたいな事を書かなきゃ!と思う。
あと“。”とかも、ちょっとな~、ってところで使って・・・。
書いていったらキリがない。ホント、お粗末!
ま、人間って簡単には成長しない!って事なんでしょうか?
それとも才能の問題!
「ストレンジャー」は一世を風靡した感がある。
その時に聴き過ぎて、今はもう聴かなくなったのか、
他の作品同様、単なる過去のモノを聴いている余裕など無いくらい、
今、リリースされている最新の音楽状況をチェックするのに
忙しいのかは“?”なんですがね・・・。
そうそう、知り合いのアーティストで文中のビリーの引退コンサート
を観に、わざわざニューヨークまで行ったヤツがいた。
後日談で、強行スケジュールだったがゆえに、ナント、本番中、時差ボケで
殆ど寝ていた!と言う、笑うに笑えない話もあった。
KANさんは、ホント音楽好きらしく、札幌や東京の洋楽アーティスト
のライヴ会場で、良く見かけた。
KANさんに限らず、アーティストの方々はライヴを含めて勉強熱心。
音楽に関わっている皆さんが、ミンナそうだといいのに!
憧れのニューヨークの街の臭いを感じさせたビリーの歌。
柄にもなく、とあるピアニストのコンサートを観に出掛けた。
たまには、この手の静寂さを求められる(勿論オーディエンス側に)のも
いいもんだ。と、じっくりと鑑賞させて頂きました。
でぇ、コンサートの中程で、ちょっとお遊びっぽいコーナーがあって、
そこで一つの曲を国が違えば、きっとこんなアレンジになるのでは?
みたいな事を演っていたの。
確か曲は唱歌の「赤とんぼ」だったかな。それをフランスのパリなら
シャンソン風とかに演っちゃう訳。分かる?
メロディはあくまで「赤とんぼ」だからネ。
それでニューヨークになるとこうなるのでは。と演ったのが、あの印象的
な「ストレンジャー」のフレーズを土台にしたもの。
う~ん、もうすっかり忘れていたネ。その存在を。そうビリー・ジョエル
っていたな~。と。
ここんとこ全然名前も歌声も聴く事がないな~と思ったら、確か2~3年前
に、最後のライヴって事で、マディソン・スクエア・ガーデンで引退(!?)
コンサートを演った事を思い出した。
ニューヨークはブロンクス生まれの彼が注目を集めるようになったのが、
2枚目のソロ・アルバム「ピアノマン」をリリースした1973年の事。
70年代に入ってポップス・シーンに吹き荒れたシンガー・ソングライター
旋風のど真ん中いた訳だが、後々の印象としては、シンガー・ソングライター
と言うより、よりポップス派に近いシンガーのイメージが強い。
それはビリーを一躍世界的に有名人に仕立て上げた、前述のヒット曲
「ストレンジャー」以降の活躍振りが大きいからに違いない。
実際、73年の「ピアノマン」のリリース時は、評論家と熱心な音楽ファン
くらいしか、ビリー・ジョエルに注目しなかったのだから。
それから4年後、アルバム「THE STRANGER」がリリースされ、「ストレン
ジャー」と「素顔のままで」の2曲のビッグヒットが生まれビリーの
存在を決定付ける。

この原稿を書く為に、おそらく10年とか20年振りとかの気の遠くなり
そうな時間をおいたアルバム「ストレンジャー」を引っ張り出し、
本当に久々にターンテーブルにのせた。
そこには、あの当時感じとろうとした、未だ見ぬ大都会“ニューヨーク”
への、仄かな憧れを思い出させる音が一杯詰まっていた。
この前後の数年しか彼の活動振りを知らないが、ニューヨークのポップス・
シーンというと、真っ先にビリーの名前が出てくる。
我が日本で同じピアノ弾きというと、真っ先にKANの名前が浮かんでくる。
あのヒット曲の後に出した自信作「ゆっくり風呂につかりたい」を久々に
聴いてみた。

ホノボノとした作風のポップ・ソングが一杯詰まっていて、まだあの頃の
日本のポップスって良質だったんだ。と再認識。
と言う事で、のんびり湯につかりながら新年!なんていいな~。
BILLY JOEL / THE STRANGER (1977年度作品)
KAN / ゆっくり風呂につかりたい (1991年度作品)
2009年10月20日
名盤/ S&G × B&B
続・名盤を探しに行こう!/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.80(2000年12月号掲載)
「明日に架ける橋」は確かに年末に聴きたくなる曲だった事がある。
今年は思わぬところで、この人たちが札幌に来てくれて、嬉しい思い
をした方も多いでしょう。
いやはや年末の話ねぇ。
2000年も不景気だったんですね。
でも、今より酷くはなかった!
だって、今の方が現実的に不景気風に断然晒されているもんね。
こうなると、年を越せるんだろうか?この日本は!と思ってしまう。
ブレバタの「あの頃のまま」は、ホント、いい曲です。
たまに耳にすると、思わず聴き入ってしまう。
ユーミンって、こんな風にあっちこっちにいいものを残している。
さてさて、年末まであともう少し。
この再掲載、それまで完了するのかな・・・・・。
やっぱり1年の締めはこの歌なのかなっ?
何と早い事か!もう師走だ!1年がアッという間に過ぎてしまった。
(そりゃそうだ。これを書いているのは11月の頭で、まだ2カ月近く
残っているもん。)
コンビニじゃ、もうクリスマスケーキと年賀状の予約が始まっていたし、
某家電店では、来年の夏のボーナス商戦をやっていた。
おい!どうなっている日本。不景気で、この冬のボーナスも出ないかも
知れないのに、それを越えちゃってどうする。と、俺が心配しても
しょうがないか・・・・・。
でも本当に歳を取ると月日の経つのが早くて、1年なんて、小中学生の
頃の10分の1位のサイズに縮んじゃったんじゃないか、と思う程早い
もんね。
そんな話は置いておいて、皆さん、年末になると聴きたくなる音楽って
ないですか。浮かれる為に聴くクリスマス・ソングじゃなくて・・・。
俺の場合、何故かサイモン&ガーファンクルの「明日に架ける橋」なん
だよネ。
何処からともなく頭の中に、あのメロディが流れて来て、ジャケット
まで浮かんで来るんだから。
まぁ、逆に言うと、真夏の暑い時に聴きたいとは思わない曲とも言える。
あのゴスペルチックに唄い上げていくドラマチックな曲の構成が、
1年をとにかく無事に過ごしたクライマックスに相応しいのか、
それとも、詞に歌われている献身的な愛を求めたくなる時期なのか、
はたまたジャケットが醸し出す冬っぽい雰囲気がそうさせるのかは
分からないが、年末になると頭の中で鳴り出すのです。

この曲を含んだ同名のアルバム「明日に架ける橋」は1970年の2月に
リリースされ、グラミー賞の6部門を獲得する快挙を成し遂げた名盤。
その反面、サイモン&ガーファンクルの最後のスタジオ録音作としても
知られる1枚。
彼らにしてみると、すでに「サウンド・オヴ・サイレンス」で獲得した人気に
拍車を掛けたアルバムとも言える。
リリース当時、ビートルズと双璧をなす程「明日を架ける橋」をはじめ、
アルバムに収録された「コンドルは飛んで行く」「いとしのセシリア」
「ボクサー」そして「バイ・バイ・ラヴ」といったシングル曲が、頻繁に
ラジオから流れ、プロ、アマ問わず、多くの人達に唄われていた。
それらの曲は、今だに輝きを失う事なく、エヴァーグリーンとしてポップス
界に記録されている。
久々にアルバムを聴いてみても、その完成度の高さには頷いてしまう作品。
さて、このサイモン&ガーファンクルが歌詞に登場してくるのが、同じ
男性デュオ“ブレッド&バター”が唄う「あの頃のまま」。
ユーミンが作った名曲ですネ。この曲は。

もう彼らは活動していないのでしょうか。仲々のセンスで紡ぎ出すポップス
は捨て難かったのに。機会があれば、是非一聴を!
SIMON & GARFUNKLE / 明日に架ける橋(1970年度作品)
BREAD & BUTTER / Late Late Summer (1979年度作品)
Vol.80(2000年12月号掲載)
「明日に架ける橋」は確かに年末に聴きたくなる曲だった事がある。
今年は思わぬところで、この人たちが札幌に来てくれて、嬉しい思い
をした方も多いでしょう。
いやはや年末の話ねぇ。
2000年も不景気だったんですね。
でも、今より酷くはなかった!
だって、今の方が現実的に不景気風に断然晒されているもんね。
こうなると、年を越せるんだろうか?この日本は!と思ってしまう。
ブレバタの「あの頃のまま」は、ホント、いい曲です。
たまに耳にすると、思わず聴き入ってしまう。
ユーミンって、こんな風にあっちこっちにいいものを残している。
さてさて、年末まであともう少し。
この再掲載、それまで完了するのかな・・・・・。
やっぱり1年の締めはこの歌なのかなっ?
何と早い事か!もう師走だ!1年がアッという間に過ぎてしまった。
(そりゃそうだ。これを書いているのは11月の頭で、まだ2カ月近く
残っているもん。)
コンビニじゃ、もうクリスマスケーキと年賀状の予約が始まっていたし、
某家電店では、来年の夏のボーナス商戦をやっていた。
おい!どうなっている日本。不景気で、この冬のボーナスも出ないかも
知れないのに、それを越えちゃってどうする。と、俺が心配しても
しょうがないか・・・・・。
でも本当に歳を取ると月日の経つのが早くて、1年なんて、小中学生の
頃の10分の1位のサイズに縮んじゃったんじゃないか、と思う程早い
もんね。
そんな話は置いておいて、皆さん、年末になると聴きたくなる音楽って
ないですか。浮かれる為に聴くクリスマス・ソングじゃなくて・・・。
俺の場合、何故かサイモン&ガーファンクルの「明日に架ける橋」なん
だよネ。
何処からともなく頭の中に、あのメロディが流れて来て、ジャケット
まで浮かんで来るんだから。
まぁ、逆に言うと、真夏の暑い時に聴きたいとは思わない曲とも言える。
あのゴスペルチックに唄い上げていくドラマチックな曲の構成が、
1年をとにかく無事に過ごしたクライマックスに相応しいのか、
それとも、詞に歌われている献身的な愛を求めたくなる時期なのか、
はたまたジャケットが醸し出す冬っぽい雰囲気がそうさせるのかは
分からないが、年末になると頭の中で鳴り出すのです。

この曲を含んだ同名のアルバム「明日に架ける橋」は1970年の2月に
リリースされ、グラミー賞の6部門を獲得する快挙を成し遂げた名盤。
その反面、サイモン&ガーファンクルの最後のスタジオ録音作としても
知られる1枚。
彼らにしてみると、すでに「サウンド・オヴ・サイレンス」で獲得した人気に
拍車を掛けたアルバムとも言える。
リリース当時、ビートルズと双璧をなす程「明日を架ける橋」をはじめ、
アルバムに収録された「コンドルは飛んで行く」「いとしのセシリア」
「ボクサー」そして「バイ・バイ・ラヴ」といったシングル曲が、頻繁に
ラジオから流れ、プロ、アマ問わず、多くの人達に唄われていた。
それらの曲は、今だに輝きを失う事なく、エヴァーグリーンとしてポップス
界に記録されている。
久々にアルバムを聴いてみても、その完成度の高さには頷いてしまう作品。
さて、このサイモン&ガーファンクルが歌詞に登場してくるのが、同じ
男性デュオ“ブレッド&バター”が唄う「あの頃のまま」。
ユーミンが作った名曲ですネ。この曲は。

もう彼らは活動していないのでしょうか。仲々のセンスで紡ぎ出すポップス
は捨て難かったのに。機会があれば、是非一聴を!
SIMON & GARFUNKLE / 明日に架ける橋(1970年度作品)
BREAD & BUTTER / Late Late Summer (1979年度作品)
2009年10月14日
名盤/ O’Jays & ZOO
続・名盤を探しに行こう!/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.79(2000年 11月号掲載)
この時でZOOが10年目という事は、EXILEへと変身したHIROは
芸歴デビュー20周年という事ですか?
ZOOも成功したけど、今はもっと成功しているので、苦労知ら
ずって事なのかしらん。HIROは!
ダンス・シーンの先駆者とあるが、ナンカ、そこからTRF、そして
今のEXILEへと続いている辺り、ちょっと歴史を感じるな~。
珍しく日本の曲を名曲と言い切ってますな~。
それにしても、収録アルバム云々の記述がないが、それでいいのか!
と、突っ込みのひとつも入れたくなる。
フィリーサウンドね!確かに一世を風靡した感もありました。
フィリーと聞いて、やっぱ、あの当時聴いていた人は、真っ先に
TV番組“Soul Train”を思い出すのじゃないだろうか。
文中にある、あのテーマ曲を!
今と違って、動くアーティストを見る事が出来る、数少ない番組の
ひとつだった。
例え、それが“アテブリ”だったとしても・・・。
あれであの当時の黒人文化を、ちょっとだけ垣間見たような気に
なっていたのは、俺だけだったのかな?
もうお役目御免!70年代を飾ったあのお洒落なサウンド。
先月の冒頭で触れたシドニー・オリンピックは、皆さん充分に楽しん
だでしょうか?とは書いてみたものの、実はこれを書き出したのが9月末
なんです。
本来ならば締切を睨みつつ月始めに必死に書いているんですが、10月初旬
はMIX2000があって、とても原稿などまともに書いていられない可能性が
あるって事で、テレビのオリンピック放送を横目で見つつ、早々と書く
作戦をとった訳。
それにしてもシンクロの飛び込みとかケイリンとかトランポリンだとか、
知らないうちに競技になっていて、ちょっと新鮮な驚きでした。
まぁ、それはおいておいて、深まる秋に深いソウルっつうのは如何でした
でしょうか。
あんな風に亡くなった人の事ばっかり書きながら、ふと頭を過ったのが
“フィラデルフィア・ソウル(フィリー・ソウル)”の事。
今じゃ誰も語らない(ちょっと大袈裟か)、所謂葬り去られた感が強い
フィリー・ソウル。
フィラデルフィアは知っているけれども、そこにソウル・サウンドが
あったなんて知らないっすよネ。
簡単に言うと「70年代に流行った都会的なソウル・ミュージック」って
事になる。
それは60年代にはR&Bって言われた黒人音楽が、70年代にはソウルと
いう言葉で総称され、更に多様化する。
その中の一つに、このフィリー・ソウルがあった訳。
仕掛け人は、プロデュースや作曲などでコンビを組んでいたケニー・
ギャンブルとレオン・ハフ。
この二人が設立したレーベル“フィラデルフィア・インターナショナル・
レコード(PIR)”が、その中心地。
一口に都会的なソウルって言われても、今のコンテンポラリーなソウル
に耳慣れた人には、聴き分けられない。が、例えば「ソウル・トレイン
のテーマ」を思い出してくれれば、雰囲気は分かるはず。
その一世を風靡したPIRの代表作と言えばオージェイズの「裏切り者
のテーマ」がある。

我が日本でも本国に負けず劣らずのヒットを記録したので、聴き覚えが
ある方も多いだろうし、それなりのお年の方なら、きっとディスコで
ステップを踏んだであろう。
ソウルフルであるのは勿論の事、流麗なストリングスで装飾されたダンサブル
なサウンドは実にポップでお洒落で、都会の匂いを感じさせる。
濃い目のソウルはちょっとネ。な~んて言ってる方は、この辺から聴き
始めるのも良し。
我が国のダンス・シーンの先駆者“ZOO”の「Choo Choo Train」は、
そんなフィリー・サウンドの美味しい所を感じさせる名曲。

メンバーは各方面で活躍中とかで、今年はデビューから10年目との事。
あぁ~スキー・シーズン到来でっせ!
O’JAYS / 裏切り者のテーマ (1972年度作品)
ZOO / Present Pleasure (1991年度作品)
Vol.79(2000年 11月号掲載)
この時でZOOが10年目という事は、EXILEへと変身したHIROは
芸歴デビュー20周年という事ですか?
ZOOも成功したけど、今はもっと成功しているので、苦労知ら
ずって事なのかしらん。HIROは!
ダンス・シーンの先駆者とあるが、ナンカ、そこからTRF、そして
今のEXILEへと続いている辺り、ちょっと歴史を感じるな~。
珍しく日本の曲を名曲と言い切ってますな~。
それにしても、収録アルバム云々の記述がないが、それでいいのか!
と、突っ込みのひとつも入れたくなる。
フィリーサウンドね!確かに一世を風靡した感もありました。
フィリーと聞いて、やっぱ、あの当時聴いていた人は、真っ先に
TV番組“Soul Train”を思い出すのじゃないだろうか。
文中にある、あのテーマ曲を!
今と違って、動くアーティストを見る事が出来る、数少ない番組の
ひとつだった。
例え、それが“アテブリ”だったとしても・・・。
あれであの当時の黒人文化を、ちょっとだけ垣間見たような気に
なっていたのは、俺だけだったのかな?
もうお役目御免!70年代を飾ったあのお洒落なサウンド。
先月の冒頭で触れたシドニー・オリンピックは、皆さん充分に楽しん
だでしょうか?とは書いてみたものの、実はこれを書き出したのが9月末
なんです。
本来ならば締切を睨みつつ月始めに必死に書いているんですが、10月初旬
はMIX2000があって、とても原稿などまともに書いていられない可能性が
あるって事で、テレビのオリンピック放送を横目で見つつ、早々と書く
作戦をとった訳。
それにしてもシンクロの飛び込みとかケイリンとかトランポリンだとか、
知らないうちに競技になっていて、ちょっと新鮮な驚きでした。
まぁ、それはおいておいて、深まる秋に深いソウルっつうのは如何でした
でしょうか。
あんな風に亡くなった人の事ばっかり書きながら、ふと頭を過ったのが
“フィラデルフィア・ソウル(フィリー・ソウル)”の事。
今じゃ誰も語らない(ちょっと大袈裟か)、所謂葬り去られた感が強い
フィリー・ソウル。
フィラデルフィアは知っているけれども、そこにソウル・サウンドが
あったなんて知らないっすよネ。
簡単に言うと「70年代に流行った都会的なソウル・ミュージック」って
事になる。
それは60年代にはR&Bって言われた黒人音楽が、70年代にはソウルと
いう言葉で総称され、更に多様化する。
その中の一つに、このフィリー・ソウルがあった訳。
仕掛け人は、プロデュースや作曲などでコンビを組んでいたケニー・
ギャンブルとレオン・ハフ。
この二人が設立したレーベル“フィラデルフィア・インターナショナル・
レコード(PIR)”が、その中心地。
一口に都会的なソウルって言われても、今のコンテンポラリーなソウル
に耳慣れた人には、聴き分けられない。が、例えば「ソウル・トレイン
のテーマ」を思い出してくれれば、雰囲気は分かるはず。
その一世を風靡したPIRの代表作と言えばオージェイズの「裏切り者
のテーマ」がある。

我が日本でも本国に負けず劣らずのヒットを記録したので、聴き覚えが
ある方も多いだろうし、それなりのお年の方なら、きっとディスコで
ステップを踏んだであろう。
ソウルフルであるのは勿論の事、流麗なストリングスで装飾されたダンサブル
なサウンドは実にポップでお洒落で、都会の匂いを感じさせる。
濃い目のソウルはちょっとネ。な~んて言ってる方は、この辺から聴き
始めるのも良し。
我が国のダンス・シーンの先駆者“ZOO”の「Choo Choo Train」は、
そんなフィリー・サウンドの美味しい所を感じさせる名曲。

メンバーは各方面で活躍中とかで、今年はデビューから10年目との事。
あぁ~スキー・シーズン到来でっせ!
O’JAYS / 裏切り者のテーマ (1972年度作品)
ZOO / Present Pleasure (1991年度作品)
2009年10月07日
名盤/ Otis Redding & 小坂忠
続・名盤を探しに行こう!/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.78(2000年10月号掲載)
オリンピックと言えば、東京は残念でした。
とは言うものの、あまり東京でやる必要性みたいのを感じていな
かったので、個人的には残念とは思わなかった。
地球上の何処でやろうが、この発達した世の中、多少の不便を
我慢すれば、一応、リアルタイムで観る事が出来るのだから。
無理して、あの人が溢れている所で開催する事はない。
(音楽同様“生”に拘るなら別だけど・・・)
石原都知事は、これに使ったお金とか新銀行東京で失ったお金とかを、
どうやって回収するんだろう?
ツケは都民が全部被ってしまうんだろうか?
それにしても、スポーツ界と較べると、相変わらず音楽で世界に
出て行くのが難しい状況が続いている。
ちゃんとチャレンジしている日本人アーティストは居るのだけど、
なかなかいい結果が得られないようだ。
こじんまりと国内で競っている!とあるが、近頃のオリコンチャート
をみていると、シングルなんて酷いもんだ。
もはや音楽じゃないようなモノが一杯溢れている。
こんなのと比較されるまっとうな音楽をやっている方々の心中は
如何に?と思ってしまう。
売れているものの目安としてのチャートだから、世間一般の目が行く
のは分るが、どこかでこれと戦わないと陽の目をみる事が出来ないと
なると、なんかな・・・・・。
閑話休題。
オーティスが生きていたら、アル・グリーンなどのベテラン同様、
時々、凄くいい作品を出し続けていた事だろう。
ま、こんな“タラレバ”の話はしてもしょうがないのは分って
書いています。ハイ!
この人が生きていたら、R&Bシーンはどうなっていただろう?
“頑張れ!日本”と、日々テレビ中継に夢中になり、俄日本人魂を
発揮し続けたオリンピックの季節は、皆さんどう過ごされたでしょうか?
やっぱりこんな風に、ここぞとばかりに日本人選手の活躍振りに一喜一憂
してたんでしょうネ。(多分、私もそうなっていりはず)
まぁ、そんな事はどうでもいいんですけど、所謂、こうした国際的な場で、
勝ち負けは別として、世界と競え合えるスポーツっていいなっ~と。
それに較べると音楽って、こじんまりと国内で競い合って、セールスが
どうだぁ!とか言っている訳だもんネ。
野球にしろ、サッカーにしろ、ゴルフにしろ、海外で立派にやっている
日本人が大勢いるのをみると、もっと世界を相手にするミュージシャン
が出ていても可笑しくないのにな~と、つくづく思ってしまう今日この頃
です。
ってな話は置いといて、先月の亡くなったアーティストの話を今月も引き
ずります。
忘れちゃいかん!偉大なソウル・シンガーを!そう!オーティス・
レディングを。
熱心な読者(いるのかな?)には、先頃のO.V.ライトの項で、その名前
が出てきたのでご記憶の方も多いとは思うのですが・・・。
そのオーティス、日本でも「ドッグ・オヴ・ザ・ベイ」が大ヒットして
一躍有名になったけど、時すでに遅しで、この時点で飛行機事故で他界
していたのです。
サザン・ソウルを代表するシンガー“オーティス・レディング”が本当に
評価されたのが、この事故死の後。
当時ロック狂いだった筆者にも、数多くのロック・ミュージシャンの口
から発せられるオーティスの名前は、興味を抱く対象には充分な存在で
あり、後追いでその偉業を確かめる事になる。
そのオーティスの3枚目のアルバム「オーティス・ブルー」は、彼の
代表曲「リスペクト」を、そして同じく多くのカバー・ヴァージョン
が生まれた「愛しすぎて」を収録した1枚。
他にもストーンズの「サティスファクション」やサム・クックのナンバー
をカバーした「チェンジ・ゴナ・カム」や「シェイク」などを収録。
彼の名唱をたっぷりと味わえるアルバムに仕上がっている。
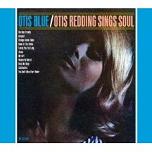
そんなオーティスを聴いていたかどうかは分からないが、このアルバム
から10年後に発表された小坂忠の「ほうろう」は、実にソウルフルな
唄声を聴く事が出来る作品。

それは当然ながら、よりアップ・トゥ・デイトなサウンドに包まれた
ものだが、ゴスペルチックに唄われる「機関車」などには、今だに身震い
を覚える。こんなのをもっともっと薄めると、今流行の和製R&Bに
なるのかしらん。
などと思ってみました。
“秋深し 深いソウルが 身に染みる。”な~んてネ。お粗末でした。
Otis Redding / OTIS BLUE(1965年度作品)
小坂忠 / ほうろう (1975年度作品)
Vol.78(2000年10月号掲載)
オリンピックと言えば、東京は残念でした。
とは言うものの、あまり東京でやる必要性みたいのを感じていな
かったので、個人的には残念とは思わなかった。
地球上の何処でやろうが、この発達した世の中、多少の不便を
我慢すれば、一応、リアルタイムで観る事が出来るのだから。
無理して、あの人が溢れている所で開催する事はない。
(音楽同様“生”に拘るなら別だけど・・・)
石原都知事は、これに使ったお金とか新銀行東京で失ったお金とかを、
どうやって回収するんだろう?
ツケは都民が全部被ってしまうんだろうか?
それにしても、スポーツ界と較べると、相変わらず音楽で世界に
出て行くのが難しい状況が続いている。
ちゃんとチャレンジしている日本人アーティストは居るのだけど、
なかなかいい結果が得られないようだ。
こじんまりと国内で競っている!とあるが、近頃のオリコンチャート
をみていると、シングルなんて酷いもんだ。
もはや音楽じゃないようなモノが一杯溢れている。
こんなのと比較されるまっとうな音楽をやっている方々の心中は
如何に?と思ってしまう。
売れているものの目安としてのチャートだから、世間一般の目が行く
のは分るが、どこかでこれと戦わないと陽の目をみる事が出来ないと
なると、なんかな・・・・・。
閑話休題。
オーティスが生きていたら、アル・グリーンなどのベテラン同様、
時々、凄くいい作品を出し続けていた事だろう。
ま、こんな“タラレバ”の話はしてもしょうがないのは分って
書いています。ハイ!
この人が生きていたら、R&Bシーンはどうなっていただろう?
“頑張れ!日本”と、日々テレビ中継に夢中になり、俄日本人魂を
発揮し続けたオリンピックの季節は、皆さんどう過ごされたでしょうか?
やっぱりこんな風に、ここぞとばかりに日本人選手の活躍振りに一喜一憂
してたんでしょうネ。(多分、私もそうなっていりはず)
まぁ、そんな事はどうでもいいんですけど、所謂、こうした国際的な場で、
勝ち負けは別として、世界と競え合えるスポーツっていいなっ~と。
それに較べると音楽って、こじんまりと国内で競い合って、セールスが
どうだぁ!とか言っている訳だもんネ。
野球にしろ、サッカーにしろ、ゴルフにしろ、海外で立派にやっている
日本人が大勢いるのをみると、もっと世界を相手にするミュージシャン
が出ていても可笑しくないのにな~と、つくづく思ってしまう今日この頃
です。
ってな話は置いといて、先月の亡くなったアーティストの話を今月も引き
ずります。
忘れちゃいかん!偉大なソウル・シンガーを!そう!オーティス・
レディングを。
熱心な読者(いるのかな?)には、先頃のO.V.ライトの項で、その名前
が出てきたのでご記憶の方も多いとは思うのですが・・・。
そのオーティス、日本でも「ドッグ・オヴ・ザ・ベイ」が大ヒットして
一躍有名になったけど、時すでに遅しで、この時点で飛行機事故で他界
していたのです。
サザン・ソウルを代表するシンガー“オーティス・レディング”が本当に
評価されたのが、この事故死の後。
当時ロック狂いだった筆者にも、数多くのロック・ミュージシャンの口
から発せられるオーティスの名前は、興味を抱く対象には充分な存在で
あり、後追いでその偉業を確かめる事になる。
そのオーティスの3枚目のアルバム「オーティス・ブルー」は、彼の
代表曲「リスペクト」を、そして同じく多くのカバー・ヴァージョン
が生まれた「愛しすぎて」を収録した1枚。
他にもストーンズの「サティスファクション」やサム・クックのナンバー
をカバーした「チェンジ・ゴナ・カム」や「シェイク」などを収録。
彼の名唱をたっぷりと味わえるアルバムに仕上がっている。
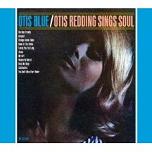
そんなオーティスを聴いていたかどうかは分からないが、このアルバム
から10年後に発表された小坂忠の「ほうろう」は、実にソウルフルな
唄声を聴く事が出来る作品。

それは当然ながら、よりアップ・トゥ・デイトなサウンドに包まれた
ものだが、ゴスペルチックに唄われる「機関車」などには、今だに身震い
を覚える。こんなのをもっともっと薄めると、今流行の和製R&Bに
なるのかしらん。
などと思ってみました。
“秋深し 深いソウルが 身に染みる。”な~んてネ。お粗末でした。
Otis Redding / OTIS BLUE(1965年度作品)
小坂忠 / ほうろう (1975年度作品)
2009年09月24日
名盤/J.Joplin & カルメン・マキ& OZ
続・名盤を探しに行こう!/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.77(2000年 9月号掲載)
どんとの訃報について書いてあるが、今年の忌野さんは、後々まで、
ナンダカンダと追悼の形で色々とマスコミなどが騒いでいる。
ここまで愛されていたとは知らなかった。
まぁ、そこにどれだけの愛情があるのかは分らないけど、清志郎に限らず
死後に起きるこうした現象をみるたびに、生前にもっとやっておけよ!
と言いたくなる。
そうすれば、多少は日本の音楽状況が良くなっていたかも知れないのに・・・。
それにしても個人的には、未だに進んで聴く事が出来ない!ので、
もう暫くは封印しておきます。
ウッドストック40周年という事で、関連商品が出回っているが、
この間、CD SHOPでみたジェファーソン・エアプレーンの映像のヨーマ・
コーコウネンが、ちらっと観ただけど、相当格好良かった!
あれは発掘映像なのかな?
ディレクターズカットのDVDを持っていても、もう何年も観ていないので、
すっかり忘れています。
ジャニスも、今はほとんど聴かなくなったアーティストの一人。
たまに引っ張りだすのは、このアルバムじゃなくて「Kozmic Blues」の方!
遠くなった70年代のロックは、未だ掘り出しモノ多し!
こりゃ、尽きる事がないかも!とも思ってしまう今日この頃です。
70年代は遠くなりけり。そして、ジャニスは静かに眠り続ける。
某音楽雑誌に“どんと”の大特集が載っていた。
今年の1月に、彼の訃報を聞いた時は全然信じられなかったし、
今だにその実感が沸いていない身には、ようやくそれが現実だと
認識させるのに充分な内容だったし、アーティスト“どんと”が、
こんなにも多くの方々から愛され、支持されていたという事実が
分かって嬉しかった。
この名盤~でもローザ・ルクセンブルグ、そしてボ・ガンボスと、
彼が歩んだ道の一端を紹介する事が出来たが、何せCDが発売されて
いなかったりで、読者の皆さんには御迷惑をかけた。
が、これを機に、全て再リリースという、素晴らしい事態となったので、
今のうちに、是非手に入れておいて下さい。
そう言えば、以前、某アーティストのラジオ番組の手伝いをしていた時に、
毎年この時期(これを書いているのはお盆に入る直前です)になると、
決まって死んだアーティストの特集をやっていた事を思い出した。
そして曲がオンエアーされている間、良く話したのが“このアーティスト
が生きていたら、どうなっていたと思う?”なんて事。
そんな話の筆頭に出てくるアーティストと言えば、ジミ・ヘンドリックス
でありジム・モリソンでありジョン・レノンであり、そしてジャニス・
ジョプリンであった。
この他にも大勢のアーティストが亡くなっているが、やはり主役となり
うるのは、僕らがポピュラー・ミュージックを聴き始めた60年代に、
もっとも刺激的な音楽を届けてくれた人達だった。
そして、前述したアーティストの中で、唯一この名盤~に登場していない
のがジャニス・ジョプリンだ。
先日、季節柄か彼女の「SUMMERTIME」がラジオから流れてきて、一瞬
聴きいってしまった。
今でも身に染みる熱唱だ。と、つくづく思った。
彼女自身のオリジナル・アルバムは、たったの2枚しか残っていない。
(死後に出たライヴ盤やサントラ盤は除く)。そして、彼女の名声を
高めたビッグ・ブラザー&ザ・ホールディング・カンパニーの「Cheap
Thrill」を加えても3枚っきり。
一気に全部聴いて欲しい枚数だけれども、初心者にはヒット曲「MOVE
OVER」や「ME & BOGGY McGEE」が収録された遺作「PEARL」がお薦めか。

まぁ、そこから遡って「Cheap Thrill」に辿り着いてくれれば、ジャニス
も喜んでくれるだろう。
そんな世界中のロック・シンガーを目指す女性達が憧れたジャニス同様、
70年代の日本で、ロック・シンガーを目指す女性達の憧れの的だったのが
カルメン・マキ。

その神秘的な瞳を隠すロングヘアーを振り乱して唄う姿は、今でも胸に
焼き付いています。
勿論、名曲「私は風」は大好きです!
Janis Joplin / Pearl (1971年度作品)
カルメン・マキ & OZ / カルメン・マキ & Z(1975年度作品)
Vol.77(2000年 9月号掲載)
どんとの訃報について書いてあるが、今年の忌野さんは、後々まで、
ナンダカンダと追悼の形で色々とマスコミなどが騒いでいる。
ここまで愛されていたとは知らなかった。
まぁ、そこにどれだけの愛情があるのかは分らないけど、清志郎に限らず
死後に起きるこうした現象をみるたびに、生前にもっとやっておけよ!
と言いたくなる。
そうすれば、多少は日本の音楽状況が良くなっていたかも知れないのに・・・。
それにしても個人的には、未だに進んで聴く事が出来ない!ので、
もう暫くは封印しておきます。
ウッドストック40周年という事で、関連商品が出回っているが、
この間、CD SHOPでみたジェファーソン・エアプレーンの映像のヨーマ・
コーコウネンが、ちらっと観ただけど、相当格好良かった!
あれは発掘映像なのかな?
ディレクターズカットのDVDを持っていても、もう何年も観ていないので、
すっかり忘れています。
ジャニスも、今はほとんど聴かなくなったアーティストの一人。
たまに引っ張りだすのは、このアルバムじゃなくて「Kozmic Blues」の方!
遠くなった70年代のロックは、未だ掘り出しモノ多し!
こりゃ、尽きる事がないかも!とも思ってしまう今日この頃です。
70年代は遠くなりけり。そして、ジャニスは静かに眠り続ける。
某音楽雑誌に“どんと”の大特集が載っていた。
今年の1月に、彼の訃報を聞いた時は全然信じられなかったし、
今だにその実感が沸いていない身には、ようやくそれが現実だと
認識させるのに充分な内容だったし、アーティスト“どんと”が、
こんなにも多くの方々から愛され、支持されていたという事実が
分かって嬉しかった。
この名盤~でもローザ・ルクセンブルグ、そしてボ・ガンボスと、
彼が歩んだ道の一端を紹介する事が出来たが、何せCDが発売されて
いなかったりで、読者の皆さんには御迷惑をかけた。
が、これを機に、全て再リリースという、素晴らしい事態となったので、
今のうちに、是非手に入れておいて下さい。
そう言えば、以前、某アーティストのラジオ番組の手伝いをしていた時に、
毎年この時期(これを書いているのはお盆に入る直前です)になると、
決まって死んだアーティストの特集をやっていた事を思い出した。
そして曲がオンエアーされている間、良く話したのが“このアーティスト
が生きていたら、どうなっていたと思う?”なんて事。
そんな話の筆頭に出てくるアーティストと言えば、ジミ・ヘンドリックス
でありジム・モリソンでありジョン・レノンであり、そしてジャニス・
ジョプリンであった。
この他にも大勢のアーティストが亡くなっているが、やはり主役となり
うるのは、僕らがポピュラー・ミュージックを聴き始めた60年代に、
もっとも刺激的な音楽を届けてくれた人達だった。
そして、前述したアーティストの中で、唯一この名盤~に登場していない
のがジャニス・ジョプリンだ。
先日、季節柄か彼女の「SUMMERTIME」がラジオから流れてきて、一瞬
聴きいってしまった。
今でも身に染みる熱唱だ。と、つくづく思った。
彼女自身のオリジナル・アルバムは、たったの2枚しか残っていない。
(死後に出たライヴ盤やサントラ盤は除く)。そして、彼女の名声を
高めたビッグ・ブラザー&ザ・ホールディング・カンパニーの「Cheap
Thrill」を加えても3枚っきり。
一気に全部聴いて欲しい枚数だけれども、初心者にはヒット曲「MOVE
OVER」や「ME & BOGGY McGEE」が収録された遺作「PEARL」がお薦めか。

まぁ、そこから遡って「Cheap Thrill」に辿り着いてくれれば、ジャニス
も喜んでくれるだろう。
そんな世界中のロック・シンガーを目指す女性達が憧れたジャニス同様、
70年代の日本で、ロック・シンガーを目指す女性達の憧れの的だったのが
カルメン・マキ。

その神秘的な瞳を隠すロングヘアーを振り乱して唄う姿は、今でも胸に
焼き付いています。
勿論、名曲「私は風」は大好きです!
Janis Joplin / Pearl (1971年度作品)
カルメン・マキ & OZ / カルメン・マキ & Z(1975年度作品)
2009年09月16日
名盤/ LENINE & 宮沢和史
続・名盤を探しに行こう!/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.76(2000年8月号掲載)
外タレのライヴねぇ~。
札幌には、ホント、旬な来日ミュージシャンが来る事が少ない。
近頃だと、oasisなんかは良く来てくれたな~って感じ。
これは集客が出来ないからなのか?
それともいい会場が無いからなのか?
ま、移動費など、ほかの都市と較べたら高くつくから、動員が出来
ないと招聘元は辛いって現実があるのは分るが・・・。
ベックは、狙いでやっていたのかどうか知らないが、何か学園祭の
出し物みたいなライヴだったように記憶している。(失礼かな?)
未だに音楽に刺激を求めているのは変らないんだけど、なかなか、
これってモノには遭遇しない。
(俺の聴き方が足りないのは知りつつ書いてるんだけれど)
すでに世界中から寄せ集めるだけ集めてしまったのでしょうかね。
チョッピリ刺激的な音楽を求めている方は、一度聴いてみなさい。
久し振りに外タレのライヴを観た。
ひとつは札幌でも観る事が出来た“BECK”。そしてもうひとつは東京で
観た“LENINE(レニーニ)”。
思い起こせば、外タレのライヴを観るのは‘98年のストーンズの
“BRIDGES TO BABYLON 1998”以来2年振り。
こんな洋楽の文章を書いている割には、お粗末な勉強振りなので、
反省しなければ!と思いつつ、所謂、ライヴを観たいと思わせるタマ
が居ない洋楽界が悪い。と、開き直る。
それにしても、ベックにしてもレニーニにしても、その本国を含めた
活躍振りをみると、実に“旬”なアーティスト。
特に札幌には、そのアーティストが活躍中の旬な時期のリアル・タイム
で来る事が少ないので、ベックのライヴを観れた事はラッキーとしか
言いようがない。
そんな訳で、如何にもベックの話になりそうだが、今月はもう一人の方、
そう、レニーニについて書こうと思っている。
レニーニにと言っても、多分、多くの読者の方はご存じないと思うが、
今やブラジルのコンンテンポラリー・ミュージック界の第一人者。と
言っても過言ではない存在。
ブラジルと言えば、当然サンバやボッサノヴァが真先に頭に浮かぶのが、
音楽ファンには一般的だろうが、あの国にも、我が日本同様に、
世界のポピュラー・ミュージックの流れに乗った音楽がたくさんある。
それがロックの潮流であったり、ヒップホップであったりブラック・
ミュージックであったりと、影響を受けているものは種々雑多。
そして彼らが作りだすものは、それらとブラジル音楽をミックスした、
究めて優れたハイブリッドな音楽。
そんな音楽を作っている一人にレニーニがいる。
彼が1997年に発表したアルバム「未知との遭遇の日々」には、そんな
時代性をたっぷりと吸収した音楽が詰まっている。

ロックやファンク、そしてヒップホップをぶち込んで、ブラジル音楽が
本来持っているパーカッシヴさと融合したサウンドは、充分に刺激的で、
それこそ未知との遭遇だ。
この刺激がクセになってハマッてしまった人も多いハズ。
ライヴでは、思いのほかファンク色の強い演奏を連発し驚いたが、そう
言えば、もう一人の近代ブラジル音楽の担い手カルリーニョス・ブラウン
が最近のインタビューで、ブラジルには元々ファンクのような音楽があった
・・・・・云々という記事を思い出し、何ら不自然な事じゃないな~と納得。
そんな訳で、音楽の刺激が欲しい方は、是非一度、このレニーニを聴いて
みて下さい。
そんなブラジルに逸早く目をつけたのが宮沢和史。
彼の熱病的ブラジルへの憧れを詰め込んだのがアルバム「アフロ病」。

レニーニもブラウンも参加し、一人の日本人をバックアップ。
仲々の聴き応えの作品に仕上がっている。
因みにこのアルバムのオリジナルは、ポルトガル語ヴァージョンの方です。
念の為!
LENINE / 未知との遭遇の日々(1997年度作品)
宮沢和史 / アフロ病(アフロシック) (1998年度作品)
Vol.76(2000年8月号掲載)
外タレのライヴねぇ~。
札幌には、ホント、旬な来日ミュージシャンが来る事が少ない。
近頃だと、oasisなんかは良く来てくれたな~って感じ。
これは集客が出来ないからなのか?
それともいい会場が無いからなのか?
ま、移動費など、ほかの都市と較べたら高くつくから、動員が出来
ないと招聘元は辛いって現実があるのは分るが・・・。
ベックは、狙いでやっていたのかどうか知らないが、何か学園祭の
出し物みたいなライヴだったように記憶している。(失礼かな?)
未だに音楽に刺激を求めているのは変らないんだけど、なかなか、
これってモノには遭遇しない。
(俺の聴き方が足りないのは知りつつ書いてるんだけれど)
すでに世界中から寄せ集めるだけ集めてしまったのでしょうかね。
チョッピリ刺激的な音楽を求めている方は、一度聴いてみなさい。
久し振りに外タレのライヴを観た。
ひとつは札幌でも観る事が出来た“BECK”。そしてもうひとつは東京で
観た“LENINE(レニーニ)”。
思い起こせば、外タレのライヴを観るのは‘98年のストーンズの
“BRIDGES TO BABYLON 1998”以来2年振り。
こんな洋楽の文章を書いている割には、お粗末な勉強振りなので、
反省しなければ!と思いつつ、所謂、ライヴを観たいと思わせるタマ
が居ない洋楽界が悪い。と、開き直る。
それにしても、ベックにしてもレニーニにしても、その本国を含めた
活躍振りをみると、実に“旬”なアーティスト。
特に札幌には、そのアーティストが活躍中の旬な時期のリアル・タイム
で来る事が少ないので、ベックのライヴを観れた事はラッキーとしか
言いようがない。
そんな訳で、如何にもベックの話になりそうだが、今月はもう一人の方、
そう、レニーニについて書こうと思っている。
レニーニにと言っても、多分、多くの読者の方はご存じないと思うが、
今やブラジルのコンンテンポラリー・ミュージック界の第一人者。と
言っても過言ではない存在。
ブラジルと言えば、当然サンバやボッサノヴァが真先に頭に浮かぶのが、
音楽ファンには一般的だろうが、あの国にも、我が日本同様に、
世界のポピュラー・ミュージックの流れに乗った音楽がたくさんある。
それがロックの潮流であったり、ヒップホップであったりブラック・
ミュージックであったりと、影響を受けているものは種々雑多。
そして彼らが作りだすものは、それらとブラジル音楽をミックスした、
究めて優れたハイブリッドな音楽。
そんな音楽を作っている一人にレニーニがいる。
彼が1997年に発表したアルバム「未知との遭遇の日々」には、そんな
時代性をたっぷりと吸収した音楽が詰まっている。

ロックやファンク、そしてヒップホップをぶち込んで、ブラジル音楽が
本来持っているパーカッシヴさと融合したサウンドは、充分に刺激的で、
それこそ未知との遭遇だ。
この刺激がクセになってハマッてしまった人も多いハズ。
ライヴでは、思いのほかファンク色の強い演奏を連発し驚いたが、そう
言えば、もう一人の近代ブラジル音楽の担い手カルリーニョス・ブラウン
が最近のインタビューで、ブラジルには元々ファンクのような音楽があった
・・・・・云々という記事を思い出し、何ら不自然な事じゃないな~と納得。
そんな訳で、音楽の刺激が欲しい方は、是非一度、このレニーニを聴いて
みて下さい。
そんなブラジルに逸早く目をつけたのが宮沢和史。
彼の熱病的ブラジルへの憧れを詰め込んだのがアルバム「アフロ病」。

レニーニもブラウンも参加し、一人の日本人をバックアップ。
仲々の聴き応えの作品に仕上がっている。
因みにこのアルバムのオリジナルは、ポルトガル語ヴァージョンの方です。
念の為!
LENINE / 未知との遭遇の日々(1997年度作品)
宮沢和史 / アフロ病(アフロシック) (1998年度作品)
2009年09月10日
名盤/ Emeline Michel & ピラニアンズ
続・名盤を探しに行こう!/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.75(2000年 7月号掲載)
エメリーヌは去年、輸入盤で新作が出回っているのを雑誌記事で
読んで買いに行ったが、札幌でも東京でも探し出す事が出来なかった。
しょうがないから、それ以前に出たアルバムの国内盤がたまたま
あったので、それを手にいれた。
その後も、その新作を探してはいるが、なかなかなくて、未だ手に
していない。
きっと入荷が少ないのだろう。
で、このアルバムは、ホントに思い出したように、今も時々聴いている。
国内の某女性アーティストとあるが、誰だったっけ?
思い出す事が出来ません。
自分で書いておきながら、こうだもんね。無責任極まりない!
なんか凄く気になる。
廃盤云々で言うと、この時点でも廃盤だったと思うけど、現在も
同じく廃盤状態。
但し、活動を再開しているピラニアンズは、ベスト盤か何かに
このアルバムの収録曲が入っているので、そちらを手に入れれば
聴く事が出来る。っつうか、ネット上で試聴可能。
またエメリーヌは、同じくネット上で、「FLANM」のPVが観る事が
出来たりして、なんだかんだ言っても便利な世の中ですわ!
真夏じゃなくて初夏に心地好いハイチの女性シンガー。
あれやこれやと考えているうちに締め切りが迫ってしまった。
久し振りに味わう強迫観念に、ちょっと参ったな~。ってのが正直な
ところ。
何だかんだと言っても、ここんとこ快調に出て来た、書く切っ掛けが
出て来ないんです。
こういう時には季節物に頼るのが一番などと勝手に思い込み、安易な
がらも思いを巡らす。
初夏の気持ち良い風を受けながら聴く!ってのをテーマにしたらどう
でしょう。と、楽をしたい気持ちを応援する悪魔が囁く。
締め切りという崖っぷちに立たされた者にとって、その囁きは悪魔
じゃなくて天使のそれだ。(音楽の神様、ごめんなさい!)
そんな訳で、初夏の云々で出て来たのが、もう何年も前に愛聴して
いたエメリーヌ・ミッシェルという女性シンガーの「フラーム」という
アルバム。

よく自分でも、こんな名前を覚えていたなと感心しつつCDを捜すと、
懐かしくも愛嬌のある笑顔が映ったジャケットが出て来た。
ほんお3~4年前の作品と思っていたが、10年も前の作品だった。
参考までにライナーを読むと、この作品の前年に「コンビット~
バーニング・リズム・オブ・ハイチ」というハイチのポップ・ミュー
ジックのコンピレーション・アルバムがリリースされ、その編集を
手掛けたのが、映画監督のジョナサン・デミだと言う。
映画監督などに興味はないが、デミの名前にこんなところで出会うとは
思わなかった。
何の事はない、先月ここでちょっとだけ触れたトーキング・ヘッズの
映画「ストップ・メイキング・センス」の監督だ。
さて、普段まったく縁のないであろうハイチのポップ・ミュージック
=ヘイシャン・ミュージック。
遡ればワールド・ミュージックが最初に盛り上がった頃に、俄に注目
された事もあって、それがメインストリームになる事はなかった。
ハイチのポップ・ミュージックについて詳しく語る事が出来なくて申し訳
ないが、ダンス的要素が強いのは確か。
このエメリーヌのアルバムは、そんな要素が強いが、それは決して汗だく
で踊るそれではなく、どちらかと言うと、軽やかにステップを踏む感じ。
タイトル・チューンは、近年のかの地の代表的なリズム“ズーク”で、
他のどの曲も南国的な臭いが薫り、彼女の瑞々しい唄声ともに、心の中に
涼風を送ってくれる。
でぇ、国内に目を向けると、某女性アーティストのあのアルバム。って
事で、捜したが見つからず。
ピンチーヒッターで、手近にあったピラニアンズの“サボテンマン”を
引っ張り出してみた。

仲々、この時期にはいい感じ。ってなところで紙数が尽きた。
尚、時間が無かったので調べる余裕無し。両作品共、発売時のCDナンバー
などを記した。廃盤になっていたらゴメンナサイ!
Emeline Michel / FLANM (1990年度作品)
ピラニアンズ / サボテンマン(1994年度作品)
Vol.75(2000年 7月号掲載)
エメリーヌは去年、輸入盤で新作が出回っているのを雑誌記事で
読んで買いに行ったが、札幌でも東京でも探し出す事が出来なかった。
しょうがないから、それ以前に出たアルバムの国内盤がたまたま
あったので、それを手にいれた。
その後も、その新作を探してはいるが、なかなかなくて、未だ手に
していない。
きっと入荷が少ないのだろう。
で、このアルバムは、ホントに思い出したように、今も時々聴いている。
国内の某女性アーティストとあるが、誰だったっけ?
思い出す事が出来ません。
自分で書いておきながら、こうだもんね。無責任極まりない!
なんか凄く気になる。
廃盤云々で言うと、この時点でも廃盤だったと思うけど、現在も
同じく廃盤状態。
但し、活動を再開しているピラニアンズは、ベスト盤か何かに
このアルバムの収録曲が入っているので、そちらを手に入れれば
聴く事が出来る。っつうか、ネット上で試聴可能。
またエメリーヌは、同じくネット上で、「FLANM」のPVが観る事が
出来たりして、なんだかんだ言っても便利な世の中ですわ!
真夏じゃなくて初夏に心地好いハイチの女性シンガー。
あれやこれやと考えているうちに締め切りが迫ってしまった。
久し振りに味わう強迫観念に、ちょっと参ったな~。ってのが正直な
ところ。
何だかんだと言っても、ここんとこ快調に出て来た、書く切っ掛けが
出て来ないんです。
こういう時には季節物に頼るのが一番などと勝手に思い込み、安易な
がらも思いを巡らす。
初夏の気持ち良い風を受けながら聴く!ってのをテーマにしたらどう
でしょう。と、楽をしたい気持ちを応援する悪魔が囁く。
締め切りという崖っぷちに立たされた者にとって、その囁きは悪魔
じゃなくて天使のそれだ。(音楽の神様、ごめんなさい!)
そんな訳で、初夏の云々で出て来たのが、もう何年も前に愛聴して
いたエメリーヌ・ミッシェルという女性シンガーの「フラーム」という
アルバム。

よく自分でも、こんな名前を覚えていたなと感心しつつCDを捜すと、
懐かしくも愛嬌のある笑顔が映ったジャケットが出て来た。
ほんお3~4年前の作品と思っていたが、10年も前の作品だった。
参考までにライナーを読むと、この作品の前年に「コンビット~
バーニング・リズム・オブ・ハイチ」というハイチのポップ・ミュー
ジックのコンピレーション・アルバムがリリースされ、その編集を
手掛けたのが、映画監督のジョナサン・デミだと言う。
映画監督などに興味はないが、デミの名前にこんなところで出会うとは
思わなかった。
何の事はない、先月ここでちょっとだけ触れたトーキング・ヘッズの
映画「ストップ・メイキング・センス」の監督だ。
さて、普段まったく縁のないであろうハイチのポップ・ミュージック
=ヘイシャン・ミュージック。
遡ればワールド・ミュージックが最初に盛り上がった頃に、俄に注目
された事もあって、それがメインストリームになる事はなかった。
ハイチのポップ・ミュージックについて詳しく語る事が出来なくて申し訳
ないが、ダンス的要素が強いのは確か。
このエメリーヌのアルバムは、そんな要素が強いが、それは決して汗だく
で踊るそれではなく、どちらかと言うと、軽やかにステップを踏む感じ。
タイトル・チューンは、近年のかの地の代表的なリズム“ズーク”で、
他のどの曲も南国的な臭いが薫り、彼女の瑞々しい唄声ともに、心の中に
涼風を送ってくれる。
でぇ、国内に目を向けると、某女性アーティストのあのアルバム。って
事で、捜したが見つからず。
ピンチーヒッターで、手近にあったピラニアンズの“サボテンマン”を
引っ張り出してみた。

仲々、この時期にはいい感じ。ってなところで紙数が尽きた。
尚、時間が無かったので調べる余裕無し。両作品共、発売時のCDナンバー
などを記した。廃盤になっていたらゴメンナサイ!
Emeline Michel / FLANM (1990年度作品)
ピラニアンズ / サボテンマン(1994年度作品)
2009年09月04日
名盤/John Lennon
続・名盤を探しに行こう!/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.74(2000年6月号掲載)
凄いタイミングで、このキャッチコピーだ事。
巡り合わせと言うか、何と言うか分りませんが、ビートルズの
リマスターCDの発売が直前に迫って、これが出てくるとは・・・。
人が迷っているってぇ時に、こういう背中を押すような言葉は効く!
間違いなくそうなんだから、それは分っているって!
さてさて、ヘッズの本来持っているものを表現するのに16年って、
それはどんな劇場のシステムだっけ?
もうすっかり忘れてしまいました。
映画と言えば、ストーンズの「SHINE A LIGHT」は、IMAXシアター用
もあるんだっけ?
何か、インタビューでそのような事を言っていたような気がする。
IMAXは、札幌ファクトリーにあった時に観たけれど、あれだけ
スクリーンがデカイと、どこをどう観ていいやら。
デカけりゃいいってもんじゃない!のを実体験した訳だけど、あるなら、
それで観たい気もする。
で、驚異のサウンド蘇生術とあるが、ホント、良くなって蘇ってしまう
から困る。(困るってぇのは、買いたくなっちゃうから)
中には、あの当時意図したサウンドはこうだったなどと言うアーティスト
もいたりして、じゃあ、長年聴いていたのは、志し半ばって訳!とも聞き
返したくなる。(テクノロジー的な問題だからしょうがないけど・・・)
頭を柔らかくして、新しいオリジナルと考えるのもありかと思うが・・・、
ま、深く考えないで「いいか!」と言う事にしましょ。
オリジナルに拘る事なかれ!素直にいい音なんだから・・・・・
トーキング・ヘッズの名作映画「STOP MAKING SENSE」が、デジタル
処理したニュープリントでこの春上映されている。
この作品が発表されたのが84年の事。当時、公開されたものの、このデジ
タル処理のプリントとサウンドに対応した劇場がなく、デビット・バーン
にとっては不本意な公開のされ方をされていただけに、ようやく納得出来る
状態になった訳だ。
それにしても、その作品本来が持っているモノを表現するのに16年も
掛ってしまうなんて・・・・・。
そう言えば、CD化による過去の作品のリミックス&デジタル・リマスタリング
には目を!いやいや耳を見張るものがある。
CDというパッケージに見合った録音技術なりテクノロジーがなかった時代
のものを、それに見合うように作り直す。と言ったら語弊があるだろうか。
まぁ、簡単に言ってしまうと、多分そういう事なんだろうけど。
そしてそれと同時に、当時録音はしていたんだけれどミックスの際に
カットされた音なんかもあって、それを新たに加えたり別の楽器に差し替え
たり、はたまた音そのものを抜いたりとかする作業なんかが、ここで言う
リミックスって訳。
そのリミックス&デジタル・リマスタリングで、つい先頃話題となったのが
ジョン・レノンの名盤「imagine」。

2000年に因んでミレミアム・エディションと名付けられたこの1枚、本当
に音がいい。
当然「Yellow Submarine Songtrack」が出た時に、それは予想出来た事
だけど・・・・・、実際に聴いて、改めてそう実感したのは事実。
とは言うものの、オリジナルはアナログ盤しか持ってない身なので、
CD音源の比較対象はベスト盤に収められた曲のみなんですが・・・・・。
まぁ、今の音になっているという点では、非常にジョンのヴォーカルを
含めて各楽器の音像がはっきりしている事かな。
CDについているオノ・ヨーコのインタビューによると、リミックスを
手掛けたピーター・コビンが“制作当時の精神から離れず、音を良く
する”的な作業を良くやってくれた。みたいな事が書かれていた。
まぁ、これ程のアルバムになってしまうと、原曲を壊すような下手な
リミックスなんて出来っこないしネ。
「imagine」はじめ「Jealous Guy」[Oh My Love]などなど、全10曲どれが
欠けてもアルバム「imagine」が成立しない程、今では一つの塊と化した
この作品。
躊躇していたアナログ盤から買い直しするも良し、初めてジョンの音楽に
触れる為に買うも良し、是非宇多田ヒカル同様、日本の一家に一枚な
アルバムにして下さい。
という訳で、賛否両論はあるものの、今後もリミックス&デジタル・
リマスタリングという驚異のサウンド蘇生術を施した名盤が多数リリース
されると思うので、それはそれで楽しみな今日この頃なのです。
John Lennon / imagine (1971年度作品)
Vol.74(2000年6月号掲載)
凄いタイミングで、このキャッチコピーだ事。
巡り合わせと言うか、何と言うか分りませんが、ビートルズの
リマスターCDの発売が直前に迫って、これが出てくるとは・・・。
人が迷っているってぇ時に、こういう背中を押すような言葉は効く!
間違いなくそうなんだから、それは分っているって!
さてさて、ヘッズの本来持っているものを表現するのに16年って、
それはどんな劇場のシステムだっけ?
もうすっかり忘れてしまいました。
映画と言えば、ストーンズの「SHINE A LIGHT」は、IMAXシアター用
もあるんだっけ?
何か、インタビューでそのような事を言っていたような気がする。
IMAXは、札幌ファクトリーにあった時に観たけれど、あれだけ
スクリーンがデカイと、どこをどう観ていいやら。
デカけりゃいいってもんじゃない!のを実体験した訳だけど、あるなら、
それで観たい気もする。
で、驚異のサウンド蘇生術とあるが、ホント、良くなって蘇ってしまう
から困る。(困るってぇのは、買いたくなっちゃうから)
中には、あの当時意図したサウンドはこうだったなどと言うアーティスト
もいたりして、じゃあ、長年聴いていたのは、志し半ばって訳!とも聞き
返したくなる。(テクノロジー的な問題だからしょうがないけど・・・)
頭を柔らかくして、新しいオリジナルと考えるのもありかと思うが・・・、
ま、深く考えないで「いいか!」と言う事にしましょ。
オリジナルに拘る事なかれ!素直にいい音なんだから・・・・・
トーキング・ヘッズの名作映画「STOP MAKING SENSE」が、デジタル
処理したニュープリントでこの春上映されている。
この作品が発表されたのが84年の事。当時、公開されたものの、このデジ
タル処理のプリントとサウンドに対応した劇場がなく、デビット・バーン
にとっては不本意な公開のされ方をされていただけに、ようやく納得出来る
状態になった訳だ。
それにしても、その作品本来が持っているモノを表現するのに16年も
掛ってしまうなんて・・・・・。
そう言えば、CD化による過去の作品のリミックス&デジタル・リマスタリング
には目を!いやいや耳を見張るものがある。
CDというパッケージに見合った録音技術なりテクノロジーがなかった時代
のものを、それに見合うように作り直す。と言ったら語弊があるだろうか。
まぁ、簡単に言ってしまうと、多分そういう事なんだろうけど。
そしてそれと同時に、当時録音はしていたんだけれどミックスの際に
カットされた音なんかもあって、それを新たに加えたり別の楽器に差し替え
たり、はたまた音そのものを抜いたりとかする作業なんかが、ここで言う
リミックスって訳。
そのリミックス&デジタル・リマスタリングで、つい先頃話題となったのが
ジョン・レノンの名盤「imagine」。

2000年に因んでミレミアム・エディションと名付けられたこの1枚、本当
に音がいい。
当然「Yellow Submarine Songtrack」が出た時に、それは予想出来た事
だけど・・・・・、実際に聴いて、改めてそう実感したのは事実。
とは言うものの、オリジナルはアナログ盤しか持ってない身なので、
CD音源の比較対象はベスト盤に収められた曲のみなんですが・・・・・。
まぁ、今の音になっているという点では、非常にジョンのヴォーカルを
含めて各楽器の音像がはっきりしている事かな。
CDについているオノ・ヨーコのインタビューによると、リミックスを
手掛けたピーター・コビンが“制作当時の精神から離れず、音を良く
する”的な作業を良くやってくれた。みたいな事が書かれていた。
まぁ、これ程のアルバムになってしまうと、原曲を壊すような下手な
リミックスなんて出来っこないしネ。
「imagine」はじめ「Jealous Guy」[Oh My Love]などなど、全10曲どれが
欠けてもアルバム「imagine」が成立しない程、今では一つの塊と化した
この作品。
躊躇していたアナログ盤から買い直しするも良し、初めてジョンの音楽に
触れる為に買うも良し、是非宇多田ヒカル同様、日本の一家に一枚な
アルバムにして下さい。
という訳で、賛否両論はあるものの、今後もリミックス&デジタル・
リマスタリングという驚異のサウンド蘇生術を施した名盤が多数リリース
されると思うので、それはそれで楽しみな今日この頃なのです。
John Lennon / imagine (1971年度作品)
2009年09月03日
名盤/ O.V. WRIGHT & S・Delicious
続・名盤を探しに行こう!/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.73(2000年 5月号掲載)
この間、某中古盤屋でJunior Walkerの2枚組アンソロジーを
廉価で見つけました。
安かった理由は、盤面が反っていた為で、検盤した時に“これは?”
とも思いましたが、昔、このように反っていたアナログ盤を、
寝押しで直した事を思い出し、改めて買う事にしたのです。
寝押しなんて、今の若い人達は知らないよね。
(お父さんお母さん、いやいや爺さん婆さんに聞いてみたら・・・)
ま、なんともアナログでアナクロな事でしょ。(笑)
と言う訳で、寝押しして、ある程度直ったら聴くとします。これは!
ここで書かれている、体系的に音楽を聴いていく!という事が、
近頃は、よっぽどの音楽好きじゃないとしないようで、何とも探究心
の無さ!
色々なアーティストが影響を受けたり、良く聴いている音楽なんかを、
雑誌のインタビュー記事などで読むと、無性にそれが聴きたくなる!
聴いたら聴いたで、色々と勉強になる事が多い。
その連続が結局は自分の音楽生活の財産になる訳で、それはそれで
楽しい事なんだけどな~。
ま、いいか!
アメリカンコーヒーがいつの間にか駆逐された(!?)ように、濃いものの
復権はあるのか?
なんて全然関係ない事を引き合いに出しちゃ駄目で、ようするに、
近年の薄味な洗練されたソウルに変って、たまにはドップリと!
っていうのもいいのでは!って事です。
濃いめのソウル・ミュージックはお好きですか?
前号で、日本のロック・シーンでは欠かせない存在“はっぴいえんど”
について、全くと言ってもいい程触れれなくて、ちょっと消化不良。
また何かの機会に彼らについては書きます。
それで“後追いとなったバッファロー~”云々は、結局、体系的に好き
なミュージシャンを追及すると、必ず出てくる問題で、リアル・タイム
で聴けなかった悔しさや、もっと早くに知っていたら的残念さの度合い
が、何とも、それはそれでいいのです。(勿論、次のバネになる。って
いう意味で。)まぁ、そんな事を繰り返して豊かな音楽生活が築き上がる
のです。な~んてネ。
でぇ、私の場合、スタートラインが“THE ROLLING STONES”なもんで、
やたらこの“後追い”を、後々まで鍛え上げられた訳でありまして、
・・・・・(分かるひとには分かりますよネ。)で、説明は省きます。
そんな彼らが初期にカバーしていたR&Bに「That’s how strong my
Love is」ッつう曲がありまして、結構お気に入りなんで調べたらオー
ティス・レディングに辿り付いた訳。ストーンズは、他にもオーティス
作品をカバーしていたから、こりゃまとめて勉強せねばいかん。など
と思いつつ日々を過ごすうちに、かの「That’s how strong my love
is」のオリジナルはO.V.ライトなる人物、という事実が分かった。
うら若き俺には、そんなマニアックな人まで知りません。って事で、
半ば諦めていた時に突如と現れたのが、O.V.ライトの「INTO SOMETHING」
というアルバム。

メンフィス・ソウルの名門“HI RECORDS”が再開後にリリースしたのが
この作品。
当時、発売と同時に、全ソウル・ファンが輸入盤屋に押し掛け買い求めた。
(ちょっと大袈裟!)って位、噂が噂を呼んだヤツ。
件の「That’s how~」は、「GOD BLESSED OUR LOVE~男が女を愛する時~
That’s how~」のメドレー形式で再演されており、それこそサザン・
ソウルの名バラードの名唄って訳。
この作品で、どっぷりとサザン・ソウルの魅力の虜になった人も多いはずで、
この後、O.V.をはじめ多数のサザン系の作品が、日本の市場に出廻った
ように記憶している。
さて、この当時、今のような全国的な人気を誇っていなかったR&Bが、
唯一熱かった地域が関西方面。
ブルーズをはじめ、浪速系の黒っぽい旋風が全国を駆け巡った中、真打ち
的に登場したのがスターキング・デリシャス。
そんな彼らの唯一アルバムが、ようやくCD化された。

タイフーン・レディ“大上留利子”の見事な唄いっぷりと、ブラス・セク
ションを加えたバンドによる大きなうねりのある演奏。そして何よりも、
商売っ気無しのブラック・ミュージックへのリスペクト精神を感じさせる
事。これがソウルで、今時の雨後の竹の子状態の魂は別もん、とは訳が
違う。という事で、機会を作って聴いてみて下さい。
勿論、「That’s how~」演ってまんねん。
O.V.WRIGHT / INTO SOMETHING(CAN’T SHAKE LOOSE) (1977年度作品)
Starking Delicious / Starking Delicious(1977年度作品)
Vol.73(2000年 5月号掲載)
この間、某中古盤屋でJunior Walkerの2枚組アンソロジーを
廉価で見つけました。
安かった理由は、盤面が反っていた為で、検盤した時に“これは?”
とも思いましたが、昔、このように反っていたアナログ盤を、
寝押しで直した事を思い出し、改めて買う事にしたのです。
寝押しなんて、今の若い人達は知らないよね。
(お父さんお母さん、いやいや爺さん婆さんに聞いてみたら・・・)
ま、なんともアナログでアナクロな事でしょ。(笑)
と言う訳で、寝押しして、ある程度直ったら聴くとします。これは!
ここで書かれている、体系的に音楽を聴いていく!という事が、
近頃は、よっぽどの音楽好きじゃないとしないようで、何とも探究心
の無さ!
色々なアーティストが影響を受けたり、良く聴いている音楽なんかを、
雑誌のインタビュー記事などで読むと、無性にそれが聴きたくなる!
聴いたら聴いたで、色々と勉強になる事が多い。
その連続が結局は自分の音楽生活の財産になる訳で、それはそれで
楽しい事なんだけどな~。
ま、いいか!
アメリカンコーヒーがいつの間にか駆逐された(!?)ように、濃いものの
復権はあるのか?
なんて全然関係ない事を引き合いに出しちゃ駄目で、ようするに、
近年の薄味な洗練されたソウルに変って、たまにはドップリと!
っていうのもいいのでは!って事です。
濃いめのソウル・ミュージックはお好きですか?
前号で、日本のロック・シーンでは欠かせない存在“はっぴいえんど”
について、全くと言ってもいい程触れれなくて、ちょっと消化不良。
また何かの機会に彼らについては書きます。
それで“後追いとなったバッファロー~”云々は、結局、体系的に好き
なミュージシャンを追及すると、必ず出てくる問題で、リアル・タイム
で聴けなかった悔しさや、もっと早くに知っていたら的残念さの度合い
が、何とも、それはそれでいいのです。(勿論、次のバネになる。って
いう意味で。)まぁ、そんな事を繰り返して豊かな音楽生活が築き上がる
のです。な~んてネ。
でぇ、私の場合、スタートラインが“THE ROLLING STONES”なもんで、
やたらこの“後追い”を、後々まで鍛え上げられた訳でありまして、
・・・・・(分かるひとには分かりますよネ。)で、説明は省きます。
そんな彼らが初期にカバーしていたR&Bに「That’s how strong my
Love is」ッつう曲がありまして、結構お気に入りなんで調べたらオー
ティス・レディングに辿り付いた訳。ストーンズは、他にもオーティス
作品をカバーしていたから、こりゃまとめて勉強せねばいかん。など
と思いつつ日々を過ごすうちに、かの「That’s how strong my love
is」のオリジナルはO.V.ライトなる人物、という事実が分かった。
うら若き俺には、そんなマニアックな人まで知りません。って事で、
半ば諦めていた時に突如と現れたのが、O.V.ライトの「INTO SOMETHING」
というアルバム。

メンフィス・ソウルの名門“HI RECORDS”が再開後にリリースしたのが
この作品。
当時、発売と同時に、全ソウル・ファンが輸入盤屋に押し掛け買い求めた。
(ちょっと大袈裟!)って位、噂が噂を呼んだヤツ。
件の「That’s how~」は、「GOD BLESSED OUR LOVE~男が女を愛する時~
That’s how~」のメドレー形式で再演されており、それこそサザン・
ソウルの名バラードの名唄って訳。
この作品で、どっぷりとサザン・ソウルの魅力の虜になった人も多いはずで、
この後、O.V.をはじめ多数のサザン系の作品が、日本の市場に出廻った
ように記憶している。
さて、この当時、今のような全国的な人気を誇っていなかったR&Bが、
唯一熱かった地域が関西方面。
ブルーズをはじめ、浪速系の黒っぽい旋風が全国を駆け巡った中、真打ち
的に登場したのがスターキング・デリシャス。
そんな彼らの唯一アルバムが、ようやくCD化された。

タイフーン・レディ“大上留利子”の見事な唄いっぷりと、ブラス・セク
ションを加えたバンドによる大きなうねりのある演奏。そして何よりも、
商売っ気無しのブラック・ミュージックへのリスペクト精神を感じさせる
事。これがソウルで、今時の雨後の竹の子状態の魂は別もん、とは訳が
違う。という事で、機会を作って聴いてみて下さい。
勿論、「That’s how~」演ってまんねん。
O.V.WRIGHT / INTO SOMETHING(CAN’T SHAKE LOOSE) (1977年度作品)
Starking Delicious / Starking Delicious(1977年度作品)
2009年09月01日
名盤/ B・Springfield & はっぴいえんど
続・名盤を探しに行こう!/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.72(2000年4月号掲載)
音楽映画と言えば、近頃はWoodstockが40周年って事で、未公開
シーンがふんだんに盛り込まれた記念盤がリリースされたんじゃな
かったっけ!
ニール・ヤングのBOX同様、気にはなるが、なかなか買うまでには
至らない。
結局ニール・ヤングは、何年か前の来日の際に観る事が出来たので
いいのですが、バッファローは、何年か前のBOXを手に入れたが、
意外と聴いていないのが正直なところ。
同じく、ここで載り上げ「ちゃんとデビュー作から聴きましょう!」
なんて書いている割には“はっぴいえんど”も、紙ジャケットに
なった時にまとめて買ったが、あまり聴き込むって事をしなかった。
あぁ~、単なる物欲から買っているだけじゃん!って思われるのが
嫌だね。
気持ち的には、いつもたっぷりと聴くぞ!って買って帰るのだけど、
なんせ色々と誘惑が多いから・・・。
そんな中、この間書いたザ・ビートルズのリマスターCDも、買ったは
いいが・・・って事になりそうで、相変わらず迷っているのですが、
気持ちはどんどん“買わなくちゃ!”って方になっています。
70年代のカリフォルニア・サウンドの源とも言えるバッファロー達の
存在
当たらないと定評がある音楽映画だが、この号を読んでいる頃には、
札幌でも公開され、思わぬヒットになっているかも知れない「ブエナ・
ビスタ・ソシアル・クラブ」。
まだ観ていないけど、いくつかの映画評では上々の評判なので“思わぬ
ヒット”なんて書いたけど、ひょっとして、ひょっとしているかも知れ
ない。ちょっとした楽しみです。ハイ。
この「ブエナ・ビスタ~」同様、前評判が良かった音楽映画に、以前に
この欄でも触れたニール・ヤングの「YEAR OF THE HORSE」があったが、
あれは結局、予想通りハズレだったんですよネ。
昨年末、その「YEAR OF THE HORSE」がレンタル・ビデオ屋に並んでいる
のを発見。う~ん、ビデオになっても借手はいるんかい?と思っていたら、
結構レンタル中の札が付いていてひと安心。
是非是非、お近くのレンタル屋でお手にとって下さい。ついでに勢いで
借りて観て下さい。
さて、そのニール・ヤング。前号のクラプトンとは対象的に、今だに
追っ掛けているミュージシャンの一人。
新譜が出たといってはCD SHOPに走り、来日情報には聞き耳を立てる。
ってな具合で、未だ観ぬ“生”の姿を夢見てやまぬロックン・ローラー
の一人。
そのニールが、故郷カナダから旅立ちロサンジェルスで再会したスティ
ーヴ・スティルスと共に始動させたのが“Buffalo Springfield”なる
伝説のバンド。
何故伝説かと言うと、2年弱の活動期間で、残したアルバムが3枚、
トップ10ヒットが「For What It’s Worth」が1曲。ってな感じで、
仲々立派な成績なんだけど、そのあまりにも短い活動期間故に、
バッファロー~の良さに気付いた時は、すでに空中分解って訳。
本国アメリカでもそんな感じだから、我が日本なんて悲惨なもの。当然、
活動期のリアル・タイムでのリリースは無し。僕の記憶が正しければ、
国内盤がリリースされたのはバッファロー~から派生したC,S,N&Yが
爆発的に売れた後の70年代に入ってからの事。
彼らが残した僅か3枚の中の2作目に当たる「Again」は、発売当時、
ビートルズの「サージェント・ペッパーズ~」的な位置付けで語られた
作品。

個人的には、それこそC,S,N&Y以降に辿りついた音楽だけに思い入れは
いま一つだが、リアル・タイムで聴いていたら相当ショックを受けたに
違いない作品。
あの有名な「Satisfaction」のギター・リフを拝借した「MR.SOUL」はじめ
「BLUEBIRD」「ROCK&ROLL WOMAN」など超有名曲揃いだが、何と言っても
ニールとスティーヴンの存在感が凄いし、後のPOCOへと繋がるリッチー・
ヒューレーが居た事も見逃せないなど、70年代のカリフォルニア・サウンド
の事を思うと胸が熱くなる1枚。
紙数が尽きてしまったが、このバッファロー~の影響の下始動したのが、
あの“はっぴいえんど”。

日本のロックを語る上ではずせない人達。ちゃんとデビュー作「はっぴい
えんど」から聴きましょ。
Buffalo Springfield / Again (1967年度作品)
はっぴいえんど / はっぴいえんど(1970年度作品)
Vol.72(2000年4月号掲載)
音楽映画と言えば、近頃はWoodstockが40周年って事で、未公開
シーンがふんだんに盛り込まれた記念盤がリリースされたんじゃな
かったっけ!
ニール・ヤングのBOX同様、気にはなるが、なかなか買うまでには
至らない。
結局ニール・ヤングは、何年か前の来日の際に観る事が出来たので
いいのですが、バッファローは、何年か前のBOXを手に入れたが、
意外と聴いていないのが正直なところ。
同じく、ここで載り上げ「ちゃんとデビュー作から聴きましょう!」
なんて書いている割には“はっぴいえんど”も、紙ジャケットに
なった時にまとめて買ったが、あまり聴き込むって事をしなかった。
あぁ~、単なる物欲から買っているだけじゃん!って思われるのが
嫌だね。
気持ち的には、いつもたっぷりと聴くぞ!って買って帰るのだけど、
なんせ色々と誘惑が多いから・・・。
そんな中、この間書いたザ・ビートルズのリマスターCDも、買ったは
いいが・・・って事になりそうで、相変わらず迷っているのですが、
気持ちはどんどん“買わなくちゃ!”って方になっています。
70年代のカリフォルニア・サウンドの源とも言えるバッファロー達の
存在
当たらないと定評がある音楽映画だが、この号を読んでいる頃には、
札幌でも公開され、思わぬヒットになっているかも知れない「ブエナ・
ビスタ・ソシアル・クラブ」。
まだ観ていないけど、いくつかの映画評では上々の評判なので“思わぬ
ヒット”なんて書いたけど、ひょっとして、ひょっとしているかも知れ
ない。ちょっとした楽しみです。ハイ。
この「ブエナ・ビスタ~」同様、前評判が良かった音楽映画に、以前に
この欄でも触れたニール・ヤングの「YEAR OF THE HORSE」があったが、
あれは結局、予想通りハズレだったんですよネ。
昨年末、その「YEAR OF THE HORSE」がレンタル・ビデオ屋に並んでいる
のを発見。う~ん、ビデオになっても借手はいるんかい?と思っていたら、
結構レンタル中の札が付いていてひと安心。
是非是非、お近くのレンタル屋でお手にとって下さい。ついでに勢いで
借りて観て下さい。
さて、そのニール・ヤング。前号のクラプトンとは対象的に、今だに
追っ掛けているミュージシャンの一人。
新譜が出たといってはCD SHOPに走り、来日情報には聞き耳を立てる。
ってな具合で、未だ観ぬ“生”の姿を夢見てやまぬロックン・ローラー
の一人。
そのニールが、故郷カナダから旅立ちロサンジェルスで再会したスティ
ーヴ・スティルスと共に始動させたのが“Buffalo Springfield”なる
伝説のバンド。
何故伝説かと言うと、2年弱の活動期間で、残したアルバムが3枚、
トップ10ヒットが「For What It’s Worth」が1曲。ってな感じで、
仲々立派な成績なんだけど、そのあまりにも短い活動期間故に、
バッファロー~の良さに気付いた時は、すでに空中分解って訳。
本国アメリカでもそんな感じだから、我が日本なんて悲惨なもの。当然、
活動期のリアル・タイムでのリリースは無し。僕の記憶が正しければ、
国内盤がリリースされたのはバッファロー~から派生したC,S,N&Yが
爆発的に売れた後の70年代に入ってからの事。
彼らが残した僅か3枚の中の2作目に当たる「Again」は、発売当時、
ビートルズの「サージェント・ペッパーズ~」的な位置付けで語られた
作品。

個人的には、それこそC,S,N&Y以降に辿りついた音楽だけに思い入れは
いま一つだが、リアル・タイムで聴いていたら相当ショックを受けたに
違いない作品。
あの有名な「Satisfaction」のギター・リフを拝借した「MR.SOUL」はじめ
「BLUEBIRD」「ROCK&ROLL WOMAN」など超有名曲揃いだが、何と言っても
ニールとスティーヴンの存在感が凄いし、後のPOCOへと繋がるリッチー・
ヒューレーが居た事も見逃せないなど、70年代のカリフォルニア・サウンド
の事を思うと胸が熱くなる1枚。
紙数が尽きてしまったが、このバッファロー~の影響の下始動したのが、
あの“はっぴいえんど”。

日本のロックを語る上ではずせない人達。ちゃんとデビュー作「はっぴい
えんど」から聴きましょ。
Buffalo Springfield / Again (1967年度作品)
はっぴいえんど / はっぴいえんど(1970年度作品)
2009年08月10日
名盤/ Allman Brothers & IDLEWILD
続・名盤を探しに行こう!/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.71(2000年 3月号掲載)
まだまだ誤字が多いね。
「正誤表をつけなくちゃ!」なんて気になってしまう。
エリック・クラプトンも、先日札幌まで来てくれたS&Gも、
全く今では興味がない。
南部と言えばディレイニー&ボニーで、そしてこのオールマンに
代表されるサザーンロックですな。
あぁ~サザーンソウルってぇのもあるか・・・。
オールマンのこの「Brothers & Sisters」は、ホントいいアルバムだ。
未だに時折引っ張り出して聴いているし、他のアルバムも、これまた
ホントに回数は少ないが引っ張り出しては聴いている。
この当時、それこそ沢山のサザーンロックのバンドが紹介されたけど、
それらのバンドの皆さんは、今はどうしている事やら。
あの広いアメリカ大陸の事だから、どこかで未だにライヴ三昧な
ツアーをしているか、或いはとっくに解散しているか・・・。
ただ、その情報が日本に入ってきていないだけかも、とも思ってしま
います。
近頃のサザーンロック事情は知らないけど、名前が聞こえてくる
Derek Trucksは、ちょっとは気にはなってます。
サザン・ロックを聴くなら、ここから始まってもいいかも・・・・・。
どうもエリック・クラプトン好きと思われている節がある。
サンプル盤を頂いたり、最新情報を頂いたりと、こちらが要求も
していない事が、好意的(!?)にレコード会社の方から昨年何度かあった。
クラプトン好きと思われる原因として、この名盤~にクラプトンが最多
出場アーティストって事も起因しているのかも知れない。
“CREAM”“Derek & The Dominos”そしてソロ時代と、ほぼ彼の代表的な
節目の作品を載り上げてきた訳だから・・・・・。
まぁ、今だにそれらの作品を聴く事もあるのだけれども、基本的には、
今じゃ、どうでもいいアーティストなんです。
興味がないと言うか、新譜とかはラジオでたまに聴く程度で充分だし、
なしてはライヴなんかは、お金を出してまで観たいと思わないんです。
ベスト盤が、日本で100万枚売れたと聞いて“クラプトンも美空ひばり
同様、国民的歌手になってしまった”と思ったのは僕だけでしょうか。
な~んてネ。(クラプトン・ファンよ怒らないで!)
さて、そんなクラプトンが残してくれた収穫の一つにアメリカ南部の
音楽があります。
それこそ“Derek & The Dominos”の章で触れたスワンプやサザン・ロック
などだが、取り分け「LAYLA」での共演で、その名を広く知られるように
なったデュアン・オールマンの存在を知らしめた功績は大きい。その
デュアンが率いるバンド“ALLMAN BROTHERS BAND”は、サザン・ロックを
代表するバンドの一つでもあるし、70年代のアメリカン・ロック全盛時には、
“THE BAND”“GRATEFUL DEAD”と共に、三大アメリカン・バンドと
賞されたバンドだ。
そのデュアンを不幸にも交通事故で失い、またベーシストのべりー・
オークリーまでも同じく事故で失うという二重苦を乗り越えて発表した
アルバム「Brothers and Sisters」は、彼らを代表すると言うより、
サザン・ロックを代表するアルバムだ。
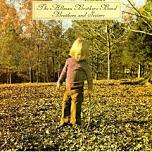
カントリー・フレイヴァー溢れるヒット曲「Ramblin’Man」に後押しされ
アルバムは全米で大ヒット。
それを受けて我が日本でも人気が爆発し、それまで燻っていたサザン・
ロック自体の人気にまで火を付けて立役者的存在と言っても過言ではない。
サザン・ロックが本来持っていた泥臭ささやブルーズ・ロック的な重々
しさを、より洗練したものへ昇華しつつ、バンドが持っているダイナミズム
を失わない。そんな意気込みがアルバム全体から感じ取れる。
楽器一つ一つが躍動感に溢れ、バンド全体が唄っているかのような
「Jessica」や「Southbound」など、今聴いても興奮する材料が一杯だ。
サザン・ロックはここから入ってもいいかもネ!
そんな当時、日本でもサザン・ロックを目指したバンドは多数いたが、
オールマンのアルバム・タイトルを、そのまま頂いた“IDOLWILD SOUTH”の
唯一の作品「KEEP ON TRUKIN’」が先頃CD化された。
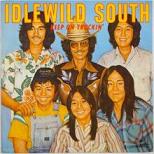
目指すはALLMAN BROTHERS BAND(!?)。小細工なしの、憧れと愛情に
溢れた演奏振りが微笑ましいアルバムだ。
併せて聴いてみては・・・・・。
The Allman Brothers Band / Brothers and Sisters (1973年度作品)
IDLEWILD SOUTH / KEEP ON TRUCKIN’(1999年度作品)
Vol.71(2000年 3月号掲載)
まだまだ誤字が多いね。
「正誤表をつけなくちゃ!」なんて気になってしまう。
エリック・クラプトンも、先日札幌まで来てくれたS&Gも、
全く今では興味がない。
南部と言えばディレイニー&ボニーで、そしてこのオールマンに
代表されるサザーンロックですな。
あぁ~サザーンソウルってぇのもあるか・・・。
オールマンのこの「Brothers & Sisters」は、ホントいいアルバムだ。
未だに時折引っ張り出して聴いているし、他のアルバムも、これまた
ホントに回数は少ないが引っ張り出しては聴いている。
この当時、それこそ沢山のサザーンロックのバンドが紹介されたけど、
それらのバンドの皆さんは、今はどうしている事やら。
あの広いアメリカ大陸の事だから、どこかで未だにライヴ三昧な
ツアーをしているか、或いはとっくに解散しているか・・・。
ただ、その情報が日本に入ってきていないだけかも、とも思ってしま
います。
近頃のサザーンロック事情は知らないけど、名前が聞こえてくる
Derek Trucksは、ちょっとは気にはなってます。
サザン・ロックを聴くなら、ここから始まってもいいかも・・・・・。
どうもエリック・クラプトン好きと思われている節がある。
サンプル盤を頂いたり、最新情報を頂いたりと、こちらが要求も
していない事が、好意的(!?)にレコード会社の方から昨年何度かあった。
クラプトン好きと思われる原因として、この名盤~にクラプトンが最多
出場アーティストって事も起因しているのかも知れない。
“CREAM”“Derek & The Dominos”そしてソロ時代と、ほぼ彼の代表的な
節目の作品を載り上げてきた訳だから・・・・・。
まぁ、今だにそれらの作品を聴く事もあるのだけれども、基本的には、
今じゃ、どうでもいいアーティストなんです。
興味がないと言うか、新譜とかはラジオでたまに聴く程度で充分だし、
なしてはライヴなんかは、お金を出してまで観たいと思わないんです。
ベスト盤が、日本で100万枚売れたと聞いて“クラプトンも美空ひばり
同様、国民的歌手になってしまった”と思ったのは僕だけでしょうか。
な~んてネ。(クラプトン・ファンよ怒らないで!)
さて、そんなクラプトンが残してくれた収穫の一つにアメリカ南部の
音楽があります。
それこそ“Derek & The Dominos”の章で触れたスワンプやサザン・ロック
などだが、取り分け「LAYLA」での共演で、その名を広く知られるように
なったデュアン・オールマンの存在を知らしめた功績は大きい。その
デュアンが率いるバンド“ALLMAN BROTHERS BAND”は、サザン・ロックを
代表するバンドの一つでもあるし、70年代のアメリカン・ロック全盛時には、
“THE BAND”“GRATEFUL DEAD”と共に、三大アメリカン・バンドと
賞されたバンドだ。
そのデュアンを不幸にも交通事故で失い、またベーシストのべりー・
オークリーまでも同じく事故で失うという二重苦を乗り越えて発表した
アルバム「Brothers and Sisters」は、彼らを代表すると言うより、
サザン・ロックを代表するアルバムだ。
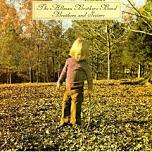
カントリー・フレイヴァー溢れるヒット曲「Ramblin’Man」に後押しされ
アルバムは全米で大ヒット。
それを受けて我が日本でも人気が爆発し、それまで燻っていたサザン・
ロック自体の人気にまで火を付けて立役者的存在と言っても過言ではない。
サザン・ロックが本来持っていた泥臭ささやブルーズ・ロック的な重々
しさを、より洗練したものへ昇華しつつ、バンドが持っているダイナミズム
を失わない。そんな意気込みがアルバム全体から感じ取れる。
楽器一つ一つが躍動感に溢れ、バンド全体が唄っているかのような
「Jessica」や「Southbound」など、今聴いても興奮する材料が一杯だ。
サザン・ロックはここから入ってもいいかもネ!
そんな当時、日本でもサザン・ロックを目指したバンドは多数いたが、
オールマンのアルバム・タイトルを、そのまま頂いた“IDOLWILD SOUTH”の
唯一の作品「KEEP ON TRUKIN’」が先頃CD化された。
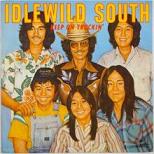
目指すはALLMAN BROTHERS BAND(!?)。小細工なしの、憧れと愛情に
溢れた演奏振りが微笑ましいアルバムだ。
併せて聴いてみては・・・・・。
The Allman Brothers Band / Brothers and Sisters (1973年度作品)
IDLEWILD SOUTH / KEEP ON TRUCKIN’(1999年度作品)
2009年07月17日
名盤/ TLC & DOUBLE
続・名盤を探しに行こう!/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.70(2000年2月号掲載)
TLCとDOUBLEね!
この辺の方々って、先日お亡くなりになったマイケル・ジャクソン世代
なんでしょうね。きっと!
R&Bねぇ!この頃、訳の分らない程、一杯ジャパニーズR&Bシンガーが
出て来たのを覚えています。
それが今も残っているかと言うと、僅かですな~。
でも、こういう流行り方をした後に、ちゃんとスタイルとしての日本の
R&Bみたいのがあるから不思議だ。
ナント言うか、その~本場のR&Bと比較しちゃ駄目で(当たり前!)、
あくまでも“日本の!”って事で、楽しむのには何の弊害もない。
ステレオ写真って記述は、今で言う3D写真の事。
ま、この程度のオマケと言うか特典でレコ店に走っていたんだ。
今じゃ、DVDやら何やらと特典を付けなきゃ、客が走ってくれない!
なんて話を聞く。
オマケ目当てね!これって、もう完全に本末転倒で、レコード会社は
自分で自分の首を絞めている。
で、この方々、TLCはレフト・アイを失った後はどうなったんでしょうか?
ちょっとその辺の情報には疎くなっています。
そしてDOUBLEはTAKAKO一人で、しっかりとDOUBLEとしての活動を続け、
ちょっと前に10周年を迎え、近頃はDJ Lillyとしても活躍。
いい感じのマイペースぶりで、未だにR&B一筋の姿勢を崩す事なく活動。
そのファンを裏切らない姿には、ホント、頭が下がりますわ。
タイトル通りクレイジーでセクシィでクールま作品で溢れたアルバム。
毎年の恒例行事(と思うけど・・・・・)タワーレコーズの1999年の
ベストセラーが発表になった。
洋楽はそれなりにジャンル分けはしているが、邦楽は、所謂J-POPの
ジャンルのみ。
それを大きく分けて、洋・邦楽のポピュラー・ミュージックのベスト40
が発表されている。
邦楽は、言わずと知れた宇多田ヒカル「First Love」。洋楽が、エリック・
クラプトンのベストを抜いて、何とTLCの「Funmail」が年間1位の座を
獲得している。
まぁ、発売期間の問題もあると思うけど、まさかのTLCだよネ。
確かに「No Scrubs」とかは流行ってたけど、ここまでポピュラリティ
を日本で獲得していたとは夢にも思わなかった。
もしかして、これってジャパニーズR&Bの追い風に乗ったおかげかなっ。
なんて思いつつ、そういえば、僕もあのステレオ写真の限定盤ジャケット
が欲しくて、買いに走ったっけ。
彼女達については、デビュー当時、雑誌かなにかで見たポートレートで、
その名前を記憶している程度で、音楽そのものには一切触れていなかった。
それが一気に引き寄せられる事になったのがセカンド・アルバム
「CrazySexyCool」がリリースされた94年の事。

それがやたらラジオでかかっていた「Creep」なのか「Diggin’On You」
なのか、はたまた「Waterfalls」なのかは、今ではハッキリとは覚えて
ない。が、多分引かれた一番の要素は、そのプリンス臭かなッ。
「Waterfalls」なんて、特にプリンスっぽいでしょ。
実際アルバムにはプリンスのカヴァー曲「If I Was Your Girlfriend」
なんて曲も入っているし・・・・・。
いずれにしてもこの「CrazySexyCool」、前述のヒット曲を含め、非常に
いい楽曲が多数収録されているし、ダラス・オースティン、ジャーメン・
デュプリ、ベイビーフェイス、さらにショーン“パフィ”コームズらが
プロデューサーとして参加(ジャパニーズR&B好きな貴方なら聞いた
事のある名前の一つや二つ・・・・・)。
今聴いても、ヒップ・ホップ・ソウル系の名盤と実感出来る作品。
さて、急逝してしまったSACHIKOの意志を継いでTAKAKO一人で再
スタートさせるとの情報が入った“double”。
彼女達が残したプロローグ・アルバムと銘打った「Crystal」で聴かせた
サウンドは、TLCが「Funmail」で示した、これからのR&Bの方向性に
乗り遅れまいとした部分も感じられる作品。
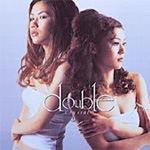
自らを“Super Sisters”と言うだけあって、改めてアルバムを聴いて
みると、この姉妹の可能性が測り知れない程大きかったかも、と思って
しまう。
年末にリリースされた「Crystal Planet」に収録されたデモ・テイク
での唄の上手さも光っていたしネ。
そんな訳で、2000年になっても日本の音楽業界はR&B系から目を離せ
ない。って状況が続くんでしょうネ。きっと!
TLC / CrazySexyCool (1994年度作品)
double / Crystal(1999年度作品)
Vol.70(2000年2月号掲載)
TLCとDOUBLEね!
この辺の方々って、先日お亡くなりになったマイケル・ジャクソン世代
なんでしょうね。きっと!
R&Bねぇ!この頃、訳の分らない程、一杯ジャパニーズR&Bシンガーが
出て来たのを覚えています。
それが今も残っているかと言うと、僅かですな~。
でも、こういう流行り方をした後に、ちゃんとスタイルとしての日本の
R&Bみたいのがあるから不思議だ。
ナント言うか、その~本場のR&Bと比較しちゃ駄目で(当たり前!)、
あくまでも“日本の!”って事で、楽しむのには何の弊害もない。
ステレオ写真って記述は、今で言う3D写真の事。
ま、この程度のオマケと言うか特典でレコ店に走っていたんだ。
今じゃ、DVDやら何やらと特典を付けなきゃ、客が走ってくれない!
なんて話を聞く。
オマケ目当てね!これって、もう完全に本末転倒で、レコード会社は
自分で自分の首を絞めている。
で、この方々、TLCはレフト・アイを失った後はどうなったんでしょうか?
ちょっとその辺の情報には疎くなっています。
そしてDOUBLEはTAKAKO一人で、しっかりとDOUBLEとしての活動を続け、
ちょっと前に10周年を迎え、近頃はDJ Lillyとしても活躍。
いい感じのマイペースぶりで、未だにR&B一筋の姿勢を崩す事なく活動。
そのファンを裏切らない姿には、ホント、頭が下がりますわ。
タイトル通りクレイジーでセクシィでクールま作品で溢れたアルバム。
毎年の恒例行事(と思うけど・・・・・)タワーレコーズの1999年の
ベストセラーが発表になった。
洋楽はそれなりにジャンル分けはしているが、邦楽は、所謂J-POPの
ジャンルのみ。
それを大きく分けて、洋・邦楽のポピュラー・ミュージックのベスト40
が発表されている。
邦楽は、言わずと知れた宇多田ヒカル「First Love」。洋楽が、エリック・
クラプトンのベストを抜いて、何とTLCの「Funmail」が年間1位の座を
獲得している。
まぁ、発売期間の問題もあると思うけど、まさかのTLCだよネ。
確かに「No Scrubs」とかは流行ってたけど、ここまでポピュラリティ
を日本で獲得していたとは夢にも思わなかった。
もしかして、これってジャパニーズR&Bの追い風に乗ったおかげかなっ。
なんて思いつつ、そういえば、僕もあのステレオ写真の限定盤ジャケット
が欲しくて、買いに走ったっけ。
彼女達については、デビュー当時、雑誌かなにかで見たポートレートで、
その名前を記憶している程度で、音楽そのものには一切触れていなかった。
それが一気に引き寄せられる事になったのがセカンド・アルバム
「CrazySexyCool」がリリースされた94年の事。

それがやたらラジオでかかっていた「Creep」なのか「Diggin’On You」
なのか、はたまた「Waterfalls」なのかは、今ではハッキリとは覚えて
ない。が、多分引かれた一番の要素は、そのプリンス臭かなッ。
「Waterfalls」なんて、特にプリンスっぽいでしょ。
実際アルバムにはプリンスのカヴァー曲「If I Was Your Girlfriend」
なんて曲も入っているし・・・・・。
いずれにしてもこの「CrazySexyCool」、前述のヒット曲を含め、非常に
いい楽曲が多数収録されているし、ダラス・オースティン、ジャーメン・
デュプリ、ベイビーフェイス、さらにショーン“パフィ”コームズらが
プロデューサーとして参加(ジャパニーズR&B好きな貴方なら聞いた
事のある名前の一つや二つ・・・・・)。
今聴いても、ヒップ・ホップ・ソウル系の名盤と実感出来る作品。
さて、急逝してしまったSACHIKOの意志を継いでTAKAKO一人で再
スタートさせるとの情報が入った“double”。
彼女達が残したプロローグ・アルバムと銘打った「Crystal」で聴かせた
サウンドは、TLCが「Funmail」で示した、これからのR&Bの方向性に
乗り遅れまいとした部分も感じられる作品。
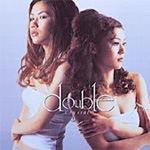
自らを“Super Sisters”と言うだけあって、改めてアルバムを聴いて
みると、この姉妹の可能性が測り知れない程大きかったかも、と思って
しまう。
年末にリリースされた「Crystal Planet」に収録されたデモ・テイク
での唄の上手さも光っていたしネ。
そんな訳で、2000年になっても日本の音楽業界はR&B系から目を離せ
ない。って状況が続くんでしょうネ。きっと!
TLC / CrazySexyCool (1994年度作品)
double / Crystal(1999年度作品)
2009年07月08日
名盤/ N with C & HARY & MAC
続・名盤を探しに行こう!/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.69(2000年 1月号掲載)
ちょっと前にNHK-BSでC,S & Nのライヴ映像を放映していた!
当然、珍しいのでDVDに収めておいた。
が、ちょっとだけ観て、後日改めて観よう!なんて思っていたけど、
そのまんまほったらかしになっています。
ま、映画とかもそうだけれども、結局、映像って、押さえても観ない
事の方が多い。
よっぽど暇になったら観るのだろうけど・・・・・。
そうそう、去年か今年にリリースされた4人が揃ったライヴ盤も、
なんか今更な~なんて感じで、試聴機で何曲か聴いて終わっちゃた。
ま、そんな事はおいておいて、この二人のこのアルバムですが、
相当愛聴しました。併せて、当時のそれぞれのソロも!
これらは、未だに時折引っ張り出して聴く事がある。
とは言うものの、この三人と言うか四人では、今となっては完全に
ニール・ヤングの一人勝ちなので、それと比較しちゃうと、聴くと
言っても本当にたまにの事。
一緒に載り上げた細野さんと久保田さんのアルバムも、これまたすっかり
ご無沙汰(失礼!)って感じ。
いけないと思いつつ、なかなか沢山音楽を聴く時間を作れなくなっている
今日この頃。
良くないな~と思い、日々反省!です。ハイ!
男同士の友情に溢れた名作アルバム!
クロズビー、スティルス、ナッシュ&ヤング(C,S,N&Y)が、10数年振り
に新作を発表したのが話題になっている。
以前に彼らの名作「Déjà vu」を、ここで載り上げた事があるが、あれが
1970年の作品だから、間に「AMERICAN DREAM」があるものの30年間で、
オリジナルが僅か3枚という超貧作さ。
とは言うものの、各々がソロ・アーティストとして充分に活躍している
ので、グループに固執する必要もない訳で、今回のリユニオンも、珠々
「久し振りに一緒に演ろうか!」なんていう、誰かのいい加減な一言が
発端だったりして・・・・・。
まぁ、ワールド・ツアーもやるらしいので、そこそこ本気のプロジェクト
かも知れない。
そんな彼らのアルバム「LOOKING FORWARD」は、変わる事のない、それぞれ
の役目をキッチリとこなしている。って感じで、尖り具合が年相応に取れた、
所謂円熟味溢れる一作。
同時代を生きてきた人達には、有り難い作品と言える。
それにしてもこの人達って、本当に友情で結ばれているんでしょうかねぇ。
ニールとスティヴンはどうもネ。なんて話は昔から聞く訳でしょ。
C,S&Nとしては結構やっているらしいし、本当のところはどうなんでしょ。
でも、間違いなく大の仲良しこよしがデイヴィッド・クロズビーとグレアム・
ナッシュのお二人さん。
この二人は間違いなく養老院まで一緒だよ。きっと。
C,S,N&Yに於いて、ニールとスティヴンの超個性派が放つ毒素を中和させて
いたかのような、この二人の存在。
その二人の仲良し振りが滲み出ているアルバムが1972年に発表した
「GRAHAM NASH/DAVID CROSBY」だ。

アルバムの冒頭を飾るのは「SOUTHBOUND TRAIN」。
“自由、平等、友愛”について歌ったもので、残り続けるアメリカの病巣を
題材にしたもの。
今聴くと、当時の時代背景を思い出してしまう。
全11曲収録中、グレアムが6曲、クロズビーが5曲と、まぁ、ちゃんと
シェアしているし、何よりもそのバランスが絶妙だ。メロディー・メイカー
で実にポップな肌触りを持つグレアムに対して、ブルージーである種の宗教
っぽさを漂わせ独自の世界を展開するクロズビー。
それがほぼ交互に並べられてアルバムは進行する。が、そこには全然違和感
などなく、まるで当然の如く二つの個性が収まっている。
これを聴いていると、何か出だしの「SOUTHBOUND TRAIN」のせいか、時が
ゆっくりと流れているような感覚に浸れる。
聴いて気に入った人は、是非それぞれのファースロ・ソロ・アルバムも
併せて聴いて欲しい。
友情と言えば、つい先頃発売された細野晴臣と久保田麻琴によるユニット
Hary & Macの「Road to Louisiana」は、20数年来の友情の賜物。

音的には先月紹介したDr.Johnのニューオーリンズ系。
男臭さとレイドバック感が、堪らなく心地好い作品。聴くべし。
Graham Nash & David Crosby / GRAHAM NASH/DAVID CROSBY (1972年度作品)
Hary & Mac / Road to Louisiana (1999年度作品)
Vol.69(2000年 1月号掲載)
ちょっと前にNHK-BSでC,S & Nのライヴ映像を放映していた!
当然、珍しいのでDVDに収めておいた。
が、ちょっとだけ観て、後日改めて観よう!なんて思っていたけど、
そのまんまほったらかしになっています。
ま、映画とかもそうだけれども、結局、映像って、押さえても観ない
事の方が多い。
よっぽど暇になったら観るのだろうけど・・・・・。
そうそう、去年か今年にリリースされた4人が揃ったライヴ盤も、
なんか今更な~なんて感じで、試聴機で何曲か聴いて終わっちゃた。
ま、そんな事はおいておいて、この二人のこのアルバムですが、
相当愛聴しました。併せて、当時のそれぞれのソロも!
これらは、未だに時折引っ張り出して聴く事がある。
とは言うものの、この三人と言うか四人では、今となっては完全に
ニール・ヤングの一人勝ちなので、それと比較しちゃうと、聴くと
言っても本当にたまにの事。
一緒に載り上げた細野さんと久保田さんのアルバムも、これまたすっかり
ご無沙汰(失礼!)って感じ。
いけないと思いつつ、なかなか沢山音楽を聴く時間を作れなくなっている
今日この頃。
良くないな~と思い、日々反省!です。ハイ!
男同士の友情に溢れた名作アルバム!
クロズビー、スティルス、ナッシュ&ヤング(C,S,N&Y)が、10数年振り
に新作を発表したのが話題になっている。
以前に彼らの名作「Déjà vu」を、ここで載り上げた事があるが、あれが
1970年の作品だから、間に「AMERICAN DREAM」があるものの30年間で、
オリジナルが僅か3枚という超貧作さ。
とは言うものの、各々がソロ・アーティストとして充分に活躍している
ので、グループに固執する必要もない訳で、今回のリユニオンも、珠々
「久し振りに一緒に演ろうか!」なんていう、誰かのいい加減な一言が
発端だったりして・・・・・。
まぁ、ワールド・ツアーもやるらしいので、そこそこ本気のプロジェクト
かも知れない。
そんな彼らのアルバム「LOOKING FORWARD」は、変わる事のない、それぞれ
の役目をキッチリとこなしている。って感じで、尖り具合が年相応に取れた、
所謂円熟味溢れる一作。
同時代を生きてきた人達には、有り難い作品と言える。
それにしてもこの人達って、本当に友情で結ばれているんでしょうかねぇ。
ニールとスティヴンはどうもネ。なんて話は昔から聞く訳でしょ。
C,S&Nとしては結構やっているらしいし、本当のところはどうなんでしょ。
でも、間違いなく大の仲良しこよしがデイヴィッド・クロズビーとグレアム・
ナッシュのお二人さん。
この二人は間違いなく養老院まで一緒だよ。きっと。
C,S,N&Yに於いて、ニールとスティヴンの超個性派が放つ毒素を中和させて
いたかのような、この二人の存在。
その二人の仲良し振りが滲み出ているアルバムが1972年に発表した
「GRAHAM NASH/DAVID CROSBY」だ。

アルバムの冒頭を飾るのは「SOUTHBOUND TRAIN」。
“自由、平等、友愛”について歌ったもので、残り続けるアメリカの病巣を
題材にしたもの。
今聴くと、当時の時代背景を思い出してしまう。
全11曲収録中、グレアムが6曲、クロズビーが5曲と、まぁ、ちゃんと
シェアしているし、何よりもそのバランスが絶妙だ。メロディー・メイカー
で実にポップな肌触りを持つグレアムに対して、ブルージーである種の宗教
っぽさを漂わせ独自の世界を展開するクロズビー。
それがほぼ交互に並べられてアルバムは進行する。が、そこには全然違和感
などなく、まるで当然の如く二つの個性が収まっている。
これを聴いていると、何か出だしの「SOUTHBOUND TRAIN」のせいか、時が
ゆっくりと流れているような感覚に浸れる。
聴いて気に入った人は、是非それぞれのファースロ・ソロ・アルバムも
併せて聴いて欲しい。
友情と言えば、つい先頃発売された細野晴臣と久保田麻琴によるユニット
Hary & Macの「Road to Louisiana」は、20数年来の友情の賜物。

音的には先月紹介したDr.Johnのニューオーリンズ系。
男臭さとレイドバック感が、堪らなく心地好い作品。聴くべし。
Graham Nash & David Crosby / GRAHAM NASH/DAVID CROSBY (1972年度作品)
Hary & Mac / Road to Louisiana (1999年度作品)
2009年06月09日
Dr.John & Bo Gumbos
続・名盤を探しに行こう!/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.68(1999年12月号掲載)
頭の中で音楽が鳴っている!ってぇのが日常茶飯事で、時々、何で
こんな曲が出てくるんだ!と思う事がある。
自然現象だから逆らう事は出来ないけど、好きでもない曲がリピート
されたら、堪ったもんじゃない。
ニューオーリンズと言えばジャズってイメージがあるけど、そこに
行かずに、このDr.Johnをはじめ、どちらかと言うとセカンドライン
を楽しんでいました。
Bo Gumbosは、なんと言っても元ローザ・ルクセンブルグのお二人が
参加していたので、このデビュー作は勿論の事、その後も、その動向
が気になってしょうがなかった!
ローザ、そしてこのボ・ガンボス、更にボ解散後を含め、どんとが残し
たものの“大きさ”って・・・。
きっと誰かが継承していってくれるんでしょうね!
ジャズだけじゃない、憧れのニューオーリンズの音楽。
ちょっと前に書いたミニー・リパートンの原稿で、Misiaについて触れた
けど、後日聞いた噂によると、ライヴで「Loving You」をカヴァーしてたん
だってネ。
まぁ、偶然の一致、って訳。何度か似たような事があって、う~ん、例えば
原稿を書き上げたら、新譜のリリース情報が飛び込んで来たとか、色々ある
わな~、長い間には。
そんな話と全然関係なく、今月は自然がなすままの事を書く事にします。
自然がなすまま、と言っても大した事じゃなくて、全く個人的に近頃頭の
中で鳴っている音楽で、まぁ、よくある頭の中で、ずぅーと鳴りっぱなしの
音楽ってあるでしょ。それがこれで、何だか「そろそろ書き時だよ!」と
催促されているみたい感じなので・・・・・。
その音楽は「IKO IKO」。「イコイコ」なんて読まないでくれよ。
「アイコ・アイコ」だぜ。
別に何処かにいる“あい子”さんの事を唄った歌じゃない。
ニューオーリンズを代表する音楽の1曲だ。
このニューオーリンズの古典的代表曲を唄うは“Dr.JOHN”なる、如何にも
インチキ臭い名前を持つミュージシャン。
とは言うものの、ロック界では、その名前は広く知れ渡った存在で活動歴
も長い。(あれっ、今年、札幌にライヴで来たんだっけ?)
そのドクター・ジョンの良く転がるピアノとダミ声が印象的な「IKO IKO」
が、ここんとこ、やたらと頭の中で繰り返されていた訳。
ドクター・ジョンことマック・レベナックは、50年代後半から、故郷ニュー
オーリンズで音楽活動を始め、数多くのセッションに参加し、ニューオーリ
ンズ・サウンドを体の隅々までに染み込ませていった人で、後に活動の場を
ロサンゼルスに移した時に、それが一気に開花する。
70年代のシンガー・ソングライター・ブームやアメリカン・ロックの隆盛
に一役かった訳で、その功績は、当時のそういった作品を振り返る事に
よって、容易に認識する事が出来る。
そのロス時代に作り上げたのが、前述の曲が収録されたアルバム「GUMBO」だ。

ニューオーリンズのR&Bをカヴァーしたこの作品は、多くのロック・ファンを
ニューオーリンズに導く役割を果たした名作と言える1枚。
勿論、ドクター・ジョンのダミ声と独特のピアノ・プレー、そしてこれまた
独特のグルーヴ感を持ったニューオーリンズ・サウンドの妙が楽しめるアルバム
なのです。
そんなニューオーリンズの音楽に愛情を示したのがボ・ガンボスの面々。
すでに解散しまったが、彼らが一貫して追求し、デビュー時から武器にして
いたのが、このニューオーリンズの音楽だ。
その彼らが、憧れの彼の地で作り上げてきたデビュー・アルバム「BO&GUMBO」
は、現地のミュージシャンとの和気あいあいのセッションも含む一作。

楽しそうな雰囲気が、まんま収録されていて、国や人種といった枠を越えた、
音楽での結束力の素晴らしさを感じさせる。
そんな訳で、ここらでいつもと違う音楽を!と思っている方は、ちょっと
ニューオーリンズへと旅立ちませんか。
Dr.John / GUMBO (1972年度作品)
BO GUMBOS / BO&GUMBO(1989年度作品)
Vol.68(1999年12月号掲載)
頭の中で音楽が鳴っている!ってぇのが日常茶飯事で、時々、何で
こんな曲が出てくるんだ!と思う事がある。
自然現象だから逆らう事は出来ないけど、好きでもない曲がリピート
されたら、堪ったもんじゃない。
ニューオーリンズと言えばジャズってイメージがあるけど、そこに
行かずに、このDr.Johnをはじめ、どちらかと言うとセカンドライン
を楽しんでいました。
Bo Gumbosは、なんと言っても元ローザ・ルクセンブルグのお二人が
参加していたので、このデビュー作は勿論の事、その後も、その動向
が気になってしょうがなかった!
ローザ、そしてこのボ・ガンボス、更にボ解散後を含め、どんとが残し
たものの“大きさ”って・・・。
きっと誰かが継承していってくれるんでしょうね!
ジャズだけじゃない、憧れのニューオーリンズの音楽。
ちょっと前に書いたミニー・リパートンの原稿で、Misiaについて触れた
けど、後日聞いた噂によると、ライヴで「Loving You」をカヴァーしてたん
だってネ。
まぁ、偶然の一致、って訳。何度か似たような事があって、う~ん、例えば
原稿を書き上げたら、新譜のリリース情報が飛び込んで来たとか、色々ある
わな~、長い間には。
そんな話と全然関係なく、今月は自然がなすままの事を書く事にします。
自然がなすまま、と言っても大した事じゃなくて、全く個人的に近頃頭の
中で鳴っている音楽で、まぁ、よくある頭の中で、ずぅーと鳴りっぱなしの
音楽ってあるでしょ。それがこれで、何だか「そろそろ書き時だよ!」と
催促されているみたい感じなので・・・・・。
その音楽は「IKO IKO」。「イコイコ」なんて読まないでくれよ。
「アイコ・アイコ」だぜ。
別に何処かにいる“あい子”さんの事を唄った歌じゃない。
ニューオーリンズを代表する音楽の1曲だ。
このニューオーリンズの古典的代表曲を唄うは“Dr.JOHN”なる、如何にも
インチキ臭い名前を持つミュージシャン。
とは言うものの、ロック界では、その名前は広く知れ渡った存在で活動歴
も長い。(あれっ、今年、札幌にライヴで来たんだっけ?)
そのドクター・ジョンの良く転がるピアノとダミ声が印象的な「IKO IKO」
が、ここんとこ、やたらと頭の中で繰り返されていた訳。
ドクター・ジョンことマック・レベナックは、50年代後半から、故郷ニュー
オーリンズで音楽活動を始め、数多くのセッションに参加し、ニューオーリ
ンズ・サウンドを体の隅々までに染み込ませていった人で、後に活動の場を
ロサンゼルスに移した時に、それが一気に開花する。
70年代のシンガー・ソングライター・ブームやアメリカン・ロックの隆盛
に一役かった訳で、その功績は、当時のそういった作品を振り返る事に
よって、容易に認識する事が出来る。
そのロス時代に作り上げたのが、前述の曲が収録されたアルバム「GUMBO」だ。

ニューオーリンズのR&Bをカヴァーしたこの作品は、多くのロック・ファンを
ニューオーリンズに導く役割を果たした名作と言える1枚。
勿論、ドクター・ジョンのダミ声と独特のピアノ・プレー、そしてこれまた
独特のグルーヴ感を持ったニューオーリンズ・サウンドの妙が楽しめるアルバム
なのです。
そんなニューオーリンズの音楽に愛情を示したのがボ・ガンボスの面々。
すでに解散しまったが、彼らが一貫して追求し、デビュー時から武器にして
いたのが、このニューオーリンズの音楽だ。
その彼らが、憧れの彼の地で作り上げてきたデビュー・アルバム「BO&GUMBO」
は、現地のミュージシャンとの和気あいあいのセッションも含む一作。

楽しそうな雰囲気が、まんま収録されていて、国や人種といった枠を越えた、
音楽での結束力の素晴らしさを感じさせる。
そんな訳で、ここらでいつもと違う音楽を!と思っている方は、ちょっと
ニューオーリンズへと旅立ちませんか。
Dr.John / GUMBO (1972年度作品)
BO GUMBOS / BO&GUMBO(1989年度作品)
2009年05月26日
名盤/ Los Lobos & Dr.StrangeLove
続・名盤を探しに行こう!/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.67(1999年11月号掲載)
`90年代の1枚ね!
確かにLos Lobosは相当嵌った!
思い起こせば`80年代から`90年代、そして現在に至るまで、
音楽を聴き始めた頃のようにはロックには惹かれなかった。
まぁ、`70年前後と比較するのもオカシイ事だけど。
PRINCE名義はナンのアルバム?さっぱり思い出せない!
変名で活動していた頃ですな~、これは!
プロデューサーを信じて、全く知らないアーティストの作品を
買う!ってのは、昔、相当有りました。
一生懸命、ジャケット裏のクレジットに目を凝らして、誰の
プロデュース?ってな感じで。
流石に近頃はそういう事は無くなってしまった。
ロスロボスは、新譜が出ると気になって直ぐに買いに行く
数少ないアーティストの一組。
Dr.StrangeLoveは、近頃、活動しているんでしょうか?
噂を聞く事がなくなりました。
90年代の1枚を選べ!と言われたら、もしかしたら、これを選ぶかも
しれない・・・・・。
まさに待望と言うに相応しいロス・ロボスの新作「THIS TIME」が届いた。
あの名作アルバム「Colossal Head」から実に3年振りである。
ちょっと前に“LATIN PLAY BOYS”が届いたばかりなので、本体(!?)ロス・
ロボスの新作が、これ程早くリリースされるとは思っていなかった。
まぁ、何というか「嬉しい!」の一言だ。
ロス・ロボスと言えば「ラ・バンバ」である。リッチー・ヴァレンスの
生涯を描いた映画の主題歌として大ヒットしたこの曲一発で終わるかと
思った彼らも、今や結成25年を超える大ベテラン。
そして、チカーノ(メキシコ系アメリカ人)を、いやいや、アメリカを
代表するバンドといって言い程、その存在感は増した。
そんな彼らが1996年に発表した前述のアルバム「コロッサル・ヘッド」
は、まさしく90年代を代表するロック・アルバムの1枚だ。

このアルバムで聴かれるのは、骨太でルーツ的臭いと時代性をしっかりと
咀嚼して飲み込んだようなサウンド・プロダクション。
勿論、ラテン・フレイヴァー溢れるロックを聴かせる訳だが、そのオリジ
ナリティー溢れる刺激度満点のサウンドには、病み付きの中毒性がある。
実際、筆者の廻りにも、一発でその中毒に掛った輩が何人もいる。
こうゆう中毒性の感触って、多分60年代~70年代の、あのロック黄金期
に味わったものに近い気がするが・・・・・、どうだろう。
また、このページで紹介している新譜の中にも、明らかに「コロッサル・
ヘッド」からの影響を受けたと思われる作品があり、そういった作品に
遭遇する度に、日本のミュージシャン達にも多大な影響を及ぼしている事
を実感させられる。
そんなロス・ロボスに誰が育てた?勿論、メンバー自身の成長もあるが、
前作「KIKO」から共同プロデュースで登場する“ミッチェル・フルーム”、
そしてこのアルバムでは“チャド・ブレイク”も加わっている。
と言う事は、まさしくこの二人が怪しいのだ。
ミッチェルとチャド。この二人を気になりだしたのが、このアルバムから。
これ以降、彼らの名前を見つけ出しては、その作品をチェックしている音楽
ファンも多いと思う。
そのチャド・ブレイクがDr.StrangeLoveの最新アルバム「twin suns」の
ミックスを手掛けた。

どちらかと言うと、ミュージシャンとしてよりプロデューサーとしての方が
知られている根岸孝旨と長田進の二人によるこのバンド。
相思相愛、類は友を呼ぶって訳じゃないけど、サウンド・クリエイター同志、
チャドとの相性バッチリ。
そのドッシリとした腰の座り具合と、トンがり具合が妙に気持ちいいロック
が満喫出来る作品に仕上がっているので、是非、ロス・ロボス・ファンにも
聴いて貰いたい。
そう言えば、何故かプロデュースがPRINCE名義のあのお方の新作が間もなく
届く。どこでどうなったか興味津々。
あぁ~、プロデューサーにも興味を持って聴く。ってのも楽しいヨ。って
話でした。
Los Lobos / Colossal Head (1996年度作品)
Dr.StraneLove / twin suns(1999年度作品)
Vol.67(1999年11月号掲載)
`90年代の1枚ね!
確かにLos Lobosは相当嵌った!
思い起こせば`80年代から`90年代、そして現在に至るまで、
音楽を聴き始めた頃のようにはロックには惹かれなかった。
まぁ、`70年前後と比較するのもオカシイ事だけど。
PRINCE名義はナンのアルバム?さっぱり思い出せない!
変名で活動していた頃ですな~、これは!
プロデューサーを信じて、全く知らないアーティストの作品を
買う!ってのは、昔、相当有りました。
一生懸命、ジャケット裏のクレジットに目を凝らして、誰の
プロデュース?ってな感じで。
流石に近頃はそういう事は無くなってしまった。
ロスロボスは、新譜が出ると気になって直ぐに買いに行く
数少ないアーティストの一組。
Dr.StrangeLoveは、近頃、活動しているんでしょうか?
噂を聞く事がなくなりました。
90年代の1枚を選べ!と言われたら、もしかしたら、これを選ぶかも
しれない・・・・・。
まさに待望と言うに相応しいロス・ロボスの新作「THIS TIME」が届いた。
あの名作アルバム「Colossal Head」から実に3年振りである。
ちょっと前に“LATIN PLAY BOYS”が届いたばかりなので、本体(!?)ロス・
ロボスの新作が、これ程早くリリースされるとは思っていなかった。
まぁ、何というか「嬉しい!」の一言だ。
ロス・ロボスと言えば「ラ・バンバ」である。リッチー・ヴァレンスの
生涯を描いた映画の主題歌として大ヒットしたこの曲一発で終わるかと
思った彼らも、今や結成25年を超える大ベテラン。
そして、チカーノ(メキシコ系アメリカ人)を、いやいや、アメリカを
代表するバンドといって言い程、その存在感は増した。
そんな彼らが1996年に発表した前述のアルバム「コロッサル・ヘッド」
は、まさしく90年代を代表するロック・アルバムの1枚だ。

このアルバムで聴かれるのは、骨太でルーツ的臭いと時代性をしっかりと
咀嚼して飲み込んだようなサウンド・プロダクション。
勿論、ラテン・フレイヴァー溢れるロックを聴かせる訳だが、そのオリジ
ナリティー溢れる刺激度満点のサウンドには、病み付きの中毒性がある。
実際、筆者の廻りにも、一発でその中毒に掛った輩が何人もいる。
こうゆう中毒性の感触って、多分60年代~70年代の、あのロック黄金期
に味わったものに近い気がするが・・・・・、どうだろう。
また、このページで紹介している新譜の中にも、明らかに「コロッサル・
ヘッド」からの影響を受けたと思われる作品があり、そういった作品に
遭遇する度に、日本のミュージシャン達にも多大な影響を及ぼしている事
を実感させられる。
そんなロス・ロボスに誰が育てた?勿論、メンバー自身の成長もあるが、
前作「KIKO」から共同プロデュースで登場する“ミッチェル・フルーム”、
そしてこのアルバムでは“チャド・ブレイク”も加わっている。
と言う事は、まさしくこの二人が怪しいのだ。
ミッチェルとチャド。この二人を気になりだしたのが、このアルバムから。
これ以降、彼らの名前を見つけ出しては、その作品をチェックしている音楽
ファンも多いと思う。
そのチャド・ブレイクがDr.StrangeLoveの最新アルバム「twin suns」の
ミックスを手掛けた。

どちらかと言うと、ミュージシャンとしてよりプロデューサーとしての方が
知られている根岸孝旨と長田進の二人によるこのバンド。
相思相愛、類は友を呼ぶって訳じゃないけど、サウンド・クリエイター同志、
チャドとの相性バッチリ。
そのドッシリとした腰の座り具合と、トンがり具合が妙に気持ちいいロック
が満喫出来る作品に仕上がっているので、是非、ロス・ロボス・ファンにも
聴いて貰いたい。
そう言えば、何故かプロデュースがPRINCE名義のあのお方の新作が間もなく
届く。どこでどうなったか興味津々。
あぁ~、プロデューサーにも興味を持って聴く。ってのも楽しいヨ。って
話でした。
Los Lobos / Colossal Head (1996年度作品)
Dr.StraneLove / twin suns(1999年度作品)
2009年05月18日
名盤/ MINNIE REPERTON & MISIA
続・名盤を探しに行こう!/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.66(1999年10月号掲載)
あぁ~こういう事ってなくなったな!
ラジオで聴いて、一発で気に入って欲しくなるのって。
MACY GRAYもそうだったけど、あとSheryl Crowもデビューの時、
ラジオでかかる度に気になってしょうがなかった。
こういう役割をしていたラジオが、今じゃ音楽情報源として衰退
しちまって、ヒットを生み出す事がなくなってしまった。
時代の流れとして片付ける事は簡単だけど、こうなったのには、
それこそラジオ側にも責任はあるはず。
オペラ界で使っていたディーヴァって言葉が突然脚光を浴びたのは、
確かこの頃が始まりで、それがR&B系の音楽をやる女性に当てはめ
出した最初と記憶している。
一杯、R&Bを装ったシンガーが出てきたな~。
ま、ファッションとか戦略でそう呼ばれて出て来たというか、不本意
にも出された人も多かったに違いない。
10年も経っちゃたら、僅か数人しか残っていない。
そして、今もR&Bと正面切ってやっている人は!となると微妙みたいな~。
ましてや世界への扉を開ける人なんぞ出ていない。
マライアじゃなくてミニー!
そう、元祖驚異の声帯の持ち主シンガー!
久々に、その声に一発でノックアウトされたアーティストいる。
“MACY GRAY”。デビューほやほやの新人だ。
ラジオで聴いて、すぐにレコード店に直行。即ゲット!って訳。
でぇ、この手の衝動に駆られたのは久々の事なんで、ちょっと興奮ぎみ。
このメイシー・グレイについては、多分何処のレコード店でも手に入れる
事が出来るので、詳しくは書かないので、各自それぞれに調べてくれっ。
(中身は保証するヨ。但し、普段ちゃ~んと、それなりの正しき音楽を
聴いていり人達には・・・・・)
なんせ、今月から文字数を減らせ!と言われているので、ウダウダ余計な
事を書くスペースが無いんだから。
新人の女性ヴォーカルもので、こんな風に一発で魅せられた。と記憶に
残っていて、真先に思い出すのがMINNIE REPERTONだ。
ミニーの時も、深夜ラジオで日本でのデビュー曲「REASON」を聴いて、
翌日、レコード店に直行。ってな具合である。

この「REASON」を収録したアルバム「PERFECT ANGEL」がリリースされた
のは1974年の事。デビュー盤と思いきや、遡る事4年前、チェス・レコ
ードからファースト・アルバムをリリースしている。
それを聴いたスティーヴィー・ワンダーが、彼女の才能を見抜き、この
アルバムに作品を提供、更に変名まで使って参加までして、その入れ込み
ようをあらわにしている。
≪5オクターヴの声を持ったパーフェクト・エンジェル・・・・・≫
って言うのが、確か当時の宣伝文句だったと思う。
うん、確かにその“オクターヴ”って言葉を、強力に意識させたのがこの
ミニーであった訳で、今で言うと、何オクターヴかは忘れたけど、あの
マライア・キャリーみたいなもんか。
その5オクターヴの声を駆使した作品が並んだこのアルバムには、あの
名曲「LOVIN’YOU」のオリジナルが収録されている。
あまりにも一人歩きしちゃった感が強いこの曲は、いまだに多くの人達に
愛され続けているけど、肝心のミニーへの評価って、どうなんだろう。
70年代のソウルの変容をもろに受けて出来上がったこのミニーの
アルバム。空気感的には、今の日本で聴くには、仲々フィットしていると
思うのだが・・・・・。
さて、その日本でも、つい最近何オクターヴかの声で話題になったと言う
より、曲そのものがあんなにヒットしちゃったし、何だかんだと言っても、
その後のジャパニーズR&Bムーヴメントやディーヴァなる聞き慣れない言葉
を引っ張り出した張本人とも言える人。そう“Misia”だ。

彼女の存在を強力に印象付けた「つつみ込むように・・・」のDUB MIXが
収録されたアルバム「Mother Father Brother Sister」は、そんな聞き慣れ
ない言葉を代表する作品と言っていいだろう。
そうシーンは始まったばかり。ゆくゆくは世界に通じるジャパニーズR&B
って事。
う~ん、誰がその扉を開けるんだろう。
MINNIE REPERTON / PERFECT ANGEL (1974年度作品)
MISIA / Mother Father Brother Sister(1998年度作品)
Vol.66(1999年10月号掲載)
あぁ~こういう事ってなくなったな!
ラジオで聴いて、一発で気に入って欲しくなるのって。
MACY GRAYもそうだったけど、あとSheryl Crowもデビューの時、
ラジオでかかる度に気になってしょうがなかった。
こういう役割をしていたラジオが、今じゃ音楽情報源として衰退
しちまって、ヒットを生み出す事がなくなってしまった。
時代の流れとして片付ける事は簡単だけど、こうなったのには、
それこそラジオ側にも責任はあるはず。
オペラ界で使っていたディーヴァって言葉が突然脚光を浴びたのは、
確かこの頃が始まりで、それがR&B系の音楽をやる女性に当てはめ
出した最初と記憶している。
一杯、R&Bを装ったシンガーが出てきたな~。
ま、ファッションとか戦略でそう呼ばれて出て来たというか、不本意
にも出された人も多かったに違いない。
10年も経っちゃたら、僅か数人しか残っていない。
そして、今もR&Bと正面切ってやっている人は!となると微妙みたいな~。
ましてや世界への扉を開ける人なんぞ出ていない。
マライアじゃなくてミニー!
そう、元祖驚異の声帯の持ち主シンガー!
久々に、その声に一発でノックアウトされたアーティストいる。
“MACY GRAY”。デビューほやほやの新人だ。
ラジオで聴いて、すぐにレコード店に直行。即ゲット!って訳。
でぇ、この手の衝動に駆られたのは久々の事なんで、ちょっと興奮ぎみ。
このメイシー・グレイについては、多分何処のレコード店でも手に入れる
事が出来るので、詳しくは書かないので、各自それぞれに調べてくれっ。
(中身は保証するヨ。但し、普段ちゃ~んと、それなりの正しき音楽を
聴いていり人達には・・・・・)
なんせ、今月から文字数を減らせ!と言われているので、ウダウダ余計な
事を書くスペースが無いんだから。
新人の女性ヴォーカルもので、こんな風に一発で魅せられた。と記憶に
残っていて、真先に思い出すのがMINNIE REPERTONだ。
ミニーの時も、深夜ラジオで日本でのデビュー曲「REASON」を聴いて、
翌日、レコード店に直行。ってな具合である。

この「REASON」を収録したアルバム「PERFECT ANGEL」がリリースされた
のは1974年の事。デビュー盤と思いきや、遡る事4年前、チェス・レコ
ードからファースト・アルバムをリリースしている。
それを聴いたスティーヴィー・ワンダーが、彼女の才能を見抜き、この
アルバムに作品を提供、更に変名まで使って参加までして、その入れ込み
ようをあらわにしている。
≪5オクターヴの声を持ったパーフェクト・エンジェル・・・・・≫
って言うのが、確か当時の宣伝文句だったと思う。
うん、確かにその“オクターヴ”って言葉を、強力に意識させたのがこの
ミニーであった訳で、今で言うと、何オクターヴかは忘れたけど、あの
マライア・キャリーみたいなもんか。
その5オクターヴの声を駆使した作品が並んだこのアルバムには、あの
名曲「LOVIN’YOU」のオリジナルが収録されている。
あまりにも一人歩きしちゃった感が強いこの曲は、いまだに多くの人達に
愛され続けているけど、肝心のミニーへの評価って、どうなんだろう。
70年代のソウルの変容をもろに受けて出来上がったこのミニーの
アルバム。空気感的には、今の日本で聴くには、仲々フィットしていると
思うのだが・・・・・。
さて、その日本でも、つい最近何オクターヴかの声で話題になったと言う
より、曲そのものがあんなにヒットしちゃったし、何だかんだと言っても、
その後のジャパニーズR&Bムーヴメントやディーヴァなる聞き慣れない言葉
を引っ張り出した張本人とも言える人。そう“Misia”だ。

彼女の存在を強力に印象付けた「つつみ込むように・・・」のDUB MIXが
収録されたアルバム「Mother Father Brother Sister」は、そんな聞き慣れ
ない言葉を代表する作品と言っていいだろう。
そうシーンは始まったばかり。ゆくゆくは世界に通じるジャパニーズR&B
って事。
う~ん、誰がその扉を開けるんだろう。
MINNIE REPERTON / PERFECT ANGEL (1974年度作品)
MISIA / Mother Father Brother Sister(1998年度作品)
2009年04月23日
名盤/ TELEVISION & 東京ロッカーズ
続・名盤を探しに行こう!/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.65(1999年09月号掲載)
主語、述語だっけ?もう相当昔に、そういう勉強をしたので、
すっかり忘れているが、何て言うか、相変わらず文章がヘタ!と
言うか変なところが多い。
気持ちが先走っているんだろうな。こんな書き方は。
ラジオ番組に出演した記憶はあるが、ロック黄金期の話って、
何をどう話したのかは、全く記憶にない。
ピストルズとの開きは大きいとか書いてあるが、テレヴィジョンって、
結局、ごく一部でしか評価されなかった存在。
CDで買い直したのは、書いてある通り「MARQUEE MOON」の完奏版を
聴きたかったから。
今でも、時折、思い出しては聴く事がある。
東京ロッカーズは、今もCD化されていないのかしらん。
アナログ盤は、たまに中古レコード屋で見かける事があるので、
CD化されていないなら、中古屋に行けば手に入ると思います。
個人的にはパンク、ニュー・ウェイヴ時代の決定打的1枚!
トーキング・ヘッズなどを聴きながら、すっかり頭の中があの頃に戻って
しまった先月(と書いたが、実際は7月の事だからネ!)、何年振りかに
ラジオに出演させて頂きました。
日曜日の早朝にオンエアーしているAIR-G’「ロック小僧の夢」なんだ
けど、折角の日曜日、若者達は早起きなんぞしていないよな~。
たまたま聴いた方は、その渋~い声に、さぞ眠気もブッ飛んだ事でしょう。
何を話したかと言うと、タイトル通りロック話なんだけど、先月書いた
“ロックが一番輝いていた頃・・・”みたいな、まぁ、所謂年寄りが
縁側で茶でも啜りながらの“あの頃は良かった・・・”的話で、聴いて
いる人はどうかわからないけど、俺は楽しかったので、予定外に話ちゃって
2週分録ってしまった。
そんな訳で、近年稀にみるロック・モードな気分で夏を迎えてしまい、
ズルズルとそれを引きずって今月号に至ってしまった。
だから今月も、ロックものを書いちゃうよ。
でぇ、先月書いた“痙攣っぽく踊る~云々”で思い出したのが“TELEVISION”
という不世出のバンドの事。
ニューヨーク・パンク代表的存在とも言えるこのテレヴィジョンのデビュー
は1977年。
我が音楽人生にパンクなんて・・・・・と言った手前なんだが、結構デビュー
・アルバム「MARQUEE MOON」は聴きまくった1枚だ。

年代を調べて分かった事だが、セックス・ピストルズのデビューと同じ年
にこの作品はリリースされている。
後のピストルズの評価というかポピュラリティとは、あまりにも大きな
開きを感じる。
最初のシングル曲「VENUS」を聴いた時、トム・ヴァーレインのしゃくり
上げるような唄い方が、何やら不気味だったが、その楽曲の持つポップ
さが、当時、全然パンクっぽくなかったように感じた記憶がる。(でも、
このシングル盤は日本だけの発売かも・・・)
それにしてもアルバムは強烈だ。スタジオでライヴ録音的にレコーディング
されたらしいが、バンドの姿そのものを剥き出しのまま捉えたようなリアリティ
を感じさせる。
ヴァーレインのヒステリックな唄もそうだが、サウンドを組み立てる
ヴァーレインとリチャード・ロイドの2台のギターのアンサンブルが、
何とも言えない程スリリングでいい。
ドアーズが在籍していたという理由だけで目指したエレクトラからデビュー
した彼ら。そんな話も加わって、個人的には、パンクはこれで始まり、
これで終わった。と言っても過言ではない。
尚、レコードでは長年聴きなれたタイトル・チューンのフェイド・アウトは、
CDでは完奏で収められているので要注意。
さて、テレヴィジョンで担ぎ出そうと思っていた日本のバンドがいる。
このアルバムに同名の曲が収録されている“FRICTION”だ。
彼らのデビュー・アルバム「軋轢」(CD:MTR-PASSWAX-2/1980年度作品)に
ついて書こうと思って、札幌と東京で捜し廻ったが、全然見つかりません
でした。
なんせこのバンドの二人は、テレヴィジョンのデビュー時にはニューヨーク
で音楽活動していたんだから。
で、このデビュー作には、痙攣的でテンポの速いロックンロールが刻まれて
いるらしい。う~ん、本場ニューヨーク仕込みだぜ!聴いてみた~い。
でぇ、手持ちだと「東京ROCKERS」(1979年度作品)というオムニバスの
レコードで、デビュー直前の彼らのライヴを聴く事が出来たが、こちらは
どうもCD化されていないみたい。

日本のニュー・ウェイヴの夜明けを捉えた貴重な瞬間がギッシリ詰まった
作品なので、中古盤屋で見掛けたら、すぐにゲット!折角だからジャケット
だけは掲載しておきます。それじゃ、また来月。
TELEVISIN / MARQUEE MOON (1977年度作品)
東京ロッカーズ(1979年度作品)
Vol.65(1999年09月号掲載)
主語、述語だっけ?もう相当昔に、そういう勉強をしたので、
すっかり忘れているが、何て言うか、相変わらず文章がヘタ!と
言うか変なところが多い。
気持ちが先走っているんだろうな。こんな書き方は。
ラジオ番組に出演した記憶はあるが、ロック黄金期の話って、
何をどう話したのかは、全く記憶にない。
ピストルズとの開きは大きいとか書いてあるが、テレヴィジョンって、
結局、ごく一部でしか評価されなかった存在。
CDで買い直したのは、書いてある通り「MARQUEE MOON」の完奏版を
聴きたかったから。
今でも、時折、思い出しては聴く事がある。
東京ロッカーズは、今もCD化されていないのかしらん。
アナログ盤は、たまに中古レコード屋で見かける事があるので、
CD化されていないなら、中古屋に行けば手に入ると思います。
個人的にはパンク、ニュー・ウェイヴ時代の決定打的1枚!
トーキング・ヘッズなどを聴きながら、すっかり頭の中があの頃に戻って
しまった先月(と書いたが、実際は7月の事だからネ!)、何年振りかに
ラジオに出演させて頂きました。
日曜日の早朝にオンエアーしているAIR-G’「ロック小僧の夢」なんだ
けど、折角の日曜日、若者達は早起きなんぞしていないよな~。
たまたま聴いた方は、その渋~い声に、さぞ眠気もブッ飛んだ事でしょう。
何を話したかと言うと、タイトル通りロック話なんだけど、先月書いた
“ロックが一番輝いていた頃・・・”みたいな、まぁ、所謂年寄りが
縁側で茶でも啜りながらの“あの頃は良かった・・・”的話で、聴いて
いる人はどうかわからないけど、俺は楽しかったので、予定外に話ちゃって
2週分録ってしまった。
そんな訳で、近年稀にみるロック・モードな気分で夏を迎えてしまい、
ズルズルとそれを引きずって今月号に至ってしまった。
だから今月も、ロックものを書いちゃうよ。
でぇ、先月書いた“痙攣っぽく踊る~云々”で思い出したのが“TELEVISION”
という不世出のバンドの事。
ニューヨーク・パンク代表的存在とも言えるこのテレヴィジョンのデビュー
は1977年。
我が音楽人生にパンクなんて・・・・・と言った手前なんだが、結構デビュー
・アルバム「MARQUEE MOON」は聴きまくった1枚だ。

年代を調べて分かった事だが、セックス・ピストルズのデビューと同じ年
にこの作品はリリースされている。
後のピストルズの評価というかポピュラリティとは、あまりにも大きな
開きを感じる。
最初のシングル曲「VENUS」を聴いた時、トム・ヴァーレインのしゃくり
上げるような唄い方が、何やら不気味だったが、その楽曲の持つポップ
さが、当時、全然パンクっぽくなかったように感じた記憶がる。(でも、
このシングル盤は日本だけの発売かも・・・)
それにしてもアルバムは強烈だ。スタジオでライヴ録音的にレコーディング
されたらしいが、バンドの姿そのものを剥き出しのまま捉えたようなリアリティ
を感じさせる。
ヴァーレインのヒステリックな唄もそうだが、サウンドを組み立てる
ヴァーレインとリチャード・ロイドの2台のギターのアンサンブルが、
何とも言えない程スリリングでいい。
ドアーズが在籍していたという理由だけで目指したエレクトラからデビュー
した彼ら。そんな話も加わって、個人的には、パンクはこれで始まり、
これで終わった。と言っても過言ではない。
尚、レコードでは長年聴きなれたタイトル・チューンのフェイド・アウトは、
CDでは完奏で収められているので要注意。
さて、テレヴィジョンで担ぎ出そうと思っていた日本のバンドがいる。
このアルバムに同名の曲が収録されている“FRICTION”だ。
彼らのデビュー・アルバム「軋轢」(CD:MTR-PASSWAX-2/1980年度作品)に
ついて書こうと思って、札幌と東京で捜し廻ったが、全然見つかりません
でした。
なんせこのバンドの二人は、テレヴィジョンのデビュー時にはニューヨーク
で音楽活動していたんだから。
で、このデビュー作には、痙攣的でテンポの速いロックンロールが刻まれて
いるらしい。う~ん、本場ニューヨーク仕込みだぜ!聴いてみた~い。
でぇ、手持ちだと「東京ROCKERS」(1979年度作品)というオムニバスの
レコードで、デビュー直前の彼らのライヴを聴く事が出来たが、こちらは
どうもCD化されていないみたい。

日本のニュー・ウェイヴの夜明けを捉えた貴重な瞬間がギッシリ詰まった
作品なので、中古盤屋で見掛けたら、すぐにゲット!折角だからジャケット
だけは掲載しておきます。それじゃ、また来月。
TELEVISIN / MARQUEE MOON (1977年度作品)
東京ロッカーズ(1979年度作品)
2009年04月16日
名盤/ T.HEADS & PLASTICS
続・名盤を探しに行こう!/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.64(1999年08月号掲載)
体系的に聴く!と言う事が、今の音楽ファンにはあまり無いようだ。
“ようだ”と書いたのは、ちゃんとしたデータを持っている訳じゃない
からで、何となく推測です。
パンクが原点回帰ねぇ?
どうなんでしょう。ま、いいか。
この号から俺個人のメールアドレスを明記して、意見やら希望があれば
とやったけど、正直、あまり来なかった。
人気の無いコラムだったって事です。
隠し玉的アイテムのアルバムって、昔、結構あった。
所謂、ほかの人が知らないアーティストなりアルバムを、自慢げに教えて
あげる訳。
単なる自己満足なんだけどね。
Talking Headsは、後々、“REMAIN IN LIGHT”に続いて、映画“STOP
MAKING SENCE”にも打ちのめされるんだけど。
とにかく、未だにデイヴィッド・バーンは要注意人物なのです。
PLASTICSか!
ナンカ、もうこの辺は記憶の中ではYMOとゴッチャになっていて、
今となっては聴き返す事もなく、レコードは物置の中にでも眠っている
と思います。
どちらも奇をてらった訳じゃない。
80年代の幕開けを告げたニューウェイヴ達の遺産
そんな訳で先月号の続きになってしまうが、ライ・クーダーを切っ掛けに
聴き込んだというか、ハマッてしまった音楽も多い。
まぁ、好きなアーティストが取り組んだ音楽を、体系的に聴いて行くと
いうのは、正しき音楽ファンの道を歩んでいた訳だから、それはそれで
良し。って事だろう。
でぇ、あの当時ロックが進化し続ける上で、何かしらの刺激材料が必要
だった訳で、それが60年代後半から70年代へかけての、所謂、良く
語られるロック黄金期、即ち“ロックが一番ロックらしく輝いていた
時代”の事だろう。
ジャズやらクラシック、民族音楽などなど、手近で喰い尽くして延命を
謀ったロックは、一方では原点回帰なる現象も生む。その一つがパンクだ。
パンクとニューウェイヴ。これがどうも頭の中で一つの塊になっていて
どっちもどっちだ。
ようするに我が音楽人生に於いて、大した意味を持つ音楽ではないって
事。(御免よ!パンクス達)
唯一、追い掛けたのは“THE TALKING HEADS”だけだった。
ニューヨークから現れたこのバンド。デイヴィッド・バーンという非常に
インテリジェンスを感じさせる男に率いられ、それこそデビュー当時は
パンクのメッカ“CBGB”を根城に活動していた。
そんな訳で、その当時は全然無関心な存在に過ぎなかったが、たった1枚
のアルバムが、その存在を予想以上に大きくする事になる。
1980年に発表した「REMAIN IN LIGHT」。所謂、ロックとアフリカン・ビート
の出会いの1枚だ。

個人的にはアフリカものとの出会いは、これ以前にある。
行きつけの飲み屋でフェラ・クティの洗礼を受けている。アルバムが
「ZOMBIE」なので、遡る事これより僅か1~2年前の事だろう。
その強力なリズム感に打ちのめされつつ痛飲に明け暮れた日々の中で
掴んだ、友達に自慢出来る必殺の隠し球的アルバムだった。
さて、この「REMAIN IN LIGHT」。例の1枚貰えるキャンペーンのカタログ
にもしっかりと入っていた。「80年代を代表する1枚云々~(途中省略)
~大胆な企てが完璧に結実した傑作」と説明されている。
う~ん、確かにあの当時はかなりショックを受けた記憶があるし、
と事ある毎に、トーキング・ヘッズを聴いたか!なんて言い廻って
いたような気がする。
そんな刺激を思い出そうとレコードを引っ張り出して、久々のプレイ・オン。
ライナーは今野雄二氏。ヘッド・コピーに「原始と原子の火花散る出会い」
とある。
それもご丁寧に原始にはアフリカ、原子にはアメリカとルビが振ってある。
ふ~ん、いいな。このコピー。言えてるぞ。流石、音楽評論家。
雑文書きの俺にゃ、書けないぞ。そんな名文を。
そんな事より、やっぱり恰好いいっす、これ。エスノ・ファンクだって。
CD安いから、是非買って聴いて下さい。80年代の遺産を。
ニューウェイヴで真先に思い出す日本のアーティストと言えば
プラスティックス。確か、トーキング・ヘッズと交流もあったハズ。
80年に発表されたデビュー作「ウェルカム・プラスティックス」を、
これまた引っ張り出して聴いてみた。

どうも、これでディスコで痙攣っぽく踊っている若者の姿しか浮かばないな。
な~んて。
音楽を演りたいというプリミティヴな衝動とアイデアが、何よりも勝って
出来た賜物的作品。御存じ“佐久間正英”が在籍していたバンド。と言えば、
今時の若者達は振り向いてくれるのかしらん。
これも、日本の音楽シーンが誇れる(!?)80年代の遺産かもネ。
THE TALKING HEADS / REMAIN IN LIGHT (1980年度作品)
PLASTICS / WELCOME PLASTICS(1980年度作品)
Vol.64(1999年08月号掲載)
体系的に聴く!と言う事が、今の音楽ファンにはあまり無いようだ。
“ようだ”と書いたのは、ちゃんとしたデータを持っている訳じゃない
からで、何となく推測です。
パンクが原点回帰ねぇ?
どうなんでしょう。ま、いいか。
この号から俺個人のメールアドレスを明記して、意見やら希望があれば
とやったけど、正直、あまり来なかった。
人気の無いコラムだったって事です。
隠し玉的アイテムのアルバムって、昔、結構あった。
所謂、ほかの人が知らないアーティストなりアルバムを、自慢げに教えて
あげる訳。
単なる自己満足なんだけどね。
Talking Headsは、後々、“REMAIN IN LIGHT”に続いて、映画“STOP
MAKING SENCE”にも打ちのめされるんだけど。
とにかく、未だにデイヴィッド・バーンは要注意人物なのです。
PLASTICSか!
ナンカ、もうこの辺は記憶の中ではYMOとゴッチャになっていて、
今となっては聴き返す事もなく、レコードは物置の中にでも眠っている
と思います。
どちらも奇をてらった訳じゃない。
80年代の幕開けを告げたニューウェイヴ達の遺産
そんな訳で先月号の続きになってしまうが、ライ・クーダーを切っ掛けに
聴き込んだというか、ハマッてしまった音楽も多い。
まぁ、好きなアーティストが取り組んだ音楽を、体系的に聴いて行くと
いうのは、正しき音楽ファンの道を歩んでいた訳だから、それはそれで
良し。って事だろう。
でぇ、あの当時ロックが進化し続ける上で、何かしらの刺激材料が必要
だった訳で、それが60年代後半から70年代へかけての、所謂、良く
語られるロック黄金期、即ち“ロックが一番ロックらしく輝いていた
時代”の事だろう。
ジャズやらクラシック、民族音楽などなど、手近で喰い尽くして延命を
謀ったロックは、一方では原点回帰なる現象も生む。その一つがパンクだ。
パンクとニューウェイヴ。これがどうも頭の中で一つの塊になっていて
どっちもどっちだ。
ようするに我が音楽人生に於いて、大した意味を持つ音楽ではないって
事。(御免よ!パンクス達)
唯一、追い掛けたのは“THE TALKING HEADS”だけだった。
ニューヨークから現れたこのバンド。デイヴィッド・バーンという非常に
インテリジェンスを感じさせる男に率いられ、それこそデビュー当時は
パンクのメッカ“CBGB”を根城に活動していた。
そんな訳で、その当時は全然無関心な存在に過ぎなかったが、たった1枚
のアルバムが、その存在を予想以上に大きくする事になる。
1980年に発表した「REMAIN IN LIGHT」。所謂、ロックとアフリカン・ビート
の出会いの1枚だ。

個人的にはアフリカものとの出会いは、これ以前にある。
行きつけの飲み屋でフェラ・クティの洗礼を受けている。アルバムが
「ZOMBIE」なので、遡る事これより僅か1~2年前の事だろう。
その強力なリズム感に打ちのめされつつ痛飲に明け暮れた日々の中で
掴んだ、友達に自慢出来る必殺の隠し球的アルバムだった。
さて、この「REMAIN IN LIGHT」。例の1枚貰えるキャンペーンのカタログ
にもしっかりと入っていた。「80年代を代表する1枚云々~(途中省略)
~大胆な企てが完璧に結実した傑作」と説明されている。
う~ん、確かにあの当時はかなりショックを受けた記憶があるし、
と事ある毎に、トーキング・ヘッズを聴いたか!なんて言い廻って
いたような気がする。
そんな刺激を思い出そうとレコードを引っ張り出して、久々のプレイ・オン。
ライナーは今野雄二氏。ヘッド・コピーに「原始と原子の火花散る出会い」
とある。
それもご丁寧に原始にはアフリカ、原子にはアメリカとルビが振ってある。
ふ~ん、いいな。このコピー。言えてるぞ。流石、音楽評論家。
雑文書きの俺にゃ、書けないぞ。そんな名文を。
そんな事より、やっぱり恰好いいっす、これ。エスノ・ファンクだって。
CD安いから、是非買って聴いて下さい。80年代の遺産を。
ニューウェイヴで真先に思い出す日本のアーティストと言えば
プラスティックス。確か、トーキング・ヘッズと交流もあったハズ。
80年に発表されたデビュー作「ウェルカム・プラスティックス」を、
これまた引っ張り出して聴いてみた。

どうも、これでディスコで痙攣っぽく踊っている若者の姿しか浮かばないな。
な~んて。
音楽を演りたいというプリミティヴな衝動とアイデアが、何よりも勝って
出来た賜物的作品。御存じ“佐久間正英”が在籍していたバンド。と言えば、
今時の若者達は振り向いてくれるのかしらん。
これも、日本の音楽シーンが誇れる(!?)80年代の遺産かもネ。
THE TALKING HEADS / REMAIN IN LIGHT (1980年度作品)
PLASTICS / WELCOME PLASTICS(1980年度作品)
2009年03月24日
名盤/ Ry Cooder
続・名盤を探しに行こう!/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.63(1999年07月号掲載)
テレビ問題を書いていますね。
あぁ~、この頃のテレビの影響力は相当だったようで、今はその存在を
ネットに脅かされている。
あれだけチャンネルが増えりゃ、そりゃ質が落ちるのも当然で、ホント
観るに耐えられない番組も多い。
オリコンのところは、ちょっと説明不足で、代表的な例を出すと、未だ
にあるのがバラエティとか何かで、バカなタレントがCDを出して、それ
が何位に入るとか入らないとか!ってやつ。
踊らされて買う輩がいるのはしょうがないが、そのせいで、どうでもいい
ような曲がチャートの上位に入ってしまう。
そんな金儲けのお遊びと一緒に比較される、まっとうな音楽の悲しさ!
一生懸命作ったミュージシャンに申し訳ないでしょ。
そんなアホバカなヤツと優劣を問われてもと思うのですが、どう考えても
売れているものが“勝ち!”の世の中ですからね。
ラジオの衰退は、もうこの頃から危惧していたんですね。
ここで言うラジオはFM局の事だけど。
これだけラジオからヒットが出ていないと、やっぱりその存在を音楽業界
から疑われてもしょうがない。
なんせFM局は“音楽を売り!”にしてきたのだから。
ライ・クーダーは、書いてある通りローリング・ストーンズで、その存在を
知った。
音も聴いた事もないアーティストのLPを買うなんて、あの金の無いガキの
頃に出来る訳ないから、こうして手に入れたモノは貴重だった。
ギタリストって事で、エリック・クラプトンの如く、ガンガン弾いているのか
と思ったら、渋くて“?”が頭の中をクルクル廻っていたってぇのが正直な
ところ。
でも、ここで出会ってから、今まで出たオリジナル・アルバムは全部手に
入れているので、長~いお付き合いとなり、それこそ彼の音楽は、
俺にとって一生モンの音楽となった。
それとライが紹介してくれた、世界各地の音楽にもたくさん触れる事が出来、
ホント、いい出会いだったと、今は感謝している。
ただ(!?)で手に入れた一生もののアーティスト“ライ・クーダー”の
デビュー作。
「民放と女性誌ばかりみていると、脳がシュリンクしてしまう!」と言った
ヴィトンだかグッチだかのお偉いさんが居る。
某週刊誌で読んだ記事だが、これは、我輩が小学生の時に、テレビのせいで
我が日本は一億総白痴化する、と教えられた事の焼き直し版だ。
昔、ドリフターズの番組が低俗だとして、結構叩かれた事を記憶している方
も多いと思うが、今のテレビ番組のバカアホ加減は、その比じゃない。
時代が変わった。の一言で片付ける問題ではないような気がする。
と、何やら固い事を書いたが、今やテレビの影響力は凄いからな。
いい例が、皆さんが良く知っている、あのオリコンの何位に入らなかったら
どうのこう、ってやつ。
良いか悪いかは別にして、まぁ、良く売れているわなぁ。そんなやつが。
そんなこんなで、テレビは現時点で最高のプロモーションの場として成立
している訳だ。
それはそれでいいんだけど、問題はそれに追従するラジオ局。何もテレビ
で売り出そうとしているやつを応援する事ないじゃない。
これだけ音楽が溢れているんだから、テレビじゃ仲々聴けないのをオン
エアーしてよ。と言いたい。
ラジオの基本はお喋りは勿論だけれども、音楽も同じ位の比重を占めて
いるハズ。
確かに、テレビ発のヒット曲を流していれば聴取率的には安心なんだろう
けど、それなら映像付きのテレビを観ればいい訳だから・・・・・。
これだけ情報の発信源が多様化して競争が激化しているんだから、他と
一緒の事をやってても駄目でしょ。
な~んて偉そうな事を書いてみたけれど、まぁ、ようはもっと一杯いろ
んな音楽を聴かせて欲しいって事。
ほら、ディレクターさん、貴方の回りには、一杯役目を果たせぬまま
捨てられていくサンプル盤が山積みなんだから・・・・・(アーメン)。
さて、話は全然変わります。大手レコード会社のワーナー・ミュージック
が、洋楽キャンペーンとしてCDを3枚買うと1枚貰えるというキャンペーン
を今月一杯やっています。(詳細は、お近くのCDショップで。)
所謂低迷する旧譜の消費拡大を狙ったものだが、対象商品の殆どが、
この名盤に出て来ても遜色がないものだ。
こういったキャンペーンは過去にもあって、我輩も記憶にあるだけで2枚
の作品を手にした事がある。
何れも、興味はあるけど買う踏ん切りがつかなかった作品で、その1枚が、
デビュー直後のライ・クーダーのアルバムだった。
ストーンズのセッションで、その存在を知ったライは、当時、ラジオは勿論、
取り上げる媒体も少なく、そりゃ、買うには賭けだったネ。
だから、オマケで貰えるならって事で手に入れた訳。
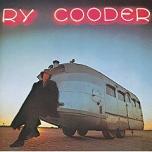
邦題「ライ・クーダー登場」は、それまで聴いていたロックに較べると、
何やら肩の力が抜けたような、すっ惚けた魅力に溢れた1枚だった。
「僕は古い曲を引っ張り出して再生しているだけ」とは彼の言葉だが、
単なるアメリカン・ミュージックのノステルジックさだけじゃなく、
そこに現代的なタッチが加えられ、彼の最大の武器ボトルネック・ギター
と妙技とあいまって、何とも言えない味わい醸し出している。
後に、ハワイやメキシコなどの民族音楽的なものを積極的に取り入れたりと、
年を追う毎に、その存在はロック・シーンで重要化して行く。
またサントラ盤の制作でも引っ張りダコのモテモテ振りで、こんな凄い
アーティストに出会えた事を、あのキャンペーンに感謝しなくちゃ。
との思いが強いのです。
だから貴方も、このチャンスに“あの気になる1枚”をどうぞ!って訳。
ライの作品も何枚か入っているから。
RY COODER / RY COODER (1971年度作品)
Vol.63(1999年07月号掲載)
テレビ問題を書いていますね。
あぁ~、この頃のテレビの影響力は相当だったようで、今はその存在を
ネットに脅かされている。
あれだけチャンネルが増えりゃ、そりゃ質が落ちるのも当然で、ホント
観るに耐えられない番組も多い。
オリコンのところは、ちょっと説明不足で、代表的な例を出すと、未だ
にあるのがバラエティとか何かで、バカなタレントがCDを出して、それ
が何位に入るとか入らないとか!ってやつ。
踊らされて買う輩がいるのはしょうがないが、そのせいで、どうでもいい
ような曲がチャートの上位に入ってしまう。
そんな金儲けのお遊びと一緒に比較される、まっとうな音楽の悲しさ!
一生懸命作ったミュージシャンに申し訳ないでしょ。
そんなアホバカなヤツと優劣を問われてもと思うのですが、どう考えても
売れているものが“勝ち!”の世の中ですからね。
ラジオの衰退は、もうこの頃から危惧していたんですね。
ここで言うラジオはFM局の事だけど。
これだけラジオからヒットが出ていないと、やっぱりその存在を音楽業界
から疑われてもしょうがない。
なんせFM局は“音楽を売り!”にしてきたのだから。
ライ・クーダーは、書いてある通りローリング・ストーンズで、その存在を
知った。
音も聴いた事もないアーティストのLPを買うなんて、あの金の無いガキの
頃に出来る訳ないから、こうして手に入れたモノは貴重だった。
ギタリストって事で、エリック・クラプトンの如く、ガンガン弾いているのか
と思ったら、渋くて“?”が頭の中をクルクル廻っていたってぇのが正直な
ところ。
でも、ここで出会ってから、今まで出たオリジナル・アルバムは全部手に
入れているので、長~いお付き合いとなり、それこそ彼の音楽は、
俺にとって一生モンの音楽となった。
それとライが紹介してくれた、世界各地の音楽にもたくさん触れる事が出来、
ホント、いい出会いだったと、今は感謝している。
ただ(!?)で手に入れた一生もののアーティスト“ライ・クーダー”の
デビュー作。
「民放と女性誌ばかりみていると、脳がシュリンクしてしまう!」と言った
ヴィトンだかグッチだかのお偉いさんが居る。
某週刊誌で読んだ記事だが、これは、我輩が小学生の時に、テレビのせいで
我が日本は一億総白痴化する、と教えられた事の焼き直し版だ。
昔、ドリフターズの番組が低俗だとして、結構叩かれた事を記憶している方
も多いと思うが、今のテレビ番組のバカアホ加減は、その比じゃない。
時代が変わった。の一言で片付ける問題ではないような気がする。
と、何やら固い事を書いたが、今やテレビの影響力は凄いからな。
いい例が、皆さんが良く知っている、あのオリコンの何位に入らなかったら
どうのこう、ってやつ。
良いか悪いかは別にして、まぁ、良く売れているわなぁ。そんなやつが。
そんなこんなで、テレビは現時点で最高のプロモーションの場として成立
している訳だ。
それはそれでいいんだけど、問題はそれに追従するラジオ局。何もテレビ
で売り出そうとしているやつを応援する事ないじゃない。
これだけ音楽が溢れているんだから、テレビじゃ仲々聴けないのをオン
エアーしてよ。と言いたい。
ラジオの基本はお喋りは勿論だけれども、音楽も同じ位の比重を占めて
いるハズ。
確かに、テレビ発のヒット曲を流していれば聴取率的には安心なんだろう
けど、それなら映像付きのテレビを観ればいい訳だから・・・・・。
これだけ情報の発信源が多様化して競争が激化しているんだから、他と
一緒の事をやってても駄目でしょ。
な~んて偉そうな事を書いてみたけれど、まぁ、ようはもっと一杯いろ
んな音楽を聴かせて欲しいって事。
ほら、ディレクターさん、貴方の回りには、一杯役目を果たせぬまま
捨てられていくサンプル盤が山積みなんだから・・・・・(アーメン)。
さて、話は全然変わります。大手レコード会社のワーナー・ミュージック
が、洋楽キャンペーンとしてCDを3枚買うと1枚貰えるというキャンペーン
を今月一杯やっています。(詳細は、お近くのCDショップで。)
所謂低迷する旧譜の消費拡大を狙ったものだが、対象商品の殆どが、
この名盤に出て来ても遜色がないものだ。
こういったキャンペーンは過去にもあって、我輩も記憶にあるだけで2枚
の作品を手にした事がある。
何れも、興味はあるけど買う踏ん切りがつかなかった作品で、その1枚が、
デビュー直後のライ・クーダーのアルバムだった。
ストーンズのセッションで、その存在を知ったライは、当時、ラジオは勿論、
取り上げる媒体も少なく、そりゃ、買うには賭けだったネ。
だから、オマケで貰えるならって事で手に入れた訳。
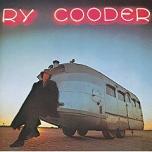
邦題「ライ・クーダー登場」は、それまで聴いていたロックに較べると、
何やら肩の力が抜けたような、すっ惚けた魅力に溢れた1枚だった。
「僕は古い曲を引っ張り出して再生しているだけ」とは彼の言葉だが、
単なるアメリカン・ミュージックのノステルジックさだけじゃなく、
そこに現代的なタッチが加えられ、彼の最大の武器ボトルネック・ギター
と妙技とあいまって、何とも言えない味わい醸し出している。
後に、ハワイやメキシコなどの民族音楽的なものを積極的に取り入れたりと、
年を追う毎に、その存在はロック・シーンで重要化して行く。
またサントラ盤の制作でも引っ張りダコのモテモテ振りで、こんな凄い
アーティストに出会えた事を、あのキャンペーンに感謝しなくちゃ。
との思いが強いのです。
だから貴方も、このチャンスに“あの気になる1枚”をどうぞ!って訳。
ライの作品も何枚か入っているから。
RY COODER / RY COODER (1971年度作品)
2009年03月17日
名盤/ Sly Stone & スガシカオ
続・名盤を探しに行こう!/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.62(1999年06月号掲載)
造詣が深い某氏って誰だったかな~などと考えながら書いています。
が、直ぐに分っちゃった。
近頃、音楽の深い話をする人がめっきりと減っちゃって寂しい限り。
ま、こっちも年取ってしまった分、そんなに熱くなって語るって事
はなくなったからいいですけど。
日本人は全員歌謡曲を演んなくちゃ~、ってところ、ちょっと考え
ちゃいますね。
今となっちゃ、歌謡曲って言葉自体が死語と言うか、若い人達に
言っても通じない音楽のジャンルじゃなないかと思う。
J-POPと言われる音楽の中でも、R&B風とHIP HOP風(または“っぽい”)
とかで流行っていてTVから流れている音楽って、結局は昔で言えば
歌謡曲なんですわ。なんせ飽くまでも“風”ですから。
と言うか、そのメロディーラインなんかは、なんともドメスティックな
感じで、日本人のDNAに沁みるんだろうな。
別に歌謡曲が悪いと言っている訳じゃないけど、DNAに訴えかけられたら、
もうどうしようもない。
さて、昨年の復活来日が、身内を含めて相当話題となったスライ・ストーン。
実際に観た人の話を聞くと、まぁ「?」ってとこだったらしいっす。
生きるレジェンドと言えば言えるけど、長い間活動していないし、そこは
俺が観たキャロル・キングやザ・フーと一緒にして考えたらかわそう。
今後、ちゃんと新しい音楽を作っていけるのかしらん。
この「FRESH」は、割と夢中で聴いた1枚で、CDは確か英国盤と米国盤とか
が違う原盤を使ったらしくて、音が違うって事で、CD番号を頼りに探して
両方を手に入れました。
スガシカオは、このデビュー盤を含め、初期は相当いい音楽を演っていた
ように思います。
なんせFUNK!そんな言葉を初めて聞いた音楽ファンも日本中にたくさん
居たんじゃないでしょうかね!
復活はあるのか?ファンク創始者の一人“スライ・ストーン”
ブラック・ミュージックに造詣が深いFM局某氏と、近頃の日本の音楽界
について、ある日の会話のさわりはこうだった。
某氏「最近のロック・バンドって、全然ロックっぽくないよな!」と。
これに対して俺は「それを言うなら、R&Bの方がそれこそそれっぽくない!」
と、一応ロックを擁護する形で問題点をすり替えて話を続けた訳。
まぁ、日本のロックの不甲斐なさを今更云々してもしょうがないし、
それよりも、今商売になるって事で、雨後のタケノコみたいに出てくる
ジャパニーズR&Bの方が・・・・・。ってな訳。
どうも俺の場合、例えば先月紹介したアリサみたいに濃いモノがないと、
R&Bって感じがしないんだな~。これが。
とは言うものの、R&Bも進化しているから、その過程で濃いものも薄れて
行くだろうし、薄れたからあり得るスタイルってものあるだろうし。
ましてはこれだけ多種多様になっている今だから、ひとつの型にはめるのは
難しいだろうしね。
んなぁ訳で、後は“血”で判断しろよ;つて事で、やっぱりR&B演るには
黒人に血が必要か!って事ですよね。
でも、そんな事言っていると、日本人は全員“歌謡曲”演んなきゃなんな
いしな~。
ところで、進化と言えば60年代末に浮上したスライ&ザ・ファミリー・
ストーンって、当時どんな受け止められ方をしたんだろう。
俺の僅かながらの記憶によると、当時TVで観た彼らは「黒人なのにロック
みたい!」な感じかなっ。
とは言うものの、音楽を聴き始めたばかりの子供に、これがロックで、
これがR&B。みたいなカテゴリー分けを出来るだけの能力があったかどうか
は疑問だから、この第一印象は、あまりあてにならないんだけれども・・・。
でも、専門誌なんかによると、70年代の新しい黒人音楽を創造した一人に
スライ・ストーンが挙げられるから、当時、黒人のR&Bよりもロックっぽく
思えたつっうのはまんざらでもないかもネ。
さて彼らのアルバムを1枚選べと言われたら、やっぱり「STAND!」でしょうかね。
という当たり前の選択は止めて「FRESH」ってのはどうでしょう。
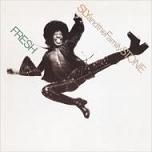
ファンクやらサイケやら、当時の世相とブラック・ミュージックの隆盛を
反映させた名作「STAND!」のホットさとは別の、ある種のクールさを感じ
させる「FRESH」。
そのクールさって、この2作の間にあるアルバム「暴動」から使われ始めた
リズム・ボックスのせいなのかなっ。と書いちゃうと、俄然「FRESH」1枚じゃ
収まらなくて、この3枚をまとめて聴かなくちゃならないような気になる。
それも良し!スライはこの時代を押さえておけば大丈夫だから。
そして、今時のジャストなファンクに慣れた体には、微妙に揺れ動くような
感じのスライのファンクが妙に気持ちいいかもネ。
いずれにしても、その後のブラックは勿論、ポップ・ミュージック全般に
多大な影響を及ぼしたスライは、是非聴いてみて欲しい。
スライが大好きって日本のミュージシャンは多い。その中の一人にスガ
シカオがいる。
今年の大ホール・ツアーでは、ちゃんと1曲カバーしていたし・・・・。
ファンクを土台に築き上げた彼の音楽には、本家のファンクやR&Bに対する
負い目はない。
それは、最初から“自分の血で音楽をする!”と言う潔いポリシーがあるからで、
決して、流行廃りで音楽をしている訳じゃないからだ。
デビュー・アルバム「Clover」は、そんな彼の清々しい音楽が詰まっている。
洋楽ファンも、スライと併せて聴いてみるべし。
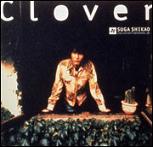
ところで、現われては消えるスライのカムバックの噂って、本当はどうなん
だろう。世紀末にむけて恰好良く復活してくれ!と思っているのは、
俺だけじゃないはずだ。
SLY & THE FAMILY STONE / FRESH (1973年度作品)
スガシカオ / Clover(1997年度作品)
Vol.62(1999年06月号掲載)
造詣が深い某氏って誰だったかな~などと考えながら書いています。
が、直ぐに分っちゃった。
近頃、音楽の深い話をする人がめっきりと減っちゃって寂しい限り。
ま、こっちも年取ってしまった分、そんなに熱くなって語るって事
はなくなったからいいですけど。
日本人は全員歌謡曲を演んなくちゃ~、ってところ、ちょっと考え
ちゃいますね。
今となっちゃ、歌謡曲って言葉自体が死語と言うか、若い人達に
言っても通じない音楽のジャンルじゃなないかと思う。
J-POPと言われる音楽の中でも、R&B風とHIP HOP風(または“っぽい”)
とかで流行っていてTVから流れている音楽って、結局は昔で言えば
歌謡曲なんですわ。なんせ飽くまでも“風”ですから。
と言うか、そのメロディーラインなんかは、なんともドメスティックな
感じで、日本人のDNAに沁みるんだろうな。
別に歌謡曲が悪いと言っている訳じゃないけど、DNAに訴えかけられたら、
もうどうしようもない。
さて、昨年の復活来日が、身内を含めて相当話題となったスライ・ストーン。
実際に観た人の話を聞くと、まぁ「?」ってとこだったらしいっす。
生きるレジェンドと言えば言えるけど、長い間活動していないし、そこは
俺が観たキャロル・キングやザ・フーと一緒にして考えたらかわそう。
今後、ちゃんと新しい音楽を作っていけるのかしらん。
この「FRESH」は、割と夢中で聴いた1枚で、CDは確か英国盤と米国盤とか
が違う原盤を使ったらしくて、音が違うって事で、CD番号を頼りに探して
両方を手に入れました。
スガシカオは、このデビュー盤を含め、初期は相当いい音楽を演っていた
ように思います。
なんせFUNK!そんな言葉を初めて聞いた音楽ファンも日本中にたくさん
居たんじゃないでしょうかね!
復活はあるのか?ファンク創始者の一人“スライ・ストーン”
ブラック・ミュージックに造詣が深いFM局某氏と、近頃の日本の音楽界
について、ある日の会話のさわりはこうだった。
某氏「最近のロック・バンドって、全然ロックっぽくないよな!」と。
これに対して俺は「それを言うなら、R&Bの方がそれこそそれっぽくない!」
と、一応ロックを擁護する形で問題点をすり替えて話を続けた訳。
まぁ、日本のロックの不甲斐なさを今更云々してもしょうがないし、
それよりも、今商売になるって事で、雨後のタケノコみたいに出てくる
ジャパニーズR&Bの方が・・・・・。ってな訳。
どうも俺の場合、例えば先月紹介したアリサみたいに濃いモノがないと、
R&Bって感じがしないんだな~。これが。
とは言うものの、R&Bも進化しているから、その過程で濃いものも薄れて
行くだろうし、薄れたからあり得るスタイルってものあるだろうし。
ましてはこれだけ多種多様になっている今だから、ひとつの型にはめるのは
難しいだろうしね。
んなぁ訳で、後は“血”で判断しろよ;つて事で、やっぱりR&B演るには
黒人に血が必要か!って事ですよね。
でも、そんな事言っていると、日本人は全員“歌謡曲”演んなきゃなんな
いしな~。
ところで、進化と言えば60年代末に浮上したスライ&ザ・ファミリー・
ストーンって、当時どんな受け止められ方をしたんだろう。
俺の僅かながらの記憶によると、当時TVで観た彼らは「黒人なのにロック
みたい!」な感じかなっ。
とは言うものの、音楽を聴き始めたばかりの子供に、これがロックで、
これがR&B。みたいなカテゴリー分けを出来るだけの能力があったかどうか
は疑問だから、この第一印象は、あまりあてにならないんだけれども・・・。
でも、専門誌なんかによると、70年代の新しい黒人音楽を創造した一人に
スライ・ストーンが挙げられるから、当時、黒人のR&Bよりもロックっぽく
思えたつっうのはまんざらでもないかもネ。
さて彼らのアルバムを1枚選べと言われたら、やっぱり「STAND!」でしょうかね。
という当たり前の選択は止めて「FRESH」ってのはどうでしょう。
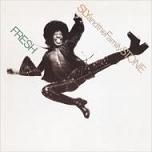
ファンクやらサイケやら、当時の世相とブラック・ミュージックの隆盛を
反映させた名作「STAND!」のホットさとは別の、ある種のクールさを感じ
させる「FRESH」。
そのクールさって、この2作の間にあるアルバム「暴動」から使われ始めた
リズム・ボックスのせいなのかなっ。と書いちゃうと、俄然「FRESH」1枚じゃ
収まらなくて、この3枚をまとめて聴かなくちゃならないような気になる。
それも良し!スライはこの時代を押さえておけば大丈夫だから。
そして、今時のジャストなファンクに慣れた体には、微妙に揺れ動くような
感じのスライのファンクが妙に気持ちいいかもネ。
いずれにしても、その後のブラックは勿論、ポップ・ミュージック全般に
多大な影響を及ぼしたスライは、是非聴いてみて欲しい。
スライが大好きって日本のミュージシャンは多い。その中の一人にスガ
シカオがいる。
今年の大ホール・ツアーでは、ちゃんと1曲カバーしていたし・・・・。
ファンクを土台に築き上げた彼の音楽には、本家のファンクやR&Bに対する
負い目はない。
それは、最初から“自分の血で音楽をする!”と言う潔いポリシーがあるからで、
決して、流行廃りで音楽をしている訳じゃないからだ。
デビュー・アルバム「Clover」は、そんな彼の清々しい音楽が詰まっている。
洋楽ファンも、スライと併せて聴いてみるべし。
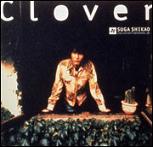
ところで、現われては消えるスライのカムバックの噂って、本当はどうなん
だろう。世紀末にむけて恰好良く復活してくれ!と思っているのは、
俺だけじゃないはずだ。
SLY & THE FAMILY STONE / FRESH (1973年度作品)
スガシカオ / Clover(1997年度作品)