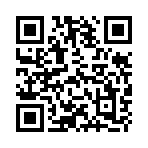keith yoshidaの新・飯がわりに1枚!(Again) › 名盤を探しに行こう!
2009年03月11日
名盤/ Aretha & 角松敏生
続・名盤を探しに行こう!/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.61(1999年05月号掲載)
この大阪での出来事は、スガシカオが大阪城ホールという、デカイ会場で
ライヴを演るので、どんなもんかなっ!と観に行った時ですね。
彼のバックバンド“Family Sugar”の面々と一緒に行った、とある店の
出来事です。
アリサ・フランクリンと言えば、この間のオバーマ就任式で唄ってました。
ちゃんと観なかったけど、TV画面にアリサが映っているのをなんとなく
眺めていました。
基本的にライヴ盤は好きじゃないので聴く機会が少ない。
今時、ライヴと言えばDVDでしょ。いつの間にか安価になっちゃって
(と言うか最初から安かったような・・・)、ライヴは映像を伴った方がいい
に決まっているから、ライヴ盤ってぇのは、もう殆どお役目御免状態。
昔は、映像ものは価格が高かったから、なかなか買えなかった。
ニール・ヤングの「RUST NEVER SLEEPS」のVHSなんか、輸入盤で
20,000円くらいして、買うのに相当勇気が必要だった。
そんな時代を過ごした者には隔世な感じがしますな~。
観られないライヴを想像すると言う事で、自身の想像力を豊かに出来るのに!
とは思ってしまうが、もう、そんな事も言っていられない時代なんでしょ。
ネットを通じて、観なくてもいいものまで観えちゃう!困った時代。
今の世の中、便利さが簡単に供与されて、それを当たり前のように使いこなす
ようになったけど、それとは裏腹に失ったモノが沢山有る!っつうのに、早く気
づいてよ!皆さん!
圧倒的な熱気を感じさせる70年代のライヴ盤の名作。
前号の続きっぽくなるが、ジミ・ヘンドリックスにしてもロリー・ギャラガー
にしてもライヴ盤が仲々捨て難い。
個人的には、フェイヴァリットなアーティストでもライヴ盤を頻繁に聴く。
という事がないので、両アーティストのライヴ盤は、ちょっとだけライヴ盤
の良さを見直す切っ掛けとなりそうだ。
そう言えば、昨年末からここで載り上げたボブ・ディランのライヴ盤や映画
「YEAR OF THE HORSE」観覧後のニール・ヤングの聴き方など、なんとなく
ライヴ盤付いている事は間違いないようだ。
それも60年代末から70年代初頭のものが多く、所謂ロックがロックらしく
輝いていたと言われる時代で、やっぱりロックはこの辺に落ち着くのかな~。
そんな中、先日大阪に行った際、地元のFM局の方々の隠れ家的飲み屋で、
これまた決定的なライヴ盤に再会してしまい、一緒に居たミュージシャン
連中と大盛り上がりしてしまった。
テーブルをドラム変わりにする者もいれば、空でギターやベイスを弾く者、
そしてバーナード・パーディ云々とミュージシャン談義に花を咲かせる者、
勿論一緒に唄っちゃうのは当たり前。
そんな大騒ぎを演出しちゃう位、皆に愛されているあんたはし幸福者だよ。
と思ったのがR&B界の大御所アリサ・フランクリン。
そして彼女の名作ライヴ盤「live at fillmore west」。
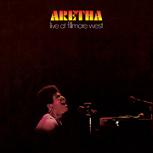
フィルモア・ウェストと言えば、あの当時のロックの震源地。数多くの
ロックの名演がここで生まれ語り継がれている訳だが、そこに黒人女性
シンガーNo.1の彼女が乗り込んでのパフォーマンスの模様を収録したのが、
このアルバムだ。
敵地に乗り込んだ感もあるこの場を、彼女はまず、代表曲「リスペクト」
で客の心を掴みかかる。そして、それに輪をかけるように、カバーで白人
のヒット曲のオンパレードをぶちかます訳。
「愛への讃歌」「明日に架ける橋」「エリナー・リグビー」、そしてブレッド
の「二人の架け橋」まで唄っちゃうサービス振り。
勿論、この後きっちりと自身のナンバーなどで、どっぷりとブラックしちゃて
帳尻を合わす訳なんだけど・・・・・。
まぁ、圧巻はレイ・チャールズが飛び入りする「Spirit in The Sky」の盛り
上がり辺りか。百聞は一見じゃなくて一聴云々。とにかく聴きなさい。
ゴスペルを土台にした、彼女のソウルフルでエモーショナルな唄っぷりを。
あんな風に唄えたら、さぞかし気持ちいいだろう。と思っちゃう程、アリサ
の唄いっぷりに脱帽しちゃうから。
日本のアーティストで、ライヴ盤を手に入れようと思ったのが角松敏生。
あぁ~、この人、俺全然普段聴かないから、良く知らないんだけど、89年
に出たライヴ盤「`89 8.26/MORE DESIRE」の「機関車」を聴いて、一発で
欲しくなりました。

小坂忠のオリジナル自体がそうだったように、実にソウルフルな唄いっぷりの
カバーに惹かれた訳で、ライヴ盤自体、角松が愛してやまないであろう、
まだ商業主義に犯されていない、70年代の日本のロックの名曲達をカバー
したもの。
聴く度に、鈴木茂をはじめとする錚々たる面々による、この一夜限りのライヴ
に立ち会えた幸運なオーディエンスを、羨ましいと思うのは俺だけだろうか。
ってな訳で、仲々観れないアーティストとイヴェントを楽しむには、ライヴ
盤ってありがたい。
でも、やっぱり、当たり前だけど“生”には敵いません。ハイ。
ARETHA FRANKLIN / ALTHA LIVE AT FILLMORE WEST (1971年度作品)
角松敏生 / TOSHIKI KADOMATSU SPECIAL LIVE `89.8.26(1989年度作品)
Vol.61(1999年05月号掲載)
この大阪での出来事は、スガシカオが大阪城ホールという、デカイ会場で
ライヴを演るので、どんなもんかなっ!と観に行った時ですね。
彼のバックバンド“Family Sugar”の面々と一緒に行った、とある店の
出来事です。
アリサ・フランクリンと言えば、この間のオバーマ就任式で唄ってました。
ちゃんと観なかったけど、TV画面にアリサが映っているのをなんとなく
眺めていました。
基本的にライヴ盤は好きじゃないので聴く機会が少ない。
今時、ライヴと言えばDVDでしょ。いつの間にか安価になっちゃって
(と言うか最初から安かったような・・・)、ライヴは映像を伴った方がいい
に決まっているから、ライヴ盤ってぇのは、もう殆どお役目御免状態。
昔は、映像ものは価格が高かったから、なかなか買えなかった。
ニール・ヤングの「RUST NEVER SLEEPS」のVHSなんか、輸入盤で
20,000円くらいして、買うのに相当勇気が必要だった。
そんな時代を過ごした者には隔世な感じがしますな~。
観られないライヴを想像すると言う事で、自身の想像力を豊かに出来るのに!
とは思ってしまうが、もう、そんな事も言っていられない時代なんでしょ。
ネットを通じて、観なくてもいいものまで観えちゃう!困った時代。
今の世の中、便利さが簡単に供与されて、それを当たり前のように使いこなす
ようになったけど、それとは裏腹に失ったモノが沢山有る!っつうのに、早く気
づいてよ!皆さん!
圧倒的な熱気を感じさせる70年代のライヴ盤の名作。
前号の続きっぽくなるが、ジミ・ヘンドリックスにしてもロリー・ギャラガー
にしてもライヴ盤が仲々捨て難い。
個人的には、フェイヴァリットなアーティストでもライヴ盤を頻繁に聴く。
という事がないので、両アーティストのライヴ盤は、ちょっとだけライヴ盤
の良さを見直す切っ掛けとなりそうだ。
そう言えば、昨年末からここで載り上げたボブ・ディランのライヴ盤や映画
「YEAR OF THE HORSE」観覧後のニール・ヤングの聴き方など、なんとなく
ライヴ盤付いている事は間違いないようだ。
それも60年代末から70年代初頭のものが多く、所謂ロックがロックらしく
輝いていたと言われる時代で、やっぱりロックはこの辺に落ち着くのかな~。
そんな中、先日大阪に行った際、地元のFM局の方々の隠れ家的飲み屋で、
これまた決定的なライヴ盤に再会してしまい、一緒に居たミュージシャン
連中と大盛り上がりしてしまった。
テーブルをドラム変わりにする者もいれば、空でギターやベイスを弾く者、
そしてバーナード・パーディ云々とミュージシャン談義に花を咲かせる者、
勿論一緒に唄っちゃうのは当たり前。
そんな大騒ぎを演出しちゃう位、皆に愛されているあんたはし幸福者だよ。
と思ったのがR&B界の大御所アリサ・フランクリン。
そして彼女の名作ライヴ盤「live at fillmore west」。
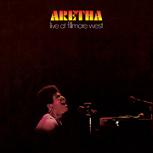
フィルモア・ウェストと言えば、あの当時のロックの震源地。数多くの
ロックの名演がここで生まれ語り継がれている訳だが、そこに黒人女性
シンガーNo.1の彼女が乗り込んでのパフォーマンスの模様を収録したのが、
このアルバムだ。
敵地に乗り込んだ感もあるこの場を、彼女はまず、代表曲「リスペクト」
で客の心を掴みかかる。そして、それに輪をかけるように、カバーで白人
のヒット曲のオンパレードをぶちかます訳。
「愛への讃歌」「明日に架ける橋」「エリナー・リグビー」、そしてブレッド
の「二人の架け橋」まで唄っちゃうサービス振り。
勿論、この後きっちりと自身のナンバーなどで、どっぷりとブラックしちゃて
帳尻を合わす訳なんだけど・・・・・。
まぁ、圧巻はレイ・チャールズが飛び入りする「Spirit in The Sky」の盛り
上がり辺りか。百聞は一見じゃなくて一聴云々。とにかく聴きなさい。
ゴスペルを土台にした、彼女のソウルフルでエモーショナルな唄っぷりを。
あんな風に唄えたら、さぞかし気持ちいいだろう。と思っちゃう程、アリサ
の唄いっぷりに脱帽しちゃうから。
日本のアーティストで、ライヴ盤を手に入れようと思ったのが角松敏生。
あぁ~、この人、俺全然普段聴かないから、良く知らないんだけど、89年
に出たライヴ盤「`89 8.26/MORE DESIRE」の「機関車」を聴いて、一発で
欲しくなりました。

小坂忠のオリジナル自体がそうだったように、実にソウルフルな唄いっぷりの
カバーに惹かれた訳で、ライヴ盤自体、角松が愛してやまないであろう、
まだ商業主義に犯されていない、70年代の日本のロックの名曲達をカバー
したもの。
聴く度に、鈴木茂をはじめとする錚々たる面々による、この一夜限りのライヴ
に立ち会えた幸運なオーディエンスを、羨ましいと思うのは俺だけだろうか。
ってな訳で、仲々観れないアーティストとイヴェントを楽しむには、ライヴ
盤ってありがたい。
でも、やっぱり、当たり前だけど“生”には敵いません。ハイ。
ARETHA FRANKLIN / ALTHA LIVE AT FILLMORE WEST (1971年度作品)
角松敏生 / TOSHIKI KADOMATSU SPECIAL LIVE `89.8.26(1989年度作品)
2009年03月02日
名盤/ RORY GALLAGHER
続・名盤を探しに行こう!/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.60(1999年04月号掲載)
「洋楽を知ってもらう!」という志はいいのだが、どうも“WE!”の
読者に、それが響いていたのかは疑問。
日本のミュージシャンばかりを手掛けるイヴェンターが配っている
フリーペーパーだから、その手の音楽ファンしかいなかったのかも。
もう少し体系的に聴き込むファンがいても可笑しくはないのに、どうも
この時代を含め、今の、いわゆるJ-POPファンは、そういった事が動機
にならないらしい。
ま、いいんだけど、ルーツを聴く、ましてや本物を聴く感動ってモンに、
それじゃ、辿り着けない。
軽薄短小、そういう時代の風潮って訳。
ロリーさんは残念ながら縁が薄いと言うか、こういう機会がないと聴く
事がなかった。それは今も変わらないけど・・・。
ホント、久しぶりにこのアルバムを聴いたけど、ハードロックよりの
云々の記述に、確かに近い感触のサウンドもあるけど、やっぱ泥臭さが
ね~。ま、それがあの時代だって言ってしまえばお仕舞いだけど。
何度再発されているのかは知らないけれど、近頃では紙ジャケで、レコ
ード盤でリリースされたオリジナル通りのジャケットになったようだ。
古くからのファンには、その方が馴染むでしょ。
ギター・フリークは聴き直す価値有り。骨っぽいロリーのブルース・ロック!
「邦楽についての書き方が不充分だ。」とのお叱りとも不満とも受け取れる
指摘を戴いた。
ん~、困った。本当にそうなんだから言い訳出来ない。
連載60回記念なのに、お祝じゃなくて苦情だぜ。
大体、この連載を始めた切っ掛けは、WE!読者が普段聴いている日本の
ミュージシャン達が、影響を受けたり愛聴しているであろう洋楽を知って
貰おう。と言う主旨だった。と言い訳したりして。
だから洋楽さえ紹介すればいい訳で、まぁ、邦楽は刺身の“つま”みたい
なもん。な~んて言っちゃっていいのかしら。
ところで、某プロモーター氏から祝60回記念として(多分、某氏は、
そんな事を全然意識していない。)再発された“ロリー・ギャラガー”
のCDを一式戴いた。
ん~、貢ぎ物だ。弱いんだよな。これに。
まぁ、体質的には政治家と一緒だから、袖の下を渡されちゃ、いいように
首を振らなきゃいけないだろう。
そんな事より、近頃、日々ジミヘンなんです。そう、ジミ・ヘンドリックス。
切っ掛けはひょんな事。何年か前に再発されたジミのCDを手に入れて、
その音の良さにビックリ。
慌てて全部買い揃えたのに追い撃ちをかけるように、Band of Gypsysの
ライヴまで限りなくコンプリートな形でリリースされ、そりゃ~聴くのが
大変なんですわ・・・・・。
ギターを弾きまくりの快感に溺れる我身にロリー・ギャラガー。これこそ
火に油を注ぐようなもの。
そんな訳でロリー・ギャラガーなんだけれど、多分、こんな事がなければ、
この名盤で載り上げる事はなかったろう。だって、すっかりその存在を
忘れていたもん。さらに“つま”となる日本人が全然頭に浮かばない。
例えで言うと、料理人が包丁1本で世間を渡ってるみたいに、この人の
場合は、それをギター1本に持ち替えてでしょう。そんなイメージの
日本人っていたっけ。既に書いたCharや仲井戸麗一なんかは抜かして・・・。
誰かいたっけ・・・・・。
さて、ロリー・ギャラガーである。忘れていただけあって、我が家のレコード
棚を捜しても、LPがたった1枚しかなかった。
76年の「コーリング・カード」で、もともと、これと前年に発表された
「Against The Grain」があれば事はすむと思っていた。
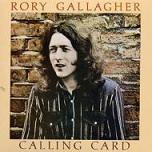
こうしてCD化されたものを聴き比べて、結局愛着がある「コーリング・
カード」を選んだ訳だけど、それ以前にリリースされたブルーズ・フィーリング
溢れるプリミティヴな演奏が楽しめる各アルバムも捨て難い。
この「コーリング・カード」の顔とも言えるヒット・チューン「Moonchild」
に代表されるように、ブルース・ロックからハード・ロックへシフト・チェンジ中
の、当時のロリーの充実振りが隋所で聴かれる1枚で、共同
プロデューサーとしてディープ・パープルのロジャー・グローヴァーが
参加している事を、今回ライナーノーツを読んで初めて知った。
ってな訳で、往年のパープル・ファンにも結構楽しめる内容とも言えるし、
ギターリスト好きは勿論、そうそう、洗練される前のクラプトンが好き!
って人にもお薦めだ。
で、ここまで書いたけど、やっぱり、ブルースとギターが似合って、一匹
狼的日本人ギターリストって、思い浮かばない。だから、前述通り、
今月は無理して“つま”は付けません。あしからず。
RORY GALLAGHER / CALLING CARD(1976年度作品)
Vol.60(1999年04月号掲載)
「洋楽を知ってもらう!」という志はいいのだが、どうも“WE!”の
読者に、それが響いていたのかは疑問。
日本のミュージシャンばかりを手掛けるイヴェンターが配っている
フリーペーパーだから、その手の音楽ファンしかいなかったのかも。
もう少し体系的に聴き込むファンがいても可笑しくはないのに、どうも
この時代を含め、今の、いわゆるJ-POPファンは、そういった事が動機
にならないらしい。
ま、いいんだけど、ルーツを聴く、ましてや本物を聴く感動ってモンに、
それじゃ、辿り着けない。
軽薄短小、そういう時代の風潮って訳。
ロリーさんは残念ながら縁が薄いと言うか、こういう機会がないと聴く
事がなかった。それは今も変わらないけど・・・。
ホント、久しぶりにこのアルバムを聴いたけど、ハードロックよりの
云々の記述に、確かに近い感触のサウンドもあるけど、やっぱ泥臭さが
ね~。ま、それがあの時代だって言ってしまえばお仕舞いだけど。
何度再発されているのかは知らないけれど、近頃では紙ジャケで、レコ
ード盤でリリースされたオリジナル通りのジャケットになったようだ。
古くからのファンには、その方が馴染むでしょ。
ギター・フリークは聴き直す価値有り。骨っぽいロリーのブルース・ロック!
「邦楽についての書き方が不充分だ。」とのお叱りとも不満とも受け取れる
指摘を戴いた。
ん~、困った。本当にそうなんだから言い訳出来ない。
連載60回記念なのに、お祝じゃなくて苦情だぜ。
大体、この連載を始めた切っ掛けは、WE!読者が普段聴いている日本の
ミュージシャン達が、影響を受けたり愛聴しているであろう洋楽を知って
貰おう。と言う主旨だった。と言い訳したりして。
だから洋楽さえ紹介すればいい訳で、まぁ、邦楽は刺身の“つま”みたい
なもん。な~んて言っちゃっていいのかしら。
ところで、某プロモーター氏から祝60回記念として(多分、某氏は、
そんな事を全然意識していない。)再発された“ロリー・ギャラガー”
のCDを一式戴いた。
ん~、貢ぎ物だ。弱いんだよな。これに。
まぁ、体質的には政治家と一緒だから、袖の下を渡されちゃ、いいように
首を振らなきゃいけないだろう。
そんな事より、近頃、日々ジミヘンなんです。そう、ジミ・ヘンドリックス。
切っ掛けはひょんな事。何年か前に再発されたジミのCDを手に入れて、
その音の良さにビックリ。
慌てて全部買い揃えたのに追い撃ちをかけるように、Band of Gypsysの
ライヴまで限りなくコンプリートな形でリリースされ、そりゃ~聴くのが
大変なんですわ・・・・・。
ギターを弾きまくりの快感に溺れる我身にロリー・ギャラガー。これこそ
火に油を注ぐようなもの。
そんな訳でロリー・ギャラガーなんだけれど、多分、こんな事がなければ、
この名盤で載り上げる事はなかったろう。だって、すっかりその存在を
忘れていたもん。さらに“つま”となる日本人が全然頭に浮かばない。
例えで言うと、料理人が包丁1本で世間を渡ってるみたいに、この人の
場合は、それをギター1本に持ち替えてでしょう。そんなイメージの
日本人っていたっけ。既に書いたCharや仲井戸麗一なんかは抜かして・・・。
誰かいたっけ・・・・・。
さて、ロリー・ギャラガーである。忘れていただけあって、我が家のレコード
棚を捜しても、LPがたった1枚しかなかった。
76年の「コーリング・カード」で、もともと、これと前年に発表された
「Against The Grain」があれば事はすむと思っていた。
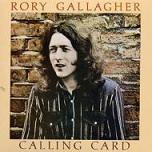
こうしてCD化されたものを聴き比べて、結局愛着がある「コーリング・
カード」を選んだ訳だけど、それ以前にリリースされたブルーズ・フィーリング
溢れるプリミティヴな演奏が楽しめる各アルバムも捨て難い。
この「コーリング・カード」の顔とも言えるヒット・チューン「Moonchild」
に代表されるように、ブルース・ロックからハード・ロックへシフト・チェンジ中
の、当時のロリーの充実振りが隋所で聴かれる1枚で、共同
プロデューサーとしてディープ・パープルのロジャー・グローヴァーが
参加している事を、今回ライナーノーツを読んで初めて知った。
ってな訳で、往年のパープル・ファンにも結構楽しめる内容とも言えるし、
ギターリスト好きは勿論、そうそう、洗練される前のクラプトンが好き!
って人にもお薦めだ。
で、ここまで書いたけど、やっぱり、ブルースとギターが似合って、一匹
狼的日本人ギターリストって、思い浮かばない。だから、前述通り、
今月は無理して“つま”は付けません。あしからず。
RORY GALLAGHER / CALLING CARD(1976年度作品)
2009年02月18日
名盤/井上陽水& BOZ SCAGGS
続・名盤を探しに行こう!/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.59(1999年03月号掲載)
前回の名盤のところに書いたニール・ヤングのアーカイヴシリーズの
BOXのDVDの10枚組って、映像と言うよりDVDオーディオらしい・・・。
う~ん、良く考えりゃ「そうか!」と思うけど、一体、ホントはどう
なんでしょう。
知っている人が居ましたら、ちゃんと教えて下さいな!
さてと話が変って今回の名盤です。
これはハッキリと覚えている。
何がって?ようするに陽水とボズを結び付けた瞬間!
完全に呑み屋で一人呑みしている時に、BGMとして流れていた
ボズの唄を聴いてですね。
その唄い方を聴いていて、誰かに似ているな~と。
何かイージーに思えるけど、物事ってそんなもんです。
ボズも、前に書いたブルース・スプリングスティーン同様、全く聴く
事がなくなった。
ま、たまにラジオから聴こえてくる分にはいいんですけど、改めて
アルバムを出してまでとはいかない。
時々新譜を出したりしているようだけど、それって日本向けに
作ちゃってる訳じゃないですよね。
本国ではどんな活動しているのか、さっぱり分からないもんで。
レストラン経営云々で、この人の情報は止まったままです。
それにしても「SILK DEGREES」以降の何作かは、とんでもない
くらい夢中になったのに・・・・・。
井上陽水は今年デビュー40周年だそうです。
まだまだバリバリの現役で、たま出てくる新作アルバムは、きちんと、
その時代感覚を租借した音になっていて、驚く事がある。
どこで勉強しているんだろう?
あの時代、一度、挫折から立ち直るには、フォークで出るのが近道
だったのかなっ?と今更ながら考えてしまう。
作風からすると、本質はフォークじゃないよな~、この人は。
見事に“大人の音楽を齧った!”と思わせた顔役(!?)のアルバム。
A.O.Rである。と唐突に書き出しても困っちゃうよね。
なんの事はない“Adult Oriented Rock”の略である。ものの本によると
「大人向きのロック」と、実に分かり易く書いてあった。
突然こんな事から書き出してしまったけど、A.O.Rって、いまだに音楽を
表現する時に使う事がある。読者の方も、何度か出会った事があるでしょ。
“大人向きロック”ってどんなんだろう。と、ふと考えると、これが漠然
としている。果たして今の時代に適当な表現の言葉なんだろうかと。
このA.O.Rって言葉が生まれたのは70年代中頃の事だったと記憶している。
背景的には60年末から70年代初頭のイギリス~アメリカのニュー・ロック
やらプログレ、ウェストコーストらの勢力が一段落した後、シンガー・
ソンングライターやシティ・ミュージックが勢力を延ばした時と同時位
だろう。
まぁ、ロックンロール・ミュージックが誕生してから、ビートルズを経由
して巨大産業化していく過程で育った子供達が、そこそこの大人になって、
いつまでもガキの音楽“ロックンロール”なんぞ聴いてられない。
と言ったかどうかは分からないけど、多分、そんなマーケットに向けて
作られたのが、このA.O.Rだったのかも知れない。
その第一人者と言い切っていいのかどうかは分からないが、真先に浮かんで
くるのは“ボズ・スキャグス”だ。
で、当然、その後のシーンに多大な影響を及ぼした大ベストセラー・
アルバム「SILK DEGREES」の事になると思うでしょう。ところがどっこい、
捻くれ者だから違うんだな。これが。
前号のスプリングスティーン同様、その人気が爆発する直前がいいんだな。
何故か・・・・・。
と言う訳で、ボズの場合、絶対的に「SLOW DANCER」なのです。

このアルバム、日本で発売された当時「シスコの顔役」などと言う物騒な
邦題を付けられていた訳で、レコード店であのジャケットを見たら、タイ
トルのイメージと相まって、そりゃ~、それなりのインパクトがあったのは
確かだ。
元々R&B的な資質を持ち、そういった方向性を模索していたボズにとって、
このアルバムで出会ったプロデューサー“ジョニー・ブリストル”との
相性はドンピシャだった。
今回、この原稿を書くにあたって久々にレコード棚から引っ張り出して
聴いてみたが、正に名曲名演名唱の3拍子揃い踏みの連続で、名盤「SILK
DEGREES」なんのその。って感じなのです。
CD化に伴って、あの売らんが為の再発の劣悪デザインのジャケットが一掃
され、オリジナル・ジャケットになって価格も廉価のいい事づくめ。
男も惚れる(!?)あの水着姿をみつつ、ボズの歌声に酔って下さい。
そんなボズの名曲達を聴きながら、こんな歌い方する日本人がいるな~、
と顔が浮かんできたのが井上陽水。
まぁ、日本のA.O.Rの先駆者と言っても過言じゃないでしょ。
真先にフォークへの拘わりをすてて(!?)ロック的なアプローチを開始後数年。
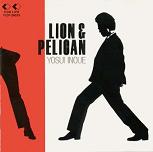
徐々に陽水流A.O.Rは進化を遂げ「LION & PELICAN」という名盤を産み出す
訳。あの「リバーサイドホテル」(ヒットしたのは6年も後の事)が収録された
アルバムだ。ってな所で、またも紙面が尽きてきた。
陽水については、再度何かの機会に取り上げたいと思う。
そしてボズ、陽水両者共、あのサングラスが大人を演出する上で欠かせない
小道具だったりして・・・・・。そんな訳ないか~。
BOZ SCAGGS / SLOW DANCER (1974年度作品)
井上陽水 / LION & PELICAN (1982年度作品)
Vol.59(1999年03月号掲載)
前回の名盤のところに書いたニール・ヤングのアーカイヴシリーズの
BOXのDVDの10枚組って、映像と言うよりDVDオーディオらしい・・・。
う~ん、良く考えりゃ「そうか!」と思うけど、一体、ホントはどう
なんでしょう。
知っている人が居ましたら、ちゃんと教えて下さいな!
さてと話が変って今回の名盤です。
これはハッキリと覚えている。
何がって?ようするに陽水とボズを結び付けた瞬間!
完全に呑み屋で一人呑みしている時に、BGMとして流れていた
ボズの唄を聴いてですね。
その唄い方を聴いていて、誰かに似ているな~と。
何かイージーに思えるけど、物事ってそんなもんです。
ボズも、前に書いたブルース・スプリングスティーン同様、全く聴く
事がなくなった。
ま、たまにラジオから聴こえてくる分にはいいんですけど、改めて
アルバムを出してまでとはいかない。
時々新譜を出したりしているようだけど、それって日本向けに
作ちゃってる訳じゃないですよね。
本国ではどんな活動しているのか、さっぱり分からないもんで。
レストラン経営云々で、この人の情報は止まったままです。
それにしても「SILK DEGREES」以降の何作かは、とんでもない
くらい夢中になったのに・・・・・。
井上陽水は今年デビュー40周年だそうです。
まだまだバリバリの現役で、たま出てくる新作アルバムは、きちんと、
その時代感覚を租借した音になっていて、驚く事がある。
どこで勉強しているんだろう?
あの時代、一度、挫折から立ち直るには、フォークで出るのが近道
だったのかなっ?と今更ながら考えてしまう。
作風からすると、本質はフォークじゃないよな~、この人は。
見事に“大人の音楽を齧った!”と思わせた顔役(!?)のアルバム。
A.O.Rである。と唐突に書き出しても困っちゃうよね。
なんの事はない“Adult Oriented Rock”の略である。ものの本によると
「大人向きのロック」と、実に分かり易く書いてあった。
突然こんな事から書き出してしまったけど、A.O.Rって、いまだに音楽を
表現する時に使う事がある。読者の方も、何度か出会った事があるでしょ。
“大人向きロック”ってどんなんだろう。と、ふと考えると、これが漠然
としている。果たして今の時代に適当な表現の言葉なんだろうかと。
このA.O.Rって言葉が生まれたのは70年代中頃の事だったと記憶している。
背景的には60年末から70年代初頭のイギリス~アメリカのニュー・ロック
やらプログレ、ウェストコーストらの勢力が一段落した後、シンガー・
ソンングライターやシティ・ミュージックが勢力を延ばした時と同時位
だろう。
まぁ、ロックンロール・ミュージックが誕生してから、ビートルズを経由
して巨大産業化していく過程で育った子供達が、そこそこの大人になって、
いつまでもガキの音楽“ロックンロール”なんぞ聴いてられない。
と言ったかどうかは分からないけど、多分、そんなマーケットに向けて
作られたのが、このA.O.Rだったのかも知れない。
その第一人者と言い切っていいのかどうかは分からないが、真先に浮かんで
くるのは“ボズ・スキャグス”だ。
で、当然、その後のシーンに多大な影響を及ぼした大ベストセラー・
アルバム「SILK DEGREES」の事になると思うでしょう。ところがどっこい、
捻くれ者だから違うんだな。これが。
前号のスプリングスティーン同様、その人気が爆発する直前がいいんだな。
何故か・・・・・。
と言う訳で、ボズの場合、絶対的に「SLOW DANCER」なのです。

このアルバム、日本で発売された当時「シスコの顔役」などと言う物騒な
邦題を付けられていた訳で、レコード店であのジャケットを見たら、タイ
トルのイメージと相まって、そりゃ~、それなりのインパクトがあったのは
確かだ。
元々R&B的な資質を持ち、そういった方向性を模索していたボズにとって、
このアルバムで出会ったプロデューサー“ジョニー・ブリストル”との
相性はドンピシャだった。
今回、この原稿を書くにあたって久々にレコード棚から引っ張り出して
聴いてみたが、正に名曲名演名唱の3拍子揃い踏みの連続で、名盤「SILK
DEGREES」なんのその。って感じなのです。
CD化に伴って、あの売らんが為の再発の劣悪デザインのジャケットが一掃
され、オリジナル・ジャケットになって価格も廉価のいい事づくめ。
男も惚れる(!?)あの水着姿をみつつ、ボズの歌声に酔って下さい。
そんなボズの名曲達を聴きながら、こんな歌い方する日本人がいるな~、
と顔が浮かんできたのが井上陽水。
まぁ、日本のA.O.Rの先駆者と言っても過言じゃないでしょ。
真先にフォークへの拘わりをすてて(!?)ロック的なアプローチを開始後数年。
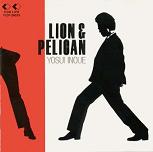
徐々に陽水流A.O.Rは進化を遂げ「LION & PELICAN」という名盤を産み出す
訳。あの「リバーサイドホテル」(ヒットしたのは6年も後の事)が収録された
アルバムだ。ってな所で、またも紙面が尽きてきた。
陽水については、再度何かの機会に取り上げたいと思う。
そしてボズ、陽水両者共、あのサングラスが大人を演出する上で欠かせない
小道具だったりして・・・・・。そんな訳ないか~。
BOZ SCAGGS / SLOW DANCER (1974年度作品)
井上陽水 / LION & PELICAN (1982年度作品)
2009年02月13日
名盤/CRAZY HORSE & 玉置浩二
続・名盤を探しに行こう!/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.58(1999年02月号掲載)
馬年の“うま”は午って書くんですよね。
こうして恥を晒し続けなきゃいけないのが、この再掲載のちょっと辛い
ところ。
ニール・ヤングと言えば、ようやく「THE HEART OF GOLD」を観る事が
出来た。
アルバム「Prairie Wind」同様、長閑に流れる感じの映画で良かったです。
近々発売されるアーカイヴシリーズのBOXは、なんとDVDの10枚セット
らしいので、観るのが大変だし、価格もそれなりになるので・・・・・、
って事で、考えちゃう人が続出なんだろうな。
当然、俺もです。
なんせこの不況!連日の悲しい報道。当事者や切羽詰った人には申し訳
ないけど、もう、うんざりですわ。
ニールと、言わば一心同体的なあのバンドが残した、数少ない中の
名作。
東京で見逃してしまった映画「YEAR OF THE HORSE」を、年末にシアタ
ー・キノで観る事が出来た。
“兎年”が間近に迫っているっていうのに、よりによって“馬年”の
映画を観るなヨ。と思わず訳分からずな人が言うかも知れないけど、
ニール・ヤングの映画だって事で許して下さい。
でぇ、映画の入りは予想通りパァーと見渡した瞬間に、指の数で充分
足りる。っつう入りで、流石ニール・ヤング。
動員するには対象がロートル過ぎます。
ついでに言っちゃうと、観ていた人の中には、ニール・ヤングじゃなく
て、ジム・ジャームッシュが監督した映画だからって観に来た映画ファン
だっているかも知れない。
そうそう、誰だか忘れたけど、映画の中でバンドのメンバーが言って
いたように“スカした映画”だと思って観に来る映画マニアがね・・・。
それにしてもニール・ヤング太ったな。映画のハイライト・シーンとも
言える「LIKE A HURRICANE」の時、20年位前の姿をダブらせるんだけれ
ども、そりゃ見事に使用前・使用後的落差で、若い時のニールの美しさ
が際立っていた。
ん~ん、やっぱりロック・スターはミック・ジャガーのように、幾つに
なっても体型を保って恰好良くなくちゃ。なんて思った次第で・・・。
まぁ、音の方は、そりゃ無敵の本物のロックンロール。改めて生のステ
ージを観たいと思った次第です。ハイ!。
そのニル・ヤングは置いといて、バックを勤めていたクレイジー・ホース
の面々。こちらも負けず劣らず年輪を感じさせる存在感だったのは確かで、
ご覧になった方の脳裏に、しっかりと、その名前を刻み込んだに違いない。
彼らの活動歴は古く、前身の“ロケッツ”を入れると、すでに40年近い
キャリアがある。が、発表したアルバムは僅かしかない。
と言うより、俺が知っている限りでは4枚。もしかしたら、もう1~2枚
出ているのかも知れない。
そして、なんと言ってもデビュー作「クレイジーホース」である。

何故なら、名曲「I DON’T WANT TO TALK ABOUT IT」が入っているからで、
俺、この1曲の為にレコードを捜しまくったもんね。
あぁ~この曲、ロッド・ステュワートの名盤「ATLANTIC CROSSING」に収録
された名バラード「もう話したくない」の原曲なんです。
洗練されたロッド版に較べると、実に素朴な感じで、ライ・クーダーの
スライド・ギターもいいんだな~。これが。
もう、本当にこれ1曲だけの為に買っても損はしない。なんて言ったら、
他はどうでもいいみたいじゃん。まぁ、ニール・ヤングのファンは是非聴く
べき1枚だし、アメリカン・ロックのルーツものを追及している方にも、
お薦め。ってアルバムかなっ。
このようにバックを勤めて注目されたバンドって多数あるけど、我が日本
での成功例と言えば、井上陽水に見出された“安全地帯”がいる。
安全地帯と言えば“玉置浩二”って位、彼が際立っているけど、彼が発表
したソロ作「カリント工場の煙突の上に」には、同年代だったら共感しそう
な風景が一杯描かれていて、涙腺を刺激する。

と言うところで紙面が尽きてきた。そんな訳で、出所は“裏方”という事
で、今月はまとめました。
CRAZY HORSE / CRAZY HORSE(1971年度作品)
玉置浩二 / カリント工場の煙突の上に(1993年度作品)
Vol.58(1999年02月号掲載)
馬年の“うま”は午って書くんですよね。
こうして恥を晒し続けなきゃいけないのが、この再掲載のちょっと辛い
ところ。
ニール・ヤングと言えば、ようやく「THE HEART OF GOLD」を観る事が
出来た。
アルバム「Prairie Wind」同様、長閑に流れる感じの映画で良かったです。
近々発売されるアーカイヴシリーズのBOXは、なんとDVDの10枚セット
らしいので、観るのが大変だし、価格もそれなりになるので・・・・・、
って事で、考えちゃう人が続出なんだろうな。
当然、俺もです。
なんせこの不況!連日の悲しい報道。当事者や切羽詰った人には申し訳
ないけど、もう、うんざりですわ。
ニールと、言わば一心同体的なあのバンドが残した、数少ない中の
名作。
東京で見逃してしまった映画「YEAR OF THE HORSE」を、年末にシアタ
ー・キノで観る事が出来た。
“兎年”が間近に迫っているっていうのに、よりによって“馬年”の
映画を観るなヨ。と思わず訳分からずな人が言うかも知れないけど、
ニール・ヤングの映画だって事で許して下さい。
でぇ、映画の入りは予想通りパァーと見渡した瞬間に、指の数で充分
足りる。っつう入りで、流石ニール・ヤング。
動員するには対象がロートル過ぎます。
ついでに言っちゃうと、観ていた人の中には、ニール・ヤングじゃなく
て、ジム・ジャームッシュが監督した映画だからって観に来た映画ファン
だっているかも知れない。
そうそう、誰だか忘れたけど、映画の中でバンドのメンバーが言って
いたように“スカした映画”だと思って観に来る映画マニアがね・・・。
それにしてもニール・ヤング太ったな。映画のハイライト・シーンとも
言える「LIKE A HURRICANE」の時、20年位前の姿をダブらせるんだけれ
ども、そりゃ見事に使用前・使用後的落差で、若い時のニールの美しさ
が際立っていた。
ん~ん、やっぱりロック・スターはミック・ジャガーのように、幾つに
なっても体型を保って恰好良くなくちゃ。なんて思った次第で・・・。
まぁ、音の方は、そりゃ無敵の本物のロックンロール。改めて生のステ
ージを観たいと思った次第です。ハイ!。
そのニル・ヤングは置いといて、バックを勤めていたクレイジー・ホース
の面々。こちらも負けず劣らず年輪を感じさせる存在感だったのは確かで、
ご覧になった方の脳裏に、しっかりと、その名前を刻み込んだに違いない。
彼らの活動歴は古く、前身の“ロケッツ”を入れると、すでに40年近い
キャリアがある。が、発表したアルバムは僅かしかない。
と言うより、俺が知っている限りでは4枚。もしかしたら、もう1~2枚
出ているのかも知れない。
そして、なんと言ってもデビュー作「クレイジーホース」である。

何故なら、名曲「I DON’T WANT TO TALK ABOUT IT」が入っているからで、
俺、この1曲の為にレコードを捜しまくったもんね。
あぁ~この曲、ロッド・ステュワートの名盤「ATLANTIC CROSSING」に収録
された名バラード「もう話したくない」の原曲なんです。
洗練されたロッド版に較べると、実に素朴な感じで、ライ・クーダーの
スライド・ギターもいいんだな~。これが。
もう、本当にこれ1曲だけの為に買っても損はしない。なんて言ったら、
他はどうでもいいみたいじゃん。まぁ、ニール・ヤングのファンは是非聴く
べき1枚だし、アメリカン・ロックのルーツものを追及している方にも、
お薦め。ってアルバムかなっ。
このようにバックを勤めて注目されたバンドって多数あるけど、我が日本
での成功例と言えば、井上陽水に見出された“安全地帯”がいる。
安全地帯と言えば“玉置浩二”って位、彼が際立っているけど、彼が発表
したソロ作「カリント工場の煙突の上に」には、同年代だったら共感しそう
な風景が一杯描かれていて、涙腺を刺激する。

と言うところで紙面が尽きてきた。そんな訳で、出所は“裏方”という事
で、今月はまとめました。
CRAZY HORSE / CRAZY HORSE(1971年度作品)
玉置浩二 / カリント工場の煙突の上に(1993年度作品)
2009年01月29日
名盤/B.SPRINGSTEEN& UA
続・名盤を探しに行こう!/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.57(1999年01月号掲載)
スプリングスティーンは書いてある通り、リリース後暫くして噂を
聞きつけ、「さてさて、どんなもんか?」なんて感じでアルバムを
買った記憶がある。
だから`73年の作品を翌年の夏に、そうそう、今と違ってその位
アメリカと日本とのタイムラグがあり、噂が海を越えて日本国内
で噂になるには、それだけ時間が掛ったって訳だ。
因みに平和ボケ云々のところは、完全に俺個人を指しているので。
スプリングスティーンは、この後のアルバム「Born To Run」で、
個人的には終わっており、「Born In The U.S.A.」で、日本を含めた
全世界が熱狂の渦の頃には、全く興味を無くしていた。
この「青春の叫び」は思い入れがある作品と書いてあるが、彼の
作品で唯一CDで買い直した1枚でもある。
原稿をパァーと見て、この二人をどう結び付けているのかと思ったら、
そういう事だったんですね、と納得。
苦し紛れの繋がりですな。(笑)
UAは、どんどん深い世界に入っていって、ちょっと簡単には手を出せ
ないと言うか、手強いと言うか、何かそんな感じに一時なったような。
歌が上手いから、ま、何やってもいいんだけれど・・・。
常に向上心を持って高いところを目指すのはいいんだけれど、もうちょい、
目線を下にしても良いのでは、とは思っている。
磨き始められた原石を見つけた衝撃を、今も思い起こさせるブルースの
あの1枚。
ボブ・ディランのブートレッグ・シリーズ「BOB DYLAN LIVE 1966」(邦題:
ロイヤル・アルバート)が凄い。
何が凄いと喰ってかかってくる人もいると思うが、詳しくは、所謂音楽
専門誌とやらの記事やCDに付いている解説などを参考にして下さい。
まともにここで書いていたら、それだけで終わってしまいそうだから。
それにしても30数年も前に、あんな演奏していたなんて・・・(絶句)。
それこそ前号の“正統派ロックン・ロールは体で感じなさい”の原点って、
こういうところから来るんだよな~。って事になる。
何か、近頃の頭で考えて体裁ばかり整えたロックなんぞに慣らされた耳と
体には、殆ど健康食品的存在の作品だ。
と、ここまで書いたら、てっきりディランが今回の名盤かなっと思うで
しょうが、なんの事ない、ブルース・スプリングスティーンを載り上げ
ます。
何故かというと、過日「MAXIMUM PACK`98」なるイヴェントでUAが唄った
「Because The Night」を聴いたからで、この歌のオリジナルでもある
パティ・スミスは、すでに掲載済み。そこで曲を提供したブルースの顔が
チラついたという訳。
まぁ、ブルースとディランどこでどうかというと、ブルースのデビュー
直後、目敏い人達からディランの再来などと言われた事もあり、満更、
的外れでもないでしょう。(と、勝手に納得。)
でぇ、そんな噂を耳にして最初に手に入れたアルバムが2枚目の「青春の
叫び(原題:The Wild,The Innocent & The E Street Shuffle)」だった。

それはデビュー盤「アズベリー・パークからの挨拶」をリリースした翌年
`74年の夏の事だった。
溢れ出す言葉とファンキーなロックン・ロール、そして嗄れた声。
もうノックアウトするのには充分だった。
夏の暑さと平和ボケしたL.A.産の音に飼い慣らされた耳と体を。
冒頭の「THE STREET SHUFFLE」のホーンに続いてファンキーなギターの
カッティングが刻まれるイントロを聴く度に、今でも熱いものが込み上げて
くる。
「40yh OF JULY,ASBURY PARK(Sunday)」や「NEWYORK CITY SERENADE」の美し
さ、「KITTY’S BACK」の躍動感などなど、ここには、その後「Born To Run」
や「Born In The U.S.A.」で大成功を収めるブルースとは違う、磨きかけ
始めた原石のような彼の姿がる。
いまだに彼のアルバムを1枚、と言われたら、僕は躊躇なくこれに手を出す
だろう。それ程思い入れがある作品だ。
さて、UAである。彼女も近年の女性J-POPシーンを塗り変えた一人だろう。
その片鱗は前述のイヴェントのステージで垣間見る事が出来たし、リリース
される作品群の中にも感じる事が出来る。
彼女の最初のフル・アルバム「11」は、大勢のプロデューサー達に囲まれて
作られた1枚。

「リズム」や「情熱」(但しdab version)といったブレイクの切っ掛けに
なったシングル曲を収録。後のアルバム「アメトラ」よりも取っ付き易い
UAがここにいるので、初心者はこれからどうぞ・・・・・。
尚、件の「Because The Night」は両者共、ライヴ盤でそれぞれ聴く事が
出来る。
BRUCE SPRINGSTEEN / 青春の叫び(1973年度作品)
UA / 11(1996年度作品)
Vol.57(1999年01月号掲載)
スプリングスティーンは書いてある通り、リリース後暫くして噂を
聞きつけ、「さてさて、どんなもんか?」なんて感じでアルバムを
買った記憶がある。
だから`73年の作品を翌年の夏に、そうそう、今と違ってその位
アメリカと日本とのタイムラグがあり、噂が海を越えて日本国内
で噂になるには、それだけ時間が掛ったって訳だ。
因みに平和ボケ云々のところは、完全に俺個人を指しているので。
スプリングスティーンは、この後のアルバム「Born To Run」で、
個人的には終わっており、「Born In The U.S.A.」で、日本を含めた
全世界が熱狂の渦の頃には、全く興味を無くしていた。
この「青春の叫び」は思い入れがある作品と書いてあるが、彼の
作品で唯一CDで買い直した1枚でもある。
原稿をパァーと見て、この二人をどう結び付けているのかと思ったら、
そういう事だったんですね、と納得。
苦し紛れの繋がりですな。(笑)
UAは、どんどん深い世界に入っていって、ちょっと簡単には手を出せ
ないと言うか、手強いと言うか、何かそんな感じに一時なったような。
歌が上手いから、ま、何やってもいいんだけれど・・・。
常に向上心を持って高いところを目指すのはいいんだけれど、もうちょい、
目線を下にしても良いのでは、とは思っている。
磨き始められた原石を見つけた衝撃を、今も思い起こさせるブルースの
あの1枚。
ボブ・ディランのブートレッグ・シリーズ「BOB DYLAN LIVE 1966」(邦題:
ロイヤル・アルバート)が凄い。
何が凄いと喰ってかかってくる人もいると思うが、詳しくは、所謂音楽
専門誌とやらの記事やCDに付いている解説などを参考にして下さい。
まともにここで書いていたら、それだけで終わってしまいそうだから。
それにしても30数年も前に、あんな演奏していたなんて・・・(絶句)。
それこそ前号の“正統派ロックン・ロールは体で感じなさい”の原点って、
こういうところから来るんだよな~。って事になる。
何か、近頃の頭で考えて体裁ばかり整えたロックなんぞに慣らされた耳と
体には、殆ど健康食品的存在の作品だ。
と、ここまで書いたら、てっきりディランが今回の名盤かなっと思うで
しょうが、なんの事ない、ブルース・スプリングスティーンを載り上げ
ます。
何故かというと、過日「MAXIMUM PACK`98」なるイヴェントでUAが唄った
「Because The Night」を聴いたからで、この歌のオリジナルでもある
パティ・スミスは、すでに掲載済み。そこで曲を提供したブルースの顔が
チラついたという訳。
まぁ、ブルースとディランどこでどうかというと、ブルースのデビュー
直後、目敏い人達からディランの再来などと言われた事もあり、満更、
的外れでもないでしょう。(と、勝手に納得。)
でぇ、そんな噂を耳にして最初に手に入れたアルバムが2枚目の「青春の
叫び(原題:The Wild,The Innocent & The E Street Shuffle)」だった。

それはデビュー盤「アズベリー・パークからの挨拶」をリリースした翌年
`74年の夏の事だった。
溢れ出す言葉とファンキーなロックン・ロール、そして嗄れた声。
もうノックアウトするのには充分だった。
夏の暑さと平和ボケしたL.A.産の音に飼い慣らされた耳と体を。
冒頭の「THE STREET SHUFFLE」のホーンに続いてファンキーなギターの
カッティングが刻まれるイントロを聴く度に、今でも熱いものが込み上げて
くる。
「40yh OF JULY,ASBURY PARK(Sunday)」や「NEWYORK CITY SERENADE」の美し
さ、「KITTY’S BACK」の躍動感などなど、ここには、その後「Born To Run」
や「Born In The U.S.A.」で大成功を収めるブルースとは違う、磨きかけ
始めた原石のような彼の姿がる。
いまだに彼のアルバムを1枚、と言われたら、僕は躊躇なくこれに手を出す
だろう。それ程思い入れがある作品だ。
さて、UAである。彼女も近年の女性J-POPシーンを塗り変えた一人だろう。
その片鱗は前述のイヴェントのステージで垣間見る事が出来たし、リリース
される作品群の中にも感じる事が出来る。
彼女の最初のフル・アルバム「11」は、大勢のプロデューサー達に囲まれて
作られた1枚。

「リズム」や「情熱」(但しdab version)といったブレイクの切っ掛けに
なったシングル曲を収録。後のアルバム「アメトラ」よりも取っ付き易い
UAがここにいるので、初心者はこれからどうぞ・・・・・。
尚、件の「Because The Night」は両者共、ライヴ盤でそれぞれ聴く事が
出来る。
BRUCE SPRINGSTEEN / 青春の叫び(1973年度作品)
UA / 11(1996年度作品)
2009年01月15日
名盤/ DR.FEELGOOD & ザ・ハイロウズ
続・名盤を探しに行こう!/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.56(1998年12月号掲載)
マンマだと、やっぱ恥ずかしい誤字がある。
あそこの非難は避難だよな。
あと英語のカタカナ表記は迷ってしまう。
発音に近い表記か、日本語での一般的な表記か、ってのを。
まぁ、いづれにしても校正はちゃんとやっていたのかしらん!
と今更ながら思ってしまう。
書き直す前の“起”の部分って何だったんだろう?と・・・。
さっぱり思い出せない。
それに反して、渋公のザ・ハイロウズのライヴは、ちょっとだけ記憶の
隅に“良かった!”と、破片となって残っている。
それにしても“音楽そのものだけで~”である。
本来はそれが先に成立しての活動でしょうが!
本末転倒と言うべきか、我が国においては時代のサイクルがそうさせて
いるのかどうかは知らないが、「なんかな~!」である。
いつの時代にも存在する正統派、ロックン・ロール・バンドは
体で感じなさい。
先月は連載始って以来、初の原稿書き直し事件が起きてしまい、急遽
出だしの部分をストーンズに書き換えてしまった。
何せ冒頭部分は四コマ・マンガに例えるば起承転結の“起”の部分。
すでに書き上がっている後の部分に如何に繋げるか、無い知恵を搾って
みても、急には出てこんわな。
それで、何となくタイトルが似ているストーンズの「NO SECURITY」を
借用して緊急非難した訳。
いやはや、なんともそんな訳でちょっと無理っぽい繋がりになって
しまったかなっ。な~んて・・・・・。
閑話休題。秋口に2本の結構いいライヴを見る事が出来た。ひとつは
渋谷公会堂で観た“THE HIGH-LOWS”。そしてもうひとつは延期になって
いたスガシカオの札幌公演。
詳細について書く余裕など無いので、両ライヴの良かった共通点だけを
ひとつ書いておこう。
それは両方共「音楽そのものだけで充分に成立していた。」という事。
余計な舞台装飾もない。きらびやかで凝った照明も無い。客に媚びた
喋りも無い。ひたすら自分の音楽を演り倒す。的なスタイルに終始
したライヴだった。
特にハイロウズは、札幌で観た時より切れ味鋭く、カチッとまとまって
いて、流石ライヴ・バンドって感じで面目躍如。
元々、彼らにはストーンズ直系のロック・バンド的認識で接していた
訳だけど、この日のライヴを観て、それよりもう少し若い世代、例える
なら、70年代のブリティシュ・ビート・バンド的臭いを感じる事が
出来た。
でぇ、真先に頭を過ったのはドクター・フィールグッドだった。
とは言うものの、ビート系が好きな人には名ギタリスト“ウィルコ・
ジョンソン”在籍時、即ちデビュー直後位がいいらしいが、僕が彼ら
と遭遇したのはウィルコ脱退後のアルバムで、彼らにとっては6枚目
となる「プライヴェット・プラクテス」だった。

ギターはジョン・メイヨーに代わっているものの、他の3人のメンバー
は結成当時と同じで、演っている音楽自体もR&Bやブルースを下敷き
にした正統派ロックン・ロール。
何の事はない、遡る事十数年、ストーンズがデビューから一貫して
追及していたロックン・ロールと同じ姿が、そこにはあった。
そんな訳で系列的にハイロウズからドクター・フィールグッドっての
はありで、ましてはパンク・ムーヴメントの洗礼を受けた年代の
ミュージシャンならなおさらって訳だ。
さてハイロウズの衝撃のデビュー・アルバム「THE HIGH-LOWS」は、
あの浮かれたバンド・ブームが完全に一段落した後に届いた。

だからという訳じゃないけど、アルバムの冒頭の「グッドバイ」では
♪さよならする~綺麗さっぱり♪なんて唄っちゃって、全然相応しく
ないの。再出発に。
ん~、あの二人色々あったんだろうネ。
これで過去にけじめを付けたかのように、ジャングル・ビートが飛び
出し、新生“ザ・ハイロウズ”の正統派ロックン・ロールの幕が開く。
さぁ、どちらも“のり一発!”で楽しみたいロックン・ロール。
そう理由やら理屈やら余計な事考えないで、体で反応して下さい。
それが正しい聴き方なんだから・・・・・。
DR.FEELGOOD / PRIVATE PRACTICE(1978年度作品)
THE HIGH-LOWS / THE HIGH-LOWS(1995年度作品)
Vol.56(1998年12月号掲載)
マンマだと、やっぱ恥ずかしい誤字がある。
あそこの非難は避難だよな。
あと英語のカタカナ表記は迷ってしまう。
発音に近い表記か、日本語での一般的な表記か、ってのを。
まぁ、いづれにしても校正はちゃんとやっていたのかしらん!
と今更ながら思ってしまう。
書き直す前の“起”の部分って何だったんだろう?と・・・。
さっぱり思い出せない。
それに反して、渋公のザ・ハイロウズのライヴは、ちょっとだけ記憶の
隅に“良かった!”と、破片となって残っている。
それにしても“音楽そのものだけで~”である。
本来はそれが先に成立しての活動でしょうが!
本末転倒と言うべきか、我が国においては時代のサイクルがそうさせて
いるのかどうかは知らないが、「なんかな~!」である。
いつの時代にも存在する正統派、ロックン・ロール・バンドは
体で感じなさい。
先月は連載始って以来、初の原稿書き直し事件が起きてしまい、急遽
出だしの部分をストーンズに書き換えてしまった。
何せ冒頭部分は四コマ・マンガに例えるば起承転結の“起”の部分。
すでに書き上がっている後の部分に如何に繋げるか、無い知恵を搾って
みても、急には出てこんわな。
それで、何となくタイトルが似ているストーンズの「NO SECURITY」を
借用して緊急非難した訳。
いやはや、なんともそんな訳でちょっと無理っぽい繋がりになって
しまったかなっ。な~んて・・・・・。
閑話休題。秋口に2本の結構いいライヴを見る事が出来た。ひとつは
渋谷公会堂で観た“THE HIGH-LOWS”。そしてもうひとつは延期になって
いたスガシカオの札幌公演。
詳細について書く余裕など無いので、両ライヴの良かった共通点だけを
ひとつ書いておこう。
それは両方共「音楽そのものだけで充分に成立していた。」という事。
余計な舞台装飾もない。きらびやかで凝った照明も無い。客に媚びた
喋りも無い。ひたすら自分の音楽を演り倒す。的なスタイルに終始
したライヴだった。
特にハイロウズは、札幌で観た時より切れ味鋭く、カチッとまとまって
いて、流石ライヴ・バンドって感じで面目躍如。
元々、彼らにはストーンズ直系のロック・バンド的認識で接していた
訳だけど、この日のライヴを観て、それよりもう少し若い世代、例える
なら、70年代のブリティシュ・ビート・バンド的臭いを感じる事が
出来た。
でぇ、真先に頭を過ったのはドクター・フィールグッドだった。
とは言うものの、ビート系が好きな人には名ギタリスト“ウィルコ・
ジョンソン”在籍時、即ちデビュー直後位がいいらしいが、僕が彼ら
と遭遇したのはウィルコ脱退後のアルバムで、彼らにとっては6枚目
となる「プライヴェット・プラクテス」だった。

ギターはジョン・メイヨーに代わっているものの、他の3人のメンバー
は結成当時と同じで、演っている音楽自体もR&Bやブルースを下敷き
にした正統派ロックン・ロール。
何の事はない、遡る事十数年、ストーンズがデビューから一貫して
追及していたロックン・ロールと同じ姿が、そこにはあった。
そんな訳で系列的にハイロウズからドクター・フィールグッドっての
はありで、ましてはパンク・ムーヴメントの洗礼を受けた年代の
ミュージシャンならなおさらって訳だ。
さてハイロウズの衝撃のデビュー・アルバム「THE HIGH-LOWS」は、
あの浮かれたバンド・ブームが完全に一段落した後に届いた。

だからという訳じゃないけど、アルバムの冒頭の「グッドバイ」では
♪さよならする~綺麗さっぱり♪なんて唄っちゃって、全然相応しく
ないの。再出発に。
ん~、あの二人色々あったんだろうネ。
これで過去にけじめを付けたかのように、ジャングル・ビートが飛び
出し、新生“ザ・ハイロウズ”の正統派ロックン・ロールの幕が開く。
さぁ、どちらも“のり一発!”で楽しみたいロックン・ロール。
そう理由やら理屈やら余計な事考えないで、体で反応して下さい。
それが正しい聴き方なんだから・・・・・。
DR.FEELGOOD / PRIVATE PRACTICE(1978年度作品)
THE HIGH-LOWS / THE HIGH-LOWS(1995年度作品)
2009年01月05日
名盤/Carly Simon & 古内東子
続・名盤を探しに行こう!/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.55(1998年11月号掲載)
これはネタに困っている時に、たまたま見掛けた古内東子のポスターが、
妙に色っぽかったので、そこからカーリーへと結び付けた記憶がある。
大体50数回も書いてりゃ、何度となくネタ切れになるのはしょうがない。
紹介したい洋楽はいくらでもあるが、それに合わせる邦楽がね~。
そこが苦労したところでもあります。ハイ!
ジャケット話になると、どうしてもLPに分があるのは分かっているが、
例えば、このカーリー・サイモンの何点かのジャケットは、明らかに
あのサイズだからいいのであって、CDサイズだと、手を出す気にも
なれない。
パッケージ商品の強みでもあるジャケットの価値は、CDでは、どこか
忘れさられた感もある。
あのサイズで魅力のあるジャケットを考えないと、益々売れなくなって
しまうような気がする。
CDを含めてパッケージ全体で一つのアート!みたいな感じにして商品
価値を高めない・・・、といつも思ってはいるのですが・・・・。
ジャケットだけでも“買い!”のアルバム多数有り。
勿論、音楽も素敵なカーリーの世界。
我が唯一のアイドル“The Rolling Stones”の恒例のライヴ盤が
リリースされた。
恒例というのは、ここんとこツアーをやる度に必ず出しているか
らで、まぁ、言ってみれば、一種のお約束事みたいなもんで、それ
程大騒ぎするものじゃない。
でぇ、毎回、シークレット・ギグでの曲や未発表曲を入れたりの
アイデアで楽しませてくれるけど、今回の「NO SECURITY」は、どうも
選曲一発勝負みたいな感じ。ん~、ファンなら納得の内容って訳だ。
おまけに、これに併せたツアーも年明け早々に計画中らしいので、
何か年取っても益々盛ん・・・・・ってな感じ。
それにしてもジャケットが良くないな~。年々センスが悪くなっている
気がする。これこそ年のせいかしらん。
ところで「NO SECURITY」ってタイトルに聞き覚えがあるなと考えていたら、
何の事はないカーリー・サイモンの「NO SECRETS」と勘違いしていた。
彼女、まんざらストーンズと繋がりがない訳でもないので、今月はこの
カーリーさんについて書いてみよう。

以前に取り上げたキャロル・キング同様、1970年代を代表する女性
シンガー・ソングライターの一人。勿論、現在も良質の作品を作り出して
活躍中の現役バリバリのアーティストだ。
姉とのサイモン・シスターズを経て71年にソロ・デビューを果たし、
折からのシンガー・ソングライター・ブームにのって、翌年リリースした
アルバム「NO SECRETS」収録の「うつろな愛(You’re So Vain)」が
大ヒットし、一躍時の人になった彼女。
この「うつろな愛」でデュエットしているミック・ジャガーとデキてる。
なんて噂もなんのそので、あっ!という間にジャームズ・テイラーと結婚
して、世の男性の嘆きを誘ったりもした女性だ。
アルバム「ノー・シークレッツ」は彼女にとって3枚目の作品。
リチャード・ペリーのプロデュースのもと、より洗練された都会派の女性
を表現し、そのサウンドは、フォーク色濃い色合いから、のちのお洒落で
ポップ・ソウル風なものの原形的なものまで、バラエティに聴かせる一枚
に仕上がっている。
ところで彼女のアルバムは、ジャケットがな~んとも素敵なものが多い。
と言うか、実に男心をくすぐるのが多いんだな。これが。
まぁ、この「NO SECRETS」ではノーブラ論争が起こったりもしたけど、
後の作品は、もっとセクシーな姿態を披露してくれる。という訳で、
一連の彼女の作品は、是非LPで買う事をお薦めする。
セクシーと言えば、近年のJ-POPの女性シンガー・シーンを塗り変えた
一人と言ってもいい古内東子さんも、よく見掛けるヴィジュアルは、
どことなくセクシーな感じでいい。

彼女のデビュー作「SLOW DOWN」をこのWEで紹介した時、現役女子大生
ながら、その大人びた感じの雰囲気もん云々って事を書いた記憶がうっすら
とあるけど、年々、その成熟度に磨きがかかっている事を、音楽面でも
ヴィジュアル面でも感じさせてくれている。
いいね、やっぱり。そういったところでも楽しませてくれるのって女性
だけの特権かなっ。
なんて書いたら差別発言で嫌がられるのかしらん。
まぁ、感じ方は人それぞれ。今後もそんな事を期待しつつ、御両人の活躍
を楽しみにしています。
CARLY SIMON / NO SECRETS(1972年度作品)
古内東子 / SLOW DOWN(1993年度作品)
Vol.55(1998年11月号掲載)
これはネタに困っている時に、たまたま見掛けた古内東子のポスターが、
妙に色っぽかったので、そこからカーリーへと結び付けた記憶がある。
大体50数回も書いてりゃ、何度となくネタ切れになるのはしょうがない。
紹介したい洋楽はいくらでもあるが、それに合わせる邦楽がね~。
そこが苦労したところでもあります。ハイ!
ジャケット話になると、どうしてもLPに分があるのは分かっているが、
例えば、このカーリー・サイモンの何点かのジャケットは、明らかに
あのサイズだからいいのであって、CDサイズだと、手を出す気にも
なれない。
パッケージ商品の強みでもあるジャケットの価値は、CDでは、どこか
忘れさられた感もある。
あのサイズで魅力のあるジャケットを考えないと、益々売れなくなって
しまうような気がする。
CDを含めてパッケージ全体で一つのアート!みたいな感じにして商品
価値を高めない・・・、といつも思ってはいるのですが・・・・。
ジャケットだけでも“買い!”のアルバム多数有り。
勿論、音楽も素敵なカーリーの世界。
我が唯一のアイドル“The Rolling Stones”の恒例のライヴ盤が
リリースされた。
恒例というのは、ここんとこツアーをやる度に必ず出しているか
らで、まぁ、言ってみれば、一種のお約束事みたいなもんで、それ
程大騒ぎするものじゃない。
でぇ、毎回、シークレット・ギグでの曲や未発表曲を入れたりの
アイデアで楽しませてくれるけど、今回の「NO SECURITY」は、どうも
選曲一発勝負みたいな感じ。ん~、ファンなら納得の内容って訳だ。
おまけに、これに併せたツアーも年明け早々に計画中らしいので、
何か年取っても益々盛ん・・・・・ってな感じ。
それにしてもジャケットが良くないな~。年々センスが悪くなっている
気がする。これこそ年のせいかしらん。
ところで「NO SECURITY」ってタイトルに聞き覚えがあるなと考えていたら、
何の事はないカーリー・サイモンの「NO SECRETS」と勘違いしていた。
彼女、まんざらストーンズと繋がりがない訳でもないので、今月はこの
カーリーさんについて書いてみよう。

以前に取り上げたキャロル・キング同様、1970年代を代表する女性
シンガー・ソングライターの一人。勿論、現在も良質の作品を作り出して
活躍中の現役バリバリのアーティストだ。
姉とのサイモン・シスターズを経て71年にソロ・デビューを果たし、
折からのシンガー・ソングライター・ブームにのって、翌年リリースした
アルバム「NO SECRETS」収録の「うつろな愛(You’re So Vain)」が
大ヒットし、一躍時の人になった彼女。
この「うつろな愛」でデュエットしているミック・ジャガーとデキてる。
なんて噂もなんのそので、あっ!という間にジャームズ・テイラーと結婚
して、世の男性の嘆きを誘ったりもした女性だ。
アルバム「ノー・シークレッツ」は彼女にとって3枚目の作品。
リチャード・ペリーのプロデュースのもと、より洗練された都会派の女性
を表現し、そのサウンドは、フォーク色濃い色合いから、のちのお洒落で
ポップ・ソウル風なものの原形的なものまで、バラエティに聴かせる一枚
に仕上がっている。
ところで彼女のアルバムは、ジャケットがな~んとも素敵なものが多い。
と言うか、実に男心をくすぐるのが多いんだな。これが。
まぁ、この「NO SECRETS」ではノーブラ論争が起こったりもしたけど、
後の作品は、もっとセクシーな姿態を披露してくれる。という訳で、
一連の彼女の作品は、是非LPで買う事をお薦めする。
セクシーと言えば、近年のJ-POPの女性シンガー・シーンを塗り変えた
一人と言ってもいい古内東子さんも、よく見掛けるヴィジュアルは、
どことなくセクシーな感じでいい。

彼女のデビュー作「SLOW DOWN」をこのWEで紹介した時、現役女子大生
ながら、その大人びた感じの雰囲気もん云々って事を書いた記憶がうっすら
とあるけど、年々、その成熟度に磨きがかかっている事を、音楽面でも
ヴィジュアル面でも感じさせてくれている。
いいね、やっぱり。そういったところでも楽しませてくれるのって女性
だけの特権かなっ。
なんて書いたら差別発言で嫌がられるのかしらん。
まぁ、感じ方は人それぞれ。今後もそんな事を期待しつつ、御両人の活躍
を楽しみにしています。
CARLY SIMON / NO SECRETS(1972年度作品)
古内東子 / SLOW DOWN(1993年度作品)
2008年12月29日
名盤/Curtis Mayfield & ICE
続・名盤を探しに行こう!/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.54(1998年10月号掲載)
近頃あまり聴く事もなくなったカーティス。
こんな原稿を読み返すと、時代の気分次第で、随分と聴くモノが
変わってくるのを実感。
洋楽の旧譜のボーナストラックは、これでもか!これでもか!と、
こちらの財布の中身の事情に関わらず、新手を繰り出すので、
マニアの方々は大変だと思う。
どこかで見切りをつけないと、同じ作品のヴァージョン違いを、
延々と買うハメになってしまう。
近頃のSHM-CDとか、それに追従する各社の高音質CDでの出し
直しも同類か。
あきらかに音の向上が分かればいいけど、そうじゃないと、ある意味
意地で買ってます!みたいなもんになっちまう。
とは言うものの、ちょっとでも音が良くなっているという情報があれば、
それはそれで気になってしょうがない。
ま、贅沢な悩みと言えば言えるけど、なんかな~。
ボーナストラック連発のリイシュー盤が花盛り!まともに買っていたら、
お金がいくらあっても足りないぞ~。
先月からの続きになってしまうが、紙ジャケットと中古盤について
書きます。
中古盤屋で手に入れたもので結構嬉しかったのが、カーティス・メイ
フィールドの「WILD AND FREE」というベスト盤。
2枚組ですでに廃盤になっていた物で、何年か前のカーティス作品の
CD化の際に組まれた国内編集物と思われる作品。
ジャケットをよく見ると94年になっていたから、ジムコ・レコーズ
が初CD化を含めた何枚かをリイシューした時の副産物かなっ。
ロックっぽい側面とソウル・アーティスト然とした面の2枚に別れた
作りは、それなりに聴き勝手が良くて便利なので、何処かで見掛けたら
手に入れておくといい。勿論、紙ジャケットです。
このカーティスのように、何度となく再発を繰り返しているアーティスト
も珍しい。(レーベルの問題だからアーティストに責任は無いんだけど・・・)
そんな訳で、発売する度に、あの手この手、そう、手を変え品を変え、
ユーザーやマニア心をくすぐります。
今回もビクターからカートム・レーベルのリイシュー・シリーズの一貫
として彼の作品10タイトルが、ボーナス・トラック付きで発売されている。
中でも、昨年25周年記念盤として発売されたもののエディト盤として
11ものボーナス・トラックを加えた「SUPERFLY」には、心が動かされます。
あぁ~、あれから20数年も過ぎてしまったのネ。我が青春のブラック・
ムーヴィーの洗礼から・・・・・。
このカーティスの出世作「SUPERFLY」は、70年代初め一世を風靡した
ブラック・ムーヴィーのサントラ盤。
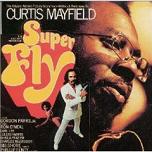
この映画のヒットと共に、カーティスの存在が一気に上昇気流に乗った
のは言うまでもない。
近年ではポール・ウェラーをはじめレニー・クラヴィッツらが、その影響力
を語る事も多く、若い人達の間でもカーティスへの関心が高まり、廃盤に
なっても、すぐに再度市場に出回るとうになった。
さて、この「SUPERFLY」。サントラ盤。といっても、絵がなくても大丈夫
な程、1枚のアルバムとしての完成度を持っている。
「フレディの死」と「スーパーフライ」の2曲のミリオン・セラー・チューン
はじめ収められた9曲が、クールなファンクというか、秘めた熱っぽさを
都会的センスのよさでカムフラージュしている。
ベスト盤が、そのアーティストの入門編に最適って言われるけど、カーティス
はこの「SUPERFLY」から入ってもいいんじゃにですか。
でぇ、ベスト盤と言えば「ICE TRACKS」のセールスが好調なアイスのお二人。
彼らの出世作「WAKE UP EVERBODY」の1曲目を聴く度に、いつもカーティス
の「SUPERFLY」を思い出してしまう。

パクリとかの問題じゃなくて、宮内さんもカーティスが好きなんだろう。
ギターのカッティングやらストリングスの絡め方など、同じ都会派クール・
ファンク(!?)、勉強になった部分が一杯あったに違いない。
両者並べて聴いてみると、何となくそんな感じがします。
ところで、いまだに「SUPERFLY」はLPで聴いているので、件の11もの
ボーナス・トラックを聴くのが楽しみな今日この頃です。
CURTIS MAYFIELD / SURPERFLY(1972年度作品)
ICE / WAKE UP EVERYBODY(1993年度作品)
Vol.54(1998年10月号掲載)
近頃あまり聴く事もなくなったカーティス。
こんな原稿を読み返すと、時代の気分次第で、随分と聴くモノが
変わってくるのを実感。
洋楽の旧譜のボーナストラックは、これでもか!これでもか!と、
こちらの財布の中身の事情に関わらず、新手を繰り出すので、
マニアの方々は大変だと思う。
どこかで見切りをつけないと、同じ作品のヴァージョン違いを、
延々と買うハメになってしまう。
近頃のSHM-CDとか、それに追従する各社の高音質CDでの出し
直しも同類か。
あきらかに音の向上が分かればいいけど、そうじゃないと、ある意味
意地で買ってます!みたいなもんになっちまう。
とは言うものの、ちょっとでも音が良くなっているという情報があれば、
それはそれで気になってしょうがない。
ま、贅沢な悩みと言えば言えるけど、なんかな~。
ボーナストラック連発のリイシュー盤が花盛り!まともに買っていたら、
お金がいくらあっても足りないぞ~。
先月からの続きになってしまうが、紙ジャケットと中古盤について
書きます。
中古盤屋で手に入れたもので結構嬉しかったのが、カーティス・メイ
フィールドの「WILD AND FREE」というベスト盤。
2枚組ですでに廃盤になっていた物で、何年か前のカーティス作品の
CD化の際に組まれた国内編集物と思われる作品。
ジャケットをよく見ると94年になっていたから、ジムコ・レコーズ
が初CD化を含めた何枚かをリイシューした時の副産物かなっ。
ロックっぽい側面とソウル・アーティスト然とした面の2枚に別れた
作りは、それなりに聴き勝手が良くて便利なので、何処かで見掛けたら
手に入れておくといい。勿論、紙ジャケットです。
このカーティスのように、何度となく再発を繰り返しているアーティスト
も珍しい。(レーベルの問題だからアーティストに責任は無いんだけど・・・)
そんな訳で、発売する度に、あの手この手、そう、手を変え品を変え、
ユーザーやマニア心をくすぐります。
今回もビクターからカートム・レーベルのリイシュー・シリーズの一貫
として彼の作品10タイトルが、ボーナス・トラック付きで発売されている。
中でも、昨年25周年記念盤として発売されたもののエディト盤として
11ものボーナス・トラックを加えた「SUPERFLY」には、心が動かされます。
あぁ~、あれから20数年も過ぎてしまったのネ。我が青春のブラック・
ムーヴィーの洗礼から・・・・・。
このカーティスの出世作「SUPERFLY」は、70年代初め一世を風靡した
ブラック・ムーヴィーのサントラ盤。
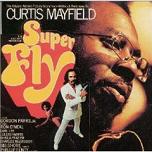
この映画のヒットと共に、カーティスの存在が一気に上昇気流に乗った
のは言うまでもない。
近年ではポール・ウェラーをはじめレニー・クラヴィッツらが、その影響力
を語る事も多く、若い人達の間でもカーティスへの関心が高まり、廃盤に
なっても、すぐに再度市場に出回るとうになった。
さて、この「SUPERFLY」。サントラ盤。といっても、絵がなくても大丈夫
な程、1枚のアルバムとしての完成度を持っている。
「フレディの死」と「スーパーフライ」の2曲のミリオン・セラー・チューン
はじめ収められた9曲が、クールなファンクというか、秘めた熱っぽさを
都会的センスのよさでカムフラージュしている。
ベスト盤が、そのアーティストの入門編に最適って言われるけど、カーティス
はこの「SUPERFLY」から入ってもいいんじゃにですか。
でぇ、ベスト盤と言えば「ICE TRACKS」のセールスが好調なアイスのお二人。
彼らの出世作「WAKE UP EVERBODY」の1曲目を聴く度に、いつもカーティス
の「SUPERFLY」を思い出してしまう。

パクリとかの問題じゃなくて、宮内さんもカーティスが好きなんだろう。
ギターのカッティングやらストリングスの絡め方など、同じ都会派クール・
ファンク(!?)、勉強になった部分が一杯あったに違いない。
両者並べて聴いてみると、何となくそんな感じがします。
ところで、いまだに「SUPERFLY」はLPで聴いているので、件の11もの
ボーナス・トラックを聴くのが楽しみな今日この頃です。
CURTIS MAYFIELD / SURPERFLY(1972年度作品)
ICE / WAKE UP EVERYBODY(1993年度作品)
2008年12月24日
名盤/ Carole King & 荒井由実
続・名盤を探しに行こう/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.53(1998年09月号掲載)
今や全盛の紙ジャケって、この頃が始まりだったんですね!
“オモチャ”と一刀両断しているところが、いいですね。今更ながら。
なんて云うか、日本の印刷技術が誇る、あくまでも精巧な複製品ですから。
あれは。
ユーミンが果たせなかった“一家に一枚”は、この年か翌年に宇多田ヒカルが
1stアルバムで、ほぼ達成する事になる。
その位売れたモンスターアルバムでした。
キャロルさんは、最近、この「つづれおり」の後に出た「MUSIC」を良く聴きます。
ところで今の音楽ファン達は、シンガー・ソングライター(SSW)の意味を分かって
いるのかしらん?
な~んて疑問が、コピーを見て、頭の中に湧いてきた。
職業作家(作詞・作曲家)の音楽が当たり前だった頃から、音楽を聴いている
人達には、このSSWの出現は「作品も作れて歌も唄えるなんて凄い才能の
持ち主!」と驚く程、その存在が眩しかった。
それがいつの間にか、シンガー・ソングライター=アーティストという図式の中で、
所謂、ジャリタレまでもが、詞や曲を書くのが当たり前になってしまって、アーテ
ィストと名乗るようになった日本の音楽界。
なんて云うか、そんな輩の、お気軽な価値付けの為に利用されている。
そんなところもあったりして、どこかのタイミングで、ちょっぴり本来の意味からズレ
ちゃって、価値が落ちたのは確か。
だから俺は憂いでます。と書いたら大袈裟か・・・・・・(笑)
元祖!シンガー・ソングライター。
キングの超名作アルバムを一家に一枚!
近頃やたらと流行っている紙ジャケットによる限定盤シリーズ。
マニア心をくすぐるオリジナル仕様で、購買意欲をそそるんだけれども、
ありゃ、どう見ても玩具だな。オリジナルのアナログ盤を持っている者としては。
まぁ、洋酒とかのミニチュア瓶ってあるけど、あれと似たようなもので、中に詰まって
いるものは同じ味なんだけど・・・・・。って訳だ。
大体、CDになってからは、どうも音楽が玩具化しているように思えて仕方がない。
本来、保存されるべき文化として成立しレコード化されてきたはずなのに、CD時代
に突入してからは、大量消費文化と化し、時代のスピードと同じ速さで消費され、
捨てられている。
まぁ、保存されるべき内容のモノが少ないから。なんて言っちゃお終いだけど・・・・・。
そんな訳で、中古屋でレコード捜しのついでに、大量に売られているCDにも手を
延ばすと、結構掘り出しモノを見つける事が多い。
特に僕のように、ヒット物やメジャー・アーティストに対する興味が薄い人には、思わ
ぬ作品を、とんでもない安価で手に出来る。
先日も東京の某店で、「TAPESTRY REVISITED」なるアルバムを百円でゲット。
百円だよ。玉子のワン・パッケージより安いんだぜ。
それで、あのキャロル・キングのポップス史に残る超名作アルバムに敬意を表した、
このトリビュート・アルバムが買えちゃうんだから・・・・・。
トリビュート盤って近年の流行モノっぽくて、色んな作品が出ているけど、一人の
アーティストの一作品を丸々ってのは珍しい。

それ程までに愛されている「TAPESTRY」って、どんなアルバム。と言うより、
キャロル・キング自身を知らない人には、彼女の事から話さなければならないかも。
とは言うものの、この紙面で詳細を書くには無理があるので、超簡単に紹介しちゃうと、
所謂、元祖シンガー・ソングライター。
まぁ、今、多くのアーティストが自前で作って唄っちゃってるけど、そうゆう風な方向
付けした張本人って訳だ。(あのビートルズが、初めてニューヨークを訪れた際に、
最初に表敬訪問したのが彼女)
「TAPESTRY~つづれおり」は1971年に彼女のセカンド・アルバムとして発表された。
リード・シングルとして「イッツ・トゥ・レイト」が大ヒット。
又、収録された「君の友だち」をジャームズ・テイラーがカヴァーして大ヒットさせ、
そういった相乗効果で、当時、1000万枚を超える爆発的記録を作った1枚。
前述した通り、アルバム丸ごとカヴァーしたトリビュート盤が出来ても不思議じゃない
程、名曲揃いアルバムと言える。(全ポップス・ファンが一家に一枚的作品)
一方、我が国で一家に一枚的存在になりそうだった松任谷由実さん。
彼女が荒井由実でデビューしたのが1973年の事。
多分にキャロル・キングの影響を受けたであろう事が伺える。
アルバム「ミスリム」は、「TAPESTRY」同様、力強くてシンプルな演奏に支えられた
彼女の唄と作品が、キッチリと世の中に、その存在意識を投げ掛けたアルバム。

キング、そしてユーミンどちらの作品も、後の世界、そして日本のポップス界に、
多大な影響を与えた一作と言える。
尚、ユーミンの初期の作品のいくつかは、件の紙ジャケットで、現在廉価で限定
発売中です。
Carole King / Tapestry(1971年度作品)
荒井由実 / MISSLIM (1973年度作品)
Vol.53(1998年09月号掲載)
今や全盛の紙ジャケって、この頃が始まりだったんですね!
“オモチャ”と一刀両断しているところが、いいですね。今更ながら。
なんて云うか、日本の印刷技術が誇る、あくまでも精巧な複製品ですから。
あれは。
ユーミンが果たせなかった“一家に一枚”は、この年か翌年に宇多田ヒカルが
1stアルバムで、ほぼ達成する事になる。
その位売れたモンスターアルバムでした。
キャロルさんは、最近、この「つづれおり」の後に出た「MUSIC」を良く聴きます。
ところで今の音楽ファン達は、シンガー・ソングライター(SSW)の意味を分かって
いるのかしらん?
な~んて疑問が、コピーを見て、頭の中に湧いてきた。
職業作家(作詞・作曲家)の音楽が当たり前だった頃から、音楽を聴いている
人達には、このSSWの出現は「作品も作れて歌も唄えるなんて凄い才能の
持ち主!」と驚く程、その存在が眩しかった。
それがいつの間にか、シンガー・ソングライター=アーティストという図式の中で、
所謂、ジャリタレまでもが、詞や曲を書くのが当たり前になってしまって、アーテ
ィストと名乗るようになった日本の音楽界。
なんて云うか、そんな輩の、お気軽な価値付けの為に利用されている。
そんなところもあったりして、どこかのタイミングで、ちょっぴり本来の意味からズレ
ちゃって、価値が落ちたのは確か。
だから俺は憂いでます。と書いたら大袈裟か・・・・・・(笑)
元祖!シンガー・ソングライター。
キングの超名作アルバムを一家に一枚!
近頃やたらと流行っている紙ジャケットによる限定盤シリーズ。
マニア心をくすぐるオリジナル仕様で、購買意欲をそそるんだけれども、
ありゃ、どう見ても玩具だな。オリジナルのアナログ盤を持っている者としては。
まぁ、洋酒とかのミニチュア瓶ってあるけど、あれと似たようなもので、中に詰まって
いるものは同じ味なんだけど・・・・・。って訳だ。
大体、CDになってからは、どうも音楽が玩具化しているように思えて仕方がない。
本来、保存されるべき文化として成立しレコード化されてきたはずなのに、CD時代
に突入してからは、大量消費文化と化し、時代のスピードと同じ速さで消費され、
捨てられている。
まぁ、保存されるべき内容のモノが少ないから。なんて言っちゃお終いだけど・・・・・。
そんな訳で、中古屋でレコード捜しのついでに、大量に売られているCDにも手を
延ばすと、結構掘り出しモノを見つける事が多い。
特に僕のように、ヒット物やメジャー・アーティストに対する興味が薄い人には、思わ
ぬ作品を、とんでもない安価で手に出来る。
先日も東京の某店で、「TAPESTRY REVISITED」なるアルバムを百円でゲット。
百円だよ。玉子のワン・パッケージより安いんだぜ。
それで、あのキャロル・キングのポップス史に残る超名作アルバムに敬意を表した、
このトリビュート・アルバムが買えちゃうんだから・・・・・。
トリビュート盤って近年の流行モノっぽくて、色んな作品が出ているけど、一人の
アーティストの一作品を丸々ってのは珍しい。

それ程までに愛されている「TAPESTRY」って、どんなアルバム。と言うより、
キャロル・キング自身を知らない人には、彼女の事から話さなければならないかも。
とは言うものの、この紙面で詳細を書くには無理があるので、超簡単に紹介しちゃうと、
所謂、元祖シンガー・ソングライター。
まぁ、今、多くのアーティストが自前で作って唄っちゃってるけど、そうゆう風な方向
付けした張本人って訳だ。(あのビートルズが、初めてニューヨークを訪れた際に、
最初に表敬訪問したのが彼女)
「TAPESTRY~つづれおり」は1971年に彼女のセカンド・アルバムとして発表された。
リード・シングルとして「イッツ・トゥ・レイト」が大ヒット。
又、収録された「君の友だち」をジャームズ・テイラーがカヴァーして大ヒットさせ、
そういった相乗効果で、当時、1000万枚を超える爆発的記録を作った1枚。
前述した通り、アルバム丸ごとカヴァーしたトリビュート盤が出来ても不思議じゃない
程、名曲揃いアルバムと言える。(全ポップス・ファンが一家に一枚的作品)
一方、我が国で一家に一枚的存在になりそうだった松任谷由実さん。
彼女が荒井由実でデビューしたのが1973年の事。
多分にキャロル・キングの影響を受けたであろう事が伺える。
アルバム「ミスリム」は、「TAPESTRY」同様、力強くてシンプルな演奏に支えられた
彼女の唄と作品が、キッチリと世の中に、その存在意識を投げ掛けたアルバム。

キング、そしてユーミンどちらの作品も、後の世界、そして日本のポップス界に、
多大な影響を与えた一作と言える。
尚、ユーミンの初期の作品のいくつかは、件の紙ジャケットで、現在廉価で限定
発売中です。
Carole King / Tapestry(1971年度作品)
荒井由実 / MISSLIM (1973年度作品)
2008年12月22日
名盤/T.REX & De+LAX
続・名盤を探しに行こう/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.52(1998年08月号掲載)
何回か前に文字数が減った旨が本文中に載っていたが、ホント、減った
お陰で、相当、こうして書き直すのが楽になりました。
だって、ちょっとペースが上がったでしょう。
禁断シリーズね・・・・・。
プログレもグラムも、どっかでその要素には出くわす事があるので、ロック
好きな方は、時間とお金があったら勉強を!
“アダバナ”ですか、T・レックスは?ま、いいか。
ちょっと最近聴き直しています。ロック界の徒花(!?)達の唄を・・・・・
禁断の果実の第2弾って訳じゃないけど、今回は『グラム・ロック』を書こうかなっ。
(前にデヴィッド・ボウイを書いたけど・・・・・・)
何でそんな気になったかと言うと、6月に閉めちゃった日清パワーステーションに、
De-LAXというバンドの再編ライヴを観に行ったからで、そのステージを観つつ、
あれやこれやと彼らの全盛時を思い出したからにほかならない。
その全盛時、彼らがステージでカバーしていたのがT.REXの「20th Century Boy」
なる曲。数有るT.REXのヒット曲の中の1曲だ。
「ブギーの申し子」なる言葉が示すように、マーク・ボラン率いるT.REXは70年代
のグラム・ロックな時代をブギーで染めた。
T.REXの全盛時、即ち71年から数年間、僕はすでにイギリスのロック・シーンを
離れアメリカ、特に西海岸のロック・シーンへと心が動かされていたので、彼らの
活動振りの詳細については、正直良く分からない。ってのが本音。
でも、海を越えて我が日本でも連発されるヒット曲の数々は、いやがうえでも耳に
入ってきた。
「ゲット・イット・オン」「テレグラム・サム」「メタル・グルー」等など。結構好きなナン
バーも多い。
さて、そのT・レックスのアルバムを1枚載り上げるとなると「電気の武者」あたりに
落ち着くかなっ。

タイトル(原題だよ)とジャケットが、まずはカッコイイ!「GET IT ON」と「JEEPSTER」
の2大ヒット曲が入っているが、冒頭の「MANBO SUN」から怪しげなブギーのリズム
とサウンド、そしてボランの何やら艶っぽいヴォーカルが炸裂する辺りがたまりません。
彼らの出発点でもあるアコースティック・サウンドとアルバム・タイトルに象徴される
エレクトリックを纏った姿の融合点とも言える「COSMIC DANCER」や「PLANET
QUEEN」といった作品は、今聴いても面白い。
なんて言うか、時代が作り出したグラマラスな空気感と、ボランの才気が全体に
蔓延していて、単なるヒットメイカーのアイドル然とした姿とは別世界を覗かして
くれる作品。ん~ん、再評価の価値有り。でぇ、件の「20th~」は後にベスト盤に収録。
そして、たった一夜のパーティー(つまらん金儲けの再編ツアーなどやるなよ)
の為に集まったデラックスの面々。パワステ終演後、何と新宿のロフトで深夜ギグ。
6年振りのステージの感触を存分に楽しんだようだ。
かく言う僕も一ファンとして存分に楽しませて貰った。こちらも、再評価の価値が
あるかもネ。
現在リリース中なのがデビュー盤とセカンド・アルバム「NEUROMANCER」。
そしてベスト的内容の2枚組のヒストリー盤のみ。枚数を重ねる毎に、その強烈な
個性がより出てきたのに、後期の名作達は現在廃盤中。
ってな訳で、てっとり早く彼らを知りたい人はヒストリー盤を。そして、ちゃんと
オリジナル盤で攻めたい!って人はデビュー作「De-LAX」から順序良く聴き始めよう。

温故知新。まぁ、新譜でいいのがなけりゃ、無理して買うな!たまにゃ旧譜で過去の
財産を見直しなさい。
因みに、来月の16日はマーク・ボランの21回目の命日です。
T REX / ELECTRIC WARRIOUS (1971年度作品)
De+LAX / De-LAX-SENSATION- (1988年度作品)
Vol.52(1998年08月号掲載)
何回か前に文字数が減った旨が本文中に載っていたが、ホント、減った
お陰で、相当、こうして書き直すのが楽になりました。
だって、ちょっとペースが上がったでしょう。
禁断シリーズね・・・・・。
プログレもグラムも、どっかでその要素には出くわす事があるので、ロック
好きな方は、時間とお金があったら勉強を!
“アダバナ”ですか、T・レックスは?ま、いいか。
ちょっと最近聴き直しています。ロック界の徒花(!?)達の唄を・・・・・
禁断の果実の第2弾って訳じゃないけど、今回は『グラム・ロック』を書こうかなっ。
(前にデヴィッド・ボウイを書いたけど・・・・・・)
何でそんな気になったかと言うと、6月に閉めちゃった日清パワーステーションに、
De-LAXというバンドの再編ライヴを観に行ったからで、そのステージを観つつ、
あれやこれやと彼らの全盛時を思い出したからにほかならない。
その全盛時、彼らがステージでカバーしていたのがT.REXの「20th Century Boy」
なる曲。数有るT.REXのヒット曲の中の1曲だ。
「ブギーの申し子」なる言葉が示すように、マーク・ボラン率いるT.REXは70年代
のグラム・ロックな時代をブギーで染めた。
T.REXの全盛時、即ち71年から数年間、僕はすでにイギリスのロック・シーンを
離れアメリカ、特に西海岸のロック・シーンへと心が動かされていたので、彼らの
活動振りの詳細については、正直良く分からない。ってのが本音。
でも、海を越えて我が日本でも連発されるヒット曲の数々は、いやがうえでも耳に
入ってきた。
「ゲット・イット・オン」「テレグラム・サム」「メタル・グルー」等など。結構好きなナン
バーも多い。
さて、そのT・レックスのアルバムを1枚載り上げるとなると「電気の武者」あたりに
落ち着くかなっ。

タイトル(原題だよ)とジャケットが、まずはカッコイイ!「GET IT ON」と「JEEPSTER」
の2大ヒット曲が入っているが、冒頭の「MANBO SUN」から怪しげなブギーのリズム
とサウンド、そしてボランの何やら艶っぽいヴォーカルが炸裂する辺りがたまりません。
彼らの出発点でもあるアコースティック・サウンドとアルバム・タイトルに象徴される
エレクトリックを纏った姿の融合点とも言える「COSMIC DANCER」や「PLANET
QUEEN」といった作品は、今聴いても面白い。
なんて言うか、時代が作り出したグラマラスな空気感と、ボランの才気が全体に
蔓延していて、単なるヒットメイカーのアイドル然とした姿とは別世界を覗かして
くれる作品。ん~ん、再評価の価値有り。でぇ、件の「20th~」は後にベスト盤に収録。
そして、たった一夜のパーティー(つまらん金儲けの再編ツアーなどやるなよ)
の為に集まったデラックスの面々。パワステ終演後、何と新宿のロフトで深夜ギグ。
6年振りのステージの感触を存分に楽しんだようだ。
かく言う僕も一ファンとして存分に楽しませて貰った。こちらも、再評価の価値が
あるかもネ。
現在リリース中なのがデビュー盤とセカンド・アルバム「NEUROMANCER」。
そしてベスト的内容の2枚組のヒストリー盤のみ。枚数を重ねる毎に、その強烈な
個性がより出てきたのに、後期の名作達は現在廃盤中。
ってな訳で、てっとり早く彼らを知りたい人はヒストリー盤を。そして、ちゃんと
オリジナル盤で攻めたい!って人はデビュー作「De-LAX」から順序良く聴き始めよう。

温故知新。まぁ、新譜でいいのがなけりゃ、無理して買うな!たまにゃ旧譜で過去の
財産を見直しなさい。
因みに、来月の16日はマーク・ボランの21回目の命日です。
T REX / ELECTRIC WARRIOUS (1971年度作品)
De+LAX / De-LAX-SENSATION- (1988年度作品)
2008年12月17日
名盤/ PINK FLOYD & 四人囃子
続・名盤を探しに行こう/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.51(1998年07月号掲載)
見捨てられたとか、忘れられたとか、なんとも酷い表現。
消耗品と化した今時のJ-POPよりも文化的で、遙かに美しいプログレなのに!
ラジオ番組のインタビューって何だろう?全く記憶にありません。
どうせなら、ジミヘンとかドアーズって言っときゃ良かった(笑)
プログレは、多分、同時代を生きた人の中には、瞬間的にハマったって人が多い
のではないかと思われます。
フロイドはじめ、YES、EL&Pなどなど時代を彩ったアーティストは多数居るけど、
なんと言っても“PINK FLOYD”の存在感は別格でしょ。
あぁ~、KING CRIMSONもそうか?
ロックが不良とか色々書いてあるが、今の時代じゃ考えられないくらい、市民権
を得られなかった時もあったのです。
で、結局、未だに聴くのは前述の別格な存在の二つだけ・・・・・。
まぁ、それはしょうがないか。
見捨てられ、忘れられた音楽
“プログレ”って、どんな音楽だったっけ・・・・・
禁断の果実とまでは言わないが、今時ロックファンの間でも、殆ど聴いて
いる人が居ないじゃないかと思われるのが“プログレシッヴ・ロック(通称
=プログレ)”と言われるカテゴリーの音楽。
先日、とあるラジオ番組のインタビューで「思い出に残っているコンサートは?」
と聞かれて、「ん~、ピンク・フロイドかなっ」なんて答えたら、相手の方がチン
プンカンプン状態でした。
俺としては、もの凄くポピュラリティのあるアーティストを自信を持って言った
だけなんだけどな・・・・・。
でぇ、その後「今観たいアーティストは?」ってえのに「ニール・ヤング」って答え
たら、益々可笑しくなっちゃって・・・・・。
きっとB’zとかGLAYって答えときゃ、世の中平和に収まったのに。
でぇ、本当に思い出というか印象に残っているコンサートのベスト3に入るのが
1972年3月13日の「ピンク・フロイド札幌公演」。
なんせ、俺、まだ高校生だったもね。
友達と試験の真最中だったけど「観に行こう」なんて約束していて、見事に裏切ら
れ、一人淋しさと、心細さに耐えて観に行ったコンサートだった。
まぁ、あの頃、コンサートが頻繁にあった訳でもないし、ましてや本格的なロック・
コンサートなんて皆無な時代。
そりゃ、ロックなんだから不良は集まるし、ハッパや薬でイッちゃった奴が一杯いて、
ヤバイ!危険!ってのが世間一般的なあの時代のロックに対する認識。
それにしてもよくピンク・フロイドが来たよな。この札幌まで。
記録を調べたら東京、大阪、京都と札幌の4カ所の公演で、ちょっと開催地としては
変則的かもしれない。
でも当日、中島スポーツセンターに集まった観客達は、間違いなく全盛期間近の
ピンク・フロイドを体験する一夜を過ごした。
その夜の一部は「月の裏側」という未発表作品。
ご丁寧にも訳詞の載ったチラシが配られたこの未発表の大作こそ、のちに彼らの
人気を全世界で決定付けた「狂気」だったのです。

この「狂気」は翌73年3月に発売されて以来、全米のアルバム・チャート100位
内に連続566週チャートイン(何と10年以上だぜ)、という空前の大ヒットとなる。
我が日本でも一家に1枚的ポピュラリティを得たアルバムと記憶する。
今聴き返してみると、当時感じていた大仰さや小難しさを全然感じる事なく聴け、
何というか適度な“癒しの音楽”風に聴こえるから不思議だ。
勿論、こんなに売れたら真似、いやいや信奉して追従する者がいたって不思議じゃ
ありません。この日本でも。
四人囃子は、そんな日本のプログレ界の頂点に立った存在だった。
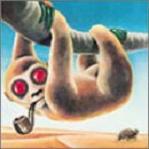
彼らのデビュー作は“癒し”とは別次元の、そうそう、ロックに対する熱~い情熱が
感じ取れる。
いってみれば、あの時代の日本のロックのジレンマみたいもんか。ん~ン、頑張れ!
日本みたいな。
そんな訳で、プログレ捨てたモンじゃないヨ。でぇ、気持ちはW杯、頑張って日本!
(6/7記)
PINK FLOYD / 狂気(1973年度作品)
四人囃子 / 一触触発(1974年度作品)
Vol.51(1998年07月号掲載)
見捨てられたとか、忘れられたとか、なんとも酷い表現。
消耗品と化した今時のJ-POPよりも文化的で、遙かに美しいプログレなのに!
ラジオ番組のインタビューって何だろう?全く記憶にありません。
どうせなら、ジミヘンとかドアーズって言っときゃ良かった(笑)
プログレは、多分、同時代を生きた人の中には、瞬間的にハマったって人が多い
のではないかと思われます。
フロイドはじめ、YES、EL&Pなどなど時代を彩ったアーティストは多数居るけど、
なんと言っても“PINK FLOYD”の存在感は別格でしょ。
あぁ~、KING CRIMSONもそうか?
ロックが不良とか色々書いてあるが、今の時代じゃ考えられないくらい、市民権
を得られなかった時もあったのです。
で、結局、未だに聴くのは前述の別格な存在の二つだけ・・・・・。
まぁ、それはしょうがないか。
見捨てられ、忘れられた音楽
“プログレ”って、どんな音楽だったっけ・・・・・
禁断の果実とまでは言わないが、今時ロックファンの間でも、殆ど聴いて
いる人が居ないじゃないかと思われるのが“プログレシッヴ・ロック(通称
=プログレ)”と言われるカテゴリーの音楽。
先日、とあるラジオ番組のインタビューで「思い出に残っているコンサートは?」
と聞かれて、「ん~、ピンク・フロイドかなっ」なんて答えたら、相手の方がチン
プンカンプン状態でした。
俺としては、もの凄くポピュラリティのあるアーティストを自信を持って言った
だけなんだけどな・・・・・。
でぇ、その後「今観たいアーティストは?」ってえのに「ニール・ヤング」って答え
たら、益々可笑しくなっちゃって・・・・・。
きっとB’zとかGLAYって答えときゃ、世の中平和に収まったのに。
でぇ、本当に思い出というか印象に残っているコンサートのベスト3に入るのが
1972年3月13日の「ピンク・フロイド札幌公演」。
なんせ、俺、まだ高校生だったもね。
友達と試験の真最中だったけど「観に行こう」なんて約束していて、見事に裏切ら
れ、一人淋しさと、心細さに耐えて観に行ったコンサートだった。
まぁ、あの頃、コンサートが頻繁にあった訳でもないし、ましてや本格的なロック・
コンサートなんて皆無な時代。
そりゃ、ロックなんだから不良は集まるし、ハッパや薬でイッちゃった奴が一杯いて、
ヤバイ!危険!ってのが世間一般的なあの時代のロックに対する認識。
それにしてもよくピンク・フロイドが来たよな。この札幌まで。
記録を調べたら東京、大阪、京都と札幌の4カ所の公演で、ちょっと開催地としては
変則的かもしれない。
でも当日、中島スポーツセンターに集まった観客達は、間違いなく全盛期間近の
ピンク・フロイドを体験する一夜を過ごした。
その夜の一部は「月の裏側」という未発表作品。
ご丁寧にも訳詞の載ったチラシが配られたこの未発表の大作こそ、のちに彼らの
人気を全世界で決定付けた「狂気」だったのです。

この「狂気」は翌73年3月に発売されて以来、全米のアルバム・チャート100位
内に連続566週チャートイン(何と10年以上だぜ)、という空前の大ヒットとなる。
我が日本でも一家に1枚的ポピュラリティを得たアルバムと記憶する。
今聴き返してみると、当時感じていた大仰さや小難しさを全然感じる事なく聴け、
何というか適度な“癒しの音楽”風に聴こえるから不思議だ。
勿論、こんなに売れたら真似、いやいや信奉して追従する者がいたって不思議じゃ
ありません。この日本でも。
四人囃子は、そんな日本のプログレ界の頂点に立った存在だった。
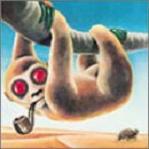
彼らのデビュー作は“癒し”とは別次元の、そうそう、ロックに対する熱~い情熱が
感じ取れる。
いってみれば、あの時代の日本のロックのジレンマみたいもんか。ん~ン、頑張れ!
日本みたいな。
そんな訳で、プログレ捨てたモンじゃないヨ。でぇ、気持ちはW杯、頑張って日本!
(6/7記)
PINK FLOYD / 狂気(1973年度作品)
四人囃子 / 一触触発(1974年度作品)
2008年12月08日
名盤/ERIC JUSTIN KAZ
続・名盤を探しに行こう/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.50(1998年06月号掲載)
ようやく半分の50回です。
なんだかんだで3年掛かりました。
「掲載する!」と宣言してから。
1年ほどで、直ぐに出来るかなと思っていたら、こんなに掛かっても、
まだ未完結。
ナント申しましょうか、人間の駄目さ加減みたいなモノで、
何の縛りもないと、こうもノンベンダラリとしてしまうもんだと。
この調子でやっていったら、結局6年程掛かってしまう訳で、
それって実際に掲載していた時と、たいした変わらないな~と。
(実際は8年強だから)
この連載を始める切っ掛けって、そんなんだっけ?ってのが、
チョッピリ、今となってはあるな。これを読むと。
名盤が“魔法の言葉”っね!
う~ん、いいところ付いているようで、そうでもないか。
でも当時は、魔法を掛けられたように名盤と名がつくものを漁った記憶
がある。
ジャスティン・カズは、ホント、あまり人に知られたくなかったアーティスト。
秘蔵中の秘蔵の1枚ってぇのは、シリーズで発売前に輸入盤で持って
いて、大事に聴いていて、「俺は持っているぜ~!」という優越感に浸れる
アルバムだった。(笑)
今でも国内盤と併せて2枚アナログ盤を持っている。が、ここで書かれた
初CD化も、その後の紙ジャケ化も、買ってない。
何故か、何年か前に来日し、札幌でもライヴを行ったけど、行っていません。
ライヴがどうだったかは知らないが、ライヴのイメージが無い人だったので、
行かなくてもいいかと・・・・・。
多分、その方が、いい印象のままで彼を聴き続ける事が出来るでしょ!
因みに、文中の名曲「Love Has No Pride」の、ご本家エリックが唄う
ヴァージョンは、後に組んだバンドのアルバム「American Flyer」の発売
まで待たねばならなかった!
70年代の名作がザクザク発売される、あのシリーズは要チェックです。
気付けば今回で“連載が何と50回!”。こりゃ~我ながら驚愕に値するな。
この長寿さは。と、感慨に耽ったりして・・・・・。
何か誌面はカラー化とか、色々と進化を遂げているんだけれど、我が文章
=相変わらずの稚拙さ。でぇ~、良く書いているわな。
てな訳で、、心機一転、これを機会に全面改装。なんて気には全然なりませ
んので、まぁ、続く限りお付き合いを・・・・・。で、今回はこの“名盤~”を書く
切っ掛けみたいな事でも書いてみましょうか。
そもそも音楽を聴き始めた頃、探究心が非常に強くて、情報を得る為に多く
の音楽番組や専門書などを漁りまくる日々が続いた。(似たような経験をし
ている読者もいるハズ)
そんな中で必ずぶつかったのが、お偉い先生方が仰る“名盤”という魔法の
言葉。
この魔法の言葉に出くわす度に“こりゃ~凄そう!聴かなくちゃ”って事で買
いに行くんだけど、如何せん売ってないのです。その聴かなくちゃいけない
モノが・・・・・。
そんな訳で、あっちこっちのレコード屋(勿論、中古屋や輸入盤専門店など)
へ行って捜す日々が続く中で、1枚見つけては喜び、また1枚見つけては喜ぶ。
といった何とも音楽愛好家として清く正しい少年時代を思い出したのが、そも
そもの切っ掛けかなっ。
勿論、まだこんなにいい音楽が一杯あるってのも知って貰いたい。って一心
もあったのも事実。
でも、お偉いさん達が口にする名盤って、すでに廃盤や国内盤が発売されて
いない非常に希少価値が高いモノが多くて、簡単に入手出来なかった。
(当時は輸入盤は高価で品薄状態だった。)
そんな苦闘の日々があってこそ、所謂“名盤”と言われる作品を手にする事
が出来た訳で、ここでは、この名盤=入手困難。って図式をぶち壊して、
出来るだけ簡単に入手出来るモノを紹介して行こうと始めた訳。(マニアック
なモノは出来るだけ外してネ。)
そんなこんなで、この名盤って魔法の言葉を大々的に使って宣伝されたのが
76年の「ロック名盤復活シリーズ」だった。
当時のアメリカン・ロックの隆盛やシンガー・ソングライター・ブームを反映した
企画で、それこそ幻と言われた名盤が、ユーザーの人気投票で発売される
という好企画。
その中の1枚で、本当に長い間幻だったエリック・ジャスティン・カズの
「IF YOU’RE LONELY」が先頃“名盤探検隊”と銘打ったシリーズの1枚と
してCD化された。

エリック・カズは、以前ここでとり上げたリンダ・ロンシュタットの名曲「Love
Has No Pride」の作者。
その朴訥とした歌い振りとソウルフルな作風が魅力的なシンガー・ソング
ライターで、この作品こそ僕の秘蔵中の秘蔵の1枚だった。
予想外にこのシリーズのモノが売れているらしくて、品切れ店が続出らしい。
なんて話を聞いて、いいモノの情報は何処からともなくしっかりと伝わるん
だな。と感心。まぁ、このジャケット同様、ソファーに寝転んでリラックスして
聴きたい名作だ。
そんな訳で、また幻にならないうちに手に入れておいて下さい。
ERIC JUSTIN KAZ / IF YOU’RE LONELY (1972年度作品)
Vol.50(1998年06月号掲載)
ようやく半分の50回です。
なんだかんだで3年掛かりました。
「掲載する!」と宣言してから。
1年ほどで、直ぐに出来るかなと思っていたら、こんなに掛かっても、
まだ未完結。
ナント申しましょうか、人間の駄目さ加減みたいなモノで、
何の縛りもないと、こうもノンベンダラリとしてしまうもんだと。
この調子でやっていったら、結局6年程掛かってしまう訳で、
それって実際に掲載していた時と、たいした変わらないな~と。
(実際は8年強だから)
この連載を始める切っ掛けって、そんなんだっけ?ってのが、
チョッピリ、今となってはあるな。これを読むと。
名盤が“魔法の言葉”っね!
う~ん、いいところ付いているようで、そうでもないか。
でも当時は、魔法を掛けられたように名盤と名がつくものを漁った記憶
がある。
ジャスティン・カズは、ホント、あまり人に知られたくなかったアーティスト。
秘蔵中の秘蔵の1枚ってぇのは、シリーズで発売前に輸入盤で持って
いて、大事に聴いていて、「俺は持っているぜ~!」という優越感に浸れる
アルバムだった。(笑)
今でも国内盤と併せて2枚アナログ盤を持っている。が、ここで書かれた
初CD化も、その後の紙ジャケ化も、買ってない。
何故か、何年か前に来日し、札幌でもライヴを行ったけど、行っていません。
ライヴがどうだったかは知らないが、ライヴのイメージが無い人だったので、
行かなくてもいいかと・・・・・。
多分、その方が、いい印象のままで彼を聴き続ける事が出来るでしょ!
因みに、文中の名曲「Love Has No Pride」の、ご本家エリックが唄う
ヴァージョンは、後に組んだバンドのアルバム「American Flyer」の発売
まで待たねばならなかった!
70年代の名作がザクザク発売される、あのシリーズは要チェックです。
気付けば今回で“連載が何と50回!”。こりゃ~我ながら驚愕に値するな。
この長寿さは。と、感慨に耽ったりして・・・・・。
何か誌面はカラー化とか、色々と進化を遂げているんだけれど、我が文章
=相変わらずの稚拙さ。でぇ~、良く書いているわな。
てな訳で、、心機一転、これを機会に全面改装。なんて気には全然なりませ
んので、まぁ、続く限りお付き合いを・・・・・。で、今回はこの“名盤~”を書く
切っ掛けみたいな事でも書いてみましょうか。
そもそも音楽を聴き始めた頃、探究心が非常に強くて、情報を得る為に多く
の音楽番組や専門書などを漁りまくる日々が続いた。(似たような経験をし
ている読者もいるハズ)
そんな中で必ずぶつかったのが、お偉い先生方が仰る“名盤”という魔法の
言葉。
この魔法の言葉に出くわす度に“こりゃ~凄そう!聴かなくちゃ”って事で買
いに行くんだけど、如何せん売ってないのです。その聴かなくちゃいけない
モノが・・・・・。
そんな訳で、あっちこっちのレコード屋(勿論、中古屋や輸入盤専門店など)
へ行って捜す日々が続く中で、1枚見つけては喜び、また1枚見つけては喜ぶ。
といった何とも音楽愛好家として清く正しい少年時代を思い出したのが、そも
そもの切っ掛けかなっ。
勿論、まだこんなにいい音楽が一杯あるってのも知って貰いたい。って一心
もあったのも事実。
でも、お偉いさん達が口にする名盤って、すでに廃盤や国内盤が発売されて
いない非常に希少価値が高いモノが多くて、簡単に入手出来なかった。
(当時は輸入盤は高価で品薄状態だった。)
そんな苦闘の日々があってこそ、所謂“名盤”と言われる作品を手にする事
が出来た訳で、ここでは、この名盤=入手困難。って図式をぶち壊して、
出来るだけ簡単に入手出来るモノを紹介して行こうと始めた訳。(マニアック
なモノは出来るだけ外してネ。)
そんなこんなで、この名盤って魔法の言葉を大々的に使って宣伝されたのが
76年の「ロック名盤復活シリーズ」だった。
当時のアメリカン・ロックの隆盛やシンガー・ソングライター・ブームを反映した
企画で、それこそ幻と言われた名盤が、ユーザーの人気投票で発売される
という好企画。
その中の1枚で、本当に長い間幻だったエリック・ジャスティン・カズの
「IF YOU’RE LONELY」が先頃“名盤探検隊”と銘打ったシリーズの1枚と
してCD化された。

エリック・カズは、以前ここでとり上げたリンダ・ロンシュタットの名曲「Love
Has No Pride」の作者。
その朴訥とした歌い振りとソウルフルな作風が魅力的なシンガー・ソング
ライターで、この作品こそ僕の秘蔵中の秘蔵の1枚だった。
予想外にこのシリーズのモノが売れているらしくて、品切れ店が続出らしい。
なんて話を聞いて、いいモノの情報は何処からともなくしっかりと伝わるん
だな。と感心。まぁ、このジャケット同様、ソファーに寝転んでリラックスして
聴きたい名作だ。
そんな訳で、また幻にならないうちに手に入れておいて下さい。
ERIC JUSTIN KAZ / IF YOU’RE LONELY (1972年度作品)
2008年12月04日
名盤/STONES & SLIDERS
続・名盤を探しに行こう/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.49(1998年05月号掲載)
十代の頃に目覚めた音楽、そしてアイドルとなったストーンズ。
よく考えると、こうして何十年もアイドルとして存在しているモノが
あるって事は凄い事なんじゃないか、と。
40数年もバンドを続けるのも凄いけど、それをいまだに追っ掛けて
いる人が大勢いるってのがね・・・。
ま、この長い年月の積み重ねは、いい存在に出会えた人だけが
味わえるというか分かる、ある意味勝利でしょうね!これは!
そして、これは3度目の来日に併せて書いたのかなっ?
センターステージは、いまや日本のアイドルまでにも普及している、
大会場には欠かせない演出道具の一つ。
動員が悪いってのが書いてあるが、初来日の東京ドーム10日間
50万人動員ってぇのがバブルで、当時、多分日本じゃ、その十分
の一くらいしかアルバムが売れていなかったんじゃないかな、
ストーンズは!
その後の来日で福岡に行ったりして、動員が駄目で・・・。
(もしかしたらこの時かも?)
そんな事知っているから札幌公演の入りを心配したんですよ。
見事に当たっちゃたけど・・・。
で、タイミング良く今週末から映画「SHINE A LIGHT」が全国で公開
される。
以前だと、もうそれだけでワクワクしたけど、今はなんと言うか、頻繁
にDVDが発売されているのもあって、そんな事もなくなったな~と。
所謂満たされている!状態で、映像にそれ程飢えていない。
公開タイミングで東京出張があるので、どこか大きなスクリーンの
映画館で観ようかとも思ったが、スケジュール的に無理そうなので、
さっさとそれを諦めて、シアターキノで前売り券を買ってきた。
オマケで付いてきたでっかいポストカード、使い道もなければ飾るには
デザインが・・・・・です。
観終わって、気が向いたら感想を書きますね!
やっぱり来日記念に書かせて貰います。
我が永遠のアイドル“ザ・ローリング・ストーンズ”について
何かここんとこオリンピックみたく何年かに一度来日している、恒例
“ローリング・ストーンズ日本公演”に、これまた恒例で行って来ました。
東京公演の最終日だったんだけど、驚く程客が入ってなくて、我が目を
疑って、何度も会場全体を見渡してしまった。
あぁ~、あの人気はバブルと共に去ったのネ。なんて思うのと同時に、
これで正常な状態に戻ったな。と変な安心感を抱いた。
まぁ、内容についてはそれなりにマスコミが取り上げているので、どうの
こうのとは言いたくないが、見事なエンターテイメントであり、伝統芸、
ってとこかなっ。なんて言うか“お決まりのフルコース”って訳。
でもその中で光っていたのが、今回の売りの一つ“センターステージ”
(詳細は自分で調べて)での演奏。
これだけはブッ飛びました。本当に体は思わずのけぞったし、涙は溢れるし、
これがストーンズだ!俺が愛したストーンズだ!な~んて世界に入り込ん
じゃった。
演ったのはチャック・ベリーのカバー「Little Queenie」と「Crazy Mama」。
そして「Like A Rolling Stone」の3曲。
最後のディランのカバーは全然ツマらんくてシラケちゃったけど、あとは
流石年季もんの凄さだった。
でぇ、今回そのベリーを取り上げようと思って何軒かのCD屋に行ったけど、
全然CDが売っていないの。
そんな訳で、ストーンズ公演からもう一つの涙モンだった「Memory Motel」
の話でもしようかなっ。と・・・・・。
これは今回の公演のもう一つの売り、インタネットを使ったリクエスト集計に
よる“日替わりメニュー”の1曲。
で、何とこの日は、長年ライヴで聴きたかった前述の「メモリー・モーテル」。
この曲が収録されたアルバム「BLACK AND BLUE」は、ツアー・ギタリスト
としてかり出されていたロン・ウッドが正式メンバーとして迎い入れられた
記念碑的作品。

当時のレイドバック的風潮を反映してか、どことなくユル~イ感が漂う作品で、
あの「悲しみのアンジー」より遙かに美しいナンバー「メモリー・モーテル」と
「愚か者の涙」を収録。
他にもストーンズ・ファンならずとも、分かる人には分かる名曲名演揃いの、
隠れ名盤の誉れ高いアルバム。
さて、そのストーンズを追随するバンド多数あれど、この時期のユルさ加減
を、と言ったらそうはいない。
先頃、15年目にして初のベスト盤「HOT MENU」をリリースしたストリート・
スライダーズが、もしかしたらそんなユルさ加減を追求していたのかも知れ
ない。
抜こうにも抜けないユルさの表現を、デビュー以来もがき続け、やっと彼ら
なりに完成に近付けたのが「SCREW DRIVER」辺りか。

タイトながらも、そんなユルさの気配が漂った力作と言える1枚だった。
ところで、以前この名盤で紹介したストーンズの名作ライヴ盤「LOVE YOU
LIVE」が、現在廉価で再発中。最高のライヴ・バンドと言われた頃の凄さを
是非その耳で確かめて。
The Rolling Stones / Black And Blue(1976年度作品)
The Street Sliders / Screw Driver(1989年度作品)
Vol.49(1998年05月号掲載)
十代の頃に目覚めた音楽、そしてアイドルとなったストーンズ。
よく考えると、こうして何十年もアイドルとして存在しているモノが
あるって事は凄い事なんじゃないか、と。
40数年もバンドを続けるのも凄いけど、それをいまだに追っ掛けて
いる人が大勢いるってのがね・・・。
ま、この長い年月の積み重ねは、いい存在に出会えた人だけが
味わえるというか分かる、ある意味勝利でしょうね!これは!
そして、これは3度目の来日に併せて書いたのかなっ?
センターステージは、いまや日本のアイドルまでにも普及している、
大会場には欠かせない演出道具の一つ。
動員が悪いってのが書いてあるが、初来日の東京ドーム10日間
50万人動員ってぇのがバブルで、当時、多分日本じゃ、その十分
の一くらいしかアルバムが売れていなかったんじゃないかな、
ストーンズは!
その後の来日で福岡に行ったりして、動員が駄目で・・・。
(もしかしたらこの時かも?)
そんな事知っているから札幌公演の入りを心配したんですよ。
見事に当たっちゃたけど・・・。
で、タイミング良く今週末から映画「SHINE A LIGHT」が全国で公開
される。
以前だと、もうそれだけでワクワクしたけど、今はなんと言うか、頻繁
にDVDが発売されているのもあって、そんな事もなくなったな~と。
所謂満たされている!状態で、映像にそれ程飢えていない。
公開タイミングで東京出張があるので、どこか大きなスクリーンの
映画館で観ようかとも思ったが、スケジュール的に無理そうなので、
さっさとそれを諦めて、シアターキノで前売り券を買ってきた。
オマケで付いてきたでっかいポストカード、使い道もなければ飾るには
デザインが・・・・・です。
観終わって、気が向いたら感想を書きますね!
やっぱり来日記念に書かせて貰います。
我が永遠のアイドル“ザ・ローリング・ストーンズ”について
何かここんとこオリンピックみたく何年かに一度来日している、恒例
“ローリング・ストーンズ日本公演”に、これまた恒例で行って来ました。
東京公演の最終日だったんだけど、驚く程客が入ってなくて、我が目を
疑って、何度も会場全体を見渡してしまった。
あぁ~、あの人気はバブルと共に去ったのネ。なんて思うのと同時に、
これで正常な状態に戻ったな。と変な安心感を抱いた。
まぁ、内容についてはそれなりにマスコミが取り上げているので、どうの
こうのとは言いたくないが、見事なエンターテイメントであり、伝統芸、
ってとこかなっ。なんて言うか“お決まりのフルコース”って訳。
でもその中で光っていたのが、今回の売りの一つ“センターステージ”
(詳細は自分で調べて)での演奏。
これだけはブッ飛びました。本当に体は思わずのけぞったし、涙は溢れるし、
これがストーンズだ!俺が愛したストーンズだ!な~んて世界に入り込ん
じゃった。
演ったのはチャック・ベリーのカバー「Little Queenie」と「Crazy Mama」。
そして「Like A Rolling Stone」の3曲。
最後のディランのカバーは全然ツマらんくてシラケちゃったけど、あとは
流石年季もんの凄さだった。
でぇ、今回そのベリーを取り上げようと思って何軒かのCD屋に行ったけど、
全然CDが売っていないの。
そんな訳で、ストーンズ公演からもう一つの涙モンだった「Memory Motel」
の話でもしようかなっ。と・・・・・。
これは今回の公演のもう一つの売り、インタネットを使ったリクエスト集計に
よる“日替わりメニュー”の1曲。
で、何とこの日は、長年ライヴで聴きたかった前述の「メモリー・モーテル」。
この曲が収録されたアルバム「BLACK AND BLUE」は、ツアー・ギタリスト
としてかり出されていたロン・ウッドが正式メンバーとして迎い入れられた
記念碑的作品。

当時のレイドバック的風潮を反映してか、どことなくユル~イ感が漂う作品で、
あの「悲しみのアンジー」より遙かに美しいナンバー「メモリー・モーテル」と
「愚か者の涙」を収録。
他にもストーンズ・ファンならずとも、分かる人には分かる名曲名演揃いの、
隠れ名盤の誉れ高いアルバム。
さて、そのストーンズを追随するバンド多数あれど、この時期のユルさ加減
を、と言ったらそうはいない。
先頃、15年目にして初のベスト盤「HOT MENU」をリリースしたストリート・
スライダーズが、もしかしたらそんなユルさ加減を追求していたのかも知れ
ない。
抜こうにも抜けないユルさの表現を、デビュー以来もがき続け、やっと彼ら
なりに完成に近付けたのが「SCREW DRIVER」辺りか。

タイトながらも、そんなユルさの気配が漂った力作と言える1枚だった。
ところで、以前この名盤で紹介したストーンズの名作ライヴ盤「LOVE YOU
LIVE」が、現在廉価で再発中。最高のライヴ・バンドと言われた頃の凄さを
是非その耳で確かめて。
The Rolling Stones / Black And Blue(1976年度作品)
The Street Sliders / Screw Driver(1989年度作品)
2008年12月02日
名盤/Al Kooper & COSA NOSTRA
続・名盤を探しに行こう/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.48(1998年04月号掲載)
TKですか。この1998年頃も絶頂期だったのかしらん。
アル・クーパーは、まだ聴いてはいないけど、ナント、新作を出しましたね。
そう言えば、前に出した時に初来日公演があって、俺、渋谷のAXに観に
行きました。
もちろん「ジョリー」は唄いました。あとBLUES PROJECT時代の曲とか、
「Like A Rolling Stone」のフレーズを何かの曲にチャラチャラとフィーチャー
したりと、割と大きな括りでのアル・クーパー像を演ってくれたような記憶が・・・。
アルは、未だにアルバムを引っ張り出して聴く事がある。
この「赤心の歌」は勿論の事、「紐育市 (お前は女さ)」とか色々なアルバム
を聴きます。ま、好きなんでしょうね。
COSA NOSTRAの方は、ナンカ気にはしていたが、そのうち居なくなったり
再結成したりと、よく分からない状況になっていった感じ。
嘘か真は、これも分からんが女子二人が美人で酒豪って話をどこかで
聞いての締め文章。
そうありたいと思う男の願望ですね!単にこれは!
あの当時は、まぁ、今で言う“TK”みたいな凄い(!?)人だったはず。
この人は・・・。
でぇ、先月の貴重盤のレコードが結構出回っている云々の話なんだけど、
その中にアル・クーパーが1970年に発表した「EASY DOES IT」という2
枚組のアルバムがある。
このアルバムが、捜せど捜せど、滅多にお目に掛かれない代物で、長い
探索歴の中で一度だけ出会ったのが、かなりくたびれたジャケットの高額
商品。で、どうも買う勇気が出なくて・・・それ以来全く縁無状態が続いた
ヤツだ。
それがやたら出回っていて、きっとCD化されたのを買った人が、手放し
たのかなっ。なんて思ったりして。
そうそう、我輩もCD化されたヤツに飛び付いたクチで、今更LP盤は・・・。
まぁ、お金に余裕が有る時に手に入れますわ。
さて、そのアル・クーパーと言えば、まず思い起こされるのが“スーパー・
セッション”もの。まぁ、なんたって元祖な人と言っても過言ではないからネ。
それとプロデュ―サーとしての存在。
あのロックがもっともロックらしかった70年前後の活躍振りは特筆もの。
そして自らのアーティスト性も忘れてはならない。
シンガー・ソングライターとしての資質やマルチ・プレイヤー振り。と言った
ところが、アルを語る上で、必ず話題として持ち出される。
そんなアルの作品の中で、一枚だけ選びなさいと言われたら、僕は迷わず
「赤心の歌(Naked Songs)」を挙げる。

低音の声の唄い出しから徐々に高揚していくように盛り上がる冒頭の「自分
自身でありなさい」、決して上手くはないが味のあるフレーズを聴かせるギタ
ーが唸る「時の流れのごとく」、そして名曲「ジョリー」と繋がる流れは、何度
聴いても飽きる事がない。
また、他の彼のアルバム同様、他アーティストの作品を上手く取り入れ、自身
の作品の中に溶け込ます術は抜群で、ここでも地味な存在だったジョン・プラ
インの「サム・ストーン氏の場合には」や、サム・クックの作品を収録している。
まぁ、全編、ちょっと頼りないヴォーカルに付き合わされる訳だけど、今聴いて
も古さを感じさせない“やっぱり名盤”と頷く一枚。
そうそう、発売当時、ロック・ファンよりも、どちらかと言うと、R&B寄りの音楽
を聴いていた人達に支持されていたように記憶している。
その名盤の中の名曲「ジョリー」が頻繁にラジオから流れてきたのが、つい
数年前の事。見事にカヴァーしてくれたのがCOSA NOSTRAの面々。
勿論、アルバムにも収録しているが、MAXI SINGLEとして同曲を何ヴァー
ジョンか収録したものも発売している。

「ジョリー」を収録したアルバム「LOVE THE MUSIC」は、タイトル・チューンの
リズム(これが「悪魔を憐れむ歌」なんだな~)のオーバーチュア後の実質的
一曲目が「Be Yourself」。
これって「赤心の歌」の1曲目の原題の一部だぜぃ。もう凄~くヒップなアルバム
です。
もしかしたら、コンセプトにあの時代があったのかしらん。などと思いつつ、
とっても酒豪(!?)らしい美女お二人と盛り上がりながら過ごす夜も悪くないな~。
なんて勝手に思う春の良き日でした。
Al Kooper / Naked Song(1972年度作品)
COSA NOSTRA / LOVE THE MUSIC(1995年度作品)
Vol.48(1998年04月号掲載)
TKですか。この1998年頃も絶頂期だったのかしらん。
アル・クーパーは、まだ聴いてはいないけど、ナント、新作を出しましたね。
そう言えば、前に出した時に初来日公演があって、俺、渋谷のAXに観に
行きました。
もちろん「ジョリー」は唄いました。あとBLUES PROJECT時代の曲とか、
「Like A Rolling Stone」のフレーズを何かの曲にチャラチャラとフィーチャー
したりと、割と大きな括りでのアル・クーパー像を演ってくれたような記憶が・・・。
アルは、未だにアルバムを引っ張り出して聴く事がある。
この「赤心の歌」は勿論の事、「紐育市 (お前は女さ)」とか色々なアルバム
を聴きます。ま、好きなんでしょうね。
COSA NOSTRAの方は、ナンカ気にはしていたが、そのうち居なくなったり
再結成したりと、よく分からない状況になっていった感じ。
嘘か真は、これも分からんが女子二人が美人で酒豪って話をどこかで
聞いての締め文章。
そうありたいと思う男の願望ですね!単にこれは!
あの当時は、まぁ、今で言う“TK”みたいな凄い(!?)人だったはず。
この人は・・・。
でぇ、先月の貴重盤のレコードが結構出回っている云々の話なんだけど、
その中にアル・クーパーが1970年に発表した「EASY DOES IT」という2
枚組のアルバムがある。
このアルバムが、捜せど捜せど、滅多にお目に掛かれない代物で、長い
探索歴の中で一度だけ出会ったのが、かなりくたびれたジャケットの高額
商品。で、どうも買う勇気が出なくて・・・それ以来全く縁無状態が続いた
ヤツだ。
それがやたら出回っていて、きっとCD化されたのを買った人が、手放し
たのかなっ。なんて思ったりして。
そうそう、我輩もCD化されたヤツに飛び付いたクチで、今更LP盤は・・・。
まぁ、お金に余裕が有る時に手に入れますわ。
さて、そのアル・クーパーと言えば、まず思い起こされるのが“スーパー・
セッション”もの。まぁ、なんたって元祖な人と言っても過言ではないからネ。
それとプロデュ―サーとしての存在。
あのロックがもっともロックらしかった70年前後の活躍振りは特筆もの。
そして自らのアーティスト性も忘れてはならない。
シンガー・ソングライターとしての資質やマルチ・プレイヤー振り。と言った
ところが、アルを語る上で、必ず話題として持ち出される。
そんなアルの作品の中で、一枚だけ選びなさいと言われたら、僕は迷わず
「赤心の歌(Naked Songs)」を挙げる。

低音の声の唄い出しから徐々に高揚していくように盛り上がる冒頭の「自分
自身でありなさい」、決して上手くはないが味のあるフレーズを聴かせるギタ
ーが唸る「時の流れのごとく」、そして名曲「ジョリー」と繋がる流れは、何度
聴いても飽きる事がない。
また、他の彼のアルバム同様、他アーティストの作品を上手く取り入れ、自身
の作品の中に溶け込ます術は抜群で、ここでも地味な存在だったジョン・プラ
インの「サム・ストーン氏の場合には」や、サム・クックの作品を収録している。
まぁ、全編、ちょっと頼りないヴォーカルに付き合わされる訳だけど、今聴いて
も古さを感じさせない“やっぱり名盤”と頷く一枚。
そうそう、発売当時、ロック・ファンよりも、どちらかと言うと、R&B寄りの音楽
を聴いていた人達に支持されていたように記憶している。
その名盤の中の名曲「ジョリー」が頻繁にラジオから流れてきたのが、つい
数年前の事。見事にカヴァーしてくれたのがCOSA NOSTRAの面々。
勿論、アルバムにも収録しているが、MAXI SINGLEとして同曲を何ヴァー
ジョンか収録したものも発売している。

「ジョリー」を収録したアルバム「LOVE THE MUSIC」は、タイトル・チューンの
リズム(これが「悪魔を憐れむ歌」なんだな~)のオーバーチュア後の実質的
一曲目が「Be Yourself」。
これって「赤心の歌」の1曲目の原題の一部だぜぃ。もう凄~くヒップなアルバム
です。
もしかしたら、コンセプトにあの時代があったのかしらん。などと思いつつ、
とっても酒豪(!?)らしい美女お二人と盛り上がりながら過ごす夜も悪くないな~。
なんて勝手に思う春の良き日でした。
Al Kooper / Naked Song(1972年度作品)
COSA NOSTRA / LOVE THE MUSIC(1995年度作品)
2008年12月01日
名盤/Towa Tei & nokko
続・名盤を探しに行こう/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.47(1998年03月号掲載)
コンピュータの進歩はこの原稿を書いた後、ご存知のように凄まじい。
21世紀に入りコンピュータが無い時代など考えられなくなった。
この間のThe Whoのライヴで、60年代の映像に触れたが、あの映像を
観て、当時のアナクロな感じっていいかもね!などと瞬間的に思いもした
が、実際、今の世の中の流れの中じゃ無理ってぇのが、直ぐに頭の中を
過ぎった。
使いこなすのが大変だけど、コンピュータの無い時代なんて、もう考えら
れない。でぇ、仲良くなりなさい!だと。そんなの余計なお世話だ!
さて、テクノ少年達のバイブルって表現が正しいかどうかは不明だが、
今や売れっ子の中田ヤスタカ辺りが、そんな少年の一人だったんじゃない
かな。
テイ・トウワはDEEE LITEの時は謎の東洋人で、突如現われたような
気がする。
ソロ活動に入った時の方のインパクト・・・・・相当ありました。
久し振りに「あぁ~、この人の頭の中を覗いて見たい!」と思った次第。
コンピュータに触れる切っ掛けを作ったあの1枚!
年末年始、札幌と東京で、またもやこの20年程捜していたレコードを見つけて、
ちょっと機嫌がいい日が続いています。
それにしても中古市場は、相次ぐ旧譜のCD化の影響かなんかで、以前なら
考えられないようなレコードが、ごっそりと適価で出回っている。
これらは、CDに買い変えた人達が手放した物なのかしらん・・・。
なんて思いつつ、久しく中断していた中古屋巡りが仲々楽しい今日この頃。
中古と言えばコンピュータも次々と高性能の新型が出てくるもんだから、
中古品やら新古品やらが溢れている。
それにしても仲々好き勝手に操れないコンピュータ。と、苦手意識を持ちつつ
も“時代が使えなくちゃ!”と耳元で囁いているような強迫観念に押されて悪戦
苦闘の日々。という同胞も多いハズ。
さて、この俺をそのコンピュータに向かわせる切っ掛けを作ったアルバムがある。
テイ・トウワの「Future Listening !」だ。

んっ、これを聴いてプログラミングを駆使して音楽を作ろう!と思ったかって。
そんな事は全く考えません。答えは簡単にCD-ROMだ。
勿論非売品で、たしかソフト会社が、テイのこのアルバムに絡めて、何だかの
コンテストをやった時のものだ。
そのROMについてこれ以上書くのは誌面の都合で省くが、それを理解する為に、
ついに手をだしたって訳。コンピュータに。
そんな切っ掛けを作ってくれたテイ・トウワのこのアルバム。
ジャケットのあのポーズが、すっかり有名(!?)になっちゃったりして。まぁ、
新時代のテクノ少年達のバイブルのような1枚とも言える。
それにしても聴き心地満点なアルバムだな。これは。
きっと、当時、メッチャ音がいいクラブで聴いたら、腰砕け状態だったろう。
例えば「Technova」を作り出す発想。例えば「Luv Connection」や「甘い生活」
の洗練されたコンテンポラリーさ。
例えば「Batucada」や「Obrigado」でのボッサへのアプローチ。などなど上げ
出したら全ての曲目について何かをコメントしなければならない程、その
才能を余すところなく発揮している。
タスキに書かれた豪華キャスティングの面々の事を云々するより、その
コーディネイトの妙が冴え渡った作品だ。
勿論、このアルバムから生み出された2枚のリミックス盤も併せて聴く事を
お薦めする。テイ・トウワ恐ろるべし。
そのテイ氏が、このアルバムと同時期にプロデュースした作品がある。
ノッコの「人魚」(作曲は筒美京平)という実に美しいナンバー。
この1曲の為にアルバム「colored」を購入したりして。まぁ、「ライブが
はねたら」も入っているし・・・。

この2曲を繰り返し繰り返し聴く。ってのが、このアルバムとのもっぱらの
付き合い方。
てな訳で、コンピュータ=テイ氏。という話だったけど、皆さんも、これからは
コンピュータと仲良くなりなさいよヨ。そういう時代なんだから。
Towa Tei / Future Listening ! (1994年度作品)
Nokko / colored (1994年度作品)
2008年11月18日
名盤/CARPENTERS & 桑名正博
続・名盤を探しに行こう/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.46(1998年02月号掲載)
職業作家って、いつのまにか演歌とかアイドルとか、その辺だけに存在
する時代になったように思う。
今、音楽演っている人達って、大体作品の自作自演の方が多い訳で、
そんな人達が、あっちこっちに一杯居て、ま、なんか適当に提供して成り
立っている。
で、たいして才能のない輩が、自分のアルバムも無理して自作自演の曲
だけで埋めちゃうから、なんかつまらないアルバムが出来てしまう。
曲が足りないなら、作家にいい曲なり詞を頼めばいいのに。
それで完成度を高めた方が、よっぽど後世に残る立派な作品になるのに。
昔、シンガー・ソングライターが出てきた時、そりゃーそりゃー、凄い才人が
現れたもんだ!と巷の一般的な音楽ファンは思ったよ。
それが今じゃ当たり前になってしまった。
食糧事情が良くなって、ミンナ、脳味噌も増え、感性にも磨きが掛かり、
バリバリ曲とか書けるようになったようだ。あぁ、道具の進歩もね。
カーペンターズの大リバイバルって、5年位前の事かと思っていたら、
十数年も前の事だったんだ。
移り往く時代は早い!記憶の回路に残っている情報は、相当不確かなモノ
に変形しているようで、当てにしてはいけない!と反省。
名盤の影にプロフェショナルな作曲家有り!職業作家(!?)を見直そう!
今こそ・・・。
皆さん、恒例の年末年始の行事は無事終わったでしょうか。一年の総括って
事で、この時期、適当に理由を付けて、もっともらしく一年を振り返るものですが、
さっぱりそんな気にさせてくれない今日この頃です。
なんて書いていられない程、このコラムの文字数が減らされたので、さっそく
本題に入らなければ・・・・・。
さて、年末この音楽業界を賑わせた話題の一つに“筒美京平”がある。
まぁ、知らない人には“日本の歌謡ポップス史に残る最重要作曲家”の一人と
して貰いましょうか。
きっと知らず知らずのうちに、この大先生の作品を一杯一杯聴いて育った!って
人が多いとは思うのですが。
でぇ、この筒美京平の話は置いといて、海外に目を向けてポップス界に影響を
与えた作曲家となると、真先にバート・バカラックの名前が出てくるのは、ある
程度年齢がいった方だけでしょうネ。
若い方には、ちょっと前に大リバイバル・ブームを巻き起こしたカーペンターズ
の最初のミリオン・ヒット曲でもあり、その人気を決定付けた「遙かなる影{原題:
(They Long To Be)CLOSE TO YOU}」の作者と言った方が分かり易いかも知れ
ないし、勉強熱心な方なら、近年の再評価の動きでCDが沢山リリースされたり、
昨年は来日コンサートまでやっているので、充分に知っていたりして。
そんな訳で、せっかく名前が出たので、たまにはあまりにもポピュラリティが有り
過ぎるアーティストもいいでしょ。って事で、ちょっとだけカーペンターズの事を
書きます。
前述の名曲「遙かなる影」を収録したアルバム「CLOSE TO YOU」が発表された
のは1970年。

全米No.1という輝かしいタイトルを獲得した「遙かなる影」は、
我が日本でも大ヒットをした訳で、この曲からカーペンターズの黄金時代が
築かれっる訳だが、どうも僕の記憶上では、それがアメリカのそれと同時期だった
のかどうかが定かではない。
何せ、ヒット曲の連発につぐ連発だったので、どの曲がどの時期にヒットってのが、
頭の中で団子状態で一つなのです。
ともあれこのアルバムは、ポール・ウィリアムスとロジャー・ニコルス作の美しい
「愛のプレリュード」で幕を開ける。
そしてバカラック作品は3曲収録。何時何処で聴いても変わらないエヴァーグ
リーンなポップスが見事に収められた1枚に仕上げられている。
話は筒美京平に戻るが、日本のロック黎明期に彼が手を組んだのが桑名正博。
その卓越した歌唱力でロック・シンガーとして嘱望されていた彼と77年に「哀愁
トゥナイト」を発表。のちに「セクシャルバイオレットNo.1」の大ヒットを生む訳だが、
彼の名作アルバム「TEQUILA MOON」でも4曲の作品を提供して見事なメロディ・
メイカー振りを聴かせている。

そんな筒美氏の歴史が刻まれた作品集がCD4枚組で2セット限定発売された。
レコード会社の枠を越えた一つの文化遺産とも言える作品なので、買える方は
是非・・・高いけど。
CARPENTERS / CLOSE TO YOU(1970年度作品)
桑名正博 / TEQUILA MOON(1978年度作品)
Vol.46(1998年02月号掲載)
職業作家って、いつのまにか演歌とかアイドルとか、その辺だけに存在
する時代になったように思う。
今、音楽演っている人達って、大体作品の自作自演の方が多い訳で、
そんな人達が、あっちこっちに一杯居て、ま、なんか適当に提供して成り
立っている。
で、たいして才能のない輩が、自分のアルバムも無理して自作自演の曲
だけで埋めちゃうから、なんかつまらないアルバムが出来てしまう。
曲が足りないなら、作家にいい曲なり詞を頼めばいいのに。
それで完成度を高めた方が、よっぽど後世に残る立派な作品になるのに。
昔、シンガー・ソングライターが出てきた時、そりゃーそりゃー、凄い才人が
現れたもんだ!と巷の一般的な音楽ファンは思ったよ。
それが今じゃ当たり前になってしまった。
食糧事情が良くなって、ミンナ、脳味噌も増え、感性にも磨きが掛かり、
バリバリ曲とか書けるようになったようだ。あぁ、道具の進歩もね。
カーペンターズの大リバイバルって、5年位前の事かと思っていたら、
十数年も前の事だったんだ。
移り往く時代は早い!記憶の回路に残っている情報は、相当不確かなモノ
に変形しているようで、当てにしてはいけない!と反省。
名盤の影にプロフェショナルな作曲家有り!職業作家(!?)を見直そう!
今こそ・・・。
皆さん、恒例の年末年始の行事は無事終わったでしょうか。一年の総括って
事で、この時期、適当に理由を付けて、もっともらしく一年を振り返るものですが、
さっぱりそんな気にさせてくれない今日この頃です。
なんて書いていられない程、このコラムの文字数が減らされたので、さっそく
本題に入らなければ・・・・・。
さて、年末この音楽業界を賑わせた話題の一つに“筒美京平”がある。
まぁ、知らない人には“日本の歌謡ポップス史に残る最重要作曲家”の一人と
して貰いましょうか。
きっと知らず知らずのうちに、この大先生の作品を一杯一杯聴いて育った!って
人が多いとは思うのですが。
でぇ、この筒美京平の話は置いといて、海外に目を向けてポップス界に影響を
与えた作曲家となると、真先にバート・バカラックの名前が出てくるのは、ある
程度年齢がいった方だけでしょうネ。
若い方には、ちょっと前に大リバイバル・ブームを巻き起こしたカーペンターズ
の最初のミリオン・ヒット曲でもあり、その人気を決定付けた「遙かなる影{原題:
(They Long To Be)CLOSE TO YOU}」の作者と言った方が分かり易いかも知れ
ないし、勉強熱心な方なら、近年の再評価の動きでCDが沢山リリースされたり、
昨年は来日コンサートまでやっているので、充分に知っていたりして。
そんな訳で、せっかく名前が出たので、たまにはあまりにもポピュラリティが有り
過ぎるアーティストもいいでしょ。って事で、ちょっとだけカーペンターズの事を
書きます。
前述の名曲「遙かなる影」を収録したアルバム「CLOSE TO YOU」が発表された
のは1970年。

全米No.1という輝かしいタイトルを獲得した「遙かなる影」は、
我が日本でも大ヒットをした訳で、この曲からカーペンターズの黄金時代が
築かれっる訳だが、どうも僕の記憶上では、それがアメリカのそれと同時期だった
のかどうかが定かではない。
何せ、ヒット曲の連発につぐ連発だったので、どの曲がどの時期にヒットってのが、
頭の中で団子状態で一つなのです。
ともあれこのアルバムは、ポール・ウィリアムスとロジャー・ニコルス作の美しい
「愛のプレリュード」で幕を開ける。
そしてバカラック作品は3曲収録。何時何処で聴いても変わらないエヴァーグ
リーンなポップスが見事に収められた1枚に仕上げられている。
話は筒美京平に戻るが、日本のロック黎明期に彼が手を組んだのが桑名正博。
その卓越した歌唱力でロック・シンガーとして嘱望されていた彼と77年に「哀愁
トゥナイト」を発表。のちに「セクシャルバイオレットNo.1」の大ヒットを生む訳だが、
彼の名作アルバム「TEQUILA MOON」でも4曲の作品を提供して見事なメロディ・
メイカー振りを聴かせている。

そんな筒美氏の歴史が刻まれた作品集がCD4枚組で2セット限定発売された。
レコード会社の枠を越えた一つの文化遺産とも言える作品なので、買える方は
是非・・・高いけど。
CARPENTERS / CLOSE TO YOU(1970年度作品)
桑名正博 / TEQUILA MOON(1978年度作品)
2008年11月12日
名盤/CREAM & BLANKEY JET CITY
続・名盤を探しに行こう/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.45(1998年01月号掲載)
カラー印刷化記念第二弾ってとこですね!これは。
本文中に書いてある通り、ホント、短絡。
クリームだって引き合いに出されて迷惑だちゅうのに。この程度で。
そうか、前回はカラー化の話を知らないままで原稿をかいていたの
か!って事で、Vol.44で書いた“グラムロック云々”って下り、まった
くの記憶違い。記憶違いがあっても当然の10年前だもんね。
クリームのアルバム、この時点で30年も前の作品。で、今では40年
も前って事か!ゲッ!
ま、何十年も聴き続けられるアルバムを、こうして一杯知っているのは、
幸せって事。
そういう時代をリアルタイムで生きてきた事を感謝しなくちゃ!と思う。
今の時代はどうなんだろう?
いわゆるJ-POPは、粗製濫造と、ちょっと前に捕まった人みたく、少ない
才能での大量生産。
一生聴き続けられる音楽をどれだけ作ったのかしらん?あの人は。
本当は、身近で一生ものの音楽が生まれているのに、なかなか出会う
機会がないのは残念な事です。
男三人寄ればナンパ(!?)じゃなくてバンド!バンドだよ!最小編成バンド、
3ピースバンドの底力を聴け!
突然のカラー版に刷新って事で、このページもきっと多少雰囲気が変わった
事でしょう。なんせ現物を見ないまま、この原稿を書き始めたので、カラー化
になった良さが、さっぱり分かりませんし、前回もカラー化の話が無い状態で
原稿を進めていたので、それに対処した名盤を選んでいなかった。
で、絵的に物足りなかったかなっ。なんて思いつつ、カラー版に合う名盤ねぇ。
と考えてみました。
とは言うものの、文字自体がカラフルになる訳じゃないし、結局はジャケット
だよな。そうなると一杯あるし・・・。と、唐突にクリームの「カラフル・クリーム」
のジャケットが目に浮んできた。

タイトルもピッタリだし、短絡とは思いつつ、年末進行で時間もない事なので、
今月はこれっきゃないですわ。
ところでCD化になってからでも、このアルバムはこのタイトルで発売されて
いるのかしらん。と心配になってCDショップに確かめに出掛けてみた。
なんと運良く廉価盤で\1,200という安さで国内盤が発売されていた。
なんでも特別限定価格だそうで、まぁ、何が特別でこうなったかは知らんが、
安く手に入れるチャンスには違いないので、こういったチャンスはモノにしよ
うぜ。
さて、この「カラフル・クリーム(原題:DISREAL GEAR)」が発表されたのは
1967年の事。もう30年も前の昔の話だ。
この年、ビートルズが「サージェント・ペッパーズ~」を、ストーンズが「サタニッ
ク・マジェスティーズ」をと、まだまだドラッグ文化が幅を効かせた時代だった。
クリーム自体、エリック・クラプトン、ジャック・ブルース、ジンジャー・ベイカー
の凄腕ミュージシャンによるトリオで、その評価はライヴの場にあったようだし、
残された音源もそっち方面に偏っている(活動期間が短かったという制約も
あるが)。
かくゆう我輩も、どっちかと言うと、そうしたライヴ盤の方を愛聴した。
この赤みがかったサイケ調のジャケットに包まれた作品は、彼らのスタジオ
録音の二作目。
代表曲の一つ「Sunshine Of Your Love」などを収録。ブルーズ色が濃かった
デビュー作と較べると、よりロック色を強めた一枚。生まれた背景が、ロックの
時代としては激動の時だっただけに、まさにその激動の瞬間を華々しく飾った
アルバムと言える。
国内に目を向けると、ロックらしいロック・バンドというと真先に“Blankey Jet
City”の名前が浮んでくる。

3ピースバンドの彼らが94年に発表した「幸せの鐘が鳴り響き僕はただ悲しい
ふりをする」は、そのロック臭さを嗅ぐ度に、日本のロックもまだ大丈夫!と
安心してしまう。ってとこで紙数も尽きたので・・・、まぁ、ロックのエネルギーを、
たった3人で表現した好盤の話でした。
THE CREAM / カラフル・クリーム(1967年度作品)
BLANKEY JET CITY / 幸せの鐘が鳴り響き僕はただ悲しいふりをする(1994年度作品)
Vol.45(1998年01月号掲載)
カラー印刷化記念第二弾ってとこですね!これは。
本文中に書いてある通り、ホント、短絡。
クリームだって引き合いに出されて迷惑だちゅうのに。この程度で。
そうか、前回はカラー化の話を知らないままで原稿をかいていたの
か!って事で、Vol.44で書いた“グラムロック云々”って下り、まった
くの記憶違い。記憶違いがあっても当然の10年前だもんね。
クリームのアルバム、この時点で30年も前の作品。で、今では40年
も前って事か!ゲッ!
ま、何十年も聴き続けられるアルバムを、こうして一杯知っているのは、
幸せって事。
そういう時代をリアルタイムで生きてきた事を感謝しなくちゃ!と思う。
今の時代はどうなんだろう?
いわゆるJ-POPは、粗製濫造と、ちょっと前に捕まった人みたく、少ない
才能での大量生産。
一生聴き続けられる音楽をどれだけ作ったのかしらん?あの人は。
本当は、身近で一生ものの音楽が生まれているのに、なかなか出会う
機会がないのは残念な事です。
男三人寄ればナンパ(!?)じゃなくてバンド!バンドだよ!最小編成バンド、
3ピースバンドの底力を聴け!
突然のカラー版に刷新って事で、このページもきっと多少雰囲気が変わった
事でしょう。なんせ現物を見ないまま、この原稿を書き始めたので、カラー化
になった良さが、さっぱり分かりませんし、前回もカラー化の話が無い状態で
原稿を進めていたので、それに対処した名盤を選んでいなかった。
で、絵的に物足りなかったかなっ。なんて思いつつ、カラー版に合う名盤ねぇ。
と考えてみました。
とは言うものの、文字自体がカラフルになる訳じゃないし、結局はジャケット
だよな。そうなると一杯あるし・・・。と、唐突にクリームの「カラフル・クリーム」
のジャケットが目に浮んできた。

タイトルもピッタリだし、短絡とは思いつつ、年末進行で時間もない事なので、
今月はこれっきゃないですわ。
ところでCD化になってからでも、このアルバムはこのタイトルで発売されて
いるのかしらん。と心配になってCDショップに確かめに出掛けてみた。
なんと運良く廉価盤で\1,200という安さで国内盤が発売されていた。
なんでも特別限定価格だそうで、まぁ、何が特別でこうなったかは知らんが、
安く手に入れるチャンスには違いないので、こういったチャンスはモノにしよ
うぜ。
さて、この「カラフル・クリーム(原題:DISREAL GEAR)」が発表されたのは
1967年の事。もう30年も前の昔の話だ。
この年、ビートルズが「サージェント・ペッパーズ~」を、ストーンズが「サタニッ
ク・マジェスティーズ」をと、まだまだドラッグ文化が幅を効かせた時代だった。
クリーム自体、エリック・クラプトン、ジャック・ブルース、ジンジャー・ベイカー
の凄腕ミュージシャンによるトリオで、その評価はライヴの場にあったようだし、
残された音源もそっち方面に偏っている(活動期間が短かったという制約も
あるが)。
かくゆう我輩も、どっちかと言うと、そうしたライヴ盤の方を愛聴した。
この赤みがかったサイケ調のジャケットに包まれた作品は、彼らのスタジオ
録音の二作目。
代表曲の一つ「Sunshine Of Your Love」などを収録。ブルーズ色が濃かった
デビュー作と較べると、よりロック色を強めた一枚。生まれた背景が、ロックの
時代としては激動の時だっただけに、まさにその激動の瞬間を華々しく飾った
アルバムと言える。
国内に目を向けると、ロックらしいロック・バンドというと真先に“Blankey Jet
City”の名前が浮んでくる。

3ピースバンドの彼らが94年に発表した「幸せの鐘が鳴り響き僕はただ悲しい
ふりをする」は、そのロック臭さを嗅ぐ度に、日本のロックもまだ大丈夫!と
安心してしまう。ってとこで紙数も尽きたので・・・、まぁ、ロックのエネルギーを、
たった3人で表現した好盤の話でした。
THE CREAM / カラフル・クリーム(1967年度作品)
BLANKEY JET CITY / 幸せの鐘が鳴り響き僕はただ悲しいふりをする(1994年度作品)
2008年11月04日
名盤/DAVID BOWIE & 一風堂
続・名盤を探しに行こう/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.44(1997年12月号掲載)
今まで2色刷りだった「WE!」が、この号からカラー刷りとなり、これは
なるべくカラフルな作品を!と思って選んだ2枚だったはず。
ま、ボウイとか土屋昌巳のイメージが、グラムやらを彷彿させたので、
なんとなくカラフルかなっと・・・。
紙面のカラー化って、昭和にテレビが白黒からカラーに変わったくらい
画期的でした。(当時は、確かそんな気分だった)
似合わない化粧が気持ち悪いのは女も同じで、昨今は昔と違って、
色々と自由度が高くて個性的な人も多いけど、BADなモノはBADなん
ですわ。(磨き方を間違えてないか!自分で判断出来んのか?)
でぇ、そんな事よりカラー化に伴って、早くもアルバムメモが無くなって
いる。
折角、思い出して書き足していたのに残念。
SHAZNAとか、そんなにヒットしていたのですね。現象としては記憶に
残っているが、曲として記憶に残っているのは皆無だ。
「すみれ~」は、やっぱ一風堂でしょ。
ま、SHAZNAに限らず、ここ何年も作られたヒット曲が多いから、記憶
に曲として残される作品が少ない。
これは作り手より送り手の問題だな。
グラムの記述、ルー・リードとかその部類に入っていたのかな。
化粧だけでそう見られていたなら可哀想。イギリスで加工ってのは、
そこでひん曲げられて日本には入ったって事か(!?)。
今となっては、どんな経緯でそのように書いた記憶にない。
ボウイもイマイチ、のめり込めない人だったな~。
ガキ共よ。どうせ化粧するなら、この人達みたく美しくなりなさい。
似合わない化粧ほど気持ち悪いモノはない。
ちょっと前の事だけど、日本国内のヒットチャートを眺めてみるとSHAZNAの
勢いが凄い。
デビュー曲「Melty Love」と「すみれSeptember Love」の二曲がベストテンに
入っていた。
これって新人としては結構スゲェ~事じゃないですかネ。ちゃんとしたデータ
を調べたって訳じゃないけど。それにしても第○次か知らないがバンド・ブーム
到来って雰囲気が漂っている。所謂ヴィジュアル系ってヤツでだ。
何処の誰が言い出したかは知らないが、化粧系のバンドの事をヴィジュアル
系と言うらしい。まったく・・・・・。
なんか、元々ロック・ミュージシャンってヤツは、結構化粧っ気の多いヤツが
居たから、今更それの事を指してヴィジュアル系って言うのもな・・・・・。
なんて考えたりしながら、この原稿を書き始めた。
そう言えば、昔これと似た状況があったな~と思い出したのが“グラム・ロック”
の時代。そうロックが輝かしい軌跡を描いた70年代初頭の話だ。
艶やかな化粧にド派手な衣装をまとったアーティストがステージに立つ姿を
“グラマラス”と形容した事から始まったというこのグラム・ロック。
短命ながらもセンセーショナルな出来事として、ロック史に刻み込まれている。
代表的なアーティストはディヴィッド・ボウイ、T・レックス、ロキシー・ミュージック
などのイギリス勢に加えて、アメリカ産のアリス・クーパー、ルー・リード、イギー
・ポップらが上げられるが、アメリカ物も、イギリスで手が加えられた物が多かった
ので、ムーヴメントとしての盛り上がりはイギリスと言っていいだろう。
アーティスト名を見ても分かると思うが、このグラム・ロックにはサウンド・スタイル
的な決まり事は、特に無かったようだ。
あくまでも見栄えで判断していたようで、そこが今のヴィジュアル系と言われる
ロック・シーンに似ている。
そんなグラム・ロック界で美しさで他を一歩も二歩も引き離していたのが、やっぱり
デイヴィッド・ボウイでしょ。
当時、グラム界自体に興味を抱かなかった我輩も、彼のその当時の作品は、何枚
かは所蔵している。
そんな訳で引っ張り出してきたのが「ジギー・スターダスト(原題:THE RISE AND
FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS)」というアルバム。
シングル・ヒットチューン「Starman」が収録された作品だ。
ボウイは、ここで描かれた“ジギー”という異性人がロック・スターとなる物語その
ものを現実の世界で演じきって、世界的な成功の足がかりにする。
以降、デイヴィッド・ボウイは、常にロックン・ロール・スター、いやいやロック・ヴォ
―カリストとしてトップ・ランクに位置し今日に至っているが、個人的には、いやはや
良く分からん存在なのです。
さて、後にボウイに負けず劣らずの化粧っぷりで美しくも妖艶な世界(!?)を演じた
日本人の一人に、冒頭の「すみれSeptember Love」のオリジネイター“一風堂”
の土屋昌巳氏がいる。
最近も「Mod’Fish」なる実に素晴らしいミニ・アルバム(近頃、かなりハマッています。
カッコエエ~)を発表したばかりだ。
その一風堂のスタート地点が“山本翔”というミック・ジャガー擬きのヴォーカリスト
のバック・バンドという事は意外と知られていない。
このバンド、当時、かなりニューウェイヴやテクノの影響下に居た事は確かで、
ステージを観た微かな記憶やレコードから、それらが如実に伝わってくる。
そんな彼らの音は、現在ベスト盤「LUNATIC MENU」でしか聴く事が出来ない。
(唯一のヒット曲「すみれ~」を収録しているのは言うまでもない)が、土屋昌巳の
才能の断片は充分に感じ取れる内容の1枚だ。
そんな訳で、今日の子供達も、ボウイや土屋氏の音楽を聴きつつ、己の美について
考えてみるのもいいんじゃないか、と思う今日この頃でした。
DAVID BOWIE / THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST
AND THE SPIDERS FROM MARS(1972年度作品)

一風堂 / LUNATIC MENU(1982年度作品)

Vol.44(1997年12月号掲載)
今まで2色刷りだった「WE!」が、この号からカラー刷りとなり、これは
なるべくカラフルな作品を!と思って選んだ2枚だったはず。
ま、ボウイとか土屋昌巳のイメージが、グラムやらを彷彿させたので、
なんとなくカラフルかなっと・・・。
紙面のカラー化って、昭和にテレビが白黒からカラーに変わったくらい
画期的でした。(当時は、確かそんな気分だった)
似合わない化粧が気持ち悪いのは女も同じで、昨今は昔と違って、
色々と自由度が高くて個性的な人も多いけど、BADなモノはBADなん
ですわ。(磨き方を間違えてないか!自分で判断出来んのか?)
でぇ、そんな事よりカラー化に伴って、早くもアルバムメモが無くなって
いる。
折角、思い出して書き足していたのに残念。
SHAZNAとか、そんなにヒットしていたのですね。現象としては記憶に
残っているが、曲として記憶に残っているのは皆無だ。
「すみれ~」は、やっぱ一風堂でしょ。
ま、SHAZNAに限らず、ここ何年も作られたヒット曲が多いから、記憶
に曲として残される作品が少ない。
これは作り手より送り手の問題だな。
グラムの記述、ルー・リードとかその部類に入っていたのかな。
化粧だけでそう見られていたなら可哀想。イギリスで加工ってのは、
そこでひん曲げられて日本には入ったって事か(!?)。
今となっては、どんな経緯でそのように書いた記憶にない。
ボウイもイマイチ、のめり込めない人だったな~。
ガキ共よ。どうせ化粧するなら、この人達みたく美しくなりなさい。
似合わない化粧ほど気持ち悪いモノはない。
ちょっと前の事だけど、日本国内のヒットチャートを眺めてみるとSHAZNAの
勢いが凄い。
デビュー曲「Melty Love」と「すみれSeptember Love」の二曲がベストテンに
入っていた。
これって新人としては結構スゲェ~事じゃないですかネ。ちゃんとしたデータ
を調べたって訳じゃないけど。それにしても第○次か知らないがバンド・ブーム
到来って雰囲気が漂っている。所謂ヴィジュアル系ってヤツでだ。
何処の誰が言い出したかは知らないが、化粧系のバンドの事をヴィジュアル
系と言うらしい。まったく・・・・・。
なんか、元々ロック・ミュージシャンってヤツは、結構化粧っ気の多いヤツが
居たから、今更それの事を指してヴィジュアル系って言うのもな・・・・・。
なんて考えたりしながら、この原稿を書き始めた。
そう言えば、昔これと似た状況があったな~と思い出したのが“グラム・ロック”
の時代。そうロックが輝かしい軌跡を描いた70年代初頭の話だ。
艶やかな化粧にド派手な衣装をまとったアーティストがステージに立つ姿を
“グラマラス”と形容した事から始まったというこのグラム・ロック。
短命ながらもセンセーショナルな出来事として、ロック史に刻み込まれている。
代表的なアーティストはディヴィッド・ボウイ、T・レックス、ロキシー・ミュージック
などのイギリス勢に加えて、アメリカ産のアリス・クーパー、ルー・リード、イギー
・ポップらが上げられるが、アメリカ物も、イギリスで手が加えられた物が多かった
ので、ムーヴメントとしての盛り上がりはイギリスと言っていいだろう。
アーティスト名を見ても分かると思うが、このグラム・ロックにはサウンド・スタイル
的な決まり事は、特に無かったようだ。
あくまでも見栄えで判断していたようで、そこが今のヴィジュアル系と言われる
ロック・シーンに似ている。
そんなグラム・ロック界で美しさで他を一歩も二歩も引き離していたのが、やっぱり
デイヴィッド・ボウイでしょ。
当時、グラム界自体に興味を抱かなかった我輩も、彼のその当時の作品は、何枚
かは所蔵している。
そんな訳で引っ張り出してきたのが「ジギー・スターダスト(原題:THE RISE AND
FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS)」というアルバム。
シングル・ヒットチューン「Starman」が収録された作品だ。
ボウイは、ここで描かれた“ジギー”という異性人がロック・スターとなる物語その
ものを現実の世界で演じきって、世界的な成功の足がかりにする。
以降、デイヴィッド・ボウイは、常にロックン・ロール・スター、いやいやロック・ヴォ
―カリストとしてトップ・ランクに位置し今日に至っているが、個人的には、いやはや
良く分からん存在なのです。
さて、後にボウイに負けず劣らずの化粧っぷりで美しくも妖艶な世界(!?)を演じた
日本人の一人に、冒頭の「すみれSeptember Love」のオリジネイター“一風堂”
の土屋昌巳氏がいる。
最近も「Mod’Fish」なる実に素晴らしいミニ・アルバム(近頃、かなりハマッています。
カッコエエ~)を発表したばかりだ。
その一風堂のスタート地点が“山本翔”というミック・ジャガー擬きのヴォーカリスト
のバック・バンドという事は意外と知られていない。
このバンド、当時、かなりニューウェイヴやテクノの影響下に居た事は確かで、
ステージを観た微かな記憶やレコードから、それらが如実に伝わってくる。
そんな彼らの音は、現在ベスト盤「LUNATIC MENU」でしか聴く事が出来ない。
(唯一のヒット曲「すみれ~」を収録しているのは言うまでもない)が、土屋昌巳の
才能の断片は充分に感じ取れる内容の1枚だ。
そんな訳で、今日の子供達も、ボウイや土屋氏の音楽を聴きつつ、己の美について
考えてみるのもいいんじゃないか、と思う今日この頃でした。
DAVID BOWIE / THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST
AND THE SPIDERS FROM MARS(1972年度作品)

一風堂 / LUNATIC MENU(1982年度作品)

2008年11月01日
名盤/Queen & 村田和人
続・名盤を探しに行こう/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.43(1997年11月号掲載)
冒頭からイカちゃってら~。
ストーンズには熱心だからしょうがね~と思って下さい。
「ブリッジス・トゥ・バビロン」は、最後に「Angie」のライヴ・ヴァージョン
がボーナスで入っている。
ま、ヒット曲を入れときゃ、飛びつくだろう!とリスナーを舐めた考え。
ふざけんなって!
「VOODOO~」の時は、何の意味のない小説もどきが。
古い価値観の押し付けのようなものを載せて、金を取りやがって。
完全にここの会社はユーザーを見下してるんじゃないか!
村田のアルバムメモにある会社だが、だから無くなちゃうんだよ!
ってところで、話を変えます。
毎年、今年は一杯自転車に乗るぞ!と春先に思うのだが、どうも
そうもいかなくて、結局は今年一回だけだった。
春に倉庫から出した時は、ちゃんと錆も落として、乗る気満々だった
んだけど・・・・・。ま、毎年、こんな感じですわ。自転車に関しては。
でぇ、Queenと言えば、Paul Rogersとの組み合わせ??????
俺、ご覧の通り一杯“?”を連発したもね。
この組み合わせでクイーンだ!ってぇのに。
ロジャー、もといFREEのファンの方々とQUEENのファンの方々、この
両ファンにとって、この組み合わせって・・・・・噛み合うものなのかなッ。
そうそう、そのQUEEN+PAUL ROGERSの「the cosmos rocks」なる
新譜。
最初にリリースした直後に、来日公演のライヴCDが付いた“限定スペシャル
エディション”なるものが出た。
おいおい、そんな僅かな期間で出すなら一緒に出せよ!
買う側に選択肢を持たせてくれなきゃ、出費が嵩むだけ。
ネ、ファンにしちゃうと、ライヴ盤も聴きたいが為に、またこれを買わなきゃ
ならない。
こんな事を続けていると、そのうち、急いで買うと“何か損!”をする。
みたいなのが定着して、益々新譜の動きが悪くなるんじゃないかと危惧して
いる。アッ、それは俺だけか!ま、いいっか!
ところで文章の括弧内は「。」とかいるんだっけ?
今頃になって変だな~と。
相変わらず誤字脱字多いすっね!
鼻歌まじりでサイクリング!冬を越したら行こうぜ!海の見える丘まで!
な~んてネ。自転車大好き人間はこんな歌口づさんで下さい。
それにしてもストーンズの新譜の国内盤のボーナス・トラックは酷いな~。
売ろう!という姿勢はわかるけど、あんまりではないでしょうか。
何か、ちゃんと完成している物によけいな物を付けちゃって・・・・・。
確かライナーの中にとんでもない小説なんかを載せた事があったけど、
それが買う人へのサービスとでも思っているのかしらん。
安価な輸入盤と張り合うのは分かるけど、それなら近頃よくある期間限定
の低価格ででも出してくれればいいのに・・・・・。まぁ、13曲目で止めれば
済む事なんだけれどネ。
そんな話は別にして、アルバム「BRIDGES TO BAYLON」の出来はいいの
で是非聴いてやって下さい。(前作「VOODOO LOUNGE」を最高傑作と持ち
上げたレコード会社の犬みたいなライター達が、今作をどう表現するか楽し
みな今日この頃なのです。)
全然話は変わりますが、先日生まれて初めて自転車のタイヤの空気入れに
お金がかかってしまう。という体験をしました。
生まれてこのかた、あれは自転車屋で無料で入れられるものだと思っていた
ので、軽~いカルチャー・ショックですわ。でも、もしかして、それが世間の
常識だったりして。(1回30円也。詳しく書くスペースはないけど、俺は1回
失敗して60円もかかってしまった。)
この号が出ている頃は、もう、自転車日和りと思える心地好い天気なんて
望めないかも知れないけど、雪に閉ざされる前に、もうひと乗りして、その感触
を体の中に残しておいて下さい。
さて、自転車で思い出すのが何故か“QUEEN”の事。
彼らの曲で「BYCYCLE RACE」ってのがあって、その宣伝ポスター(もしかしたら
来日公演の告知ポスターだったかも知れないが・・・。)が、見事なお尻をした
ヌードの美女が自転車にまたがっているのを、バックから写したもの。
今考えると、仲々優れたデザインの物なんだけど、それをいきつけのお店の
方から“欲しい!欲しい!”結構せがまれた事があって、すぐにその事を思い
出してしまう。
決してその方はクィーン・ファンだった訳ではなく、単に自転車マニアで、
純粋にマニア心が働いての“欲しがり”だったのですが・・・・・。
その「BYCYCLE RACE」を収録したアルバム「JAZZ」が発表されたのが1978年
の事。(リリース当時、ジミ・ヘンの「エレクトリック・レディ・ランド」のヌードに
負けず劣らずの、オールヌード嬢達が自転車にまたがった見事なポスター
が付いていた。)
何やら、クィーンとジャズって全然結び付かないように思えるし、実際、アルバム
の中でジャズを演っている訳じゃない。
ここでのクィーンは、それまでの大袈裟な作品作りやヨーロッパ的美意識などの
付きまとうイメージを振り払うかのように、シンプルなポップさを前面に押し出して
いる。が、そこはクィーン。メロディーやコーラス・ワークの美しさや、ここぞという
時に決まるブライアン・メイのギター・ワークなど、決して本質的な部分での妥協
なく仕上げているのは流石。
70年代の彼らの活動を締め括るに相応しい作品だ。
とは言うものの、この作品をお供にサイクリングってのは、ちょっと辛いかな~。
仲々、お気軽に鼻歌って曲じゃないもネ。
そんな時に引っ張り出してきたのが村田和人のアルバム。
もともとアメリカン指向のポップスを目指していた人だけあって、そのライトな感覚
は心地好さを誘う。
その名もズバリ「サイクリングに行こう」から始まるアルバム「空を泳ぐ日」は、
そんな彼の魅力が詰まった一枚だ。
山下達郎が前面バックアップって事で、鳴り物入りで登場した彼。
このアルバム発表当時、アルバム制作がLPからCDに変わった事について、
「CDは頭3曲が勝負ですよ!」なんて言っていたっけ。
まぁ、頭三曲云々はおいておいて、「サイクリングに行こう」を聴いていると、
本当に自転車に乗っている心地好さが蘇ってくるのです。
あと数ヶ月、自転車愛好家にとっては辛く冬が続くけれど、サイクリング気分を
味わせてくれる曲でも聴いて、気分を晴らしては如何でしょうか。
QUEEN / JAZZ(1978年度作品)

本文中で触れた「BYCYCLE RACE」よりも「DON’T STOP ME NOW」の
方が聴き覚えのある方が多いかも。
1曲だけジャズっぽい雰囲気を持った作品も入っているけどタイトルに
惑わせられないように。今聴き直してみると、意外と新鮮だったりして。
村田和人 / 空を泳ぐ日(1990年度作品)

残念ながら本盤は廃盤になってしまったらしい。が本文中の「サイクリング
に行こう」は、東芝時代をまとめたベスト盤「風と光のサイクリング」で聴く
事が出来る。近頃ごぶさたぎみだけど、良質なポップソングを携えて、
ひょっこりと現われるのを楽しみにしています。
Vol.43(1997年11月号掲載)
冒頭からイカちゃってら~。
ストーンズには熱心だからしょうがね~と思って下さい。
「ブリッジス・トゥ・バビロン」は、最後に「Angie」のライヴ・ヴァージョン
がボーナスで入っている。
ま、ヒット曲を入れときゃ、飛びつくだろう!とリスナーを舐めた考え。
ふざけんなって!
「VOODOO~」の時は、何の意味のない小説もどきが。
古い価値観の押し付けのようなものを載せて、金を取りやがって。
完全にここの会社はユーザーを見下してるんじゃないか!
村田のアルバムメモにある会社だが、だから無くなちゃうんだよ!
ってところで、話を変えます。
毎年、今年は一杯自転車に乗るぞ!と春先に思うのだが、どうも
そうもいかなくて、結局は今年一回だけだった。
春に倉庫から出した時は、ちゃんと錆も落として、乗る気満々だった
んだけど・・・・・。ま、毎年、こんな感じですわ。自転車に関しては。
でぇ、Queenと言えば、Paul Rogersとの組み合わせ??????
俺、ご覧の通り一杯“?”を連発したもね。
この組み合わせでクイーンだ!ってぇのに。
ロジャー、もといFREEのファンの方々とQUEENのファンの方々、この
両ファンにとって、この組み合わせって・・・・・噛み合うものなのかなッ。
そうそう、そのQUEEN+PAUL ROGERSの「the cosmos rocks」なる
新譜。
最初にリリースした直後に、来日公演のライヴCDが付いた“限定スペシャル
エディション”なるものが出た。
おいおい、そんな僅かな期間で出すなら一緒に出せよ!
買う側に選択肢を持たせてくれなきゃ、出費が嵩むだけ。
ネ、ファンにしちゃうと、ライヴ盤も聴きたいが為に、またこれを買わなきゃ
ならない。
こんな事を続けていると、そのうち、急いで買うと“何か損!”をする。
みたいなのが定着して、益々新譜の動きが悪くなるんじゃないかと危惧して
いる。アッ、それは俺だけか!ま、いいっか!
ところで文章の括弧内は「。」とかいるんだっけ?
今頃になって変だな~と。
相変わらず誤字脱字多いすっね!
鼻歌まじりでサイクリング!冬を越したら行こうぜ!海の見える丘まで!
な~んてネ。自転車大好き人間はこんな歌口づさんで下さい。
それにしてもストーンズの新譜の国内盤のボーナス・トラックは酷いな~。
売ろう!という姿勢はわかるけど、あんまりではないでしょうか。
何か、ちゃんと完成している物によけいな物を付けちゃって・・・・・。
確かライナーの中にとんでもない小説なんかを載せた事があったけど、
それが買う人へのサービスとでも思っているのかしらん。
安価な輸入盤と張り合うのは分かるけど、それなら近頃よくある期間限定
の低価格ででも出してくれればいいのに・・・・・。まぁ、13曲目で止めれば
済む事なんだけれどネ。
そんな話は別にして、アルバム「BRIDGES TO BAYLON」の出来はいいの
で是非聴いてやって下さい。(前作「VOODOO LOUNGE」を最高傑作と持ち
上げたレコード会社の犬みたいなライター達が、今作をどう表現するか楽し
みな今日この頃なのです。)
全然話は変わりますが、先日生まれて初めて自転車のタイヤの空気入れに
お金がかかってしまう。という体験をしました。
生まれてこのかた、あれは自転車屋で無料で入れられるものだと思っていた
ので、軽~いカルチャー・ショックですわ。でも、もしかして、それが世間の
常識だったりして。(1回30円也。詳しく書くスペースはないけど、俺は1回
失敗して60円もかかってしまった。)
この号が出ている頃は、もう、自転車日和りと思える心地好い天気なんて
望めないかも知れないけど、雪に閉ざされる前に、もうひと乗りして、その感触
を体の中に残しておいて下さい。
さて、自転車で思い出すのが何故か“QUEEN”の事。
彼らの曲で「BYCYCLE RACE」ってのがあって、その宣伝ポスター(もしかしたら
来日公演の告知ポスターだったかも知れないが・・・。)が、見事なお尻をした
ヌードの美女が自転車にまたがっているのを、バックから写したもの。
今考えると、仲々優れたデザインの物なんだけど、それをいきつけのお店の
方から“欲しい!欲しい!”結構せがまれた事があって、すぐにその事を思い
出してしまう。
決してその方はクィーン・ファンだった訳ではなく、単に自転車マニアで、
純粋にマニア心が働いての“欲しがり”だったのですが・・・・・。
その「BYCYCLE RACE」を収録したアルバム「JAZZ」が発表されたのが1978年
の事。(リリース当時、ジミ・ヘンの「エレクトリック・レディ・ランド」のヌードに
負けず劣らずの、オールヌード嬢達が自転車にまたがった見事なポスター
が付いていた。)
何やら、クィーンとジャズって全然結び付かないように思えるし、実際、アルバム
の中でジャズを演っている訳じゃない。
ここでのクィーンは、それまでの大袈裟な作品作りやヨーロッパ的美意識などの
付きまとうイメージを振り払うかのように、シンプルなポップさを前面に押し出して
いる。が、そこはクィーン。メロディーやコーラス・ワークの美しさや、ここぞという
時に決まるブライアン・メイのギター・ワークなど、決して本質的な部分での妥協
なく仕上げているのは流石。
70年代の彼らの活動を締め括るに相応しい作品だ。
とは言うものの、この作品をお供にサイクリングってのは、ちょっと辛いかな~。
仲々、お気軽に鼻歌って曲じゃないもネ。
そんな時に引っ張り出してきたのが村田和人のアルバム。
もともとアメリカン指向のポップスを目指していた人だけあって、そのライトな感覚
は心地好さを誘う。
その名もズバリ「サイクリングに行こう」から始まるアルバム「空を泳ぐ日」は、
そんな彼の魅力が詰まった一枚だ。
山下達郎が前面バックアップって事で、鳴り物入りで登場した彼。
このアルバム発表当時、アルバム制作がLPからCDに変わった事について、
「CDは頭3曲が勝負ですよ!」なんて言っていたっけ。
まぁ、頭三曲云々はおいておいて、「サイクリングに行こう」を聴いていると、
本当に自転車に乗っている心地好さが蘇ってくるのです。
あと数ヶ月、自転車愛好家にとっては辛く冬が続くけれど、サイクリング気分を
味わせてくれる曲でも聴いて、気分を晴らしては如何でしょうか。
QUEEN / JAZZ(1978年度作品)

本文中で触れた「BYCYCLE RACE」よりも「DON’T STOP ME NOW」の
方が聴き覚えのある方が多いかも。
1曲だけジャズっぽい雰囲気を持った作品も入っているけどタイトルに
惑わせられないように。今聴き直してみると、意外と新鮮だったりして。
村田和人 / 空を泳ぐ日(1990年度作品)

残念ながら本盤は廃盤になってしまったらしい。が本文中の「サイクリング
に行こう」は、東芝時代をまとめたベスト盤「風と光のサイクリング」で聴く
事が出来る。近頃ごぶさたぎみだけど、良質なポップソングを携えて、
ひょっこりと現われるのを楽しみにしています。
2008年10月29日
名盤/Little Feat & 矢野顕子
続・名盤を探しに行こう/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.42(1997年10月号掲載)
4年ぶりに新作アルバム「Akiko」をリリースした矢野さん。
L.A録音というそのアルバムには、何かリトル・フィートと演った頃の匂い
を感じさせる曲も入っていたりして、なかなかいい感じです。
セカンドラインの話を誰としたのかは、今となっては記憶にない。
ミーターズから始まってネヴィルなどなど、セカンドラインものは未だに
聴く事が多いし気にもなる。
皮膚感覚と言うか体で覚える!ってぇのは、まさにそうで、それが自分の
体に染み込むまで、とことん聴いて、それを自分のDNAの一部にして
しまう。ってぇのが良いかなとは思うが、近頃、そこまで熱を持って聴きたく
なる作品やアーティストに出会っていない!
フィートは、ロウエル・ジョージが他界してから、全く興味を失った。
別に彼に思い入れがある訳じゃないんだけど、何となく・・・・・。
アッコちゃんのデビューに一役買った
ファンキーなファンキーなアメリカン・バンド!
大スランプだぜ!もう、まったく出てきませんわ、何を書くか。変に暑い
9月頭の残暑のせいと、この夏場の疲れが今頃出てきたのかしらん。
(と、ここまで書いて一旦書くのを止め、ネタが天から降って来るのを
待ちます。)
一行空いているのは苦悩の後と文字数稼ぎと思って下さい。困った時の
神頼み!でも、近くにはどうも神様は存在しないようだ。
と、そんな事をうだうだと書いてもしょうがないので、人に聞いた話を餌に
して本題に入ります。
以前載り上げた“セカンドライン・ファンク”の事を覚えている人は何人居る
でしょうか。と書いても、本人も一体どんな内容だったかは忘れているのだが、
そこで載り上げたアーティストは、しっかりと手帳に記録してある。
ネヴィル・ブラザーズに久保田麻琴だもネ。実に渋くていいね。
なんて事は置いておいて、このニューオーリンズが生んだ魔法のリズムの
発祥の源は何と葬儀だった。って話を某アーティストから聞いた。
何せ前回書いたように、音楽は皮膚感覚、そして体で覚えるのが信条の身。
これがあれだとか、それだとかの脳味噌に応える教養的なものは殆どない。
だから嘘か真かは知らないが、この話を聞いた時は「なるほどな~」と感心
したものだ。それは簡単に言うとこうだ。
彼の地では葬儀の際、棺を先頭に参列者が街を行進するらしく、その時に
楽団が「聖者の行進」をバカスカ鳴らしながら先を行き、続いて一般参列者が
何らかの楽器を持ってそれに続くらしい。その時、先を行く楽団と後に続く
一般参列者の間の演奏に微妙なズレが生じる。まぁ、遅れる訳だが、これが
あの前につんのめりそうになる独特のシンコペーションの源で、第二列目
だから“セカンドライン”って訳になったとか・・・・・。
すいません。確かそんな話だったと思う。(何せ人の話をちゃんと聞かない
B型ですので・・・・・。多分音楽の専門書にはちゃんとでていると思います
ので、詳しくはそちらをどうぞ。)
さて、その魔法のリズムを上手く自分達のサウンドに取り込んで、見事な
名作を世に送り出したバンドが居る。
“リトル・フィート”。1971年にデビュー以来、それこそミュージシャンズ・ミュ
ージシャンだったこのバンドが、73年に発表したアルバム「DIXIE CHICKEN」は、
そのニューオーリンズの魔法のリズムに触発されたファンキーなアルバム
に仕上がっている。
確かこのアルバムが発表された時点では、日本国内では彼らのアルバムは
リリースされていなくて、海外での評判を聴きつけた目敏い音楽ファンや音楽
関係者が、こぞって輸入盤屋で入手していたと思う。
結局彼らのアルバムは、この後の4作目から国内盤が発売される事になり、
追ってこの「デキシー・チキン」などの過去の作品が発売されるという珍現象が
起こり、一時、音楽ファンの頭を混乱させたものだ。
このリトル・フィート、解散と再結成をなんとなく繰り返していて、もしかしたら今
もバンドは存続しているのかもしれないが、絶頂期はこの「デキシー・チキン」
から77年の「タイム・ラヴズ・ア・ヒーロー」の頃まで。
何故なら、バンドの牽引者ロウエル・ジョージが存在していたからに他ならない。
彼の没後のフィートなんて・・・・・。そんな感じなので是非聴くなら73年から70
年末までの作品を。
さて、リトル・フィートと聞いて真先に思い浮かぶのが矢野顕子である。彼女の
ファンなら納得でしょう。
そう矢野顕子のデビュー・アルバム「JAPANESE GIRL」は、このリトル・フィート
とのセッションで生まれたアルバムなのです。
きっと日本のロックの名盤○○○なんてのには必ず選ばれている作品なので、
どこかで目や耳にしている読者も多いハズ。僅か5曲だけど歴史的な5曲。
と言ったら大袈裟か。
あの時代でこのノリ。才能が才能とぶつかり合った瞬間が見事にパッケージ
された名演奏である。
あぁ~、こうゆう歴史的現場に出くわしてみたい。と思う今日この頃なのです。
Little Feat / Dixie Chicken(1973年度作品)

タイトル・チューンのノリは今も大好きです。
ニューオーリンズの黒っぽさを、独自の解釈で自分達のものにしはじめた
記念すべき名盤。
やっぱりリトル・フィートと言ったらこのアルバムに尽きるでしょ。
矢野顕子 / Japanese Girl(1976年度作品)

アルバム・クレジットのLITTLE FEAT“THE GREAT”が、何よりも彼女の
感謝と敬意の表れ。フィートとのアメリカン・サイドに細野晴臣やムーン
ライダースらによる日本でのセッション。どちらも素晴らしい!
Vol.42(1997年10月号掲載)
4年ぶりに新作アルバム「Akiko」をリリースした矢野さん。
L.A録音というそのアルバムには、何かリトル・フィートと演った頃の匂い
を感じさせる曲も入っていたりして、なかなかいい感じです。
セカンドラインの話を誰としたのかは、今となっては記憶にない。
ミーターズから始まってネヴィルなどなど、セカンドラインものは未だに
聴く事が多いし気にもなる。
皮膚感覚と言うか体で覚える!ってぇのは、まさにそうで、それが自分の
体に染み込むまで、とことん聴いて、それを自分のDNAの一部にして
しまう。ってぇのが良いかなとは思うが、近頃、そこまで熱を持って聴きたく
なる作品やアーティストに出会っていない!
フィートは、ロウエル・ジョージが他界してから、全く興味を失った。
別に彼に思い入れがある訳じゃないんだけど、何となく・・・・・。
アッコちゃんのデビューに一役買った
ファンキーなファンキーなアメリカン・バンド!
大スランプだぜ!もう、まったく出てきませんわ、何を書くか。変に暑い
9月頭の残暑のせいと、この夏場の疲れが今頃出てきたのかしらん。
(と、ここまで書いて一旦書くのを止め、ネタが天から降って来るのを
待ちます。)
一行空いているのは苦悩の後と文字数稼ぎと思って下さい。困った時の
神頼み!でも、近くにはどうも神様は存在しないようだ。
と、そんな事をうだうだと書いてもしょうがないので、人に聞いた話を餌に
して本題に入ります。
以前載り上げた“セカンドライン・ファンク”の事を覚えている人は何人居る
でしょうか。と書いても、本人も一体どんな内容だったかは忘れているのだが、
そこで載り上げたアーティストは、しっかりと手帳に記録してある。
ネヴィル・ブラザーズに久保田麻琴だもネ。実に渋くていいね。
なんて事は置いておいて、このニューオーリンズが生んだ魔法のリズムの
発祥の源は何と葬儀だった。って話を某アーティストから聞いた。
何せ前回書いたように、音楽は皮膚感覚、そして体で覚えるのが信条の身。
これがあれだとか、それだとかの脳味噌に応える教養的なものは殆どない。
だから嘘か真かは知らないが、この話を聞いた時は「なるほどな~」と感心
したものだ。それは簡単に言うとこうだ。
彼の地では葬儀の際、棺を先頭に参列者が街を行進するらしく、その時に
楽団が「聖者の行進」をバカスカ鳴らしながら先を行き、続いて一般参列者が
何らかの楽器を持ってそれに続くらしい。その時、先を行く楽団と後に続く
一般参列者の間の演奏に微妙なズレが生じる。まぁ、遅れる訳だが、これが
あの前につんのめりそうになる独特のシンコペーションの源で、第二列目
だから“セカンドライン”って訳になったとか・・・・・。
すいません。確かそんな話だったと思う。(何せ人の話をちゃんと聞かない
B型ですので・・・・・。多分音楽の専門書にはちゃんとでていると思います
ので、詳しくはそちらをどうぞ。)
さて、その魔法のリズムを上手く自分達のサウンドに取り込んで、見事な
名作を世に送り出したバンドが居る。
“リトル・フィート”。1971年にデビュー以来、それこそミュージシャンズ・ミュ
ージシャンだったこのバンドが、73年に発表したアルバム「DIXIE CHICKEN」は、
そのニューオーリンズの魔法のリズムに触発されたファンキーなアルバム
に仕上がっている。
確かこのアルバムが発表された時点では、日本国内では彼らのアルバムは
リリースされていなくて、海外での評判を聴きつけた目敏い音楽ファンや音楽
関係者が、こぞって輸入盤屋で入手していたと思う。
結局彼らのアルバムは、この後の4作目から国内盤が発売される事になり、
追ってこの「デキシー・チキン」などの過去の作品が発売されるという珍現象が
起こり、一時、音楽ファンの頭を混乱させたものだ。
このリトル・フィート、解散と再結成をなんとなく繰り返していて、もしかしたら今
もバンドは存続しているのかもしれないが、絶頂期はこの「デキシー・チキン」
から77年の「タイム・ラヴズ・ア・ヒーロー」の頃まで。
何故なら、バンドの牽引者ロウエル・ジョージが存在していたからに他ならない。
彼の没後のフィートなんて・・・・・。そんな感じなので是非聴くなら73年から70
年末までの作品を。
さて、リトル・フィートと聞いて真先に思い浮かぶのが矢野顕子である。彼女の
ファンなら納得でしょう。
そう矢野顕子のデビュー・アルバム「JAPANESE GIRL」は、このリトル・フィート
とのセッションで生まれたアルバムなのです。
きっと日本のロックの名盤○○○なんてのには必ず選ばれている作品なので、
どこかで目や耳にしている読者も多いハズ。僅か5曲だけど歴史的な5曲。
と言ったら大袈裟か。
あの時代でこのノリ。才能が才能とぶつかり合った瞬間が見事にパッケージ
された名演奏である。
あぁ~、こうゆう歴史的現場に出くわしてみたい。と思う今日この頃なのです。
Little Feat / Dixie Chicken(1973年度作品)

タイトル・チューンのノリは今も大好きです。
ニューオーリンズの黒っぽさを、独自の解釈で自分達のものにしはじめた
記念すべき名盤。
やっぱりリトル・フィートと言ったらこのアルバムに尽きるでしょ。
矢野顕子 / Japanese Girl(1976年度作品)

アルバム・クレジットのLITTLE FEAT“THE GREAT”が、何よりも彼女の
感謝と敬意の表れ。フィートとのアメリカン・サイドに細野晴臣やムーン
ライダースらによる日本でのセッション。どちらも素晴らしい!