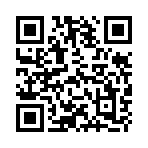keith yoshidaの新・飯がわりに1枚!(Again) › 2008年10月
2008年10月29日
名盤/Little Feat & 矢野顕子
続・名盤を探しに行こう/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.42(1997年10月号掲載)
4年ぶりに新作アルバム「Akiko」をリリースした矢野さん。
L.A録音というそのアルバムには、何かリトル・フィートと演った頃の匂い
を感じさせる曲も入っていたりして、なかなかいい感じです。
セカンドラインの話を誰としたのかは、今となっては記憶にない。
ミーターズから始まってネヴィルなどなど、セカンドラインものは未だに
聴く事が多いし気にもなる。
皮膚感覚と言うか体で覚える!ってぇのは、まさにそうで、それが自分の
体に染み込むまで、とことん聴いて、それを自分のDNAの一部にして
しまう。ってぇのが良いかなとは思うが、近頃、そこまで熱を持って聴きたく
なる作品やアーティストに出会っていない!
フィートは、ロウエル・ジョージが他界してから、全く興味を失った。
別に彼に思い入れがある訳じゃないんだけど、何となく・・・・・。
アッコちゃんのデビューに一役買った
ファンキーなファンキーなアメリカン・バンド!
大スランプだぜ!もう、まったく出てきませんわ、何を書くか。変に暑い
9月頭の残暑のせいと、この夏場の疲れが今頃出てきたのかしらん。
(と、ここまで書いて一旦書くのを止め、ネタが天から降って来るのを
待ちます。)
一行空いているのは苦悩の後と文字数稼ぎと思って下さい。困った時の
神頼み!でも、近くにはどうも神様は存在しないようだ。
と、そんな事をうだうだと書いてもしょうがないので、人に聞いた話を餌に
して本題に入ります。
以前載り上げた“セカンドライン・ファンク”の事を覚えている人は何人居る
でしょうか。と書いても、本人も一体どんな内容だったかは忘れているのだが、
そこで載り上げたアーティストは、しっかりと手帳に記録してある。
ネヴィル・ブラザーズに久保田麻琴だもネ。実に渋くていいね。
なんて事は置いておいて、このニューオーリンズが生んだ魔法のリズムの
発祥の源は何と葬儀だった。って話を某アーティストから聞いた。
何せ前回書いたように、音楽は皮膚感覚、そして体で覚えるのが信条の身。
これがあれだとか、それだとかの脳味噌に応える教養的なものは殆どない。
だから嘘か真かは知らないが、この話を聞いた時は「なるほどな~」と感心
したものだ。それは簡単に言うとこうだ。
彼の地では葬儀の際、棺を先頭に参列者が街を行進するらしく、その時に
楽団が「聖者の行進」をバカスカ鳴らしながら先を行き、続いて一般参列者が
何らかの楽器を持ってそれに続くらしい。その時、先を行く楽団と後に続く
一般参列者の間の演奏に微妙なズレが生じる。まぁ、遅れる訳だが、これが
あの前につんのめりそうになる独特のシンコペーションの源で、第二列目
だから“セカンドライン”って訳になったとか・・・・・。
すいません。確かそんな話だったと思う。(何せ人の話をちゃんと聞かない
B型ですので・・・・・。多分音楽の専門書にはちゃんとでていると思います
ので、詳しくはそちらをどうぞ。)
さて、その魔法のリズムを上手く自分達のサウンドに取り込んで、見事な
名作を世に送り出したバンドが居る。
“リトル・フィート”。1971年にデビュー以来、それこそミュージシャンズ・ミュ
ージシャンだったこのバンドが、73年に発表したアルバム「DIXIE CHICKEN」は、
そのニューオーリンズの魔法のリズムに触発されたファンキーなアルバム
に仕上がっている。
確かこのアルバムが発表された時点では、日本国内では彼らのアルバムは
リリースされていなくて、海外での評判を聴きつけた目敏い音楽ファンや音楽
関係者が、こぞって輸入盤屋で入手していたと思う。
結局彼らのアルバムは、この後の4作目から国内盤が発売される事になり、
追ってこの「デキシー・チキン」などの過去の作品が発売されるという珍現象が
起こり、一時、音楽ファンの頭を混乱させたものだ。
このリトル・フィート、解散と再結成をなんとなく繰り返していて、もしかしたら今
もバンドは存続しているのかもしれないが、絶頂期はこの「デキシー・チキン」
から77年の「タイム・ラヴズ・ア・ヒーロー」の頃まで。
何故なら、バンドの牽引者ロウエル・ジョージが存在していたからに他ならない。
彼の没後のフィートなんて・・・・・。そんな感じなので是非聴くなら73年から70
年末までの作品を。
さて、リトル・フィートと聞いて真先に思い浮かぶのが矢野顕子である。彼女の
ファンなら納得でしょう。
そう矢野顕子のデビュー・アルバム「JAPANESE GIRL」は、このリトル・フィート
とのセッションで生まれたアルバムなのです。
きっと日本のロックの名盤○○○なんてのには必ず選ばれている作品なので、
どこかで目や耳にしている読者も多いハズ。僅か5曲だけど歴史的な5曲。
と言ったら大袈裟か。
あの時代でこのノリ。才能が才能とぶつかり合った瞬間が見事にパッケージ
された名演奏である。
あぁ~、こうゆう歴史的現場に出くわしてみたい。と思う今日この頃なのです。
Little Feat / Dixie Chicken(1973年度作品)

タイトル・チューンのノリは今も大好きです。
ニューオーリンズの黒っぽさを、独自の解釈で自分達のものにしはじめた
記念すべき名盤。
やっぱりリトル・フィートと言ったらこのアルバムに尽きるでしょ。
矢野顕子 / Japanese Girl(1976年度作品)

アルバム・クレジットのLITTLE FEAT“THE GREAT”が、何よりも彼女の
感謝と敬意の表れ。フィートとのアメリカン・サイドに細野晴臣やムーン
ライダースらによる日本でのセッション。どちらも素晴らしい!
Vol.42(1997年10月号掲載)
4年ぶりに新作アルバム「Akiko」をリリースした矢野さん。
L.A録音というそのアルバムには、何かリトル・フィートと演った頃の匂い
を感じさせる曲も入っていたりして、なかなかいい感じです。
セカンドラインの話を誰としたのかは、今となっては記憶にない。
ミーターズから始まってネヴィルなどなど、セカンドラインものは未だに
聴く事が多いし気にもなる。
皮膚感覚と言うか体で覚える!ってぇのは、まさにそうで、それが自分の
体に染み込むまで、とことん聴いて、それを自分のDNAの一部にして
しまう。ってぇのが良いかなとは思うが、近頃、そこまで熱を持って聴きたく
なる作品やアーティストに出会っていない!
フィートは、ロウエル・ジョージが他界してから、全く興味を失った。
別に彼に思い入れがある訳じゃないんだけど、何となく・・・・・。
アッコちゃんのデビューに一役買った
ファンキーなファンキーなアメリカン・バンド!
大スランプだぜ!もう、まったく出てきませんわ、何を書くか。変に暑い
9月頭の残暑のせいと、この夏場の疲れが今頃出てきたのかしらん。
(と、ここまで書いて一旦書くのを止め、ネタが天から降って来るのを
待ちます。)
一行空いているのは苦悩の後と文字数稼ぎと思って下さい。困った時の
神頼み!でも、近くにはどうも神様は存在しないようだ。
と、そんな事をうだうだと書いてもしょうがないので、人に聞いた話を餌に
して本題に入ります。
以前載り上げた“セカンドライン・ファンク”の事を覚えている人は何人居る
でしょうか。と書いても、本人も一体どんな内容だったかは忘れているのだが、
そこで載り上げたアーティストは、しっかりと手帳に記録してある。
ネヴィル・ブラザーズに久保田麻琴だもネ。実に渋くていいね。
なんて事は置いておいて、このニューオーリンズが生んだ魔法のリズムの
発祥の源は何と葬儀だった。って話を某アーティストから聞いた。
何せ前回書いたように、音楽は皮膚感覚、そして体で覚えるのが信条の身。
これがあれだとか、それだとかの脳味噌に応える教養的なものは殆どない。
だから嘘か真かは知らないが、この話を聞いた時は「なるほどな~」と感心
したものだ。それは簡単に言うとこうだ。
彼の地では葬儀の際、棺を先頭に参列者が街を行進するらしく、その時に
楽団が「聖者の行進」をバカスカ鳴らしながら先を行き、続いて一般参列者が
何らかの楽器を持ってそれに続くらしい。その時、先を行く楽団と後に続く
一般参列者の間の演奏に微妙なズレが生じる。まぁ、遅れる訳だが、これが
あの前につんのめりそうになる独特のシンコペーションの源で、第二列目
だから“セカンドライン”って訳になったとか・・・・・。
すいません。確かそんな話だったと思う。(何せ人の話をちゃんと聞かない
B型ですので・・・・・。多分音楽の専門書にはちゃんとでていると思います
ので、詳しくはそちらをどうぞ。)
さて、その魔法のリズムを上手く自分達のサウンドに取り込んで、見事な
名作を世に送り出したバンドが居る。
“リトル・フィート”。1971年にデビュー以来、それこそミュージシャンズ・ミュ
ージシャンだったこのバンドが、73年に発表したアルバム「DIXIE CHICKEN」は、
そのニューオーリンズの魔法のリズムに触発されたファンキーなアルバム
に仕上がっている。
確かこのアルバムが発表された時点では、日本国内では彼らのアルバムは
リリースされていなくて、海外での評判を聴きつけた目敏い音楽ファンや音楽
関係者が、こぞって輸入盤屋で入手していたと思う。
結局彼らのアルバムは、この後の4作目から国内盤が発売される事になり、
追ってこの「デキシー・チキン」などの過去の作品が発売されるという珍現象が
起こり、一時、音楽ファンの頭を混乱させたものだ。
このリトル・フィート、解散と再結成をなんとなく繰り返していて、もしかしたら今
もバンドは存続しているのかもしれないが、絶頂期はこの「デキシー・チキン」
から77年の「タイム・ラヴズ・ア・ヒーロー」の頃まで。
何故なら、バンドの牽引者ロウエル・ジョージが存在していたからに他ならない。
彼の没後のフィートなんて・・・・・。そんな感じなので是非聴くなら73年から70
年末までの作品を。
さて、リトル・フィートと聞いて真先に思い浮かぶのが矢野顕子である。彼女の
ファンなら納得でしょう。
そう矢野顕子のデビュー・アルバム「JAPANESE GIRL」は、このリトル・フィート
とのセッションで生まれたアルバムなのです。
きっと日本のロックの名盤○○○なんてのには必ず選ばれている作品なので、
どこかで目や耳にしている読者も多いハズ。僅か5曲だけど歴史的な5曲。
と言ったら大袈裟か。
あの時代でこのノリ。才能が才能とぶつかり合った瞬間が見事にパッケージ
された名演奏である。
あぁ~、こうゆう歴史的現場に出くわしてみたい。と思う今日この頃なのです。
Little Feat / Dixie Chicken(1973年度作品)

タイトル・チューンのノリは今も大好きです。
ニューオーリンズの黒っぽさを、独自の解釈で自分達のものにしはじめた
記念すべき名盤。
やっぱりリトル・フィートと言ったらこのアルバムに尽きるでしょ。
矢野顕子 / Japanese Girl(1976年度作品)

アルバム・クレジットのLITTLE FEAT“THE GREAT”が、何よりも彼女の
感謝と敬意の表れ。フィートとのアメリカン・サイドに細野晴臣やムーン
ライダースらによる日本でのセッション。どちらも素晴らしい!
2008年10月27日
支那ちょうちんのある二階部屋
タイトルを見てピンと来た方は、まず居ないハズ。
ローラ・ニーロの歌のタイトルです。
彼女のアルバムで、唯一手に入れていなかった作品「光の季節」を、
ようやく紙ジャケCDで手に入れた。

ま、紙ジャケはどうでもいい事で、と云うより、何でナンデモカンデモ
紙ジャケット?なんでしょうね。
流行と言えば、それでお仕舞いですが・・・。
このアルバム、ライヴという事もあるが、リリース形態が複雑というか、
ちょっと色々とあって買っていなかった訳。
今回は、後にLP2枚組でリリースされた形式にボーナストラック2曲を
加えた、ま、言ってみれば満足のいく形でのリリース。
という事で、以前にもCD化されていたかどうかは知らないが、
出ていたなら、これでそのCDの価値が下落。
後から出てくるモノに色々付加価値が付くに連れて、以前のモノの
存在意義が薄れる。(マニア以外には・・・)
商売と言ってしまえばそれまでだが、これって、完全にCDの消耗品化
に拍車をかけてるんじゃないか!
何かリリース後半年も経たないうちに、ボーナスCDやら何やらを付けて
再リリースされるのもある。
CD以前のアナログ時代の旧譜に、当時の周辺事情やらを考慮して
アーカイヴ的にシングルヴァージョンなんかを追加収録するのは、資料と
しての価値があるのは分かるが、前者はただの商売。
ユーザーは戸惑う、どれがホントのオリジナル?って。
オリジナルなんてありゃしない!CDはミンナ、単なるコピー商品さ!
な~んて事にならないように。
あ、何故“支那ちょうちんのある二階部屋”かって?
なにか久々にこの曲を聴いて“いいな!”と思ったからです。
深い意味なし。
う~ん、「魂の叫び」を聴きたくなっちゃた!
ローラ・ニーロの歌のタイトルです。
彼女のアルバムで、唯一手に入れていなかった作品「光の季節」を、
ようやく紙ジャケCDで手に入れた。

ま、紙ジャケはどうでもいい事で、と云うより、何でナンデモカンデモ
紙ジャケット?なんでしょうね。
流行と言えば、それでお仕舞いですが・・・。
このアルバム、ライヴという事もあるが、リリース形態が複雑というか、
ちょっと色々とあって買っていなかった訳。
今回は、後にLP2枚組でリリースされた形式にボーナストラック2曲を
加えた、ま、言ってみれば満足のいく形でのリリース。
という事で、以前にもCD化されていたかどうかは知らないが、
出ていたなら、これでそのCDの価値が下落。
後から出てくるモノに色々付加価値が付くに連れて、以前のモノの
存在意義が薄れる。(マニア以外には・・・)
商売と言ってしまえばそれまでだが、これって、完全にCDの消耗品化
に拍車をかけてるんじゃないか!
何かリリース後半年も経たないうちに、ボーナスCDやら何やらを付けて
再リリースされるのもある。
CD以前のアナログ時代の旧譜に、当時の周辺事情やらを考慮して
アーカイヴ的にシングルヴァージョンなんかを追加収録するのは、資料と
しての価値があるのは分かるが、前者はただの商売。
ユーザーは戸惑う、どれがホントのオリジナル?って。
オリジナルなんてありゃしない!CDはミンナ、単なるコピー商品さ!
な~んて事にならないように。
あ、何故“支那ちょうちんのある二階部屋”かって?
なにか久々にこの曲を聴いて“いいな!”と思ったからです。
深い意味なし。
う~ん、「魂の叫び」を聴きたくなっちゃた!
2008年10月21日
名盤/Jefferson Airplane & PINK
続・名盤を探しに行こう/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.41(1997年9月号掲載)
前回書いていて何か変だな~と。
そうか本文中、そうそうバービーを書いているけど、肝心のアルバム
「1st OPUTION」については、本文で触れていない。
なのに名前が出てきたところでジャケットを差し込んでいる。
この形チョット不自然だ!と漸く気付いた。
掲載時は、最後のアルバム・メモのところにジャケット写真を掲載している。
あっ、そう!そうすればいいんだ!って事で、今回から、そういう形にします。
それが掲載最後まで続いたかどうかは調べてみないと分からんけど。
それとそのメモに発表年度も記していたのに書いてない!
もう、肝心なものが抜けている。
遡って書くのは面倒(ゴメン!)なので、書き込みはしませんが、お許しを。
こうしてやり直しても間違える。人間の駄目さ加減と云うより、俺の駄目さ
加減を表している。
PINKのところの岡野ハジメの間違い!スデェーな。チョー失礼!
校正してないんですか?と自虐ギャグが思わず出てしまう。
QUADRAPHONICSが廃盤ね。分かりづらい文章だこと。
JeffersonnはStarshipになってから、全く聴かなくなった。今でもAirplaneは
聴くけどStarshipは聴かないというのは変わらない。
毎朝、テレビ番組のオープニングで使われている曲もあるが、全然馴染めない。
DATE OF BIRTHのCDは行方不明、何処にいったんだろう?
書き直しながら、スッゲー聴きたくなった。
音楽は皮膚感覚で覚えましょう。そうするとサイケなんて一発で分かるから・・・。
久々に夏らしい暑さが続いた今年。如何なもんでしょうか、皆様は。
な~んて書き出したって、さっぱり分からんわな・・・。
要するに、夏は夏らしく過ごせたでしょうか。って事ですよ。
なんせ“SUMMER OF LOVE”、恋する季節の夏ですから・・・。と、キィワード
を一つ投げ出してから本題に入ります。
この夏は、先月のCD ATRANDOMで載り上げたDATE OF BIRTHのアルバム
「FOLK SONG」にハマりっぱなしで、デケェー音出して日々聴き入っていました。
殆どロックらしいロックを聴かなくなって久しいが、あの作品は、悪く言ってしまえば、
ロック黄金期の焼き直しというか、それが体に染み付いた人の“手癖”的手法で
作っちゃったもの。とも思えるのです。
だから逆に、そういったものが体に染みついている俺みたいのがフッと聴いて、
自然に体が反応した。みたいな図式が成り立つ訳で、あの当時の感覚的な
ものを喚起された感じなのです。
この間隔のより戻しは、先行シングル「クレイジーなジンクス」を聴いた時から
あって、このサウンドの感触って何だっけ?と答えを捜していた時にアルバム
が届いた。
あぁ~、サイケデリックなんだわ。これは。きっと。
サイケデリックって、今時聴くにはちょっと新鮮で、音楽の新しいキィワードかなっ。
なんて気にさせる今日この頃。
このサイケデリックという言葉、一体どんな意味かな~と思って、ものの本を
調べたら、60年代中頃からサンフランシスコを中心に流行した言葉で、ドラッグ
によってトリップした精神状態を指す・・・云々。とあって、「psyche」と「delicious」
をくっつけた造語らしい。とある。
そして、そのサイケデリック・ロックの代表がJefferson Airplaneと書いてあった。
そうか「クレイジーな~」を聴いて感じていたモゾモゾ感は、結局のところジェファ
スン・エアプレーンに辿り着く為だったのか。と納得。
閑話休題。
ヒッピー文化の聖地と持て囃された60年代後半のサンフランシスコが生んだ
サウンドがサイケデリック・ロックで、このジェファスンやグレイトフル・デッド、
クイックシルヴァー・メッセンジャー・サーヴィスらの名前が上がる。
では、そのサイケデリック・ロックのスタイルってどんなんだ!と言われれば、
言葉に窮する。
ドラッグ体験がもたらすものがなきゃ駄目。なんて事はないが、当時、ライヴ会場
では、そうしたドラッグ体験を視覚的に訴える為のライト・ショウ(とは言っても、
30年も前の事、たかが知れている)が盛んだった。それが幻想的で、サイケデ
リックと言われる理由にもなった。という説もある。
とは言うものの、例えばこのジェファスンにしても、ブルーズやフォークをベース
にブリティッシュ・ビートや今でいうワールド・ミュージックなどの刺激を受け、当時
としては斬新なミクスチャー感覚を実践して、新しいポップ・ミュージックを築き上げ
ていた訳で、前述のシスコ在住のアーティストらの活動振りなどと併せてシスコ・
サウンド=サイケデリック・ロックと呼ぶようになったらしい。
まぁ、ジェファスンを聴くというか、この元祖サイケデリックを聴くのなら、67年の
「シュールリアリスティック・ピロー」~69年の「ヴォランテアーズ」の間にリリース
された作品をお薦めする。間違っても改名後のスターシップが付いたものは聴か
ないように。
さて、80年代に堂々と「PSYCHO-DELICIOUS」なるアルバムを発表したバンドが
居る。“PINK”、もう皆さんの記憶の隅にも残っていないバンドだろう。
彼らが80年代的に、サイケデリックを具現化しようとしたかは定かではないが、
デビュー以来聴かせていた無国籍感覚やビート感、そしてポップ・ミュージックを
新たに構築しようとしていた姿勢などなど、もしかしたら、あの時代のやり方の
サイケを狙っていたのでは・・・・・。と思っているのは俺だけかしらん。
そんな訳で、ヒッピーな街シスコで興ったムーヴメントは、20年後、世界でも有数
なヒップな街“東京”でも興った。って事ですよ。な~んてネ。
Jefferson Airplane / Surrealistic Pillow(1967年度作品)
「Somebody to Love」の強烈なインパクトは今聴いても変わりません。
ジャニスかグレースか。ってのが当時のシスコの女王争い。
サイケデリック・ロックの第一歩はこのアルバムがよろしいのでは。
そして皮膚感覚で覚えましょう!サイケを!

PINK / PSYCHO-DELISIOUS(1987年度作品)
彼らの3rdアルバム。デビュー作程の新鮮さや衝撃はないけれど捨て難い1枚。
サウンドのサイケ感は丘のハジメとSALON MUSICの吉田仁のユニット
“QUADRAPHONICS”の方が凄い。が、すでに廃盤になっていた。ん~、残念。

Vol.41(1997年9月号掲載)
前回書いていて何か変だな~と。
そうか本文中、そうそうバービーを書いているけど、肝心のアルバム
「1st OPUTION」については、本文で触れていない。
なのに名前が出てきたところでジャケットを差し込んでいる。
この形チョット不自然だ!と漸く気付いた。
掲載時は、最後のアルバム・メモのところにジャケット写真を掲載している。
あっ、そう!そうすればいいんだ!って事で、今回から、そういう形にします。
それが掲載最後まで続いたかどうかは調べてみないと分からんけど。
それとそのメモに発表年度も記していたのに書いてない!
もう、肝心なものが抜けている。
遡って書くのは面倒(ゴメン!)なので、書き込みはしませんが、お許しを。
こうしてやり直しても間違える。人間の駄目さ加減と云うより、俺の駄目さ
加減を表している。
PINKのところの岡野ハジメの間違い!スデェーな。チョー失礼!
校正してないんですか?と自虐ギャグが思わず出てしまう。
QUADRAPHONICSが廃盤ね。分かりづらい文章だこと。
JeffersonnはStarshipになってから、全く聴かなくなった。今でもAirplaneは
聴くけどStarshipは聴かないというのは変わらない。
毎朝、テレビ番組のオープニングで使われている曲もあるが、全然馴染めない。
DATE OF BIRTHのCDは行方不明、何処にいったんだろう?
書き直しながら、スッゲー聴きたくなった。
音楽は皮膚感覚で覚えましょう。そうするとサイケなんて一発で分かるから・・・。
久々に夏らしい暑さが続いた今年。如何なもんでしょうか、皆様は。
な~んて書き出したって、さっぱり分からんわな・・・。
要するに、夏は夏らしく過ごせたでしょうか。って事ですよ。
なんせ“SUMMER OF LOVE”、恋する季節の夏ですから・・・。と、キィワード
を一つ投げ出してから本題に入ります。
この夏は、先月のCD ATRANDOMで載り上げたDATE OF BIRTHのアルバム
「FOLK SONG」にハマりっぱなしで、デケェー音出して日々聴き入っていました。
殆どロックらしいロックを聴かなくなって久しいが、あの作品は、悪く言ってしまえば、
ロック黄金期の焼き直しというか、それが体に染み付いた人の“手癖”的手法で
作っちゃったもの。とも思えるのです。
だから逆に、そういったものが体に染みついている俺みたいのがフッと聴いて、
自然に体が反応した。みたいな図式が成り立つ訳で、あの当時の感覚的な
ものを喚起された感じなのです。
この間隔のより戻しは、先行シングル「クレイジーなジンクス」を聴いた時から
あって、このサウンドの感触って何だっけ?と答えを捜していた時にアルバム
が届いた。
あぁ~、サイケデリックなんだわ。これは。きっと。
サイケデリックって、今時聴くにはちょっと新鮮で、音楽の新しいキィワードかなっ。
なんて気にさせる今日この頃。
このサイケデリックという言葉、一体どんな意味かな~と思って、ものの本を
調べたら、60年代中頃からサンフランシスコを中心に流行した言葉で、ドラッグ
によってトリップした精神状態を指す・・・云々。とあって、「psyche」と「delicious」
をくっつけた造語らしい。とある。
そして、そのサイケデリック・ロックの代表がJefferson Airplaneと書いてあった。
そうか「クレイジーな~」を聴いて感じていたモゾモゾ感は、結局のところジェファ
スン・エアプレーンに辿り着く為だったのか。と納得。
閑話休題。
ヒッピー文化の聖地と持て囃された60年代後半のサンフランシスコが生んだ
サウンドがサイケデリック・ロックで、このジェファスンやグレイトフル・デッド、
クイックシルヴァー・メッセンジャー・サーヴィスらの名前が上がる。
では、そのサイケデリック・ロックのスタイルってどんなんだ!と言われれば、
言葉に窮する。
ドラッグ体験がもたらすものがなきゃ駄目。なんて事はないが、当時、ライヴ会場
では、そうしたドラッグ体験を視覚的に訴える為のライト・ショウ(とは言っても、
30年も前の事、たかが知れている)が盛んだった。それが幻想的で、サイケデ
リックと言われる理由にもなった。という説もある。
とは言うものの、例えばこのジェファスンにしても、ブルーズやフォークをベース
にブリティッシュ・ビートや今でいうワールド・ミュージックなどの刺激を受け、当時
としては斬新なミクスチャー感覚を実践して、新しいポップ・ミュージックを築き上げ
ていた訳で、前述のシスコ在住のアーティストらの活動振りなどと併せてシスコ・
サウンド=サイケデリック・ロックと呼ぶようになったらしい。
まぁ、ジェファスンを聴くというか、この元祖サイケデリックを聴くのなら、67年の
「シュールリアリスティック・ピロー」~69年の「ヴォランテアーズ」の間にリリース
された作品をお薦めする。間違っても改名後のスターシップが付いたものは聴か
ないように。
さて、80年代に堂々と「PSYCHO-DELICIOUS」なるアルバムを発表したバンドが
居る。“PINK”、もう皆さんの記憶の隅にも残っていないバンドだろう。
彼らが80年代的に、サイケデリックを具現化しようとしたかは定かではないが、
デビュー以来聴かせていた無国籍感覚やビート感、そしてポップ・ミュージックを
新たに構築しようとしていた姿勢などなど、もしかしたら、あの時代のやり方の
サイケを狙っていたのでは・・・・・。と思っているのは俺だけかしらん。
そんな訳で、ヒッピーな街シスコで興ったムーヴメントは、20年後、世界でも有数
なヒップな街“東京”でも興った。って事ですよ。な~んてネ。
Jefferson Airplane / Surrealistic Pillow(1967年度作品)
「Somebody to Love」の強烈なインパクトは今聴いても変わりません。
ジャニスかグレースか。ってのが当時のシスコの女王争い。
サイケデリック・ロックの第一歩はこのアルバムがよろしいのでは。
そして皮膚感覚で覚えましょう!サイケを!

PINK / PSYCHO-DELISIOUS(1987年度作品)
彼らの3rdアルバム。デビュー作程の新鮮さや衝撃はないけれど捨て難い1枚。
サウンドのサイケ感は丘のハジメとSALON MUSICの吉田仁のユニット
“QUADRAPHONICS”の方が凄い。が、すでに廃盤になっていた。ん~、残念。

2008年10月20日
番外編/飯がわりに一撃を!/さよならJ1!
ナンカ、全然抵抗もなく、すんなりとJ2降格が決まったような感じ。
厚別は好天だったけど、ホームのゴール裏には強烈な風が吹き付けていた!
試合終了と共に競技場を後にしたけど、サポの皆さんは怒ったのかしらん。
結局はJ1仕様の選手が、あまりにも居なかったって事なんですよね。
来年も、あの重戦車のようなクライトンのプレーを観たい!
と言うか、あのくらい執念があるプレーをミンナがすれば・・・・・・・・・・。
もう何を言っても遅いんだよね。
厚別は好天だったけど、ホームのゴール裏には強烈な風が吹き付けていた!
試合終了と共に競技場を後にしたけど、サポの皆さんは怒ったのかしらん。
結局はJ1仕様の選手が、あまりにも居なかったって事なんですよね。
来年も、あの重戦車のようなクライトンのプレーを観たい!
と言うか、あのくらい執念があるプレーをミンナがすれば・・・・・・・・・・。
もう何を言っても遅いんだよね。
2008年10月14日
名盤/FLEETWOOD MAC & BARBEE BOYS
続・名盤を探しに行こう/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.40(1997年8月号掲載)
ブルーズと書いているがブルースって書くのが一般的。
バラッドなのかバラードなのか、カタカナ表記にすると色々と面倒臭い。
と云うより発音に似せようとするから、こんな表記になるのか?
ま、意味が通じればいいんだけれど。
マックは、この頃、割と夢中で聴きました。併せて書いてある通り、それこそ
通り道としてブルーズバンドの時も、ちょっと聴きました。
あっそうそう、夢中で聴いたのはスティーヴィ・ニックスが居たからかも。
だってカワイイかったもな~。
札幌公演の時、席が悪かったから、その可愛さを裸眼では観れなかったけど。
これも今となっては、殆ど聴く事がないアルバムとなってしまった。
思い出した時は、ベスト盤で済ませています。
バービー・ボーイズも然り。
こちらは今年再結成で話題を撒いたけど、どうなんでしょ。
ライジング・サン・ロック・フェスティヴァルで観たけど、コンタが変わらずの
唄いっぷりを聴かせたのには驚いた。
杏子は、ずぅーと現役だから、今更どうと言えない。
味をしめて、来年、ツアーなどをくれぐれも遣らぬよう。
お祭りの中の1シーンで充分!と思ったのは俺だけ。
それにしてもマックの全世界での数字、何て書き方をしてんだ!
おそまつでした!
女の力で大成功(!?)。マニアックなブルーズ・バンドがみせた大変身・・・。
ちょっと前の話になるが、縁があって山崎まさよしとハイロウズの甲本ヒロト
両氏の、それぞれ酒の席を同席させて戴きました。
まぁ、男同士が酒の席で話す内容なんて、例え相手がミュージシャンでも、
たかが知れている。な~んて書いたら、何やら変な想像をされそうなので、
その夜は割りと仕事っぽい話に終始していたように記憶している。と書いて
おこう。が、なんせ酒を飲んでの記憶なので定かではない。
とは言うものの、相手はミュージシャン。
当然音楽の話の一つや二つが出ても可笑しくはない。
って事で、記憶を依り戻してみると御両人が共通して話したのが“ブルーズ”
の事。
それも両人共かなり詳しそうな話っぷりで、広く浅く雑食的に音楽を聴いている
俺には、到底太刀打ちできる訳はない。
ヒロトのようにストーンズ直径のロックンロールを演っているミュージシャンだったら、
そりゃ正しく体系的に身に付けているな~ってのが分かるけど、山崎まさよし
だよね・・・。
まぁ、CD紹介でブルーズ的加速度なノリみたいな表現をしちゃった訳だけど、
あの時点で、彼のプロフィールやフェイバリットなものなんかの資料的知識は
ゼロで、聴いた感触があんな感じだったので、そんな風に書いた訳で、別に
深読みをしたんじゃないです。
その辺については、きっと然るべき人が、そうそう名のある音楽評論家の先生が、
きっと、きっちりと何処かで語ってくれるでしょ。
さてブルーズと言えば・・・、何でしょう。黒人ですよね。それが正しい答えなんで
すが、僕のように60年代後半からドップリと所謂洋楽にハマッた人にとって、
ブルーズの第一段階はホワイト・ブルーズって人が多いはずだ。
それは字を読んだ如く、白人達が演っているブルーズの事。なんかあの当時、
やたらとブルーズ・バンドが多かった。というか、ロック演るにゃ、どうしても通ら
なければいけない道だったのです。
まぁ、ロックと言われた連中の全てが、始まりは黒人音楽への憧れだった訳
だから。
そんな中にフリートウッド・マックというバンドが居た。バリバリのブルーズ・バンド
で、今だに語られる事の多い名ギタリスト“ピーター・グリーン”が在籍したバンドだ。
彼らの真摯にブルーズを追及する姿勢は、本場アメリカのシカゴへ乗り込んで
ウィリー・ディクソンやオーティス・スパンらとセッションした「BLUE’S JAM at
Chess」という作品にきっちりと残されている。
また、あのサンタナで有名な「BLACK MAGIC WOMAN」のオリジナルを収録した
アルバム「ENGLISH ROSE」は、ブリティシュ・ブルーズの名盤の1枚に数えられる
作品だ。
そん彼らが、ちょっと目を離した隙にアメリカに移住し、気が付いたら浦島太郎的に、
実にポップなロックを聴かせるバンドに変身を遂げていた。
77年に発表した「噂」は、そのピークの瞬間を見事に捉らえたアルバムだった。

それこそ前作「FLEETWOOD MAC(邦題:ファンタスティック・マック)」の全米での
大ブレイク振りの噂が、じわっじわっと我が日本にも浸透してきた頃にリリース
された快心の一発で、恐らくこれまでに、全世界で軽く、ん1,000百万枚を超す
セールスを記録したに違いない怪物的な作品。
このバカ人気、勿論音そのものの力も大きいが、ヴィジュアル的な貢献度は、
スティーヴィ・ニックスの魅力に依るところが大きいのでは・・・と。
このスティーヴィ嬢に負けず劣らず(!?)怪しい魅力を発揮していた杏子嬢を擁した
バンドが“バービー・ボーイズ”。

嘘か本当かは未確認だが、最近聞いて驚いたのは、あの東京ドームのこけら落とし
公演は、このバービー達だったとか。あれ~、そんな人気者だったのかしらん。
いやはやそれが本当だったら、俺ってすんごく無知。全然そんな認識ないもネ。
出会いは映画「台風クラブ」。そこで使われた曲が、やたらと耳に付いて離れ
なかったんだな。これが。
映画が導いた縁という訳です。
んなぁ訳で、ロックの源“BLUES”を聴きなさい!という話にしようと思ったけど、
ちょっと逸れたか。
FLEETWOOD MAC/ RUMOURS
ジャケットに写し出されたミック・フリートウッドの股間の二玉は、いまだ気に
なります。スティーヴィ・ニックス嬢のキュートさと、優れた作品を生み出す
リンジー、クリスティンらの才能。そのセールスが実証するように、永遠の名盤
に数えられる数少ない1枚。
BARBEE BOYS/ 1st OPTION
結構男女によるトゥイン・ヴォーカルはクセになりそうな程格好いいもんです。
アホバカなカラオケを、こんなデュエットで唄ったら、日本の未来も明るい!
な~んてネ。今聴き直しても好きな日本のロック・アルバムの1枚。
Vol.40(1997年8月号掲載)
ブルーズと書いているがブルースって書くのが一般的。
バラッドなのかバラードなのか、カタカナ表記にすると色々と面倒臭い。
と云うより発音に似せようとするから、こんな表記になるのか?
ま、意味が通じればいいんだけれど。
マックは、この頃、割と夢中で聴きました。併せて書いてある通り、それこそ
通り道としてブルーズバンドの時も、ちょっと聴きました。
あっそうそう、夢中で聴いたのはスティーヴィ・ニックスが居たからかも。
だってカワイイかったもな~。
札幌公演の時、席が悪かったから、その可愛さを裸眼では観れなかったけど。
これも今となっては、殆ど聴く事がないアルバムとなってしまった。
思い出した時は、ベスト盤で済ませています。
バービー・ボーイズも然り。
こちらは今年再結成で話題を撒いたけど、どうなんでしょ。
ライジング・サン・ロック・フェスティヴァルで観たけど、コンタが変わらずの
唄いっぷりを聴かせたのには驚いた。
杏子は、ずぅーと現役だから、今更どうと言えない。
味をしめて、来年、ツアーなどをくれぐれも遣らぬよう。
お祭りの中の1シーンで充分!と思ったのは俺だけ。
それにしてもマックの全世界での数字、何て書き方をしてんだ!
おそまつでした!
女の力で大成功(!?)。マニアックなブルーズ・バンドがみせた大変身・・・。
ちょっと前の話になるが、縁があって山崎まさよしとハイロウズの甲本ヒロト
両氏の、それぞれ酒の席を同席させて戴きました。
まぁ、男同士が酒の席で話す内容なんて、例え相手がミュージシャンでも、
たかが知れている。な~んて書いたら、何やら変な想像をされそうなので、
その夜は割りと仕事っぽい話に終始していたように記憶している。と書いて
おこう。が、なんせ酒を飲んでの記憶なので定かではない。
とは言うものの、相手はミュージシャン。
当然音楽の話の一つや二つが出ても可笑しくはない。
って事で、記憶を依り戻してみると御両人が共通して話したのが“ブルーズ”
の事。
それも両人共かなり詳しそうな話っぷりで、広く浅く雑食的に音楽を聴いている
俺には、到底太刀打ちできる訳はない。
ヒロトのようにストーンズ直径のロックンロールを演っているミュージシャンだったら、
そりゃ正しく体系的に身に付けているな~ってのが分かるけど、山崎まさよし
だよね・・・。
まぁ、CD紹介でブルーズ的加速度なノリみたいな表現をしちゃった訳だけど、
あの時点で、彼のプロフィールやフェイバリットなものなんかの資料的知識は
ゼロで、聴いた感触があんな感じだったので、そんな風に書いた訳で、別に
深読みをしたんじゃないです。
その辺については、きっと然るべき人が、そうそう名のある音楽評論家の先生が、
きっと、きっちりと何処かで語ってくれるでしょ。
さてブルーズと言えば・・・、何でしょう。黒人ですよね。それが正しい答えなんで
すが、僕のように60年代後半からドップリと所謂洋楽にハマッた人にとって、
ブルーズの第一段階はホワイト・ブルーズって人が多いはずだ。
それは字を読んだ如く、白人達が演っているブルーズの事。なんかあの当時、
やたらとブルーズ・バンドが多かった。というか、ロック演るにゃ、どうしても通ら
なければいけない道だったのです。
まぁ、ロックと言われた連中の全てが、始まりは黒人音楽への憧れだった訳
だから。
そんな中にフリートウッド・マックというバンドが居た。バリバリのブルーズ・バンド
で、今だに語られる事の多い名ギタリスト“ピーター・グリーン”が在籍したバンドだ。
彼らの真摯にブルーズを追及する姿勢は、本場アメリカのシカゴへ乗り込んで
ウィリー・ディクソンやオーティス・スパンらとセッションした「BLUE’S JAM at
Chess」という作品にきっちりと残されている。
また、あのサンタナで有名な「BLACK MAGIC WOMAN」のオリジナルを収録した
アルバム「ENGLISH ROSE」は、ブリティシュ・ブルーズの名盤の1枚に数えられる
作品だ。
そん彼らが、ちょっと目を離した隙にアメリカに移住し、気が付いたら浦島太郎的に、
実にポップなロックを聴かせるバンドに変身を遂げていた。
77年に発表した「噂」は、そのピークの瞬間を見事に捉らえたアルバムだった。

それこそ前作「FLEETWOOD MAC(邦題:ファンタスティック・マック)」の全米での
大ブレイク振りの噂が、じわっじわっと我が日本にも浸透してきた頃にリリース
された快心の一発で、恐らくこれまでに、全世界で軽く、ん1,000百万枚を超す
セールスを記録したに違いない怪物的な作品。
このバカ人気、勿論音そのものの力も大きいが、ヴィジュアル的な貢献度は、
スティーヴィ・ニックスの魅力に依るところが大きいのでは・・・と。
このスティーヴィ嬢に負けず劣らず(!?)怪しい魅力を発揮していた杏子嬢を擁した
バンドが“バービー・ボーイズ”。

嘘か本当かは未確認だが、最近聞いて驚いたのは、あの東京ドームのこけら落とし
公演は、このバービー達だったとか。あれ~、そんな人気者だったのかしらん。
いやはやそれが本当だったら、俺ってすんごく無知。全然そんな認識ないもネ。
出会いは映画「台風クラブ」。そこで使われた曲が、やたらと耳に付いて離れ
なかったんだな。これが。
映画が導いた縁という訳です。
んなぁ訳で、ロックの源“BLUES”を聴きなさい!という話にしようと思ったけど、
ちょっと逸れたか。
FLEETWOOD MAC/ RUMOURS
ジャケットに写し出されたミック・フリートウッドの股間の二玉は、いまだ気に
なります。スティーヴィ・ニックス嬢のキュートさと、優れた作品を生み出す
リンジー、クリスティンらの才能。そのセールスが実証するように、永遠の名盤
に数えられる数少ない1枚。
BARBEE BOYS/ 1st OPTION
結構男女によるトゥイン・ヴォーカルはクセになりそうな程格好いいもんです。
アホバカなカラオケを、こんなデュエットで唄ったら、日本の未来も明るい!
な~んてネ。今聴き直しても好きな日本のロック・アルバムの1枚。
2008年10月09日
楽しき!ジャケットだらけ!
珍しく東京でハシゴ酒。と言っても、たかだか2軒だけだが。
その2軒目に連れて行かれた店が素敵だった。
素敵ってぇのは俺にとってはであって、世間一般の人達には、
全然そんな事はないと思う。
場所は西麻布、いわゆるBarで、カウンターの向こうには、
当たり前にウィスキーやらのボトルがズラッーと並んでいる。
ここまではありきたりですが、そのボトルの後ろが壁一杯LPの
ジャケット!そうジャケットだらけ!
あぁ、こうゆうのあったな~、と。
そうそう、昔のレコード店って、こうだったな~。
売れセンやら新譜が、こんな風に誇らしげに飾られていたような
記憶がある。
違うのは売れセンやらとはでなく、マスターの気分次第ってとこ。
今日のテーマは肖像画!ってマスターが言っていた。
なるほど、ロックを中心に30枚程、絵のジャケットが並んでいた。
ジェフ・ベックの「Blow By Blow」やストーンズの「LOVE YOU LIVE」
アイリーン・キャラやジェフ・マルダーとエイモス・ギャレットの
アルバムも並んでいる。
珍しいところでは、“レッタ・ンブール”のアルバムも。
これは俺がアフリカものを聴きだした初期に聴いた作品で、すっかり
忘れていた存在。懐かしい。
こうしてジャケットを見ていると、酔いで脳みそが柔らかくなっている
のもあってか、それにまつわる、実に色んな事が思い出される。
もうそれだけで楽しい!
またチャンスがあれば行ってみようと思う。
きっと札幌にも探せばあるんだろうな、こうゆう店。
知っている方、教えて!
その2軒目に連れて行かれた店が素敵だった。
素敵ってぇのは俺にとってはであって、世間一般の人達には、
全然そんな事はないと思う。
場所は西麻布、いわゆるBarで、カウンターの向こうには、
当たり前にウィスキーやらのボトルがズラッーと並んでいる。
ここまではありきたりですが、そのボトルの後ろが壁一杯LPの
ジャケット!そうジャケットだらけ!
あぁ、こうゆうのあったな~、と。
そうそう、昔のレコード店って、こうだったな~。
売れセンやら新譜が、こんな風に誇らしげに飾られていたような
記憶がある。
違うのは売れセンやらとはでなく、マスターの気分次第ってとこ。
今日のテーマは肖像画!ってマスターが言っていた。
なるほど、ロックを中心に30枚程、絵のジャケットが並んでいた。
ジェフ・ベックの「Blow By Blow」やストーンズの「LOVE YOU LIVE」
アイリーン・キャラやジェフ・マルダーとエイモス・ギャレットの
アルバムも並んでいる。
珍しいところでは、“レッタ・ンブール”のアルバムも。
これは俺がアフリカものを聴きだした初期に聴いた作品で、すっかり
忘れていた存在。懐かしい。
こうしてジャケットを見ていると、酔いで脳みそが柔らかくなっている
のもあってか、それにまつわる、実に色んな事が思い出される。
もうそれだけで楽しい!
またチャンスがあれば行ってみようと思う。
きっと札幌にも探せばあるんだろうな、こうゆう店。
知っている方、教えて!
Posted by keith yoshida at
11:26
│Comments(0)
2008年10月06日
名盤/ROD STEWART & 憂歌団
続・名盤を探しに行こう/あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!
Vol.39(1997年7月号掲載)
熱狂の云々は、コンサ・サポの間では伝説的な試合ですな~。
Jリーグじゃなくて“JFL”の時ですね。これは。
まだJ1やJ2のデヴィジョンがなかった頃の事です。ハイ!
もう11年も経っちゃって、相変わらず試合に通っています。
わが街のチームという事で、皆さんも応援に行きましょう。
“もうちょっと強かったら行く!って”、などとの声が聞こえそう。
ま、確かに。
夢のJ1は、ホントに夢のように1年で終わっちゃいそうだし・・・。
勝ち試合を観たい!!!
ロッドも全然聴かなくなったアーティストの一人。
近年はスタンダードっぽい作品を出しているんでしたっけ?
向こうじゃ、それで悠々食えるから、老体に鞭打ってロックする
必要無いか。
これと「アトランティック・クロッシング」と、更に遡ってMERCURY
時代の幾つかのアルバムなら、今でも聴けるかも・・・。
憂歌団も全然忘れ去られた存在。
改名後の木村さん、時々、ライヴなんかでお名前をお見かけする
けど、ほかのメンバーは何処へ。
前回に続いて今回も訃報が載っているが、そのロニー・レーンの
DVDを今年になって初めて観ました。
ま、ミュージシャンズ・ミュージシャンで、結構回りから愛されて
いたんでしょうね。
そんな事が伝わってくる映画でした。
“祝・リンダ・ルイス札幌公演!”には全然関係無い、リンダの美声とはうって
変わって“ダーティ・ヴォイス”の持ち主の話です。
“行ってきました!コンサドーレ!”って訳で、あの熱狂の川崎フロンターレ戦
を観てきました。
いやはや“生”サッカー初体験で、あの奇跡の逆転劇。もう止められません。
ハイ。なんか、“Jリーグ”のチームを応援している場合じゃないですヨ。貴方。
ま~んて言われたみたいで、やたらコンサドーレに力入ちゃう今日この頃です。
それにしてもチケットを買いに行ったローソンの対応、もうちょっと早くなないか
な~。(たまたまだったかも知れないけど。)俺、気が短いし、コンビニに長々と
いるのが恥ずかしいんだよな。(オジさんは!?)
それと競技場の音響設備どうにかなんないかな。折角、FM NORTHWAVEの
スタッフが選曲とかコメントで盛り上げているのに、音が割れてるんだもん。
ちょっと聞き苦しいんだよな。とは言うものの目指せJ・リーグって事で、当分、
いやいや今シーズンが終わるまでは、出来るだけ競技場へ足を運ぼうと思っ
ている次第です。
勿論、晴れて“J・リーグ”昇格後もネ。
さてサッカーって事で思い浮かぶアーティストと言えば・・・、そりゃ言わずと知
れた“ロッド・ステュワート”ですよネ。
なんせ一時は、サッカーを見たい!と言ってはコンサートをキャンセルして出掛
けて行った。なんて話があった位だし、ライヴではサッカー・ボールを客席に目掛
けて蹴ったりと、そのフリーク振りを如何無く発揮していた訳だから。
彼が世界的なスーパースターになったのは、それこそ78年発表のアルバム
「スーパースターはブロンドがお好き」に収録された「アイム・セクシー」の大ヒット
に依る所が大きいんだけど、本国英国を含めた欧米では、あのフェイシズとして
のバンド活動と並行して行っていたソロ活動で71年に発表したアルバム「エブリ
・ピクチャー・テルズ・ア・ストーリー」で火が点いていた。
その後もこの人、結構いいアルバムを出しているんだけど、転換期の名作と言え
ば75年に発表した「アトラティック・クロッシング」は外せないだろう。
サザーランド・ブラザーズの名曲のカヴァー「セイリング」の名唱は、この人の代表
曲として語り継がれている事が多いし、収録された曲が粒揃いで、それこそ
名盤と呼ぶに相応しい一作である。
この名盤の誉れ高い「アトランティック・クロッシング」に続いて発表した作品
「ナイト・オン・ザ・タウン」も、実に味わい深い作品に仕上がっているが、前作の
影に隠れて、いまいちアルバムとしての存在感が弱い。(と思っているのは俺
だけだったりして。)でも、本当にいいアルバムだと思うよ。

レコードで言えば「アトランティック~」とは反対にA面にソウルフルなバラード、
B面にロッキン・ロールなロッドが存在する。という作り。
そしてこれ以降、加速度的にロッドに人気は膨れ上がり、前述の「アイム~」で、
ひとつの頂点に達する訳。
だが、それと反比例するように、俺のロッドへの関心は萎んでいったのも事実。
やっぱり、ロッド・ステュワートは、この「ナイト・オン・ザ・タウン」までだよな。
でぇ、日本の嗄れ枯れ市場に目を向けて見ると、真っ先に思い浮かんだのが
上田正樹。でも、サウス・トゥ・サウス時代の作品がCD化されていないような
ので、同じ関西方面から憂歌団に登場してもらいましょう。
ショーボート時代のブルーズどっぷり!ってのが憂歌団。とコアなファンは仰る
でしょうが、80年代末の洗練された味わいの彼らもいいがに~。
88年にリリースされたアルバム「BLUE’S」は、作詞家としても活躍していた康
珍化(カン・チンファ)がプロデュースを手がけた一作。
この当時、康珍化とは確か何作か一緒に作ったはずで、適度にポップで肩の
力の抜けた憂歌団サウンドと、木村秀勝(改名前です)の嗄れ声が絶妙にマッチ
して、仲々の聴き心地なのです。
という訳で今月は嗄れ声も魅力!って話しでした。
最後に、先月に続いて悲しい知らせとなるが、先頃51歳という短い人生を終えた
ロッドの盟友“ロニー・レーン”氏のご冥福を心から祈りたい。
ROD STEWART/ A NIGHT ON THE TOWN
ファスト・サイドのロックするロッドも流石だが、ちょっと都会的な匂いがする
スロー・サイドの唄っぷりは絶品だ。「今夜きめよう」「さびしき丘」などの名曲
多数。「セイリング」と同位置に置かれた「貿易風」の熱唱も捨て難い魅力に
溢れている。
憂歌団/ BLUE’S
ツボを抑えた演奏とアレンジ、そして木村さんのヴォーカルが妙に心に沁みる
時があるのです。「働け、ブルース・バンド」って曲もあるけど、生涯ブルース・
バンドっていうのもいいんじゃない。スタンダード的味わいも素敵なアルバム。
Vol.39(1997年7月号掲載)
熱狂の云々は、コンサ・サポの間では伝説的な試合ですな~。
Jリーグじゃなくて“JFL”の時ですね。これは。
まだJ1やJ2のデヴィジョンがなかった頃の事です。ハイ!
もう11年も経っちゃって、相変わらず試合に通っています。
わが街のチームという事で、皆さんも応援に行きましょう。
“もうちょっと強かったら行く!って”、などとの声が聞こえそう。
ま、確かに。
夢のJ1は、ホントに夢のように1年で終わっちゃいそうだし・・・。
勝ち試合を観たい!!!
ロッドも全然聴かなくなったアーティストの一人。
近年はスタンダードっぽい作品を出しているんでしたっけ?
向こうじゃ、それで悠々食えるから、老体に鞭打ってロックする
必要無いか。
これと「アトランティック・クロッシング」と、更に遡ってMERCURY
時代の幾つかのアルバムなら、今でも聴けるかも・・・。
憂歌団も全然忘れ去られた存在。
改名後の木村さん、時々、ライヴなんかでお名前をお見かけする
けど、ほかのメンバーは何処へ。
前回に続いて今回も訃報が載っているが、そのロニー・レーンの
DVDを今年になって初めて観ました。
ま、ミュージシャンズ・ミュージシャンで、結構回りから愛されて
いたんでしょうね。
そんな事が伝わってくる映画でした。
“祝・リンダ・ルイス札幌公演!”には全然関係無い、リンダの美声とはうって
変わって“ダーティ・ヴォイス”の持ち主の話です。
“行ってきました!コンサドーレ!”って訳で、あの熱狂の川崎フロンターレ戦
を観てきました。
いやはや“生”サッカー初体験で、あの奇跡の逆転劇。もう止められません。
ハイ。なんか、“Jリーグ”のチームを応援している場合じゃないですヨ。貴方。
ま~んて言われたみたいで、やたらコンサドーレに力入ちゃう今日この頃です。
それにしてもチケットを買いに行ったローソンの対応、もうちょっと早くなないか
な~。(たまたまだったかも知れないけど。)俺、気が短いし、コンビニに長々と
いるのが恥ずかしいんだよな。(オジさんは!?)
それと競技場の音響設備どうにかなんないかな。折角、FM NORTHWAVEの
スタッフが選曲とかコメントで盛り上げているのに、音が割れてるんだもん。
ちょっと聞き苦しいんだよな。とは言うものの目指せJ・リーグって事で、当分、
いやいや今シーズンが終わるまでは、出来るだけ競技場へ足を運ぼうと思っ
ている次第です。
勿論、晴れて“J・リーグ”昇格後もネ。
さてサッカーって事で思い浮かぶアーティストと言えば・・・、そりゃ言わずと知
れた“ロッド・ステュワート”ですよネ。
なんせ一時は、サッカーを見たい!と言ってはコンサートをキャンセルして出掛
けて行った。なんて話があった位だし、ライヴではサッカー・ボールを客席に目掛
けて蹴ったりと、そのフリーク振りを如何無く発揮していた訳だから。
彼が世界的なスーパースターになったのは、それこそ78年発表のアルバム
「スーパースターはブロンドがお好き」に収録された「アイム・セクシー」の大ヒット
に依る所が大きいんだけど、本国英国を含めた欧米では、あのフェイシズとして
のバンド活動と並行して行っていたソロ活動で71年に発表したアルバム「エブリ
・ピクチャー・テルズ・ア・ストーリー」で火が点いていた。
その後もこの人、結構いいアルバムを出しているんだけど、転換期の名作と言え
ば75年に発表した「アトラティック・クロッシング」は外せないだろう。
サザーランド・ブラザーズの名曲のカヴァー「セイリング」の名唱は、この人の代表
曲として語り継がれている事が多いし、収録された曲が粒揃いで、それこそ
名盤と呼ぶに相応しい一作である。
この名盤の誉れ高い「アトランティック・クロッシング」に続いて発表した作品
「ナイト・オン・ザ・タウン」も、実に味わい深い作品に仕上がっているが、前作の
影に隠れて、いまいちアルバムとしての存在感が弱い。(と思っているのは俺
だけだったりして。)でも、本当にいいアルバムだと思うよ。

レコードで言えば「アトランティック~」とは反対にA面にソウルフルなバラード、
B面にロッキン・ロールなロッドが存在する。という作り。
そしてこれ以降、加速度的にロッドに人気は膨れ上がり、前述の「アイム~」で、
ひとつの頂点に達する訳。
だが、それと反比例するように、俺のロッドへの関心は萎んでいったのも事実。
やっぱり、ロッド・ステュワートは、この「ナイト・オン・ザ・タウン」までだよな。
でぇ、日本の嗄れ枯れ市場に目を向けて見ると、真っ先に思い浮かんだのが
上田正樹。でも、サウス・トゥ・サウス時代の作品がCD化されていないような
ので、同じ関西方面から憂歌団に登場してもらいましょう。
ショーボート時代のブルーズどっぷり!ってのが憂歌団。とコアなファンは仰る
でしょうが、80年代末の洗練された味わいの彼らもいいがに~。
88年にリリースされたアルバム「BLUE’S」は、作詞家としても活躍していた康
珍化(カン・チンファ)がプロデュースを手がけた一作。
この当時、康珍化とは確か何作か一緒に作ったはずで、適度にポップで肩の
力の抜けた憂歌団サウンドと、木村秀勝(改名前です)の嗄れ声が絶妙にマッチ
して、仲々の聴き心地なのです。
という訳で今月は嗄れ声も魅力!って話しでした。
最後に、先月に続いて悲しい知らせとなるが、先頃51歳という短い人生を終えた
ロッドの盟友“ロニー・レーン”氏のご冥福を心から祈りたい。
ROD STEWART/ A NIGHT ON THE TOWN
ファスト・サイドのロックするロッドも流石だが、ちょっと都会的な匂いがする
スロー・サイドの唄っぷりは絶品だ。「今夜きめよう」「さびしき丘」などの名曲
多数。「セイリング」と同位置に置かれた「貿易風」の熱唱も捨て難い魅力に
溢れている。
憂歌団/ BLUE’S
ツボを抑えた演奏とアレンジ、そして木村さんのヴォーカルが妙に心に沁みる
時があるのです。「働け、ブルース・バンド」って曲もあるけど、生涯ブルース・
バンドっていうのもいいんじゃない。スタンダード的味わいも素敵なアルバム。