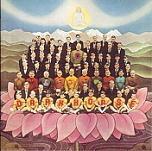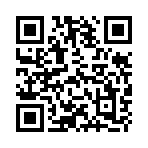keith yoshidaの新・飯がわりに1枚!(Again) › 名盤を探しに行こう! › 名盤/レニクラ&ミスチル
2010年09月09日
名盤/レニクラ&ミスチル
続・名盤を探しに行こう!「あれも聴かなくちゃ!これも聴きたし!」
Vol.98(2002年 6月掲載)
レニクラ、ミスチルって略して表記したけど、世間一般的には、
それで通じるのかしらん。
ミスターチルドレンは通じるはずだけど・・・。
新譜紹介の歴史の中で、唯一紹介した洋楽アーティストとあるが、
何でそうなったか不明。
ま、その時の気分だったんでしょうな!
ちょっと古い話になりますが、忌野清志郎の写真展をみてきました。
ミック・ジャガーとのトゥーショット、あれを見る事が出来ただけ
でも価値があった。
キヨシローの、子供のように嬉しそうな笑顔は、なんとも言えない。
レニーは二度札幌で観てますが、どちらもライヴとしての印象は
もう殆どない。
残っているのは、音楽と関係ない環境的な事。
Zepp Sapporoの時は蒸し風呂状態だったし、真駒内の時は・・・。
ま、今さらいいか!
Zeppの時は汗まみれになってしまい、着替えの為に買う気もない
Tシャツを買うはめになっちゃった。
これも今となっては、いい思い出か?
レニーのこのアルバム、久々に聴いてみようかな!
アナグロ・テイストなレニーは好きでした!!!
レニー・クラヴィッツ。唐突にこのアーティストについて書いてみよ
うと思った。彼は長い歴史(!?)を誇る新譜紹介コーナー“CD ATRA
NDOM”に登場した、数少ない洋楽アーティストの一人だ。
彼を知ったキッカケと言うか、本気で聴こうと思ったのは忌野清志
郎の一言だった。
多分ジョン・レノンのトリビュート・コンサートか何かに参加したレニ
ーを清志郎は“スッゲェ~奴が現れたぜぃ!”とオーディエンスに向
かって紹介したのです。そこでレニーは「COLD TURKEY」を1曲バ
ッシと決め、圧倒的な存在感を残していった訳なんだけど、まぁ、こ
れってテレビで観たシーンだから、実際のライヴ会場ではもっと曲を
演ったのかも知れない・・・・・。
彼がデビューしたのは1989年の事だ。鳴り物入りでデビューした
のかどうかは、今となっては記憶にないが、当時割りとシーンを賑わ
していたブラック系のロックの人なんだろうなって事と、アナログ・テイ
ストなサウンドが話題になっていたように思う。
まぁ、80年代末と言えばデジタル化が顕著で、あえてアナログっ
てぇのは、奇をてらった狙いだろう程度に思ったから、あえて飛び付
きもしなかった。が、前述の清志郎の言葉である。こうなったら気に
なってしょうがない。遅れ馳せながらアルバム「LET LOVE RULE」
を手に入れる。

薄ら覚えだが、最初の印象は“何だこんなもんか!?”だったような気
がする。スッゲェ~!って先入観の為か、もの凄いものを期待し過ぎ
た感もあり、ある意味肩透かしを食らったような感じさえした。
大騒ぎのアナログ感覚も、長年音楽に親しんでいれば、何も新しさを
感じるものでもないしね。なんて言いつつソングライティングからプロ
デュース、マルチにこなす楽器など、その殆ど何から何までやってし
まう才能には目を見張るものがあり、プリンスやテレンス・トレント・
ダ―ビーに次ぐ才能として、こりゃ~追っ掛け廻さなきゃ。って事に
なった。
ここで聴かせた70年代風のアナログ・テイストなサウンドは、レニ
―を語る上で欠かす事の出来ないキィワードとなり、後々まで彼に
付きまとう。
今のようにポピュラリティを勝ち得た存在になり、それでファンになった
方でも、遡って聴いていくと、その事に出食わすだろう。彼がデジタルを
駆使するようになったのは、デビュー10周年を迎えようとした時に発表
したアルバム「5」からである。
さて、そんな拘りのアナログ・サウンドって、一般の人にはどう聴こえて
るんだろう?古臭いのか新鮮なのか。はたまた、全く意識していないの
か。う~ん、俺は一般の耳に興味津々だ。

そして、この程めでたくデビュー10周年を迎えたミスター・チルドレンは、
アルバム「深海」をこのレニー・サウンドの立役者“ヘンリー・ハーシュ”
を迎えて作っている。チャレンジ!!大いに結構。彼らの拘りの真意は、
はたして一般の人の耳に届いているんでしょうか・・・・・?と言う事で、
また来月。
■ 資料■
LENNY KRAVITZ/ LET LOVE RULE / 1989年度作品
Mr. Children / 深海 / 1996年度作品
Vol.98(2002年 6月掲載)
レニクラ、ミスチルって略して表記したけど、世間一般的には、
それで通じるのかしらん。
ミスターチルドレンは通じるはずだけど・・・。
新譜紹介の歴史の中で、唯一紹介した洋楽アーティストとあるが、
何でそうなったか不明。
ま、その時の気分だったんでしょうな!
ちょっと古い話になりますが、忌野清志郎の写真展をみてきました。
ミック・ジャガーとのトゥーショット、あれを見る事が出来ただけ
でも価値があった。
キヨシローの、子供のように嬉しそうな笑顔は、なんとも言えない。
レニーは二度札幌で観てますが、どちらもライヴとしての印象は
もう殆どない。
残っているのは、音楽と関係ない環境的な事。
Zepp Sapporoの時は蒸し風呂状態だったし、真駒内の時は・・・。
ま、今さらいいか!
Zeppの時は汗まみれになってしまい、着替えの為に買う気もない
Tシャツを買うはめになっちゃった。
これも今となっては、いい思い出か?
レニーのこのアルバム、久々に聴いてみようかな!
アナグロ・テイストなレニーは好きでした!!!
レニー・クラヴィッツ。唐突にこのアーティストについて書いてみよ
うと思った。彼は長い歴史(!?)を誇る新譜紹介コーナー“CD ATRA
NDOM”に登場した、数少ない洋楽アーティストの一人だ。
彼を知ったキッカケと言うか、本気で聴こうと思ったのは忌野清志
郎の一言だった。
多分ジョン・レノンのトリビュート・コンサートか何かに参加したレニ
ーを清志郎は“スッゲェ~奴が現れたぜぃ!”とオーディエンスに向
かって紹介したのです。そこでレニーは「COLD TURKEY」を1曲バ
ッシと決め、圧倒的な存在感を残していった訳なんだけど、まぁ、こ
れってテレビで観たシーンだから、実際のライヴ会場ではもっと曲を
演ったのかも知れない・・・・・。
彼がデビューしたのは1989年の事だ。鳴り物入りでデビューした
のかどうかは、今となっては記憶にないが、当時割りとシーンを賑わ
していたブラック系のロックの人なんだろうなって事と、アナログ・テイ
ストなサウンドが話題になっていたように思う。
まぁ、80年代末と言えばデジタル化が顕著で、あえてアナログっ
てぇのは、奇をてらった狙いだろう程度に思ったから、あえて飛び付
きもしなかった。が、前述の清志郎の言葉である。こうなったら気に
なってしょうがない。遅れ馳せながらアルバム「LET LOVE RULE」
を手に入れる。

薄ら覚えだが、最初の印象は“何だこんなもんか!?”だったような気
がする。スッゲェ~!って先入観の為か、もの凄いものを期待し過ぎ
た感もあり、ある意味肩透かしを食らったような感じさえした。
大騒ぎのアナログ感覚も、長年音楽に親しんでいれば、何も新しさを
感じるものでもないしね。なんて言いつつソングライティングからプロ
デュース、マルチにこなす楽器など、その殆ど何から何までやってし
まう才能には目を見張るものがあり、プリンスやテレンス・トレント・
ダ―ビーに次ぐ才能として、こりゃ~追っ掛け廻さなきゃ。って事に
なった。
ここで聴かせた70年代風のアナログ・テイストなサウンドは、レニ
―を語る上で欠かす事の出来ないキィワードとなり、後々まで彼に
付きまとう。
今のようにポピュラリティを勝ち得た存在になり、それでファンになった
方でも、遡って聴いていくと、その事に出食わすだろう。彼がデジタルを
駆使するようになったのは、デビュー10周年を迎えようとした時に発表
したアルバム「5」からである。
さて、そんな拘りのアナログ・サウンドって、一般の人にはどう聴こえて
るんだろう?古臭いのか新鮮なのか。はたまた、全く意識していないの
か。う~ん、俺は一般の耳に興味津々だ。

そして、この程めでたくデビュー10周年を迎えたミスター・チルドレンは、
アルバム「深海」をこのレニー・サウンドの立役者“ヘンリー・ハーシュ”
を迎えて作っている。チャレンジ!!大いに結構。彼らの拘りの真意は、
はたして一般の人の耳に届いているんでしょうか・・・・・?と言う事で、
また来月。
■ 資料■
LENNY KRAVITZ/ LET LOVE RULE / 1989年度作品
Mr. Children / 深海 / 1996年度作品
Posted by keith yoshida at 19:04│Comments(0)
│名盤を探しに行こう!
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。