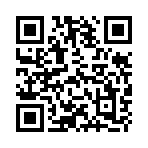keith yoshidaの新・飯がわりに1枚!(Again) › 2022年12月26日
2022年12月26日
シティポップって何だ?
ここ最近と云うより、今年もやたらとブームとしてマスコミなどで取り上げている“シティポップ”。
とは云うものの、何処でブームになっているのかは不明。
そのシティポップの情報に登場するアーティストの方々は様々で、
中には“?”がつく人もいる。
降って沸いたように取り上げられた人は、
訳も分からず、ありがたがるようだが、
ま、忘れ去られたモノが、
サイバー空間のお陰で復活し、
聴かれ、買われ、使われ、お金になる。
決して悪い事ではないのでありがたがるのも当然。
そのシティポップで思い出したのが“Jorge Calderon”。
正しい発音かは不明だが、ホルヘ・カルディロンと読むらしい。
彼のアルバムのタイトルが「City Music」(1975年発表)だった。

このズバリなタイトルと共に“シティー・ミュージック”なる表現が出てきたような記憶がある。
このシティー・ミュージックと云う言い方は短命に終わったが、
後に“AOR”に代わったと言えば、
「ハッハーン!」となる人もいたりして、分かり易いかもね!
そのAORの代表的存在の“Michael Franks”も、
日本でのデビューの際はシティー・ミュージックと謳われて出てきた。

だからAORの前身はシティー・ミュージックとなる。
件のホルヘは、どちらかと云うと、
当時のウェストコースト系のSSWなどで良く聴かれた音だが、
多少洗練された感じがするのも事実。
その洗練具合を都会っぽいと解釈し、
なるほど“街を感じさせる!=都会の音楽”と、
勝手に納得していた。
フランクスは、そこにR&Bやジャズの要素を加味し、
より洗練させたサウンドを聴かせた。
それがAORと持て囃される音楽になった、と。
あらまし、こんな感じだったと思う。
で、日本のアーティスト達が演っていたAORは、
フランクス以降のサウンドを倣っている。
その洋楽志向の強いサウンドは、
ロックやR&B、そしてファンクなどの旨味を吸収し、
腕利きのスタジオミュージシャン達に演奏させるなど、
洋楽に近づく為の志の高い試みがされたものが多かった。
そうして創られた音楽は、
ポップスの総称のように使われた“ニューミュージック”に含まれる事もあったし、その界隈の音楽に多大な影響も与えた。
大分前に松原ミキの事を書いたが、
それ以降、目にした記事などで、
今、シティポップと言われているだろうと思われるものは、
多分、それらの事を指していると思ったし、同じような音楽志向を持って創られたタレントものも含んでもいるようだ。
と、勝手にシティポップはこんなんだろうと推測してみた。
だからシティー・ミュージックとシティポップは遠からずと云う事になる。
でぇ、当時なかった言葉で括られる現状の不思議さ、
そして誰が言い出した分からないシティポップブーム。
大量消費で使い捨てされていく音楽が氾濫する中で、
時間を超えて聴かれている保存された音楽の数々。
それはある意味、創る側、そして聴く側に対して、
「日本は今のままで良いのかよ!」
と警鐘を鳴らされているのかもしれない。
とは云うものの、何処でブームになっているのかは不明。
そのシティポップの情報に登場するアーティストの方々は様々で、
中には“?”がつく人もいる。
降って沸いたように取り上げられた人は、
訳も分からず、ありがたがるようだが、
ま、忘れ去られたモノが、
サイバー空間のお陰で復活し、
聴かれ、買われ、使われ、お金になる。
決して悪い事ではないのでありがたがるのも当然。
そのシティポップで思い出したのが“Jorge Calderon”。
正しい発音かは不明だが、ホルヘ・カルディロンと読むらしい。
彼のアルバムのタイトルが「City Music」(1975年発表)だった。

このズバリなタイトルと共に“シティー・ミュージック”なる表現が出てきたような記憶がある。
このシティー・ミュージックと云う言い方は短命に終わったが、
後に“AOR”に代わったと言えば、
「ハッハーン!」となる人もいたりして、分かり易いかもね!
そのAORの代表的存在の“Michael Franks”も、
日本でのデビューの際はシティー・ミュージックと謳われて出てきた。

だからAORの前身はシティー・ミュージックとなる。
件のホルヘは、どちらかと云うと、
当時のウェストコースト系のSSWなどで良く聴かれた音だが、
多少洗練された感じがするのも事実。
その洗練具合を都会っぽいと解釈し、
なるほど“街を感じさせる!=都会の音楽”と、
勝手に納得していた。
フランクスは、そこにR&Bやジャズの要素を加味し、
より洗練させたサウンドを聴かせた。
それがAORと持て囃される音楽になった、と。
あらまし、こんな感じだったと思う。
で、日本のアーティスト達が演っていたAORは、
フランクス以降のサウンドを倣っている。
その洋楽志向の強いサウンドは、
ロックやR&B、そしてファンクなどの旨味を吸収し、
腕利きのスタジオミュージシャン達に演奏させるなど、
洋楽に近づく為の志の高い試みがされたものが多かった。
そうして創られた音楽は、
ポップスの総称のように使われた“ニューミュージック”に含まれる事もあったし、その界隈の音楽に多大な影響も与えた。
大分前に松原ミキの事を書いたが、
それ以降、目にした記事などで、
今、シティポップと言われているだろうと思われるものは、
多分、それらの事を指していると思ったし、同じような音楽志向を持って創られたタレントものも含んでもいるようだ。
と、勝手にシティポップはこんなんだろうと推測してみた。
だからシティー・ミュージックとシティポップは遠からずと云う事になる。
でぇ、当時なかった言葉で括られる現状の不思議さ、
そして誰が言い出した分からないシティポップブーム。
大量消費で使い捨てされていく音楽が氾濫する中で、
時間を超えて聴かれている保存された音楽の数々。
それはある意味、創る側、そして聴く側に対して、
「日本は今のままで良いのかよ!」
と警鐘を鳴らされているのかもしれない。